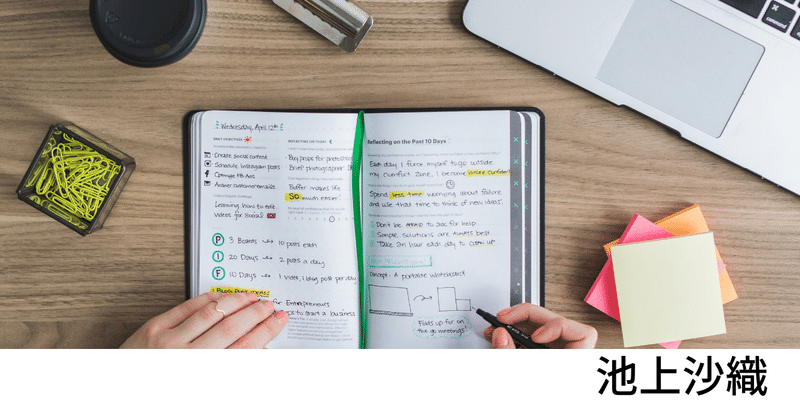
「私の死体を探してください。」 第3話
池上沙織【1】
男の間抜けヅラを見て、何度目だか分からない後悔がこみ上げてくる。後悔しかしていない。この男は自分が森林麻美先生の夫である。ということ以外に何の価値もないことをまだ分かっていないのではないか? という疑問がつきまとう。
いや、私にとっては価値がないということにすぎないのかもしれない。
でも、いわゆる男女の関係になって、どれだけ時間をかけてもこの男の魅力というものが、私にはさっぱり分からなかった。
森林先生の担当になるのは私が出版社に入社する前から叶えたかった夢だった。
森林先生のデビュー作『断罪の行方』は高校生の時に読んだ。衝撃的だった。森林先生がそれを書いたのが、自分とそう年も変わらない大学生の時だったと知ったときの驚きは今も鮮明に覚えている。私も作家になりたいと憧れた。
小学生のころから国語の成績は良かったし、読書も大好きだったし、文章も読書感想文で金賞を貰ったことも、自由作文が新聞に掲載されたことだってあったからきっと自分にならできるだろうと思っていた。
それが大きな勘違いだと気づいたのは大学生になってからだった。
どうやら私には「小説を書く」という才能がないようなのだ。何度覚悟を決めて取り組んでみても、うまく物語を構築し、文章を書き上げるという作業がどうしてもできなかった。書いては消し書いては消しを繰り返していくうちに自分では小説を書くことができないのだと悟った。
自分で書くことができないとなると、一層小説家という職業に対する憧れは募っていった。自分で書くことができないなら、せめて小説が生まれる場所に立ち会いたいと思った。
私が編集者を目指したのはそんな経緯があったからだ。
希望通り出版社に入社はしたけど、必ずしも編集部に行けるわけでも、文芸に行けるわけではないことは百も承知だったけど、私は運良く希望通りに配属され、入社三年目で森林麻美先生の担当になった。
高校生のころから十年ちかく読み続けた大好きな小説家の担当編集者になることが決まったときの興奮は今も鮮明に覚えている。
前任の担当者から引き継ぎのとき森林先生のマンションで初めてお会いした。
先生は顔出しをしない作家だったのでどんな人なのか色んなイメージを抱いていたけど、私が想像していたよりはずっと小柄で、大きな目が印象的で、とてもおきれいな方だなと思った。でも、どこかつかみどころのない人のようにも思えた。
モデルルームのように美しく調和のとれたリビングルームで私は自分が森林先生の作品のファンであるかを、自分と森林先生の作品の歴史を語ろうと思った。
「森林先生、初めまして、このたび担当になりました、池上沙織と申します。若輩ですが、森林先生の作品はデビュー作からすべて拝読しております」
「そうなの。どうもありがとう」
私が出した名刺をじっと見たままの素っ気ない返事にちりりと胸が痛んだ。確かに先生ほどの人気作家になれば、そんなことを言われるのは日常茶飯事なのかもしれない。と気を取り直した。
「インタビューも対談もほとんど拝見しています。森林先生の作品作りや着眼点にはいつもハッとするんです」
「あらそう」
森林先生は顔を上げてくれない。
私が何かを言えば言うほど、森林先生の表情から何かが落ちていき、不安になった私がどんどん熱っぽく話をしていく……。繰り返せば繰り返すほど森林先生の心の壁が高く厚くなっていくような心細い気持ちになった。
森林先生のような人気作家の担当編集者は、当然私だけではない。出版社各社の担当編集者が手ぐすねひいて次の作品、次のヒット作を狙っている。
その日、先生は私が話している間、ずっと気のない返事をして、一度も顔をあげることはなかった。一人暮らしの部屋に帰ると私はがっくりと膝を落として泣いた。顔も覚えてもらえなかったと思った。悲しくて悔しかった。ひょっとしたら悲しみを通り越して怒りさえ覚えていたかもしれない。でも、だからあんなことをしたのだと正当化はできない。
私は自分の感情にかまけてしまった。
私が本当にしなければいけなかったことは、先生の気持ちを想像することだった。未熟な私にはそれができなかった。
そこをあの男に利用されてしまった。
利用されたと一方的に言うこともできない。私には確かに好奇心があったと思う。正隆氏が森林先生の夫であるということ。ただ、その事実には純粋に興味があった。
彼に私にとってのトロフィーの要素がなかったとは決して言えない。
二回目の打ち合わせを先生の自宅でしていたとき正隆氏と初めて対面した。相変わらず森林先生の反応は薄く、私は困り果てていた。
そんなときリビングの奥のドアが突然開いた。森林先生の頭が動いてそちらに反応した。私も思わず見ると、淡いブルーのバンドシャツにデニムをはいた男性が出てきた。整えられたひげには清潔感があった。私よりも少し年上の男性。第一印象に悪いところはひとつもなかったと思う。
「ああ、ごめん打ち合わせ?」
「昨日の夜言ったと思うけど……。池上さんは私の夫に会うのは初めてよね?」
「初めまして、このたび森林先生の担当になりました。池上沙織です」
「初めまして。夫の三島正隆です」
「そうだ。正隆さん、これから出かけるのなら池上さんを駅まで送ってもらえない?」
「ああ、構わないよ」
「先生、打ち合わせの続きは……」
「今日はもう煮詰まらないと思うの、また日を改めましょう」
「でも、もう少し……」
「ちょっと考えさせてくれない?」
先生のペースで切り上げられてしまう。と焦っていた。すると正隆氏が笑って口を挟んだ。
「池上さん、麻美がこう言う時は、何を言ってもだめなんだ。そうだろう?」
「その通りなの、ごめんなさいね」
森林先生は私を見て苦笑いを浮かべた。こちらをちゃんと見てくれたことが私は単純に嬉しかった。それは先生にとって夫の正隆氏がとても重要な人物なのだという証明のように思えた。
それからすぐに私は正隆氏に白いラウンドクルーザープラドで駅まで送ってもらった。連絡先の交換は自分から言い出したことだった。やってはいけないことだったかもしれないけれど、あの時の私は必死だった。
そして、正隆氏と不倫関係になったとき、私だけの蜘蛛の糸を掴んだような気持ちでいた。それが大きな勘違いであることは、すぐに気づいたけれど、覆水盆に返らずだ。秘密を守るために私は正隆氏との関係を続けるしかなかった。私にとってこの不倫関係は口止め料でしかない。正隆氏本人にはなんの魅力も感じていない。
↓最新話までの全話はこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
