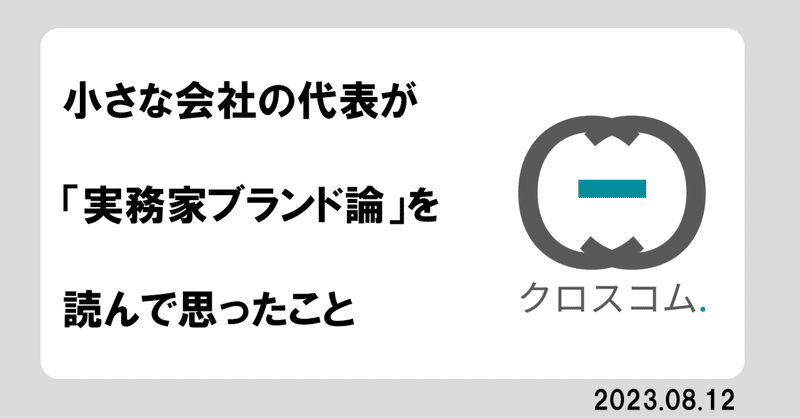
小さな会社の代表が「実務家ブランド論」を読んで思ったこと
こんにちは!本田です。
最近ブランディングに関するビジネス本を読み漁っているのですが、中でも最近特に強く共感した著書が、ダイキン工業株式会社/片山義丈さんの『実務家ブランド論』です。
この本は、ブランドの定義を言語化して、実務でブランドをつくるための現実的な方法について解説されています。タイトルにある通り、まさに実務家のためのブランディング本ですので、かなり有益な内容だと思います。
ちなみに、なぜ自分がこの著書に共感したかというと『抽象論で終わらず、実務で使えるイメージが湧きやすかった』からです。
ほかの名著も読んで、ブランド戦略に関するインプットはしているのですが、自社のブランド戦略への転換作業が難しく、実務に活用することが難しく感じていました。「この知識をどうにか実務に落とし込みたい、、、けどどう落とし込めばいいのかあんまりピンとこない、、、」と悩んでいたときに、たまたまこの著書を見かけました。ブランドというものを分かりやすく説明されていて、実務に落とし込める内容だと強く共感できました。
そこで今回は、著書『実務家ブランド論』を読んで思ったことを、著書内の文章を引用しながら書いていきます。ブランディングに関する知見がなくても理解できる内容ですので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
ブランドは妄想
ブランドとは「その人の頭の中にある勝手なイメージ=妄想」と定義すべきです。
~中略~
実務家ブランド論のブランドの定義の完全版は『(ブランドを)思い出すきっかけになるものに出会ったときに、(→知っていることに気づき→)その瞬間に頭の中に自然に浮かんだ勝手なイメージ』です。
この定義がシンプルで分かりやすいと自分も思います。ブランド戦略に詳しい方の話を聞いていると、「ブランドはステークホルダーとの約束だ」「ブランドとは競争優位になれる資産だ」などいろんな定義をよく聞きますが、それは企業が目指すべきブランドの在り方を示したもので、正確には目標であって定義ではないというのが自分の見解です。
なぜこの見解を示したのかというと、目指すべき在り方をブランドと定義すると、ブランドの主語が企業になってしまうと感じたからです。
そもそもブランドは、消費者の頭の中にある妄想そのものなので、企業が100%コントロールすることはできません。「こう思ってほしい」と意図的にブランドを形成する働きかけはできますが、実際に消費者がどう思うかはすべて消費者次第です。なので企業が消費者にできることは、「こう思ってほしい」をコトバで伝え、行動で納得してもらうしかないと自分は考えています。
本書でも、ブランドが企業サイドに属するものではないことを、妄想という言葉を使って解説されています。
「イメージ」という言葉だと、「ブランドは企業や商品サイドの持ち物であると誤認する」ことがあり、それを避けたい。
あえて「妄想(必ずしも正しいかどうか分からないもの。企業・商品は妄想しないので、自分たちのものではなく他人のもの)」という言葉を選んだのは、そのためです。
身近な例として、めちゃくちゃ個人的な意見含みますが、「俺ってめっちゃ話面白いやろ~?」って言ってくる人の話って、たいてい面白くないですよね。面白いと言ってほしい気持ちが強い一方で、言われてきた回数がほとんどない経験からの発言だと思いますが、これでブランド形成が成り立つのであれば、どの企業もブランド戦略は成功していますよ。まさしく「こう思ってほしい」と「実際に受け手が感じたイメージ」のギャップであり、ブランドの失敗例だと思っています。
だから、ブランドは企業サイドに属するものではなく、消費者サイドに属するものである。この文章に共感できたので、印象に残りました。
機能的価値では差がつけられない時代に
機能的価値では残念ながら差をつけられません。"仕方がない"ので、情緒的価値で差をつけることが重要になってきます。なぜなら生活者が商品を購入する際に、機能的価値は同じで差がない場合、「情緒的価値(ブランド)が高いと思う商品を購入」するからです。
~中略~
だから「機能的価値(美味しいラーメン)」を開発して差をつけることより、今まで以上に取り組むのは当然だけれど、同時に「情緒的な価値(なんとなく好きなラーメン)」も頑張って上げる努力をして「両方の価値」の合計で差をつけないと買ってもらえない時代なのです。
小さな会社にとってはこれも大共感です。特に売上に伸び悩んでいる会社にも理解してほしい考え方だと、個人的に思います。
例えば、ビジネススキル研修のサービスを題材に考えてみます。世の中には論理的思考力やマネジメントスキル、営業スキルなど、ビジネスに携わる人たちに必要不可欠なビジネススキルがたくさんあります。さらにオフライン研修型やオンデマンド配信型など、さまざまな形態で研修サービスを展開している企業はたくさんあるわけです。
まさに競合がたくさんいる状態というわけですが、もし自社が同じビジネススキル研修サービスを展開している場合、この市場の中でどうやって売上を作れるでしょうか?大前提ですが、研修内容の深さやスピーカーの実績など、サービスの質(機能的価値)が高くないと、顧客に検討してもらうことは難しいですよね。この検討前段階では、情緒的価値より機能的価値の方が重要なのは明らかだと思います。
しかし、どの企業の研修もサービスの質って大きく変わらない印象ってありませんか?世の中の技術やサービスの質がどんどん向上しているので、どこの研修も質(機能的価値)に違いを見出しづらい時代になっています。この機能的価値で違いを見出せない状況になって初めて、ブランド(情緒的価値)が、選ばれる理由づくりに貢献できるというわけです。
「鬼のように厳しく教えるAさんの研修なら、質の高いビジネススキルを嫌でも体得できそう…」「同じ目線で分かりやすく教えてくれるBさんの研修なら、確実に自社に持ち帰られるものありそう…」。極端な例ですがこのように、機能性ではなく、スピーカーの雰囲気や紹介文章から消費者が勝手にイメージした情報が、意思決定の判断基準になっている事例はたくさんあります。これがブランドの力であり、このイメージを意図的に作り上げることがブランド戦略ということです。
小さな会社は、サービスの質(機能的価値)だけで継続的に売上を作ることは難しいからこそ、消費者のイメージ(ブランドであり情緒的価値)を意図的につくる必要があると思っています。だからこそ片山さんの「両方の価値の合計で差をつけないと買ってもらえない」という言葉に大共感したので、印象に残りました。
ブランドづくりの現実的な手法はメディア
「あらゆる接点」「より効果的な接点」を検討するものの、「どのような企業・商品においても効果的な接点=メディア」を徹底的に使うことが、実務家が上手に情報を発信するための現実的な手法となります。
~中略~
今実務家が使うべきメディアは、トリプルメディアになります。トリプルメディアとは「オウンドメディア(owned media)」「アーンドメディア(earned media)」「ペイドメディア(paid media)」の3つのメディアのことです。
ブランドとは何か、何を伝えるべきかまでは理解できていたのですが、具体的に実務で何をすればいいのか?というのが、個人的に一番知りたいことでした。そしてこの文章を読んで思ったのは、トリプルメディアを駆使するというのは理解しつつも、小さな会社の立場としては「それぞれのメディアで発信し続けるリソースがないと、結局ブランディングできないのか?」と解釈してしまうとも思いました。
自分の経験上ですが、小さな会社のほとんどは、広告運用で獲得したリードに営業して契約につなげる導線を設計しています。つまり広告というペイドメディア(とLP)の運用と営業にほとんどのリソースを割いているので、SNSやWebサイトなどの更新は手が回らないと思っています。
なので自分の考察として、小さな会社がブランディングに取り組むなら、いまの導線内の「広告・LP・営業」の3つの場所でブランドアイデンティティを伝えていくべきだと考えています。
特に営業は直接コミュニケーションができるので、ブランドアイデンティティを最も伝えやすく伝わりやすい場所です。契約につなげる営業トークを優先する方が大事ですが、そのトーク中の言葉遣いや受け答えの中でも、ブランドアイデンティティを表現することは並行してできるとも思います。
消費者との「あらゆる接点」や「より効果的な接点」云々を考えるより、まず今の導線内の顧客接点で、言葉と行動でブランドアイデンティティを伝えていく。これがリソースが少ない小さな会社にでもできることだと思いました。
おわり
というわけで、『実務家ブランド論』を読んで個人的に印象に残ったことを紹介しました。実務に落とし込めるかどうかの視点で何度も読み返すことが多いので、大変参考になっています。
自社も小さな会社として、トリプルメディアを駆使してさらにブランドアイデンティティを伝えていきたいと思います。
最後までお付き合いありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
