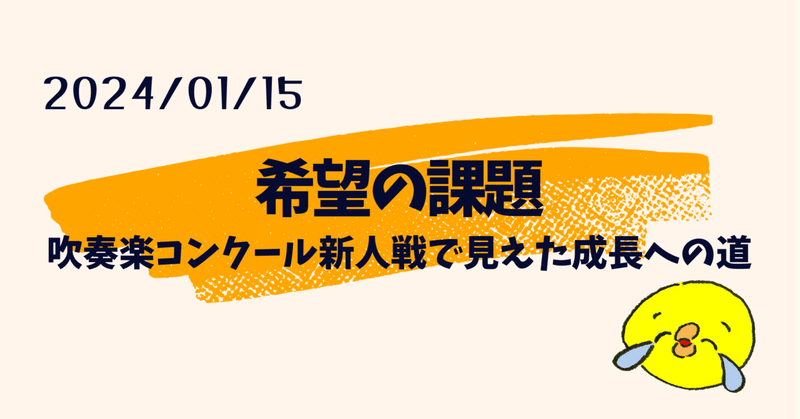
2024/01/15 希望の課題:吹奏楽新人戦で見えた成長への道
2024/01/14 吹奏楽コンクールの新人戦が終了しました。
結果は銀賞。
合同バンドでの参加ということもあり、なかなかうまくいかなことは多くありましたが、内容としてはある程度満足(納得)しています。
いろいろな課題がありますが、気になった課題が大きく2つあったので、ここに書き記しておきたいと思います。
課題① フィジカルを高める
今回の演奏の課題として、
・楽器が鳴らない
・弱奏ができない
・強奏もできない
など、「ブレスコントロール」
に課題があると思いました。
隣の芝生はなんちゃらと言いますが、
表現が豊か、要は「演奏がうまい学校」は基本的に
身体が大きい(背の高い)生徒が多い印象でした。
それと比較すると、今回出た合同チームの生徒は軽く平均5㌢は低かったのではないかと思います。
身長のコントロールはもちろんできませんが、それによって
扱えるブレスの質が変わって(差がついて)しまっていると思いました。
いくら表現する感受性や気持ちがあっても、フィジカルの部分で使えるパワーが違ってしまえば、自ずと出てくる音も違うと思います。
どんな生徒が入ってくるかは選べませんので、(フィジカル面で)どんな生徒であっても、(背が高い・筋力があるなど)身体がある程度出来上がっている生徒と遜色ないようにさせる練習を考えていかなければいかないと思います。
なので、体幹トレーニングや、アレクサンダーテクニークなどを取り入れていきたいなぁと思っています。
https://basilkritzer.jp/archives/357.html
課題② 表現しようとする気持ちを作る
これは完全にメンタル面での話になりますが、①に触れたフィジカルが強化されたとして、やはり
「どのように演奏したいか」
を演奏者である子どもたちがもっと“表現しよう”とする気持ちも高めていく必要があると思いました。
これはまさに
「感受性」
の一言に尽きるのですが、音楽に限らず、その瞬間瞬間に
「自分が何を思い、考えているのか」
を相手に伝えようとする“姿勢”を作っていくことが必要です。
とかく受け身な生徒が多い印象ですが、言葉を使わずに音楽を表現する吹奏楽では、楽器を通して“自分が思っていることを表現する”活動ですので、
“気持ちの有無”ではなく、
“(気持ちを作ることを前提として)どう伝えるか・どう表現するか”を
もっと求めていかなければならないと思いました。
もちろん、“言葉にする”ことも大事だと思いますが、言葉を使わずとも感情を伝えることはできますので、
“どうやったら相手に伝わるのか”を考え、実践する数を増やしていきます。
今回は、大きく2つの点について、今後の活動指針にもなるであろう課題を挙げてみました。
かなりの長期戦になると思いますが、コツコツ地道にやっていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
