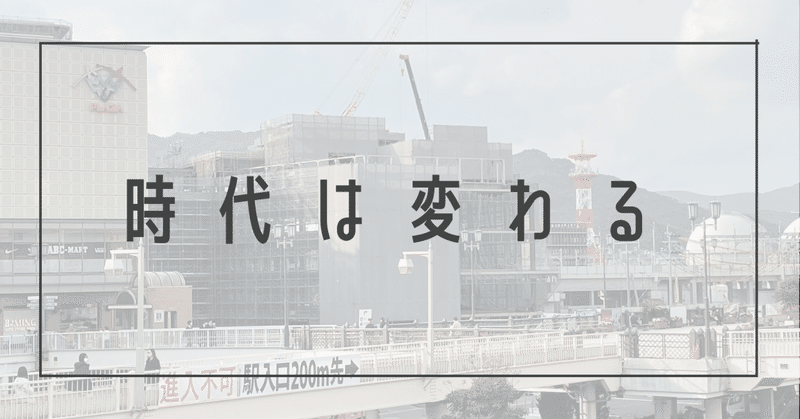
外の知識と平等と ~胡蝶の夢とSNS鎖国~
医学には「平等」な側面があります。
なぜなら、
どんなに偉い人でも、貧しい人でも、
「人間の身体の変化」という面では
平等だからです。
(もちろん個体差は千差万別ですが、
生まれて亡くなるまでの過程の意味)
「不老不死」はあり得ません。
古代の権力者、秦の始皇帝は
不老不死の妙薬を求めたそうですが、
ついには寿命が来て亡くなった。
生・老・病・死が、等しく訪れる。
生きている限りいつかは老いる。
病気にかかることもある。亡くなる。
これが自然の摂理ですよね。
しかしその摂理には無情な面がある。
ゆえに、医学者や医療者は、人が
その命を「長く」「良く」過ごすため、
健康でいられるための
知識や技を積み重ねてきました。
…ただ、社会的に不平等な環境ではどうか?
江戸時代の日本は、原則
「社会的に不平等」な環境です。
例えば、将軍様や各藩の殿様たちは
「生まれながらに高貴な人」とされた。
人間の身体、という点では、
庶民の身体と変わらないはずなのに、
高貴な人は身体もまた高貴…。
そんな風に考えられていた時代。
しかし、冒頭に書いたように
医学には「平等」な側面がある。
ゆえに、医学者や医療者は
身分制度から離れ、出家したかのような
存在になっていたのです。
身分制度の枠外に置かれることが多かった。
「不平等」な社会で
「平等」な人間の身体を診るがために、
医師は「僧侶」と同じ扱いだったのです。
本記事では江戸時代~明治時代の
医学者の話から、平等/不平等の
話を書いてみたい、と思います。
まず、そもそも江戸時代の医学者は
「僧侶」だった、という話。
江戸時代初期、知識人と言えば「僧侶」。
彼らは薬草や薬学にも詳しい。
薬に詳しい僧侶が、そのまま
医師になったケースが多いんです。
だから髪の毛を剃っている。
しかし江戸時代中期になると、
様々な医術の流派が生まれます。
そのうちの一つが「古方派」(こほうは)。
彼らは漢方医の一派で、
剃髪ではなく束髪にしていました。
◆坊主の医師は薬方派:薬草に強い
◆束髪の医師は古方派:薬方や灸に強い
しかしこの状況の中、江戸時代中期に
全く異なる系統の医学者が出現する。
そう、蘭学の「蘭方医」ですね。
ただし『解体新書』で有名な杉田玄白は
束髪ではなく剃髪姿です。
髪の区分も人によって柔軟に変わり得る。
もう少し言えば、
医師は国家資格制ではありませんでした。
江戸時代、なろうと思えば
誰でも医師になれた。自称医師です。
もちろん実力は必要なので、
下手な医師は「やぶ医者」と呼ばれる。
…さて、ここで難しい問題が生じます。
蘭方医とは「蘭学」すなわち
オランダの学問を修める人たち。
オランダは西欧の国です。
日本とは社会の前提が違った。
特に1789年の「フランス革命」以降は、
「平等」が基本の社会になっています。
日本の蘭方医たちは、
蘭学を通して「平等」の思想に触れる。
身分制度の江戸時代に、
蘭学、蘭方医、医学という針の穴から
「平等」の概念が染みこんでくる…。
江戸幕府はいわゆる「鎖国」政策を採り、
平等の考えを禁じてきました。
古くはキリシタン勢力の撲滅。
島原・天草一揆の鎮圧、絵踏。
「神の前での平等」は統治に都合が悪い。
オランダとの貿易も「出島」に限った。
日本からオランダに使節を派遣して
西欧に出先機関をつくる、
ということもしなかった。
やろうと思えばできたはずなのに。
これらは不平等な身分制度に立脚する
幕藩体制の維持のためです。
「平等」だと都合が悪かったからでしょう。
外の空気に触れた人がいると、
中の統治には不都合だった。
しかしここに「蘭方医」が登場する。
…外の空気に触れた人たちです。
特に幕末のあたりでは、
蘭学、洋学を学んだ者たちが、
身分制度の矛盾を強く感じるようになります。
これらをテーマに書かれた小説がある。
司馬遼太郎さんの『胡蝶の夢』。
…この小説はかなりの異色作です。
幕末から明治期にかけての人の世を、
政治ではなく「医療」の視点で書いた作品。
主人公は一人ではなく、三人の男が中心です。
まず『松本良順』
(まつもとりょうじゅん)という蘭方医。
そして佐渡島出身の『島倉伊之助』
(しまくらいのすけ)という弟子。
『関寛斎』(せきかんさい)という医師。
良順は、後に明治陸軍の
初代軍医総監にまで出世します。
豚肉食や牛乳、海水浴などを国民に勧めた。
伊之助は、言語学の天才です。
独・英・蘭・仏・露・中の六か国語に通じ、
医学用語の日本語訳に力を発揮する。
しかし天性のトラブルメーカーで、
40歳で死去。
司馬凌海という名前でも知られます。
寛斎は、一介の町医者になり
貧しい人には無料診療を行っていく…。
彼らを対比させながら、
江戸~明治の社会を鮮やかに描き出す。
もちろん司馬スタイルの脚色や
取捨選択も多い「小説」ですが、
ぜひ未読の方に読んでもらいたい作品!
さて、この良順が、医術の世界で
身分制度の弊害に直面します。
医者は患者を助けてこそ、なのに、
技術の無い古い医師が
権威を笠に偉そうにしている…。
良順はポンぺというオランダ人から
当時の最新の医術を学んでいました。
ゆえにこの不平等が許せない。
ポンぺ先生はこう言ったそうです。
『医師は自らの天職を
よく承知していなければならぬ。
ひとたびこの職務を選んだ以上、
もはや医師は自分自身のものではなく、
病める人のものである。もし、
それを好まぬなら他の職業を選ぶがよい』
現代の長崎大学医学部の
校是にもなっています。
良順は、彼の指導を通して、
「医師にとっては階級差別、貧富・上下の
差別はなく、ただ病人があるだけ」という
平等の思想を受け取っていきます。
後に良順は医療制度を整える中で、
この思想を普及させていく。
その一方、新選組の隊士たちを診察し、
戊辰戦争では幕府方につく…。
江戸と明治。価値観が変わっていく
社会の断面と連続を描き出した快作です。
ぜひご一読を。
最後に、まとめます。
本記事では江戸~明治の医学者の話から、
平等/不平等の話を書きました。
…この話は、昭和~平成~令和の
SNSによる「情報の平等」の話にも
通底する部分がある、と私は思います。
江戸時代では国内統治のために、
海外からの情報は制限されていた。
令和時代でも社内統治のために、
社員のSNSを禁止する会社があります。
いわば「SNS鎖国政策」…!
そんな中で、SNSを活用する読者の皆様は、
杉田玄白~松本良順たちと同様の
「新時代の旗手」のように思うのです。
でも、もしLinkedInの使い方に迷った時は、
本記事の下部のリンクから
松本良順…じゃなかった
松本 淳さんの『LinkedIn活用大全』を
お読みください。
まさにLinkedInの『解体新書』ですよ!
(最後は宣伝でした)
※ポンぺと松本良順についてはこちらもぜひ↓
※松本 淳さんの『LinkedIn活用大全』はこちら。
(ヒストジオいなおの名前も、どこかに
載っているので探してみて下さい!)↓
※司馬遼太郎さんの小説
『胡蝶の夢』はこちらから↓
◆江戸~明治の学者の人たちは
なかなかに凄いので、以下からぜひ。
※「哲学」の西周(にし あまね)↓
『「西周」という橋渡し ~日本哲学の父~』↓
※「法学」の津田真道(つだ まみち)
『津田真道の「道」~失敗続きでも切り替える~』↓
※「数学」の菊池大麓(きくち だいろく)↓
『大いなる麓 ~華麗なる学者一族~』
※みなもと太郎さんの漫画
『風雲児たち』では、江戸時代の学者たちが
どんどん出てきますのでぜひ↓
※手塚治虫さんの漫画、
『陽だまりの樹』もいいですね↓
※ドラマにもなった村上もとかさんの漫画
『JINー仁ー』も面白い↓
※よしながふみさんの漫画
『大奥』にも蘭学者たちがたくさん出てきます↓
合わせてぜひどうぞ!
よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!
