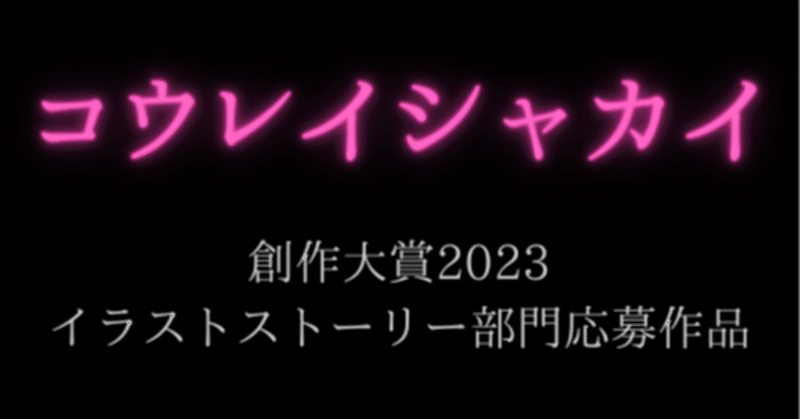
【小説】コウレイシャカイ 第九話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
階段を一気に駆け上がり、扉を開け放つ。デジャヴのような行動だが、今度は一人ではない。富寿満が派遣してくれた治安部隊の隊員達が赤い上着と白いビョルク帽の兵士達を倒し、いくつもの銃口でスレイマンを囲んでいるのだ。その中心に立つ鹿嶋は禿頭の男を睨みつけ、正面から言葉を突きつける。
「ここに来るまでにいろんな人が死んでるのを見た。いろんな人が殺されかけているのを止めた······あんたの兵士にだ、スレイマン」
「私がしたことだ、そんなことはわかっている。少年よ、それでお前は何がしたいのだ?死んだ者が完全に蘇ることはない。お前が憤ったところで生き返ることはない。それでもお前は何を足掻く?何を望む?」
「決まってんだろ」
鹿嶋は短く息を吸い、ゆっくりと手を閉じる。ある少女の顔が頭をよぎり、握った拳に力を込める。
「俺の手で、あんたを倒す」
それが合図だった。治安部隊が一斉に引き金を引き、磁石式捕縛網を発射する。スレイマンに向けるだけでなく彼の周りの空間全体を狙うことで逃げ道を塞ぎ、それと同時に鹿嶋は走り出した。スレイマンは兵士を現出して身代わりにするが、網で動けず剣すら振れない状態の者など敵ではない。鹿嶋は拳を突き出して兵士を消し去り、スレイマンに肉薄する。兵士に隠れて位置が確認できなかった間にわずかに距離を取っていたスレイマンはこれをかわして、両者の位置が逆転した。禿頭の皇帝の手には、赤い蝋の指輪が現れている。
「······私に刃向かうことは重罪だ。私の治世下では死に値する。それを知っての蛮行か?」
「あんたが人を殺していい時代なんて無いんだよ」
吐き捨てて鹿嶋は一歩踏み込み、すぐに異変に気づいて靴底を削り急ブレーキをかけた。治安部隊の隊員達が、その動きを止めている。悠然と構えるスレイマンは眉一つ動かさず重厚な声色で、
「いや、世界皇帝の治世は蘇る。これがその証拠だ」
言うと同時に、あちこちから潰れた呻きが連鎖して鹿嶋を覆った。何かがまずい。そう直感した瞬間に隊員達が首元を押さえて膝から崩れ落ちる。ある者はもがき、ある者は掠れた息を洩らし、ある者は何かを振りほどこうとのたうち回る。
(何が、起こって······?)
熟れすぎたトマトのように顔を赤くした隊員達に縋るような眼差しを送られ、鹿嶋の心臓が不自然に速まる。何かしなければいけない。だが何が起きていて何をすればいいのか考える隙も無く、
「私を脅かす者は死ぬ。それが私の法だ」
ぼとり。
苦しみ抜いた隊員達の体からふと力が抜け、顔から突っ伏してそのまま動かなくなった。
「············死んだ、のか?」
「そうだ、絞首刑に処したのだ。それにしてもやはりお前には特殊な力があるようだな。我が法の罰を受けないとは」
「············どうして、死ななきゃいけなかったんだ?」
「何度も言っているだろう。世界皇帝に刃向かった罰だ」
「そうじゃねえよ!どうして他の誰かを死なせて平気でいられるのかっつってんだよ!」
腹の底から放たれた叫びはスレイマンにぶつかり、鹿嶋の元へ跳ね返ってくる。
それでも、
「私は統治者として判断を下したまでだ。何を騒ぐ?」
スレイマンは何も変わらなかった。
立ち向かわない理由なんて無かった。
鹿嶋は煮え滾る視線をぶつけ、全力で吼える。
「スレイマンッ!!」
駆け出した鹿嶋に対し、スレイマンが現出したのは羊皮紙だった。何事かが書かれた羊皮紙を手早く巻き取り、すぐに蝋の指輪で封じる。その間に鹿嶋は最短距離で接近し、最後の一歩を踏み出した。
そして、床が落ちる。
(なッ······!?)
鹿嶋の足は着地点を失って空っぽの空間に沈み込み、体ごと下の階へ落下していく。受身を取ることを考え、すぐに全身を危機感が駆け巡った。鹿嶋の落下線上にある床が全て崩れ、一回の床が見えている。宮沢に人を殺せないという制約があるために鹿嶋はビルの屋上から落ちても死ななかったらしいが、スレイマン相手では話が違うだろう。このままでは確実に死ぬ。
鹿嶋は三階分落下したところでどうにか穴の淵を掴み取って這い上がった。あまりの衝撃に肩を脱臼していないことが奇跡のように思えた。どこかの会社のオフィスらしいフロアを移動してエレベーターホールに向かいながら、スレイマンの能力を考える。
(ヤツは『法』とか『罰』と言っていた。たぶん、ヤツを攻撃した瞬間に窒息死させられるのが兵士に隠れていたときに発動した『法』で、それだと俺に効かないから床を抜いて間接的に俺を殺そうとしたのがさっきの羊皮紙に書かれていた『法』。羊皮紙は発動ごとに消えるが、指輪は共通。この間はこんなことできてなかった······降霊から時間が経って馴染んできたってことなのか?とにかく、床が抜かれるなら上から狙えばいい!)
エレベーターが動いている。スレイマンが乗っているのだろう。彼にとっては現状鹿嶋からの攻撃手段は乏しいのだから、焦る必要が無いのだ。それをチャンスと捉えた鹿嶋はエレベーターの脇にある階段を上ってすぐ上の階の廊下に飛び出し、スレイマンに開けられた穴へと近づく。
穴はビルの建材を破壊することで空けられているらしく、粗いコンクリートや千切れた鉄筋がむき出しになっていた。そこからゆったりとした足音が聞こえてきて、鹿嶋はスレイマンが穴の真下へ来るまでの時間を予測する。
「······隠れたか。面倒なことをする」
独りごつスレイマンは鹿嶋が上の階にいることに気づいていないらしい。息を潜めて様子を窺い、下の階の廊下に空けられた穴が修復されたのを確認した鹿嶋はそっと拳を握った。足音が迫る度に意識が研ぎ澄まされていくのがはっきりとわかる。
索敵するスレイマンが穴の真下を通過し、鹿嶋は頭上から急襲をかけた。
同時に、スレイマンが新たな羊皮紙に蝋封をしていたのを目にした。
(バレてッ······!)
それでも鹿嶋が空中で体を弓なりにしならせ、スレイマンの後頭部に拳を放とうとした瞬間。
千切れた鉄筋が復活し、鹿嶋の体を貫通した。
緊急時の避難先に指定されている学校は多いが、磯棟や鹿嶋が通う高校もその一つだ。フレイヤは治安部隊本部からリアルタイムでもたらされる情報を頼りに敵兵がいる道を避け、何とか磯棟を避難所まで送り届けた。
(良かった·····)
同じく避難していたらしい同級生達と再会して表情を緩めた磯棟を見て、フレイヤは安息する。
『まだ安心ではないよ、フレイヤさん。その学校は隊員がいない。あなたがその代わりだ』
フレイヤの心を見透かしたように通信機からエディソンが釘を刺し、フレイヤは再び表情を引き締めた。今はどの隊員も出払ってしまっているために、本部ではエディソンがオペレーターの役割を担っているのだ。
それにしても、とフレイヤは白衣の上から懐の拳銃に手を当てて思う。
(これを使うことが無くて良かった。いくら位相間現象でも、引き金を引く感覚は絶対にいいものじゃないから)
そこまで思って、フレイヤは自分の姑息さが恥ずかしくなる。四足歩行型や飛行型で発砲するのは迷わないくせに何を言っているのか。どこまでも責任逃れをしようとするな。そう誰かに言われている気がした。
「フレイヤさん」
俯いたフレイヤを呼ぶ声がした。顔を上げると、笑顔の磯棟がおにぎりを手渡してくる。
「······これは?」
「お礼です。といってもそこで配ってたやつですみません。でも、ここまであたしを守ってくれて、ありがとうございます」
「私は何もしてないよ。ただ、教えてもらった安全な道を通っただけ」
「いえ、安全な道を選んでくれたから、無事でいられるんです」
「そう······なのかな。でも、私は実理ちゃんにつらいものを見せたくなかったんだと思う。こんなこと訊くのも難だけどさ、実理ちゃん、人が死んでるのを見るのは初めて?」
「······はい」
「そっか。私も実理ちゃんと同じ歳のときに初めて見た。額に穴が空いたお隣さんとか、腕が三つに分かれた先生とか、開ききった瞳孔に涙を浮かべてる裸の親友とか、顔がわからないほど焼け焦げた母親とか。いろんな人がいろんな場所で、いっぺんに死んじゃった」
「それって、陶磁器戦争······?」
「うん。実理ちゃんが私達と合流するまでに見ちゃったものが、私が見たものよりマシだなんて思わない。でも、やっぱりこれ以上つらいものは見せたくなかったのかもしれない」
フレイヤは嘘をついた。本当は、自分が見たくなかったのだ。見てしまったら、何かが崩れてしまう。ある少女の死を背負った半年前から今日まで、自分をつなぎ留めていた何かが。
「······そういうところに、鹿嶋くんは行っちゃったんですね」
「······うん。彼、そういう人だから」
フレイヤが返したきり、磯棟は黙り込んでしまう。
「やっぱり、鹿嶋くんのこと心配?」
「はい。だって、鹿嶋くんのことが好きですから」
磯棟は言い切り、まっすぐフレイヤを見つめた。まるで何かを待っているように目を逸らさないので、フレイヤは思わず目をぱちぱちさせる。
「えっと······うん、頑張ってね」
戸惑いつつフレイヤが言うと磯棟は逆に困惑した表情で、
「え、そんなあっさり?もっと何かあると思ってたんですけど!?」
「何かって······あ、私と鹿嶋くんには何も無いよ?ただの協力関係だから」
「······ホントですか?」
「うん。というか十歳も離れてたら流石に無いし、お互いに無いかな」
「ホントですか!」
「え、どうして嬉しそうなの?本当に私と鹿嶋くんに何かあるって思ってたの!?」
見る見る内に表情を明るくする磯棟を見て思わず笑ってしまうフレイヤだが、
「あ、でも」
言いかけて、余計なお世話だと口をつぐむ。だが磯棟は承知しているらしく、
「わかってます。ダレイオスの人質になっているときに大体聞いちゃいました。鹿嶋くんは幼なじみの女の子を降霊してもらうために戦ってるって」
「ああ、うん······」
降霊研究が凍結される。半ば決定事項のような富寿満の言葉を思い出し、罪悪感がフレイヤの心に深々と爪を立てた。だがそんな胸の内など知らない磯棟はためらいがちに、無意識に、しかし確かに、フレイヤをもう這い上がれない奈落へと突き落とす。
「鹿嶋くん、日咲ちゃんのこと何か言ってましたか?」
「······日咲ちゃん?」
心臓が一度だけ大きく跳ね、胸の中で恐怖に駆られて走り始める。聞き間違いかと思った。そうであってほしかった。こんな事態になったそもそものきっかけは一体誰だったのかを思い出し、それがどうしてこんなところでつながるのか訳がわからなかった。
「ああ、稲森日咲ちゃんです。半年前に亡くなった、鹿嶋くんの幼なじみ」
「··················いなもり、ひさ」
口の中で呟いて、フレイヤは流れる汗を拭った。じりじりと心が削られる感覚がするのは、錯覚か現実か。それとも、もう削られるほどの心の余裕など無いのだろうか。心臓が変な動き方をし、肺が妙に硬い気がする。
「フレイヤさん?」
磯棟に呼びかけられ、フレイヤは咄嗟に微笑んだ。だが磯棟はフレイヤの顔をまじまじと見つめ、
「大丈夫ですか?」
「平気、ちょっと暑いだけだよ」
「······あの、失礼かもなんですけど、フレイヤさんのことも聞きました。それで、その······フレイヤさん、無理しないでくださいね。フレイヤさんがつらい思いをしてると、悲しむ人がきっといますから」
「······ありがとう、実理ちゃん。ちょっとお手洗い行ってくるね」
フレイヤはそれだけ絞り出し、ふらふらとその場を離れる。トイレに入っても、鏡の向こうの自分がどんな顔をしているのかわからなかった。磯棟に優しい言葉を掛けられても、自分にそんな価値が無いことはわかっていた。
日咲という名前を鹿嶋の口から聞いても、あえて気づかないふりをしていたのかもしれない。
気づかないでいれば、誰も傷つかないから。
気づいてしまっても、向き合いきれないから。
稲森日咲。それは半年前にあの降霊者が降りた少女の名前。
半年前にフレイヤが殺した少女の名前だ。
その男には祖父がいた。厳しくも優しい、偉大な祖父だった。
その男の父は、皇帝になりたがっていた。だからその男の祖父が没するのを待たずに反乱を起こし、玉座を奪い取った。帝都を去る実の父を、その男の父は迷わず殺した。
やがて父の時代は終わり、その男は三大陸に広がる領土を統べ、地中海を制する皇帝になった。
その男には友がいた。皇女たる妹を託せるほど、信頼できる友だった。
その男の友は、力を欲していた。だからその男から兵を預かると才覚を活かし、瞬く間に武功をあげた。友の躍進が玉座を揺るがしかけると、その男は父に倣って友を殺した。妹はその男を憎んだ。その男は、統治者として正しかったのだと言い聞かせた。そして妹は、夫の後を追った。
その男には篤実な長男がいた。民衆や官僚や兵士はもちろん、帝位を争う弟達からも好かれる有望な皇子だった。
その男の長男は、将来を期待されていた。だから周りの者達は彼のために働き、戦場では彼のために命を捧げた。人々の敬意が自分よりも長男に向けられ始めると、その男は長男を殺した。弟達は憤り、末子はその男を恐れた。その男は、統治者として正しかったのだと言い聞かせた。そして末子は父が息子を殺す世の無情に心を病み、やがてその身も弱り果てて死んでいった。
その男には、美しい妻がいた。病で次男を亡くしても気丈に振る舞い、その男の長男が死んだときには、例え自分の息子達の未来を脅かしていた者であっても悲哀の涙を流す妃だった。
彼女はその男からの寵愛を得るための後宮での闘争の果てに病になった。彼女が死去するときに言い残したことは、息子達に玉座を争わせないことだった。
その男には勇敢な四男がいた。情趣深い三男との折り合いは悪かったが、武勇に優れた逞しい皇子だった。
その男は兵士に慕われていた。だから人々は彼を在りし日の長男と重ね合わせ、彼の玉座への欲望を掻き立てた。彼が反乱を起こすと、その男は三男を戦いに向かわせた。反乱者が敗れると、その男は兄に弟を殺させた。三男は母の遺言を守らなかったその男を恨んだ。その男は、統治者として正しかったと言い聞かせた。そして三男は懊悩し、享楽に溺れていった。
その男は死の間際まで統治者であり続けようとした。病体に鞭打ち白馬に跨って出陣し、遠征先で事切れた。多くの死がこびりついた仮初の世の最後に、その男は何を思ったのだろうか。降霊者として蘇ってからの行動は、統治者であり続けようとした結果なのだろうか。誰もそのことを知らないし、知る由も無かった。
腹部を貫いた鉄筋はすぐに消滅し、鹿嶋は廊下に落下する。両足で着地するがまともに動けず、振り向きざまに殴りかかってきたスレイマンの拳が直撃した。至近距離で応戦しようとするとまた床が破壊されるため、抵抗することができない。腕を掴み取られて動きを封じられ、顔面を何度も殴打された。鼻と口から出血し、意識を何度も揺さぶられる。
(ま、ずい······)
だがスレイマンは攻撃をやめて鹿嶋を突き飛ばし、代わりに兵士達を現出した。兵士達は穴が空いたことで生じた瓦礫を拾い上げ、今度は堪えきれず後ろに倒れ込んだ鹿嶋へ豪速で投げつける。鹿嶋は右腕で頭をかばいながら左腕と両脚で後退するが、足先や肩、そして血が滲む腹に瓦礫が直撃して苦悶の声を上げる。腿の付け根に瓦礫が命中した瞬間、ポケットの中身が破れると同時に痛みが爆ぜた。
「······少年よ、なぜ抗う?なぜ隷属を懇願せず、私に刃向かう?私は私を脅かし秩序を乱すものには一切容赦しない。だが平和を望むものには絶対の安心を保証する。なのになぜ自ら死へ進む?」
問いかけるスレイマンの眼は、鹿嶋だけを見ているのではないだろう。これまで敵対し、葬ってきた者達への疑問。それを悟ったからこそ、鹿嶋は自分なりの答えを叩きつける。
「平和とか、安心とか、そんなのよくわかんねえよ。『日咲に会いたい』が本当にそれでいいのかも、俺にはわかんない。でも、日咲ならきっと困ってる人を見過ごさない。あんたがやったことを見過ごしたら、俺が生きてても死んでても、日咲に会う資格なんて無い!だから俺はあんたを倒す。例え腹をぶち抜かれても、喰らいついてあんたを倒す!」
その啖呵を聞いて、スレイマンはむしろ小さく笑っていた。それは彼にとっての免罪符になったのだろう。免罪符が必要なのは、鹿嶋も同じだった。
(······何だよ、『日咲に会う資格なんて無い』だと?何がよくわかんないだ。なんで迷ってたんだよ俺は。ずっとそうだっただろ。『会う資格なんて無い』なんて思うのは、ずっと日咲に会いたかったからだろ)
投げつけられた瓦礫から頭をかばうことをやめ、鹿嶋は右拳で廊下を叩きつける。コンクリートの塊が額にぶつかるが、もう意識は揺らがない。
(俺のせいで死んだ人に会いたいだなんていいのかとか、そんな理由をつけて会わない選択肢を増やすのはやめた。こんなのは俺の都合だ。だけど俺は会って償わなきゃいけない。俺は日咲に会いたい。そうじゃなきゃ俺は前に進めない!)
廊下から能力が伝わり、兵士達が白い光のもやとなって消え去った。鹿嶋は左手をポケットに入れて中身を握りしめ、血溜まりから起き上がり、自らの足で倒すべき敵へと駆け出す。
鹿嶋に対してスレイマンは何も構えなかった。ただ羊皮紙を現出してこれを巻き取り、蝋の指輪で封じようとする。
それを鹿嶋は許さない。
左手に握った七味の粉末をスレイマンにぶちまけ、体の痛みを振り切って加速する!
「小癪な!」
スレイマンは目を閉じるが、目眩ましのつもりで投げたのではない。
先ほどのスレイマンは鹿嶋が出血すると殴るのをやめていた。位相間現象を消滅させられる鹿嶋の血液など触れたくはないだろう。だがそれは、指輪に血液が付着しないようにした結果なのではないか。新たな『法』を適用する度に新たな羊皮紙が現れていたのに、指輪はそのままだった。つまりそれは、指輪がスレイマンの能力の本質ということを示すのではないか。蝋に粉末が付くとなかなか除去できない。だから、この方法ならば、スレイマンに迫ることができるのではないか。
ほとんど賭けだった。確証なんか無かった。だが最後は、強く信じた者が勝つ。理屈なんかわからなくったって、自分の意志が、願いが、都合が、叶うと信じればいい。
鹿嶋は強く踏み込み、スレイマンの懐に入る。もう蝋の指輪は消えていた。それでも、目を開けたスレイマンは拳を握り、全力で鹿嶋を迎え打つ。何かが無くても、統治者は自分自身。語らずともそれが全てだった。
互いに、一発。
先に届いたのはスレイマンの拳だった。
それでも鹿嶋は、絶対に倒れない。
「······っらあああぁァァァァァァァッ!」
鹿嶋は顔を歪ませながら、腹の底から力を振り絞る。突き刺さった拳を払い除け、その拳を全力で振り抜く!
ゴッッ!!
激突音がして、白い光が瞬いた。荒い息が聞こえ、血が滴り落ちる。
そして最後に立っていたのは、鹿嶋陵平だった。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
