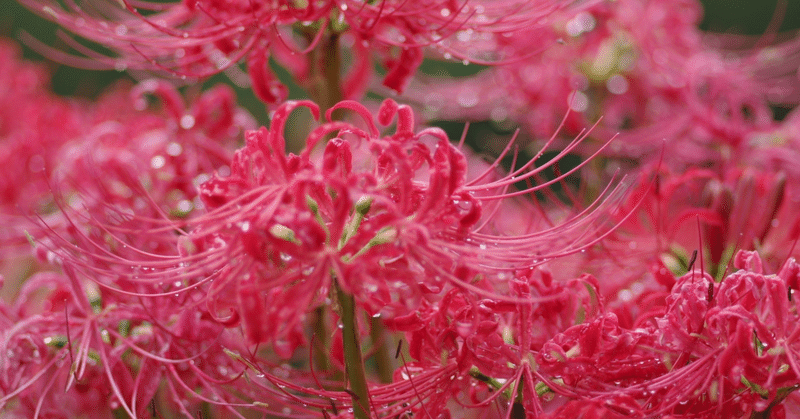
#2 妖の巫女と呼ばれた僕はたった一人の為に世界を破壊する
第二話:パートナー
「ご飯できたよー!おりてきなさーい!!」
一階の階段下から母の大きな声が家中に響きわたる。
それは夕飯の用意ができたことを知らせるもので、私の家族が唯一集まる時間だ。
ベッドで寝ころんでいた私はよっと起き上がり、階段を下りていく。
台所に着くとまだ食事は並んでいなかった。
「ほら、手伝って!小皿もみんなの分並べてね!」
私が食器棚から皿を取り出し、大きめの長方形のテーブルに並べていくと父と弟が居間から入ってきて座席に着く。おそらく一緒にゲームでもしていたのであろう。
「お、カレーじゃん!やったー!!」
好物であったカレーを前にしてはしゃぐ弟を見て少し微笑む。
弟は先月に中学にあがったばかりだ。まだまだ幼く歳が離れた弟を私は可愛がっている。
生意気な部分も多いので喧嘩もするのではあるが。
「あ、福神漬けがまだあった気がするな。どれ」
父が立ち上がり冷蔵庫から瓶に入った赤い漬物を取り出す。
車工場に勤務している父は朝が早いが夕方には帰宅する。
他の家庭に比べれば家族で過ごす時間は多いのではないだろうか。
「はい、じゃあ~いただきます。」
母の号令と共に、みんなが手を合わせて続く。
何気ない、いつもの夕食の風景だ。日曜日ということもあって少し気が重いけれど。
「玲、髪の毛、カレーにつかないようにしなさいよ。」
玲。私の名前だ。
髪がずいぶんと伸びたから、前かがみになったときに入らないように気を付けてるのだがたまに汁物につかってしまうと最悪だ。カレーなんて目も当てられない。
「その髪切らなくて平気なの?可愛いからいいけど...男の子なのに」
母が怪訝な顔をしてこちらを見ている。確かに同世代の男子はみんな短髪なのだから当然だ。
「いいの。ちゃんと先生にも言ってあるし。縛ってるから。」
私が髪を伸ばしているのには理由がある。
その理由は――
「おかわり!あ、お肉多めでね!!」
弟を見ると、それに気づいたようにハッと気づいたような表情でみてきた。
「おにいちゃんもおかわりー!?」
「ううん、だいじょうぶだよ」
そう答えると弟はキョトンとした顔になった。
こんなにおいしいのになぜ兄は食べないのだろうかと言わんばかりだ。
私は辛いものが得意ではない。一般的な中辛でも舌がヒリヒリしてしまい味覚が薄れてしまう。
「優紀、ごはん食べたらもう一戦しような!」
父が弟にそう話しかける。一緒にいつも遊んでいる格闘ゲームのことだろう。
熱中して騒ぐのでいつも母に二人して怒られているのをよく見る。
「玲もたまにはどうだ?あの毒使いうまかったじゃないか」
「また今度ね」
「つれないお嬢様だこと!」
まるで子供みたいに笑う父を横に、少しがっかりした弟を見て少し心が痛んだ。
私にはこれからやらなければいけないことがあるからだ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
食事を終え、部屋に戻ると私は今日行ってきた空き家の骨壺をじっと見た。
なぜあんな肉塊のような存在が発生したのか。
これは推測に過ぎないが、人骨にペットだった犬の骨を一緒に混ぜたのではないだろうか。
家の荒廃具合や子供部屋、もしかしたら交通事故か何かで一緒に亡くなったのかもしれない。
それで仲良かった子供と犬をあの世でも一緒に健やかに過ごせるようにと…。
あの家は邪気が濃かった。おそらく霊道にも近かったのだろう。
邪な霊に利用されてしまったのかもしれない。
「大事なパートナーだったのかな」
私にもそんな相手がいた。
7歳ぐらいのころ、祖父の家で一人で留守番をしていた時の事。
つまらず、物置を探索していた時に猫のような鳴き声がして、声のした奥の戸棚を見上げた。
猫とも犬ともいえないその生き物は、戸棚できらきらした目を輝かせながらこちらを伺っていた。
「わ、わんこ...?」
私はそう問いかけると、変な生き物は首を傾げ違うといわんばかりにこちらを見ていた。
触ろうとして手を伸ばそうとするも戸棚は高く、届きそうもなかった。
背伸びをしている私をみてその生き物はぴょんっと戸棚から飛び降り、私の前に進んだ。
「わあ~いいこ!」
幼い私が手を伸ばすと、じっと目をつぶって額を押し当ててきた。
それは柔らかな手触りだが、まるで空気のような軽やかさも感じた。
よく見ると額に星型のような文様があったのを覚えている。
しばらくすると、その生き物は外に駆けていってどこかへ行ってしまった。
私はその後、帰ってきた祖父に変な生き物の事を伝えるとどこか懐かしそうに祖父は笑った。
「それはね、お稲荷さまだよ。」
「おいなり...?あの、あまいやつ...」
「ははは、食べ物のほうじゃないよ。神様の使いのきつねのことなんだよ。」
「えー!かみさまの使い...?」
きらきら目を輝かせる私に祖父は教えてくれた。
祖父も子供の頃に同じような生き物をみたことがあるのだと。
「まだいらっしゃったんだねえ。玲もご先祖様のご利益があるのかもしれないね」
「ごりやく?なあにそれ」
「うちはね、陰陽師っていう悪いものを退治することを生業としてたんだ」
祖父によれば、先祖は遠い昔にそのような官職に就いていたらしい。
家系図のようなものを見せてもらったが幼い私にはよく理解が出来なかった。
だが資料の中に、同じく星形のものを見つけたので祖父に尋ねてみた。
「このお星さまはなあに?」
「これは五芒星とよばれるものでな。悪いものを遠ざけてくれるんだ」
そして次の日から、私が一人の時に必ずお稲荷様は現れるようになった。
私が電車の模型で遊んでいれば側にきてじっと見守るように丸くなっていたり。
庭で蟻が何かを運んでいるさまを一緒に見つめていたり。
おそらくは危なっかしい私を子守のように見ていてくれたのではないだろうか。
しばらくして祖父が癌を患い、あっという間に亡くなってしまった。
葬式のときも、通夜の時も、お稲荷様は物置の戸棚から動かなかった。
だが通夜の翌日の晩のことだった。
皆が寝静まったころ、トイレに行くために起きた私が廊下を歩いていたときのこと。
お稲荷さまが庭にいた。月明かりに照らされて、白く美しく輝いていた。
そしてその目線の先には、祖父がいた。いつも庭仕事をしていたときの作業着姿だった。
私は声をかけようとしたが、喉まででかかった言葉を押し戻した。
なぜだか、声を掛けたらいけないような気がしたのだ。
「ようやくお会いできました」
祖父がそうお稲荷様に語りかけ、まるで頷くようにお稲荷様は頭をさげた。
その光景を見ていた私を祖父はにっこりと微笑んで霧のように姿はなくなってしまった。
ハッと気づくとお稲荷様もいつの間にかいなくなっており、虫の鳴き声だけが鳴り響いていた。
翌日、私は昨日見た光景を家族に話したが夢でもみていたのだと言われてしまった。
悩みながらも物置にいくと、変わらずお稲荷様はいた。
「おじいちゃんはどこにいっちゃったの?」
私は尋ねてみた。
しかし、狐の顔はじっとこちらを見るも何も語ろうとしない、鳴こうとも。
だがその瞳はどこか優しく暖かかったのを覚えている。
それから祖父の家に行くことが少なくなると、ある日を境にお稲荷様を見かけることはなくなった。
物置はもちろんのこと、庭や畑、いっしょに蟻を観察した場所、すべて見回った。
来る日も来る日も探したが、見つけることはできなかった。
いつしか私は探すことを諦めてしまったが、そのかわりに不思議な光景を目にすることが多くなった。
まるでモヤのように通り過ぎる光や恐ろしい顔をした謎の影。
小さい頃は恐ろしくてたまらなくて、父によく泣きついていたのを覚えている。
今では見慣れてしまったがそれでも異形にまでなり果てた肉塊は怖かった。
「あ、そういえば藁人形、なんとかしなくちゃ」
おもむろにリュックから札の張られた箱を取り出し、床に置く。
中を確認すると相変わらずガタガタと震える黒く染まった藁人形が入っていた。
それを両の手で触れると、火玉のようなものがうっすらと浮かび上がる。
よくそれを見るとまるで複雑な糸が絡み合うように違う色の魂が混ざっているのがわかった。
そっと火玉に触れる。ゆらゆらと揺れるそれは陽炎のようで吹けば消えてしまいそうだった。
優しく指を入れ、解くように慎重に魂を選り分ける。
大きめの魂と、少し小さい魂に分けることができると夢をみるかのように脳裏に光景が浮かび上がる。
弟と同い年ぐらいだろうか。少年と黄金のように美しい毛並みの愛らしい犬が遊んでいる。
生まれた時から一緒で、寝るときも一緒。
ある日、少年が犬と散歩をしているときに大型のトラックが突っ込んできた―――
とっさに気づいた犬は少年を押して助けようとする。だが少年も同じことを考えていたのだ。
少年は犬を助けたかったし、犬は少年を助けたかった。
その想いが叶うことはなく彼らの命は果ててしまう。
最期を知った両親が彼らの遺骨を一緒にしたのだろう。それは決して悪しき思いではない。
ただ二人の想いが強すぎたのと場所に恵まれず邪気にあてられ変異してしまったのだ。
ぷるぷると震えるような二つの魂に私は語りかける。
「もう大丈夫。あなたたちはどこにでもいけるよ」
二つの灯が強く輝いたと思ったら、まるで霧のように消えていった。
消える間際に「ありがとう」と言われたような...気がした。
なんだか今までもこんな事をしていたような記憶が、デジャヴかのように感じる。
そう―――もっと遠い昔に―――
ほっと一息つこうとした私は大事なことを思い出した。
まだやるべきことが残っていることを。
相も変わらず黒い藁人形がそこにあった。だが邪悪な不気味さは消えていた。
肉塊を封じた時のように両の人差し指と親指を合わせ、他の指を織りなし言葉を紡ぐ。
指先に熱を感じると藁人形から黒い炎のような塊が現れた。これが邪気の正体だ。
邪気は様々な思念が陰の気に集約したもの。それ自体が意思をもち他の生命や霊体に干渉をすることで現世で顕現するのだ。
「さて、どうしたものか...。お前があの子たちを変異させたのだろう?」
黒い炎はそうだといわんばかりに揺らいだ。
「悪さをしないというのであればなにもしないよ。隠世にお帰り」
今度は微動だにしない。これは否定...なのだろうか。敵意はないようだが。
私は再び問いかける。
「まだいきたくはないのかい?」
黒い炎は揺らいだ。何かしら目的があるのかもしれない。
邪気の中には未練が故に堕ちた魂もあるのだそうだ。
どうしたものかと考えていると、黒い炎は私のすぐそばにぴたっと張り付くように近づいた。
「一緒にいたいの?」
黒い炎が揺らいだ。なぜだか気に入られたようだ。
しかし困った...本来であれば人に仇を成す存在なのでそのままというわけにもいかないのだ。
周りを見渡し、あるものをみつけた。できるかどうかはわからないが、それを手に取った。
子供の頃から大事にしていた祖父にもらったウサギのぬいぐるみだ。
私はハサミを取り出し、髪の毛を根本から何本か切り取りぬいぐるみの首の部分に結び付ける。
髪の毛は私の分身としての触媒になる。だから伸ばしている、いずれまた伸びるから。
「これ、入れるかな...少し汚れてるけど」
黒い炎はウサギのぬいぐるみに近づき、揺らぎを大きくした後すぅっ...と中に入っていった。
どうやら成功したようだ。変色するかなと心配していたのだが特に変わりはなかった。
「悪さしちゃだめだよ。いい子にしてること!守れる?」
ぬいぐるみはコクンと頷いた。
よしよしと撫でると、ぬいぐるみを抱き上げベッドに置いた。
なんとなく、そうしたい気持ちになったのだ。
―――こうして私は不思議な同居人を部屋に迎えることになった。
高校一年の春、不安と期待を胸に秘めて夜が更けていく。
これは世界に拒絶され、暗い道を孤独に歩むモノたちに寄り添う私の物語だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

