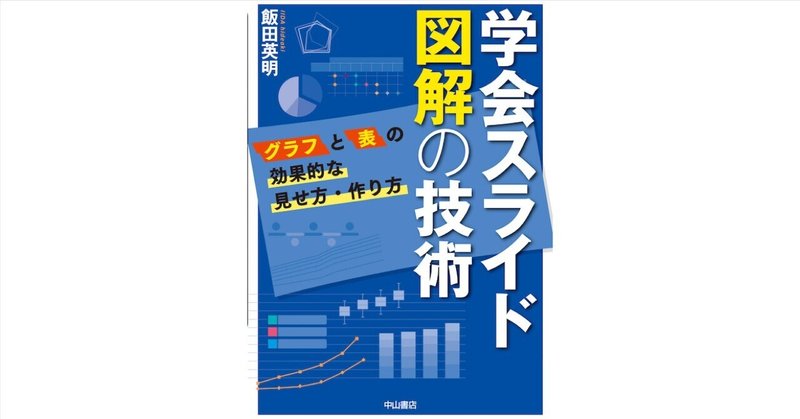最近の記事
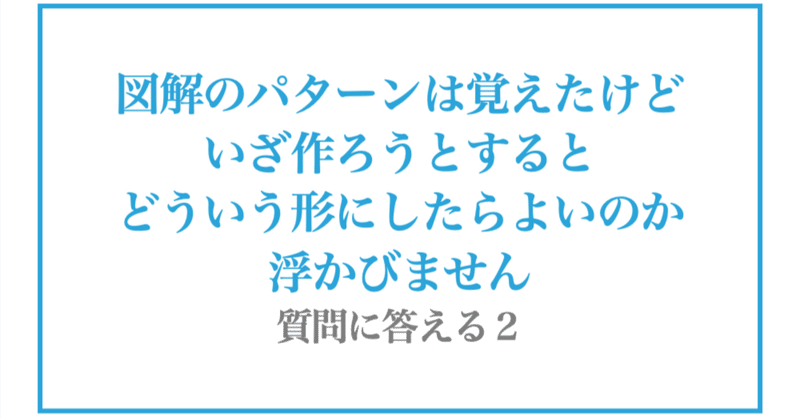
【標準図解】と【応用図解】「図解のパターンは覚えたけど、作ろうとすると、どういう形にしたらよいのか頭に浮かびません」〜質問に答える 2
いざ図解を作ろうとすると、形が思い浮かばない 図解に関する書籍やネットの記事では、身につけるべき図解としてフロー図やツリー図(階層構造図)といったいくつかのパターンが取り上げられています。それらは図解の一歩を踏み出すために役に立つものです。 ところがそれらを身につけても仕事で図を使おうとするとうまくいかないことがあります。少し複雑な内容を図にしようとすると、パターンに当てはめようとしても、具体的な形に落とし込めない。 またなんとか図解を作ってみたけれど、どうもしっくりい