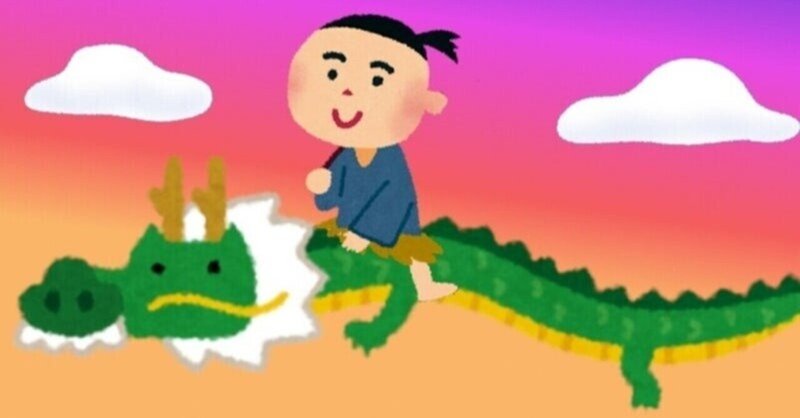
泉小太郎民話と蹴裂伝説
長野県の上田地域に小泉小太郎、松本地域に泉小太郎という民話が伝わっています。
この2つの民話は伝承されている地域が地理的に近いこと、題名が似ていることから、元々は1つの話だったのではないかという説があります。
以前の記事で、上田地域の泉小太郎民話について簡単に検討をしましたので、興味のある方は記事末のリンクを参考にしてください。
お急ぎの方のために、検討した内容を3行で整理すると、
1. ストーリーは三輪山の活玉依姫(イクタマヨリヒメ)の伝説の類型
2. 2つの別々な伝承が合わさったのではないか
3. 泉小太郎民話とは関係なさそう
という感じです。
そこで、今回は松本地域に伝わる泉小太郎のお話を紹介します。検討が多岐にわたるので、記事ごとにある程度論点を絞って進めていこうと思います。
逆に、やや消化不良になることが多いと思いますが、後で話が繋がるように努めますのでご海容ください。
泉小太郎民話の要約
長野県松本地域に伝わる民話の1つです。やや長いですが、松本平の伝説[1]から要約すると以下のようになります。ちなみに、この本には「仁科記による」とありますので、この内容の原典は仁科濫觴記※のようです。
※ 仁科濫觴記(にしならんしょうき)は、古代にこの地方の豪族であった仁科氏が編纂した記録。歴史や地名の由来などが記載され、内容の信憑性も高いとされる。
昔、松本平は湖で、犀竜(さいりゅう)が住んでいました。東方の高梨(現 須坂市高梨)には「千尋の池」があり、白竜王(はくりゅうおう)が住んでいました。
鉢伏山(はちぶせやま)で2人の間に子どもができ、日光泉小太郎と名付けられました。泉小太郎は放光寺山(ほうこうじやま)で成長しましたが、母の犀竜は小太郎の成長に従い、竜である我が身を恥じて湖に隠れてしてしまいました。
小太郎は母への思慕止みがたく、探し回ったところ、熊倉下田の奥宅入沢でようやく犀竜と再会しました。
犀竜は「私は建御名方神諏訪明神(タケミナカタノカミ/スワミョウジン)の化身である。この湖をつきやぶって水を落とし、人の住める平地をつくるのが念願である。」と言いいます。
そこで小太郎は犀竜の背に乗りました。この地は今も犀乗沢(さいのりさわ)と呼ばれています。2人はともに山清路(さんせいじ)の滝を乗り割り、水内(みうち)の橋下の岩山を切り破りました。すると、湖だった松本平は一面の沃土と化しました。
その後、犀竜は白竜王を尋ね、坂本の横吹の岩穴に隠れました。小太郎は有明(十日市場の川合)に屋形を建てました。
年を経て、白竜王と犀竜は小太郎と対面を果たします。白竜王は「自分は日輪の精霊、大日如来の化身なり。」と告げて、犀竜とともに佛崎の岩穴に入りました。
小太郎は「我は八峰瀬権現の再来なり。この里の繁栄を守護すべし。」と言って佛崎の岩穴に入りました。川合大明神(カワエダイミョウジン)は小太郎の功を稲へ祀るものです。
余談ですが、『小太郎は犀竜の背に乗り、ともに山清路(さんせいじ)の滝を乗り割り、水内(みうち)の橋下の岩山を切り破り』の部分がつとに有名で、(自分より年上の人なら分かると思いますが)「マンガ 日本昔ばなし」のオープニングで龍とその背に乗った子ども、これが犀竜と小太郎なんだそうです。
今回の記事の冒頭画像がそのイメージ画像です(笑)
物語の要点整理
何度読んでも「どこから発生したお話だろう」と興味深いんですが、お急ぎの方のために(笑)、(今後)検討したいポイントを挙げます。
■昔は松本平(松本〜安曇野にかけての松本盆地一帯。この地方で〇〇平という呼び方をする)一帯は湖だった。
■泉小太郎は、日光太郎泉小太郎という名で、父は高梨にいた白竜王、母は湖にいた犀竜である。
■白竜王は大日如来の化身、犀竜は諏訪明神の化身、泉小太郎は八峰瀬権現の再来である。
■犀竜は泉小太郎とともに、湖の水を抜き、人の住む場所を作った。
■白竜王と犀竜は水を抜いた後、佛崎の岩穴に入った。小太郎は有明に住んだ後、同じく佛崎の岩穴に入った。
■物語の各所に具体的な地名が入っており、場所の特定が可能。
湖の水を抜いて人が住める土地にするのに似た話は、日本各地にも、世界にもあり、一般に蹴裂伝説(けさくでんせつ)といわれています。上田地域のお話と同様に、泉小太郎のお話が完全オリジナルとは言えません。
また、諏訪明神の化身だとか、八峰瀬権現の生まれ変わりというフレーズから、この伝承が中世の神仏習合が盛んな時期に脚色されたか、その頃に成立したものだと考えることができます。
蹴裂伝説
最後に、蹴裂伝説について簡単に触れておきたいと思います。
蹴裂伝説とは、盆地や谷地形がどのようにできたかを物語として伝えたものです。主に「昔、湖だったところを、神様が山を割るなどして水を抜き、人が住める土地にした」というストーリーが展開されます。
日本に限らず、東アジアにも類型の伝承・伝説があることが知られており、これについて、ネットでアーカイブになっていた仏教説話大系[2]の説明が分かりやすかったので、下記に引用します。
初め湖だったところが、ある特別な力を持った人物によって切り開かれ人が住むようになったという伝説は、実はネパールだけのものではなく、同じような話はカシミール盆地にもあり、シルクロードのオアシス都市コータンにもあるのである。さらに広く見渡すと、日本にもいくつか伝えられている。信州の松本平、甲府盆地、九州の阿蘇火口原など、同じような地形の所に、この伝説が残っている。中国では有名な禹王の治水開拓伝説が類似のタイプである。
この型の話は、日本の学者によって蹴裂伝説(ケサクデンセツ)と呼ばれ、二、三の学者は「鉄器を用いての開墾や開拓を暗示している」と主張している。日本の伝承の中では、山を切り裂く時に鉄の鑿(ノミ)を使ったり、金属の精錬技術をもつ氏族とかかわりのある話になっているのである。
このように、類型の話が広い地域に分布していること、地形の成り立ちを伝えた話であること、鉄器や金属精錬技術を持った氏族との関わりが考えられることが特徴です。
長野県では、松本地域のものだけでなく、上田地域にも伝承※があります。またもや上田との類似が出てきましたね。
長野県は山々の合間にできた盆地に人が住んでいますので、蹴裂伝説が伝わる格好の地域といえるでしょう。伝承に出てくる地名も実際に残っており、松本〜安曇野〜大町にかけて、伝承に基づく立看板や銅像、神社が多数あります。
さらには、この地域にやってきた安曇族が、この地を開拓した時のことを伝えた話だという指摘もあり、底知れない広さと深さを感じてしまいます。
このあたりのことを今後検討していきたいと思います。
※ こちらは猫と鼠が出てくる。「鼠と唐猫伝説」や「唐猫伝説」と呼ばれる。
まとめ
今回は長文になってしまいましたが、松本地域に伝わる泉小太郎の民話のダイジェストと、関連する蹴裂伝説について、そのサワリを紹介しました。
サワリといっても、全てを把握しているわけではなく、伝承に埋もれた歴史の底知れない深さと、果てのない広がりを感じているといった意味です。
全てが明らかになる日は、果たして来るのでしょうか。
参考文献
[1] 高坂友喜. 松本平の伝説. 信濃郷土史刊行會, 1942.
[2] 仏教説話大系編集委員会. 仏教説話大系. 鈴木出版, 1982.
関連記事
■ 小泉小太郎民話【1/4】 ~ストーリーを考える~
■ 小泉小太郎民話【2/4】~後半のものがたり~
■ 小泉小太郎民話【3/4】~地名の由来~
■ 小泉小太郎民話【4/4】~泉小太郎との関連は?~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
