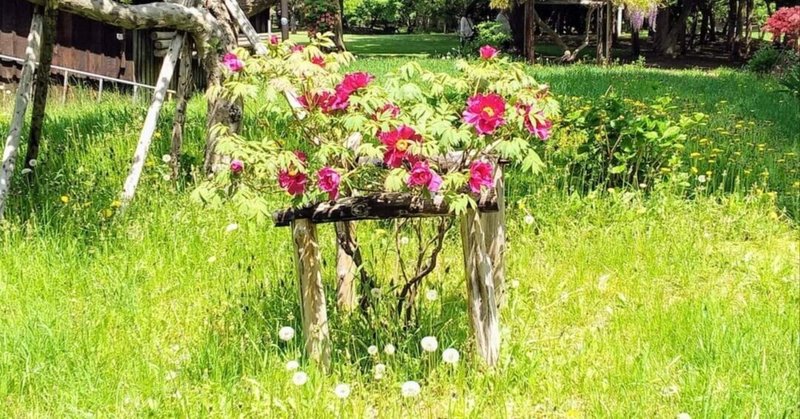
90.働き方改革と社会福祉連携推進法人
私が福祉の業界から離れていた2019年秋から2023年夏の間にこんな変化が起きていたのかと思うような、私には新発見があったので、そのことを簡単にお勉強してみます。
では、早速…。
2022年4月に社会福祉連携推進法人制度が施行されました。
2024年3月の段階で、北海道ではないですが、全国的には21法人が実践しています。
政府の社会保障・働き方改革本部は2040年を目標に、医療と福祉サービスの改革を進めています。
その中で、社会福祉連携推進法人制度は医療法人や社会福祉法人の経営統合、運営共同化を進めることを目的にしています。
介護施設の大規模化推進による医療福祉サービス改革や、医療・介護の連携による地域レベルでの最適化を推進しています。
2020年6月に“地域共生社会の実現のための社会福祉法の一部を改正する法律”が公布され、同法に基づいて2022年4月に社会福祉連携推進法人制度が創設されました。
社会福祉連携推進法人は地域共生社会の実現に向けて、地域ニーズに対応した新たな取組の創出と、その担い手となる福祉人材の確保と育成などと同時に経営基盤の強化を進めていくという観点から、地域の福祉サービス事業者間の連携や協働の為のツールとして有効に活用されることが期待されています。
これまでは、規模の大きくない社会福祉法人が人的そして資金的な課題を克服する為の手段として、“法人間連携”と“合併・事業譲渡”が活用されてきました。
この2つの手法の中間的なアプローチとして社会福祉連携推進法人制度があります。
社会福祉連携推進法人は、主に3つの目的があることが社会福祉法に定められています。
①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進すること
②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供すること
③社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること
具体的には地域福祉支援業務、災害時支援業務、経営支援業務、貸付業務、人材確保等業務、物資等供給業務…この6つの業務のうち、1つ以上を実施することが求められています。
気をつけないといけないのは、連携推進法人は社会福祉事業を行ってはいけないということですが、一定の要件の中では、限られた範囲の社会福祉事業であれば認められる可能性があるようです。
いつものことながら、ややこしい…。
とにかく、基本的には上記6つの業務を通して、以下のようなことが可能になると期待されています。
法人の独立性を保ちつつ、法人間連携よりも強固な連携が可能になります(合併では法人の独立性が保たれません)。
連携推進法人内の社員である貸付対象社会福祉法人に対して貸付が可能になります。
大きな経営課題となっている人材確保においても、共同採用や社員間の人事交流等が可能になります(法人間連携よりも更に強力に広範囲に実施できる可能性が高くなります)。
社会福祉法人やNPO法人がそれぞれ社員になって、新たに一般社団法人としての連携推進法人を設立するイメージです。
あくまでも合併ではなく、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能になると考えられます。
社員は医療法人、一般社団法人、NPO法人、株式会社など…、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する方や社会福祉法人の経営基盤を強化する為に必要な方であれば、法人格は問われません。
ただし、過半数が社会福祉法人であることが条件になっています。
社員が2法人なら2つとも社会福祉法人でなければなりませんし、社員が3法人なら2法人以上が社会福祉法人でなければいけないということです。
社会福祉連携推進法人は、個々の社会福祉法人では実施できなかったり、非効率であったりする業務について、合併や事業譲渡などの統合とまではいかない、中間的な事業形態で対応することができます。
このように社会はどんどん変化し、働き方改革も進んでいます。
現在は様々な業種の企業で、政府が推進する働き方改革への対応が行われています。
福祉業界では長時間労働や職務環境による精神的疲労、低賃金などの問題の為、慢性的な人手不足など多くの問題を抱えています。
そのことから、働き方改革を推進することで、福祉業界が抱える人手不足の解消や離職率の低下、採用率の悪さなどの改善が期待できると考えられています。
その結果、福祉業界全体の生産性の向上がこれからの少子高齢化による人口減少社会には重要になります。
現在の福祉業界は、ずっと続いていることなのですが、深刻な人手不足が問題とされています。
福祉の現場では、“きつい”、“危険”、“汚い”、“暗い”、“臭い”、“給料が安い”といった厳しい労働環境のイメージがつきまとっていることが問題視されています。
あまりに散々なイメージですが、確かにそういう雰囲気の事業所…事務所が多いのは確かです。
このように福祉職を目指す人のモチベーションを損ねるネガティヴな“K”がたくさんあるのは確かですが、ポジティヴな“K”もあります。
福祉職に必要とされる力は、“好奇心”、“観察力”、“洞察力”、“行動力”、“向上心”、“謙虚な心”といったものです。
そして、“希望”を持ち、人との繋がりに“期待”したり“感謝”したり…、その“可能性”に“感動”、“感激”することもあります。
そして、何かをやり遂げた時には“快感”があります。
良くも悪くも“K”がいっぱいです。
意識の持ち方次第で仕事への姿勢が変わるということです。
この意識改革もまた働き方改革の1つと言えるでしょう。
ひとりひとりの、その結果、組織の意識改革ができれば自然と労働環境が改善されると思いますし、職員が働きやすくなり業務の効率化に繋がります。
福祉職は長時間労働が起こりやすい職場ですが、この問題の解消にも繋がると考えられます。
また職員の満足度や生産性の向上にも繋がります。
ただ、今でも福祉職は社会的評価が低いのではないかと考えられます。
これからの時代、絶対に必要なものであると理解していても、なぜかどこか見下されているというか…。
その理由の1つは、例えば介護については家族が行うものという認識が日本には根付いていて、介護職に対する意識が低いからだと考えられます。
現在は核家族化や介護する家族の高齢化の問題もあり、従来は身内が行っていた介護を行う“家族の代理”という見方をされていることもあります。
そのことから、介護職は専門性としては社会的な評価が低いのだと思います。
このような認識がされがちだから、ヤングケアラーなどの問題が派生してしまいます。
他にも介護職は厳しい労働環境であるということも人手不足の原因です。
夜勤などを含む長時間労働による負担や、介助などで腰を痛めたり、職務環境による精神的疲労を引き起こす人も多いです。
介護サービスの向上の為には、これまで通りだと見通しがつかないのではないかとも思いますし、大幅な業務の改革が行われない限りは難しいのかなと思います。
介護職に限らず、福祉職は賃金の安さも含め、厳しい労働環境ということもあり、離職率が高く、採用率も低いという深刻な人手不足の状態が長らく続いています。
また、日本は少子高齢社会を迎えています。
この先、高齢者が増えて介護する若い人が減少すると、人手不足の問題は更に深刻化します。
人手不足の背景には、重労働な仕事内容に対する賃金の安さも原因の1つです。
要介護者の数に対する支援側の働き手不足も採用難の原因になっています。
この先、日本ではもっともっと要介護者の数は増え続けます。
それに対して、介護職の採用が全く追いつきません。
そのことから、需要と供給のバランスが崩壊している状態です。
なので、政府は働き方改革を推進しています。
ICT(情報通信技術)を導入し、パソコンやタブレット、アプリなどで入手したデータをネットワークを通じて多くの人と共有できるようにしようとしています。
これにより、業務効率化の推進やロボットやAIなどの現場活用による労働環境改善が期待できます。
ICTを介護の現場に導入することを厚生労働省も推進していて、利用者の介護状況や会議内容の記録をデータ化して全員で共有する仕組作りが進んでいます。
従来は紙で行っていた書類の管理や記録をデジタル化することで、大幅な業務効率化に繋がります。
紙で事務作業を行うと、管理の為に手間がかかるだけでなく、保管の為の場所も必要になります。
介護記録を自動化することで、介護職員の手間を大きく省くこともできます。
デジタルなことを苦手とする職員もいるかもしれませんが、音声認識機能や紙で書くのと同じ感覚で操作できるタブレットなど、機械が苦手な人も使いこなせる製品も登場しています。
介護職の場合は、経営競争を意識したサービスの拡充が長時間労働や重労働を引き起こしている可能性があります。
その為、サービスの拡充よりも、まずは福祉の理念に沿ったサービスを貫いて、負担のかかる業務の長時間化、重労働化は削減する必要があります。
その上で、社会福祉連携推進法人です。
2030年に向けて高齢者人口が増加し、生産年齢人口が大幅に減少することが予想されています。
このような人口動態の変化に加えて、地域の共同体の機能が脆弱化しつつあるといった社会構造の変化により、子育てや介護、生活困窮などに対する福祉のニーズはますます複雑化し多様化すると予想されています。
社会福祉法人の数は年々増加していて、サービスも多様化しています。
しかし、人手や設備の不足などにより、供給が間に合っていないことが問題視されています。
そこで、社会福祉の現場を円滑に運営できるように、社会福祉法人の連携と協働が推進されたということです。
社会福祉連携推進法人が行う業務は上記した通りで、地域福祉支援業務、災害時支援業務、経営支援業務、貸付業務、人材確保等業務、物資等供給業務の6つがあります。
地域福祉支援業務は“地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援”に該当します。
業務内容については、 地域住民の生活課題を把握する為のニーズ調査の実施、ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供、取組の実施状況の把握と分析、地域住民に対する取組の周知・広報、社員が地域の他の機関と協働を図る為の調整などがあります。
地域の課題を掘り下げながら、ニーズに合った企画を立案する業務が、地域福祉支援業務です。
災害時支援業務は“災害が発生した場合に、他の社員と共同して、福祉サービスの利用者の安全を確保するための支援”に該当します。
業務内容については、ニーズの事前把握、BCPの策定や避難訓練の実施、被災施設に対する被害状況調査の実施、被災施設に対する応急的な物資の備蓄・提供、被災施設の利用者の他施設への移送の調整、被災施設で不足する人材の応援派遣の調整、地方自治体との連絡・調整、災害時支援業務の一環として被災地への応急職員の派遣や他の施設への移送などがあります。
BCPの策定には感染対策も含まれます。
避難所など被災者が集団生活を送る場所では、衛生面の課題も多く、感染症が流行しやすくなります。
食事や水分を確保し、室内やトイレ、屋外の衛生環境を整えることが大切です。
また、こまめな手洗いや手指消毒、軽い症状であってもマスクを着用するなど、感染を広げない為の取組も求められます。
こうした災害時の健康維持や感染予防に対する支援も、社員の大切な業務です。
経営支援業務は“社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援”に該当します。
社員に対する経営ノウハウなどに関するコンサルティングの実施、賃金テーブルの作成などの人事・給与システムに関するコンサルティングの実施、社員の財務状況の分析や助言、社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援、社員の特定事務に関する事務処理の代行などです。
知識やノウハウを共有することで、業務の効率化アップが期待されます。
そして、社会福祉連携推進法人では、社員である社会福祉法人への貸付を行うことができます。
建物の修繕、軽微な改修、従業員の採用、処遇改善に関する費用などが想定されます。
人材確保等業務は“社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修”に該当します。
具体的には、社員合同での採用募集、出向等社員間の人事交流の調整、賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整、社員の施設における職場体験、現場実習などの調整、社員合同での研修の実施、社員の施設における外国人材の受け入れ支援などです。
これらの業務によって、人材を確保する為に必要な調整や研修が行いやすくなると考えられています。
物資等供給業務は“社会福祉事業に必要な設備または物資の供給”などの業務を行います。
紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品を一括調達、介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器を一括調達、介護記録の電子化などのICTを活用したシステムを一括調達、社員の施設で提供される給食の供給などです。
従来、物資の調達は事業所ごとの業務だったので、連携によって一括で行われると業務の負担が軽減されます。
社会福祉連携推進法人制度を導入することで、介護人材の採用・育成の連携が可能になります。
社会福祉の現場で深刻な問題になっている人手不足も、社会福祉連携推進法人によって緩和が期待できます。
中小規模の社会福祉法人では目の前の業務に追われて余力がなく、人材の確保と育成にまで手が回らない現状があります。
社会福祉連携推進法人制度により、グループ全体の介護人材の採用・育成の担当者を設けることで、事業所ごとに行われていた人材の採用や研修などが合同で行えるようになり、負担が大幅に軽減されます。
業務を効率化しながら必要な人材を確保・育成できるようになるので、とても大きなメリットになると考えられます。
連携することによって得られた規模を、各社会福祉法人の自治を保ちながら得られることも大きなメリットです。
備品の一括購入や災害時の支援なども、グループ規模で行えるようになるので、各法人での余力が生まれやすくなります。
各法人に余力ができると、提供するサービスの質の向上が期待できるようになります。
地域社会や時代の変化に合わせた新しいニーズにも対応しやすくなり、柔軟に適切なサービスを提供できるようになると考えられます。
地域には様々な人が暮らしていますし、多様なニーズが存在します。
従来のやり方では難しかったことが、社会福祉連携法人制度によってきめ細やかなサービスを提供できるようになると考えられます。
社会福祉の現場では、人手不足による職員の疲弊、人材の定着化にも悩む事業者の方も多いです。
そこで社会福祉連携推進法人制度の活用によって、負担が緩和できることが期待されます。
支え合い、つながりこそが、これからの時代の変化に対応する為の最重要なことになると理解したところで、本日のお勉強を終了します。
写真はいつの日か…札幌市内で撮影したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
