
先生のこの言葉はサインかも
子どもの発達が気になる年ごろって
2~3歳ごろが多い印象だけど
私の場合は、長男が年中の時。
「遅かった」とは
1ミリも思っていない。
でも、広汎性発達障害という
診断が出てから当時を振り返ると
2歳児クラスの時の担任の先生が
たくさんの「発達が心配」のサインを
送ってくれていたんだと思う。

長男が通っていた保育園では、
登園後に荷物をロッカーに入れて
コップやタオルを出して、
それが終わったら
“朝の集い”までは自由タイム
という流れだったけど、
長男は登園後、
真っ先にすることがあった。
それは、
教室を入ってすぐ左手にある
ラックに掛かったハンガーを整え
その本数を数えること。
たとえそれが、
“朝の集い”の直前に登園した日でも
ハンガーを整えてからでないと
みんなの元へ行かないのだとか。
他にも、コレはサインだったと思う。
「困っていても言ってきません」
例えば、服が上手く着られない、
トイレに行きたいけど言い出せない
今、何をする時間なのか分からない
などなど。
「せんせーっ」と
声をかけてくれないから
「あれ?手が止まってるよ」
となって、やっと気づくそう。
3歳児クラスまであと数か月、
という時期なると
毎日のように
(記憶ではそれくらい頻繁に)
「幼児クラスから担任が減るので
自分から声をかけてくれないと
困るんじゃないかと心配です」
「ひとりひとりに目が
行き届きにくくなるので
集団でやっていけるか心配です」
などと言われていた気がする…
3歳になりたての頃、
小児科の先生にも
「お母さんが気になるなら
言葉の先生を紹介するよ」と
さり気なく言葉の遅れを指摘された
と思うことはあった。
「あなたの子の発達が心配だ」と言うと
障がいというネガティブなイメージが先行し
先生の言葉を受け入れられず
怒ってしまう人もいると思うし、
過度に心配し過ぎて辛くなる人もいる。
それに、専門医でもないから
いい加減なことも言えない。
だから、保育園や小児科の先生は
ぼんやりとしか言えないし言わない。
でも親は、
集団の中のわが子を見る機会が少なく
特に母親は、子どもの思いを
言葉以外からも分かってしまうから
「コミュニケーションに課題がある」
と感じにくかったり、
きょうだいがいても、保育士さんほど
一度に大勢を見ることもないので
目が行き届き、その子に合わせた
お世話ができてしまうものだと思う。
だから、いろいろ気づきにくい。
そして、集団生活に入り
つまずくことが増えて初めて
発達が気になりだしたりする。

「サイン」を受け取ったとき、
「だから発達検査を受けよう」
と言いたいわけではなくて
今困っていることや、
心配されていることに対し
「どう対処しようか」ということを
考える方が先だと、私は思う。
そして個人的には、
自分で気づいたタイミングで
動けてよかったと思う。
先生に「発達の不安」を
指摘されていたら
不安な気持ちで過ごす期間が
長くなっていたと思うし
先生に「心配」と
言われていたことには、
具体的な対策を取っていたから
多少の違和感は感じつつも
あまり不安になり過ぎずに
できることに目を向けてこれた。
先生にこう言われた…
「これってサインなの?」
「ぶっちゃけ何が言いたいの?」
と思ったら、
心配なら、先生にもう少し
突っ込んで聞いてみてもいいかも。
あくまでも、「心配なら」。
違和感の答え合わせをしたいなら。
聞いてみよう。
心の準備が必要なら
下記のメルマガなどから
私にメッセージを。笑
※診断よりも大切なことを
お伝えできると思います。
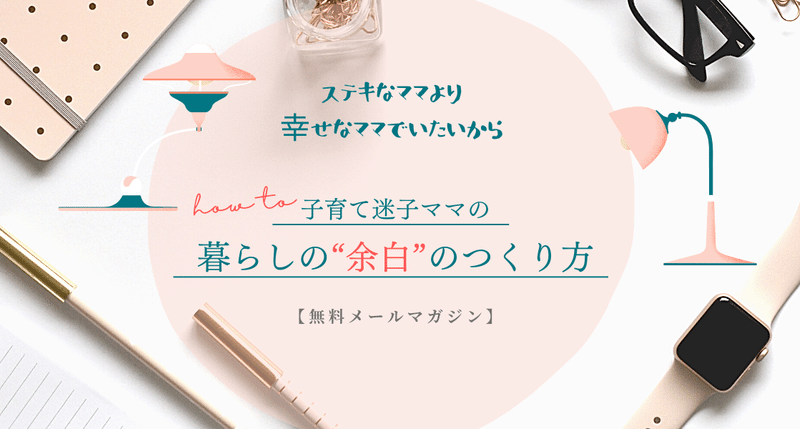

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
