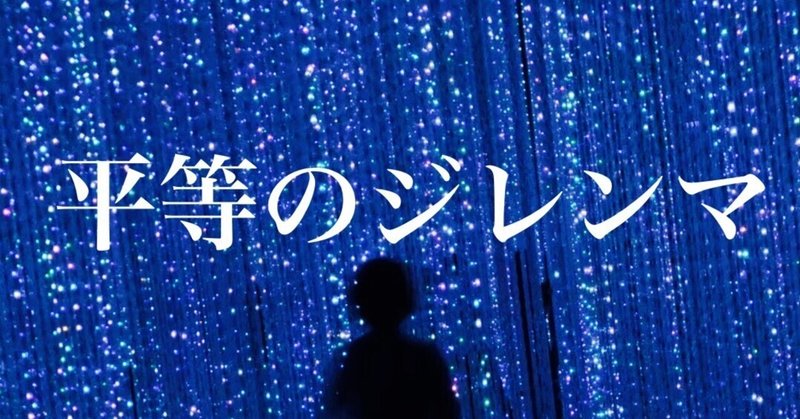
平等のジレンマ
ジェンダーギャップ・男女平等が騒がれている昨今
とあるシミュレーションを行ってみた。
肌の色が青い人種と赤い人種、この2種類の人種のみが存在するというA国を仮定しよう。
A国で医者になるには厳正な国家試験を通過する必要があり、現在の医者の人種割合は
青色人種:赤色人種=4:6 である。
すると青色人種が、医者の割合が4:6であることに不満を抱き、青色人種差別であるという主張を始めた。
しばらくするとA国内で青色人種がBLM (Blue Lives Matter)運動を初め、過激化した一部が暴動・デモを起こした。
この運動に呼応する形でA国政府は法整備を進め、A国の医者の人種割合を平等の5:5と定めた。
するとA国内で何が起きたか。青色人種の医者の受診率が激減したのだ。さらに青色人種の市民までもが、赤色人種の医者に診てもらいたいということで、担当医を変えて欲しいという事案まで発生することになった。
理由は簡単なことだ。本来は国家試験に通過する実力を持ち合わせていない青色人種が、法整備という外部的要因によって繰り上げ合格となったことで、市民は医者としての実力を確実に兼ね備えている赤色人種に診てもらいたいという心理が働いたのだ。当然のことだ、自らの命及び健康が関わっているのだから。
その影響で、法整備前から国家試験を通過しており、確実な実力がある青色人種の医者までもが色眼鏡で見られることになり、結果として全体的な青色人種の医者の受診率が激減したのだ。
この国の話に戻そう。ダイバーシティ=多様性という言葉を金科玉条の如く掲げ、企業の幹部割合を男女で定めるといった動きもある。果たしてそのような外部的要因を加えて平等を達成しようとした時に発生する新たな”不平等”が検証されているのか。
平均的にその企業の女性が男性よりも、貢献度並びに企業の利潤を最大化させることに長けていた場合、男女の幹部割合を定めることによって、本来は幹部にふさわしい女性が幹部に昇格できないことによる企業全体のインセンティブ低下は自明の理である。
企業への貢献度並びに利潤を最大化させることができるならば、極端な話、幹部が全員女性でも男性でもLGBTQの方々でも構わないはずだ。
国会議員も同じだ。『人道的・倫理的に必ず踏み外さず国益を最大化させることができる』その者が国会議員になるべきであり、女性・男性・LGBTQで枠組みを設けるのは愚策極まりない。そんなことは関係ない。
しかし現実の社会ではLGBTQの方々を侮蔑する愚か者がいる。また企業で女性がなかなか出世できない現実も理解している。であるならば国の根幹である教育を改革するべきである。義務教育課程での倫理・道徳の中身を抜本的に見直し、LGBTQ“だけど”平等という教え方ではなく、人類は平等であるという原点の教えをより強固にするべきだ。
付け焼刃のような外部的要因によって“外見的”平等を達成しようとするパフォーマンスの偽善的愚かさを一人でも多くの人に理解してほしい。
最後まで読んでいただきありがとうございます。私の癖の強い記事が良かったな〜という方は いいね❤️コメント🖋フォロー🌹していただけると嬉しいです😎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
