
【宇田川拓也氏・解説全文公開】『このミス』1位『頰に哀しみを刻め』(S・A・コスビー 著、加賀山卓朗 訳)
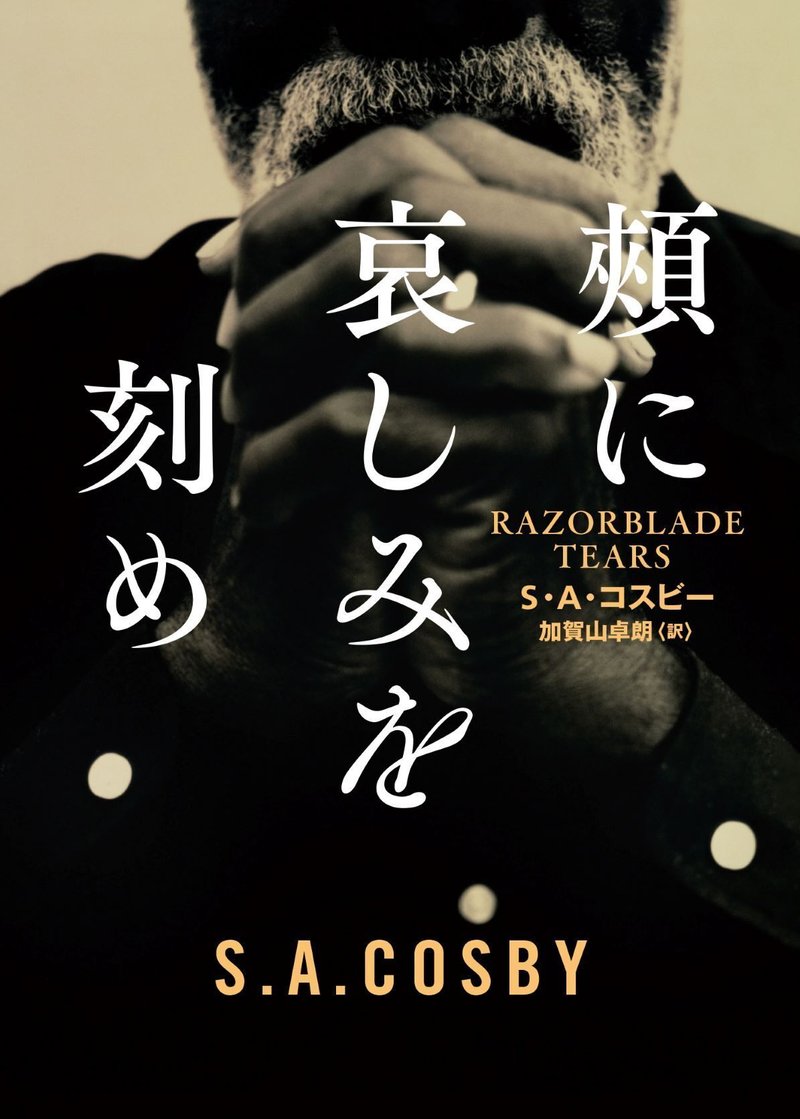
『頰に哀しみを刻め』解説
宇田川拓也(ときわ書房本店)
犯罪という刑罰を科せられるべき行い、あるいはそれを調べるための行動を通じて、人間と世界の有りようを描いた小説。いわゆる「犯罪小説」は、一説には『千夜一夜物語』にそのルーツが見て取れるともいわれているそうだ。それほど長きにわたり、創作者の意欲を掻き立て、読む者を惹きつける理由を改めて考えてみると、ひとつはそこに「正しさとはなにか」を探究する要素が含まれているからではないだろうか。
正しさ、正義、正論といったものは、絶対的なものではなく、必ずしも望ましい結果をもたらすわけではない。力や集団によって容易に歪み、捻じ曲げられもするし、都合よく利用され、ひとを深く傷つけることもある。加えて、当人も囚われていることに気付かないほどいつの間にか強く固く縛りつけ、盲目的にしてしまう危険を孕んだ、じつに厄介なものでもある。犯罪小説では往々にして、人間の救いがたい愚かさや卑劣さ、この世界の黒く残酷な一面が詳(つまび)らかにされるが、そうした内容を通じて作者は時代や環境に左右されない在るべき正しさを様々な形で問い直し、読者はそれらをページから汲み取り、正しさという不確かなものの補正に充ててきた。犯罪小説では非情な極悪人だけでなく、あえて罪を背負うことで譲れない道義を貫き、護るべきひとに手を差し伸べるような人物も数多く描かれてきたが、それもまた損得だけでは量れない正しさを探究する過程で生まれたものだといえよう。
さて、そうした犯罪小説の流れの最前線にアメリカから颯爽と現れたのが、S・A・コスビーだ。二作目となる著書にして出世作となったBlacktop Wasteland(二〇二〇年)は、このジャンルの著名な作家陣から絶賛され、有力紙の年間ベストブックにも選出。さらには、Mystery Readers International のメンバーによって選ばれるマカヴィティ賞の最優秀長編賞、ミステリ創作者と愛好者が集う年に一度の世界大会バウチャーコンにて選ばれるアンソニー賞の長編賞、雑誌Deadly Pleasures 主催によるバリー賞の長編賞など、複数のミステリ文学賞を立て続けに射止めるなど、大変高く評価された。日本でも二〇二二年に『黒き荒野の果て』の邦題でハーパーBOOKSの一冊として刊行されるや大好評を博し、年間ミステリランキングにも入選を果たしている。
本書『頬に哀しみを刻め』は、そんな注目作家の名声をさらに押し上げることとなった三作目の著書Razorblade Tears の全訳である。
物語のそもそもの起点となる出来事は、リッチモンドのダウンタウンで起きた銃撃事件。犠牲となった男性ふたり──黒人のアイザイア・ランドルフと白人のデレク・ジェンキンスは同性婚のカップルで、執拗に銃弾を射ち込むその念入りなとどめの刺し方からプロによる犯行と思われた。どうやら警察によると、ジャーナリストだったアイザイアには以前から殺しの脅迫状が届いていたらしい。
本作で中心となる人物は、このふたりの被害者の父親だ。アイザイアの父親で庭園管理会社を営むアイク・ランドルフ、そしてデレクの父親である無職のバディ・リー・ジェンキンス。ともに元囚人であり、若かりし頃の自分たちのように手を汚すことも辞さない暴力で相手を捻じ伏せ、排除するのではなく、まっとうに生きて社会的地位を確立した優秀な息子を愛し、誇りに思うも、我が子が同性愛者という現実を前に大きな溝を埋められずにいた。そこに突然降りかかった、息子が殺害されるという信じがたい悲劇。父親であるふたりには、尽きせぬ哀しみと涙、悔やんでも悔やみ切れない後悔、そして息子たちの最愛の幼い娘──孫のアリアンナが残される。
葬儀から二カ月後、進展しない警察の捜査を見かねたバディ・リーは、アイクの会社を訪ね、ふたりで犯人を捜し出すことを提案する。だがアイクはその申し出を断る。かつて元ギャング〝ライオット〟・ランドルフとして知られたアイクは、歯止めが利かなくなる暴力の恐ろしさについて知り尽くしていた。そして行動を起こすことで、刑務所を出た十五年前に〝ライオット〟と決別し、正しく生きようともがいてきたこれまでの努力が水の泡となり、平穏な暮らしが終わりを迎えかねないことも。
ところが、そんな強い自制の気持ちも吹き飛ぶような事件が起こる。アイザイアとデレクが眠る墓が何者かに破壊され、酷い侮蔑の言葉で穢されていたのだ。アイクはバディ・リーの話に乗ることを決意する。犯人を見つけ出すだけでなく、必要ならば血を流し、相手の命も絶つ覚悟とともに──。
本作は『黒き荒野の果て』と同じアメリカ南部のヴァージニア州を舞台にしているが、足を洗い堅気となった主人公が訳あって犯罪の世界にいま一度足を踏み入れることになるシンプルな筋立て、複雑な心情を様々に映す家族小説と息を呑むスリリングな犯罪小説を融合してみせる抜群の人物造形と描写力、黒人の目から見た差別や格差ゆえの生きづらさといった厳しく根深い現実も同様に引き継がれている。
そのうえで、本作ならではの最大の特色を挙げると、ジェンダーやLGBTQ+といった問題に真正面から取り組み、真相にも関わるほどの極めて重要なテーマとして扱っている点だ。犯罪小説でもこれまで、キャラクターの色づけや現代を表現する一環として、こうした問題に触れている作品はいくつもあった。けれど正直、正しさを問い直し探究する要素を持つこのジャンルでの扱われ方としては、その多くが片手間程度だった印象は否定できない。たとえば創作者が物語内の時間をどれだけ遠い過去の時代に設定しても文句はないが、いま作品を発表するとして、そこで描かれる古びた価値観や社会性、間違った道徳に対しての問題提起が一切なかったとしたら、それは失錯というしかない。S・A・コスビーは、現代の犯罪小説作家のなかでも、その重要性を誰よりも意識し、鋭く捉え実践している書き手といえよう。
さらにコスビーの美点を挙げるなら、今日的なテーマの扱いに傾注しつつも、犯罪小説としての様式と山場を損ねるような愚を犯していないことだ。
目の前に脅威が迫り、命に代えても護らなければならない者がそばにいるとき、採るべき方法はひとつしかない。飛び交う銃弾と爆炎がページを焦がすかのごときクライマックスの死闘は、亡き息子たちへの懺悔と贖罪に彩られた哀しき父親たちの挽歌であり、無法を貫いても護り抜き決着をつけるために戦うその雄姿には、胸打たれずにはいられない。筆者はこのすべてを吹き飛ばし、辺り一面が焦土と化すような戦いの激しさに、いまだ世界に蔓延し、懲りることなく無辜のひとびとを傷つけ苦しめ続ける、差別的で不寛容な醜い「正しさ」に向けられた、コスビーの憤怒を重ねて見てしまった。
そろそろ紙幅も少なくなってきたが、本作の注目すべき読みどころは、まだまだある。白人・黒人や父親・息子といった相似する人間関係の巧みな使い方、アイクの内側で動き出そうとする凶暴な〝ライオット〟の不穏な気配、犯人捜しの過程で不寛容な世間と同じく自身もまた息子にとっての生きづらさの一因だったことを思い知る痛恨の場面、人間的には大いに問題ありだが憎めないバディ・リーのキャラクター、ある登場人物のあまりに衝撃的な告白、哀しみの涙が頬を切り刻むカミソリの刃のようだと喩える秀逸なタイトルなど挙げていけば切りがないが、ぜひこうした箇所にも刮目していただきたい。
二〇二〇年代の犯罪小説が目指すべき方向性を見抜き、早くも到達したひとつの完成形といっても過言ではない本作は、『黒き荒野の果て』に続いて、マカヴィティ賞、アンソニー賞、バリー賞を受賞。同一作家が二年連続で三賞を獲得するという快挙を成し遂げ、さらにアメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)の最優秀長編賞にもノミネートされた。まだデビューしてから三作目を上梓したばかりの新鋭であることを考えると、コスビーがいかに破格で将来有望な作家であるか、よくおわかりいただけるだろう。これから一体、どれほどの活躍を見せてくれるのか。クラシックの風格と現代的なディテールに加え、今日的な問題にも果敢に切り込む、心振るわせる物語でアメリカのみならず世界の犯罪小説シーンを大いに盛り上げていただきたいものである。
最後に、本稿執筆時点でのコスビーの今後の動向について紹介しておこう。
二〇二三年六月、本国にて新作All the Sinners Bleed の刊行が決定している。長年FBI捜査官として勤めた主人公が故郷の町に戻り、その地で初めての黒人保安官となる内容で、人種差別がまかり通る閉塞的なコミュニティでの犯罪が描かれるようだ。いずれこの作品も翻訳刊行されることを切に願っている。
【好評発売中既刊】
【関連記事】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
