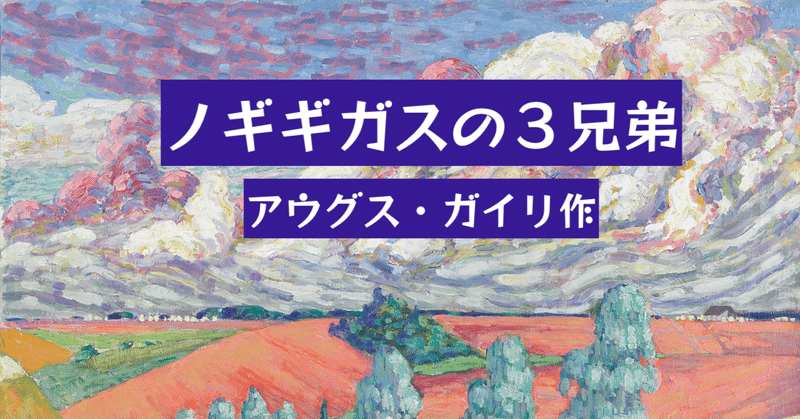
[エストニアの小説] 第2話 #10 猿狩り (全12回)
プースリクの農場の近くに雑木林があった。そこに着くと、猿はひとっ飛びでカバノキの枝に乗り、大きく目を見開いて追っ手の男たちを見た。男たちは木の下に立って、どうしたものか困惑するばかり。
「きくんだ、このワルが!」 ヨーナタンが叫んだ。「お願いだ、降りてきてくれ! 頼むから降りてきてくれ! 降りてこいと言ってるんだ!」
「家に戻って梯子を取ってこよう」 ペトロが提案した。
「それしかないな」 ヨーナタンが同意した。
「腹が減れば降りてくるだろう」と、パウロ。
「じゃあ、何週間も待つのか、猿の腹が減るまで」 ヨーナタンが反対した。
最後には、みんなで梯子を取りに家に戻った。ところがヨーナタンが猿を追って木に登ると、猿はリスのような素早さで、隣りの木にジャンプした。ヨーナタンはぶつぶつ言いながら木から降り、隣りのカバノキに梯子をかけた。ところがヨーナタンが木のてっぺんに着いて猿に手を伸ばすと、猿はサッと隣りのカバノキに乗り移った。
「これじゃダメだ」 パウロが文句を垂れた。「ミカはおまえを怖がってる。いつも怒ってばかりで、あいつに好き勝手してるからな。優しい言葉で声をかけねば、ていねいに頼むんだ」
そしてパウロは自分でやってみせた。猿にへつらい、チュチュチュッと舌を鳴らし、口笛を吹き、パチンと指を鳴らし、砂糖を見せ、お願いだからと頼みこみ、近づこうとした。パウロが懸命にお願いしながらカバノキのてっぺんに近づくと、そのとたん、ミカは隣りの木に飛び移ってしまった。
「こいつ、捕まらないぞ」 パウロが梯子を降りながら文句を言った。「待つしかないな、腹が減って降りてくるまでな」
「そうだな、このおいぼれが。おまえは待つだろうが、オレはいやだ」 ヨーナタンが怒りで真っ赤になって吠えた。「オレは50ルーブルこいつのために払ったんだぞ。そんだけの金を、風まかせで木にぶら下げておくわけにはいかない。ミカを捕まえて下に降ろすんだ」
「じゃあ、おまえがやれよ!」 怒ったパウロが、ヨーナタンに梯子を投げつけた。「俺はこんなならず者の扱いは知らん。こいつはオオライチョウみたいだ。誰も近づかせない。悪魔だってこんなに頼んだりなだめすかせば降りてくるさ、だがこいつときたら、降りてきやしない。こいつの口にシロップを注ぐか、魂を差し出すしかない!」
そのときには猿狩りの大騒ぎで、村の人たちが大勢集まってきていた。男たち、女たち、子どもたち、みんな空を見上げて、カバノキのまわりをあっちへこっちへと跳ねまわり、興奮して叫び声をあげていた。どの人も猿の大胆不敵さに、異様さに、その服に、買われたときの代金に驚きをあらわにしたが、誰ひとり、猿を下に降ろす方法を提案しようとはしなかった。
「天の神様が雷を鳴らして稲妻を光らせれば、あの猿は降りてくるんじゃないか」と誰かが言った。
「雹(ひょう)でも降れば、降りてくるだろう」と別の誰か。
そしてもう一人が、銃をもってきて猿を音で脅せば、言うことを聞いて、降りてくるだろうと言った。最後の提案はヨーナタンを激怒させた。そう言ったおやじのところに飛びついていった。と、ニペルナーティが突然、大声でこう言った。「簡単なことだ、木を切ればいい。猿はこの騒ぎに怯えている。神の力を使っても、あいつを下に降ろすことはできまい。従うくらいなら、木の上で死ぬだろう。無駄に騒いだり梯子で時間をつぶすなら、ノコギリと斧を持ってくる方がましだ」
「そうだ、そうだ」 賛成する声が聞こえてきた。「木が切り落とされたら、猿はどこに着地するだろう?」
すぐにノコギリと斧が運びこまれ、次々に木が切り倒された。そこにいた男も女もみんなが夢中になって立ち働き、誰もがこの新奇な騒ぎに参加したがった。男たちは上着を脱ぎ、女たちはスカートをたくし上げ、手のひらにペッペッと唾をはきかけ、恐ろしいほどの勢いで木の切り倒しがはじまった。同じ目的のために敵も味方も一つになり、争ったり仕返しをする暇などなく、誰ひとり、ヨーナタンが頭に包帯を巻いていることも、ペトロの腕が三角巾で吊られていることも気づかなかった。みんなの目は、木から木へと飛びまわる猿に注がれていた。
男たちが最後の木をに取りかかる頃には、夕暮れが近づいていた。
猿は木の頂上でからだを揺らせていた。沈んでいく船に乗っているみたいに、声を上げて騒ぐ人々の方を恐れおののいて見下ろした。木のまわりに投げ縄のように人の輪がつくられ、下に降りてきた猿が逃げられないようにした。
ところが最後の木がドサリと倒されると、猿はヨーナタンのところに飛びついた。そしてヨーナタンが考える間もなく、その肩に飛びのり、輪の外へ飛びだし、ライ麦畑へと走り去った。
「悪魔にでも食われろ!」 ヨーナタンが涙を流さんばかりに声をあげた。「もうちょっとでオレの手の中に、もうちょっとだった!」
「おまえにはその手しかないのか!」 パウロが怒りで顔を赤くさせて怒鳴った。
「新米のできそこないが!」
「この子豚やろう!」
「マヌケの中のマヌケだ!」
あらゆる方向から、雨嵐のような罵倒がヨーナタンに降りかかってきた。ここまでのヨーナタンの努力は、すべて水の泡と化した。たくさんの美しい木が倒された。のろのろと上着を着、スカートの裾を下す人々の姿が見られた。村人の顔は怒りと恨みがましさで赤く染まり、沈む太陽に照らされていた。襲撃の準備ができた雄牛のように、互いの顔を黙って見合った。
突然、ニペルナーティの何か命令する大声が聞こえてきた。「ライ麦畑のまわりを囲むんだ、早く!」
男たち、女たちが、フウフウハアハア言いながらライ麦畑へと突進した。ライ麦はすっかり踏みつけられたが、猿は見つからなかった。
「あいつは悪魔だ!」 男たちが呪った。
「あそこを見ろ、あそこだ!」 誰かが叫んだ。
ピョンピョンと跳ねながら猿が走っていって、シルケルのライ麦畑の中へと消えた。男たち、女たち、子どもたちが、ある者は石や棒を、ある者は斧やノコギリを手に、他の者は素手で、猿を追って突進した。そこにいるすべての人が狂喜し、狩りの熱狂にとりつかれた。猿はどうしても捉えられねばならなかった。人の命が代償となってもだ。
「いいかい、静かにして、見張るんだ」 ニペルナーティが声を荒げた。「ライ麦畑をきっちり隙間なく囲んで、ゆっくりと中央に向かって歩く。棒、斧、ノコギリは捨てて。猿は殺してはいけない。それから大声もだめだ」
ライ麦畑は囲まれ、人々は猿の首に輪縄を締めるように、ゆっくりと前に進んだ。辺りはもう薄暗かった。ライ麦が鎌で刈ったように人々の足元に落ちた。息を詰め、真剣な表情で、興奮で顔を赤く染め、人々は黙って前へ歩を進めた。
と、ヤンガが叫んだ。「つかまえた、猿をつかまえたぞ!」
ヤンガは猿の両脚をぶらさげて、助けを求めていた。ほんのひとっ飛びでヨーナタンがそばに行き、震えている小さな生きものを腕に抱いた。
「あー、この悪い子が、天罰だぞ!」 ヨーナタンが目を輝かせて叫び、猿をさも可愛いというように愛撫したり、お仕置きのように尻尾をつまんだりした。「これからは7本のロープで縛って、7つの錠をかけるからな」
「悪童を捕まえたぞ!」 そこにいた人々が喝采した。
すべての人が、その日の終わりがやっと来たと気づいた。今になって家にまだ終えていない仕事があるということを思い出した。サッと斧を肩にかけ、ノコギリを取り上げ、大急ぎで家に向かった。みんな火事場で大活躍して家に戻ってきたように、胸を張って誇らしげだった。「悪童を捕まえたぞ」と、自分たちの苦労と成果を強調するように、何度も歓声を上げた。
'Toomas Nipernaadi' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation ©: Kazue Daikoku
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
