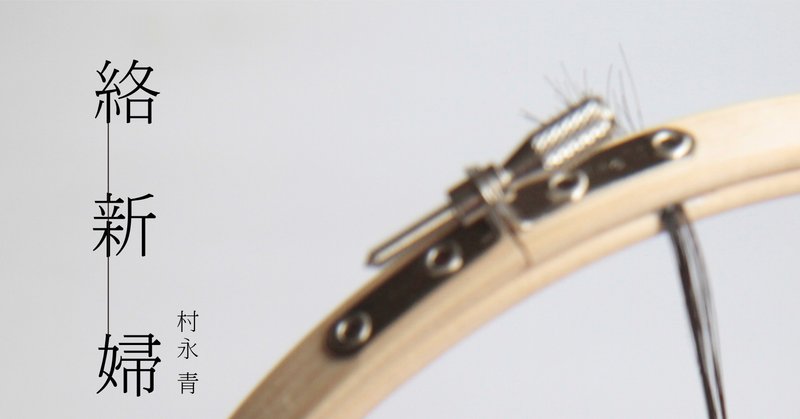
[小説連載]絡新婦 #7(期間限定 全8話+あとがき 無料公開 毎日20時連載)
・毎日20時次章掲載予定(予期せず変更もございます。ご了承下さい。)
・過去作の記事は基本期間限定無料公開のため、予期せず無料公開を終了する場合がございます。
予めご了承ください。
・一気に読みたい方は、Amazon Kindleにて絶賛発売中
絡新婦(2019)
(Kindle Unlimited会員の方は無料で読めます)
・Amazon Kindleのみ(電子書籍のみ)の販売です。ご了承下さい。
・Noteアプリを使用するとより読みやすいかもしれません。
iOSはこちらからダウンロード
Androidはこちらからダウンロード
各話リンク
#1(第1話)
#2(第2話)
#3(第3話)
#4(第4話)
#5(第5話)
#6(第6話)
#7(第7話)
#8(第8話)2020/07/25(土)更新予定
#あとがき2020/07/25(土)更新予定
乗り込んできた女は無言だった。「何処に行く。」と私が簡潔に訊ねると、「静かな場所がいい、町を外れた場所がいい。」と彼女はそう言うだけで、こちらを見ることもなく、ただ虚ろな目をして前を向いていた。そのまま車を発進させて国道へと入ったが、夜だということもありどこも込んでいたので途中で裏道に入った。ここから静かな場所ともなると、沿岸沿いぐらいだろうとそちらへ車を走らせた。行き先は特に考えてはいなかったが、とりあえず言われたとおり人気のない、静かな場所に―
車に乗ると甘ったるい匂いがした。きっと他の女性が頻繁に乗っているのだろうなと思ったが、それもどうでもよかった。男の横顔を見ると、綺麗な顔立ちをしていた。暗くてよく顔は見えないが、体型は痩せ型で華奢な印象を受けた。これだけの男ともなると、たくさんの女をこうやって夜な夜な連れまわしているのだろうか。車が脇道に入り、さっきまでの大通りとは打って変わって古い白熱電球のような光を放つ街灯が並んでいた。その光は地面まで届く事はなく、ただぼんやりとして暗いオレンジ色で辺りを照らしていた。
女も何も喋らず、ただ裏路地の車道を滑るようにしてゆっくりと走った。そこには誰の姿もなかった。町にあれだけ蠢いていた人も、乾いた音を飛び交わせる車も。辺りは静寂に包まれていたが、ただ車からだけは妙な音が相変わらず周期的に響いていた。その音は少しさきほどより大きくなっているような気がした。すると、急に車が減速しだしたので、ハザードを点滅させて近くの市民施設の駐車場へと入った。
車が急に速度を落としたので、何故だろうと運転席の男の方を見ると、車内は薄暗かったが外から差し込む光の加減で少しだけ顔が見えた。やはり綺麗な顔立ちだ。きっと年齢は20代前半といったところだろう。とても若い印象を受けたが、見た目から感じさせる年齢のわりには、凛と引き締まった印象も受けた。美男子ではあるが何処か男っぽくないなと思っていると「故障かもしれない」と言って車を降りて、車の周りを歩いては屈んで車の下を見ていた。私も仕方なく車を降りた。
車から降りて、車の下を見たが特に異常は見つけられなかった。いくらエンジンをかけようとしてもかからない。故障か。このタイミングでこの故障。例え現実から逃れようと走りだしても、国道から少しそれただけの場所までしか逃げられないなんて。何かが私たちを逃さないようにしているようだと思っていると、さらにその気持ちに拍車をかけるように、ぽつぽつと小雨が降り始めた。
車から降りると、男は何やら下を見たりしながら、車の周りをぐるぐると歩いていた。故障なのだろうか。ぼんやりとした心地で車のボンネットに寄りかかった。ぽつりぽつりと、小雨が降り始めた駐車場の周りには防風用の植え込みがあって、その木々の間から小さな川が見えた。小川には橋が架かっていて、対岸には建物があり、看板のネオンがチカチカと光っていた。建物の入り口らしきところには、大きな短冊状のものがいくつも吊るされていた。
車は一向に動く気配はないし小雨も降ってきたので、どうすると女に尋ねるよりも先に女が「あそこに入りましょうよ」と言って勝手に歩き出し、駐車場を出て行った。こちらから声をかけるよりも早く逃げるように早足で女が向かう先には小川に架かる橋があり、渡り終えたところから女が右に曲がった先にはラブホテルがあった。本当に厭になる。でも、もうあれこれ考えることすら厭になった。黒く鈍よりとした空が映る川は、時折鈍い銀色の光を放っていた。何も考えたくない。どうなろうとかまわない。私は糸杉の立ち並ぶホテルの門を潜った。
男がついてきているかも確認せずに、部屋サンプルの写真が並ぶ画面もよく見ずに部屋を勝手に選んで、紅い絨毯が敷かれた廊下をただ歩いた。選んだ部屋はどうやら1階で、少し入り組んだ廊下の先にさらに廊下が続いていた。番号を見ると、どうやら突き当たりの左側の部屋のようだ。男がついてきているか少し不安になって振り返ると、足音だけは確かに聞こえてきた。その足音を聞いてついてきていることを確認し、奥の選んだ部屋へと鍵を開けて入った。
女が消えた廊下の突き当たりの壁には絵画が飾られていて、その絵画はアネモネが生けられた花瓶と林檎がテーブルの上に置かれている静物画だった。綺麗な絵だったが、どこかその絵が感じさせる印象は暗く、全体的に落ち込んだ雰囲気だった。そう思わせるのは、花があまりにも花瓶に似つかわしくないからだろうか、それとも置かれているのがどす黒い林檎だからだろうか。本当に厭な気分にさせられるものばかり見せつけられる一日だ。
部屋に入り、ベッドへと半ば飛び込むように身を投げると、男も部屋へと入ってきた。「そのままシャワーでも浴びて。私はいいから」と男に告げると、男は言われたとおりそのままバスルームへと向かった。本当に私は何をしているんだろうか。あんな若い男まで捕まえて。自分の腹を満たすための餌ぐらいに思っているのだろうか私は。でも、どうやってこうなったかもわからないし、どうやって抜け出すのかもわからない。このままでいいとさえ思えた。本当は、駄目だとわかっているのに―
女に薦められるがまま、バスルームへと向かった。そこには今朝の鏡に映った自分よりも、一層ひどい顔をした自分が映っていた。目の下は窪み、髪は緩やかだったウェーブも崩れだらりと垂れ下がり、髪の毛先からはぼたぼたと雫が垂れていた。確かに外見だけを見れば男にも見えなくはなかった。ジャケットが体のラインを隠しているし、華奢な男にも見えなくはなかった。
しかし、服を脱いで鏡を見れば胸にはたしかに二つ乳房がついていて、とても男と呼べるような躰ではない。ぼんやりと見つめていた鏡に映る自分は結露でところどころぼんやりと見えた。私も、あんなに憎い母親と同じ女性と思うと、急に怒りが込上げてきて、感情が昂ぶり、その感情の昂ぶりは見事に私の体のバランスを崩し、涙となって私から溢れ出た。
いったい私は何をしているんだろう。
冷えた躰を浴槽まで運び、湯船に沈むと躰の中身だけがふわっと浮き上がる感じがするだけで、その他には何も感じず、お湯から伝わるはずの温度さえも感じなかった。今頃父はどうなっているだろうか。父の会社の人たちや父の事業に関係していた会社の人々が各社を慌しく蠢き、あの町と同じように低い音を立てているのだろうか。そんな状況の中、私は何をやっているんだろう。父の死から逃げているのか。見ず知らずの女性とホテルに入ることで。これからどうしようか。あの女性と一夜を過ごせばいいのだろうか。あの女性は私が女だとわかったら、どういう反応をするだろうか。そのまま彼女に私は抱かれてしまうのだろうか、それとも頬を思いっきり叩かれるのだろうか。そんな疑問ばかりが、垢のように次々と湯船に浮かび上がってきた。でも、もう何かをどうにかしようと思ってもどうにもならない状況まで私は追い詰められていた。
外の雨音も聞こえない部屋にある音といえば、自分がベッドの上で動くたびに出るシーツの擦れる音だけで、とても静かだった。服をゆっくり脱ぎ去り、バスローブに着替えた。まだ男は戻ってきそうにない。私はリモコンを取って、テレビの電源を入れた。最初に画面に映ったのは女に覆いかぶさるようにして男が腰を振っている映像だった。テレビの音量は小さく、部屋にかすかに声が聞こえる程度だった。いつもしている行為なので、見ても何も感じなかった。自分たちも数分後には、ああなっているだろう。チャンネルを変えるとニュースが流れていた。世界同時恐慌に突入した影響により国内の就業率も落ちる一方で失業率も上がってきているとキャスターが言っていた。そんな事は知っている。ハローワークに行けども仕事はなく、さらに年齢の条件でも撥ねられたりする事もこの身をもって知っている。コメンテーターは神妙な面持ちを、いや、神妙な表情の仮面を被ってはいるものの、自分には関係ないとやんわりとした声色で告げていた。
扉を開けると女はテレビを見ていた。画面の向こうでは二人のコメンテーターが世界同時恐慌について話していた。私はテレビの方へ歩み寄り、テレビの主電源を消した。こんな事は知っている。私の愛する人はそれが原因で亡くなったのだから。頭の中で何かを考えるよりも早く、足が勝手に動き出し女へと歩み寄り、ベッドの上を歩いて、仰向けになっている女へと跨った。
バスルームの扉が開くと、そこにはさっきまでの男とは少し風貌の違う人が立っていた。そこには、とても男性とは呼べないような、綺麗な艶っぽい容姿をした人がいた。その人はテレビを消して、私のところにまで来て、私に跨った。跨った瞬間、相手のバスローブの襟元がはらりと開き、そこからはとても透き通った美しい肌をした胸が見えた。しかも、その胸には端整に整った二つの乳房がついていた。私は驚いた。驚いたのはその人が女性だったからではなかった。自分が見たくなくとも、その厭らしさを感じさせない美しさは確実に私の目の前にあって、その美しさを認めざるを得なかった。私は胸から顔へと畏る畏る視線を上げると、彼女はあの目をしていた。あの今にも流れ落ちてしまいそうな涙が透き通った硝子のような膜をはったあの目を―
私はその目を直視することが出来ずに目を背けた。そして次第に首を垂れ、彼女の代わりに泣くかのようにただ只管ぼろぼろと涙を流した。彼女に縋るように手を差し伸べ、彼女を抱きしめようとしたが抱きしめる前に横に倒れこんでしまい、もう私には嗚咽を漏らすことしか出来なかった。
突然涙が込上げてきた。もう何もかも終わったはずなのに、終わらせようと思ったはずなのに涙が込上げてきた。涙は頬を伝わずに溜まる一方で、私の目を縋る様に見つめる女性の顔からは、ぼろぼろと涙が零れ出ていた。私の方に差し伸べられた彼女の手は私の腰の辺りからするりと抜け落ち、そのまま彼女は横に倒れた。私は自分をなんとか支えていた全身の力が抜け、そのまま彼女に覆いかぶさるように倒れこんだ―
何もわからない。でも唯一つ、私たちが同じだということはわかる―
「私、さっき洗面台にあったカミソリで手首を切ろうかとしたんです。」自分を嘲笑うように少し口元を歪めて、私は遥子に言った。手首を切ろうと思ったのは「もうここで死んでしまってもいいかな」や、「このまま終わってもいいだろう」といった気持ちからではなく、ただ自然とカミソリに手が伸びて、手首にカミソリを当てて、「このまま切ってしまおうか」というただそれだけのことだった。そこには決意や理由は存在せず、ごく自然な動きでしかなかった。
「私も死のうと思ったことあるわ。」私は枕に凭れ掛かりながら彼女に言った。「でも、家に戻らなくていいの・・・?」と彼女に訊ねると、彼女は首を横に振るだけだった。「私もね、さっき言ったけど娘が居るの。いや、居たの。」と言うと、彼女はぼんやりとした様子で「まだ、生きてるじゃないですか。お互い。」と宙を見つめながら言った。彼女の発した言葉、彼女の横顔、彼女の躰そのもの全てが、私にはひどく胸を傷めつけられる様な存在に他ならなかった。
「お母さん、心配してるわよきっと。」遥子が発する言葉が身を突き刺すほど痛かった。私の手元を見つめる表情、彼女の目じりの皴、子どもを産んだ経験のある女性特有の少しふっくらとして柔らかい線を描く腰のライン。たしかにそのどれもが美しいとは言いがたいが、何か心が安らぐものがそこにはあった。でも私はそんな母性に今は包まれたくもなかった。しかし、それから逃れようとしても、今彼女が私の横に居ることは変わりなかった。
「でも、なんで遥子さんは死のうと思ったんですか…?」と彼女が訊ねてきた。「私、浮気してたのよ。夫もね。でも、今思えばお互いに誤解してたかもしれないわ…。わからない…。でも…。なんだか…これ以上話をするのは恥ずかしいわ。」とお茶を濁そうしたが、彼女の瞳がそうはさせてくれなかった。まっすぐな、巴のような瞳が。「私、実はね…その浮気相手を思って自慰をしているところを娘に見られかけたの。そのときに娘を叩いてしまって。それで…なんていうか、そんな人間が母親であってはいけないっていうか…。自分自身にも嫌気が差して―」そう言った後くすっと嘲って見せようとしたけれど、私の頬には涙が伝いシーツに一つまた一つとシミを増やした―
「私も…私も父親を思って自慰をしたことがあるんです―」遥子が言う事を完全に理解することはできなかったが、何か自分も抱いたことのある思いのような気がした。私自身が過去に抱いてしまった思いとは重なりはしないものの、抱いてしまったことで相手と向き合いづらくなってしまい、決してその思いは悪いものではないのに、やってはいけないことをしてしまったという。そんな思いの部分は理解できる気がした。
「昔強姦にあったとき、父が物凄く優しくしてくれて。そのときから父以外の男性と一緒になるのは嫌だと感じるようになったんです。」誰にも話したくないことだった。そして、誰にも話したことがない気持ちだった。私が発した言葉は、自分でも驚くほど無垢な偽りのない言葉だった。「それから、たまに父を思って―」それ以上言葉はでなかった。やってしまった行為に対する罪悪感、今はその父が居ない事に対する寂寥感、父が居ないこれからの生活に対する虚無感、その他にも言葉や身振りでは表せない感情が、胸の辺りで急速に混ざり合って渦を巻いた。その感情は涙となって溢れ出ることはなかったものの、頭を鷲掴みされたかのように痛み走りを走らせ首を擡げさせた。
「お父さん、優しかったのね。」
彼女が発した声は何の同情も偽りも感じさせない、単調な声だった。発したその言葉は、今まで自分が背負っていた罪悪感に対しても、斬りつけてくるようなことはなく、一番今の自分の気持ちに寄り添ってくれる言葉だった。私は顔を上げることも、涙を流すことも出来ず、ただ俯いていた―
「本当に、私って馬鹿よね。蜘蛛みたい。」私は唐突に言った。すると、彼女は少し顔をこちらに向けてくれて「蜘蛛・・?」と訊ね返してきた。「そう、蜘蛛。巣を張ってそこに掛かったすべての獲物を食べてしまうの。毎日毎日それを続けないと生きていけないの。そんな蜘蛛みたい。」私は此処まで生きて、自分の何かが間違っていると気づいていても、何が間違っていているのかもわからないし、それ以前に何を今するべきなのかすらもわからなかった。「糸にかかったら、そちらに歩いていって、食べて。それが毎日毎日―」
蜘蛛という単語を聞いた瞬間に、街灯で見かけたあの光景を思い出してしまい、父の亡骸が脳裏に浮かんでどうしようもなくなった。逃げても、逃げても、どんなに逃げてもすべて父に繋がる。抗っても、抗っても、ますます纏わりついてきて絡め取られてしまう蜘蛛の巣に捕らわれたような気分だった。
「ごめんなさい。少し、シャワー浴びてきます。」とだけ言い残してバスルームへと駆け込んだ。鏡に映る自分は見たくなかった。とても見られるような状態ではなかった。
セックスレス―
私は夫の愛情を求めていたのだろうか。だからといって、今頃になって誰かの体を求めたところでどうにかなるわけもなかった。食べても食べても満たされない、そんなものはわかっていた。彼女は強姦にあったといっていた。そんな彼女をここに連れてきてしまったことに罪悪感を抱いた。彼女を自宅に帰してあげるべきだ。私にはとても彼女に手を差し伸べることなんか出来ない。もし、巴がそうなったら―
代わってあげることが出来るのならその強姦にあった日の彼女と入れ替わってあげたい。性に飢えている私にはお似合いだろう。そんな危険な事を想像した。彼女の硝子の様な瞳、あのときの巴の瞳、彼女の白く憂いと湿度を帯びた肌、巴の腫れた頬、手の肌の温かさ、手の痺れるような痛み、雨、ぼんやりとした無数のネオン、赤信号、裏路地の街灯、エンスト―
8へ続く(2020/07/25 20:00更新予定)
©2019 絡新婦 村永青(むらなが はる)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
