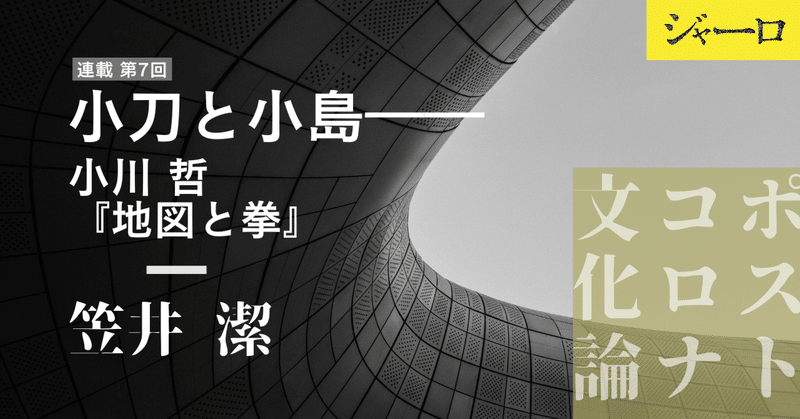
小刀と小島――小川 哲『地図と拳』|笠井 潔・ポストコロナ文化論【第7回】
▼前回はこちら
文=笠井 潔

『地図と拳』は奉天の東に設定された架空の町、李家鎮(のちに仙桃城と改称)の歴史を日露戦争前から第二次大戦後まで、日本人や中国人やロシア人など多様な人物の視点から描いた大河小説だ。
満洲を舞台とした大長篇といえば、五味川純平の『人間の條件』と『戦争と人間』、船戸与一の『満州国演義』が記憶に残る。戦中派の五味川、その子世代で戦後派の船戸にたいし、『地図と拳』の小川哲は戦争体験者の孫世代である。
『人間の條件』では「戦争と軍国主義」を批判するヒューマニズムの視点で、軍部や財閥による満洲侵略に巻きこまれた犠牲者の悲劇が描かれ、戦後市民の圧倒的な支持を集めた。敷島四兄弟が船戸作品の主人公たちだが、いずれも『人間の條件』の梶のような良心派市民とは違って、満洲侵略の意図的な加担者あるいは受益者で、作品ではその人格的荒廃が容赦なく描かれていく。次郎だけが国家機構とは無縁の自由人だが、侵略の尖兵だった大陸浪人とも類似する日本人馬賊で、満洲侵略を批判的に相対化する視点の持ち主は脇役の記者、香月しか登場しない。
侵略の被害者、犠牲者として日本民衆を捉え、戦争責任を免罪した戦後民主主義的な立場への批判が船戸にはある。その時代を生きた日本人の手は、一人の例外もなく血で汚れている。戦争責任は軍部と財閥に押しつけ、梶のような悲劇の抵抗者に自己同一化した読者の欺瞞を、船戸は抉ろうとした。
新世代の小川哲による満洲小説は、かつての五味川純平や船戸与一とは異なる質を達成しえているだろうか。かつて「眠れる豚」と侮蔑され、列強の帝国主義的侵略にさらされた中国は今日、世界第二の大国としてアメリカの世界支配に挑戦している。いまや中国は日本最大の貿易相手国だが、同時に尖閣諸島をめぐる対立は先鋭化し、日本人の対中感情は悪化してきた。
中国の覇権主義を警戒する日本だが、国際関係をパワーのせめぎ合いと捉える政治的リアリズムの観点からでは、その海洋進出も攻守ところを変えた新事態にすぎない。均衡が正義であるとするなら、負債は返済されなければならない。被害者には、やられた分だけやり返す権利がある。構成員の対立を法的に決裁する実力を備えた世界国家が存在しない以上、国家間の同害報復を否定する原理はない。
よくも悪くも第二次大戦後の冷戦構造や、ソ連崩壊後のアメリカ「独覇」体制の安定性を前提として、先行世代の満洲小説は書かれてきた。しかしウクライナ戦争に見られるように、二一世紀世界からかつてのような秩序は失われている。世界内戦の二一世紀に、日本帝国による侵略の歴史を、五味川や船戸のように小説化することはできそうにない。新世代は二〇世紀前半までの満洲と満洲国を、どのように描いているだろうか。
山室信一『キメラ――満洲国の肖像』では日露戦争以降の日本人の、満洲をめぐる帝国主義的な国家意志や国民感情が要約されている。「日本列島の脇腹に突きつけられた匕首にも擬せられる朝鮮半島とその後背にある満蒙の大地――そこで日本は国家の命運を賭して日清、日露の二つの戦争を闘い、辛くも勝利を収めた」。
満蒙は「十万の生霊、二十億の国帑(国庫金)」によって購われたかけがえのない大地と目され、その開発と経営は「明治大帝の御遺業」を継ぐ国民的使命とさえみなされたのである。そこはまた朝鮮併合以来日本と国境を接する接壌地域として国防上の要地であるとともに、その大地に眠る豊富な天然資源は日本の経済的発展を約束するものと目され、満蒙こそ日本の死活を決する特殊地域として認識されるにいたったのである。
坂本龍馬は懐に、拳銃と一緒にフィッセリングの『万国公法』を押しこんでいたという。カール・シュミットが「ヨーロッパ公法」と称するように、万国公法=国際法は一七世紀以降のヨーロッパで成立し、その世界征服の過程で域外諸国にも適用されるようになる。ただし万国公法の「国」とは三十年戦争後のヴェストファーレン体制の構成国で、実質的には海外に植民地を領有する大国を意味した。
インドは植民地化され、オスマン帝国の弱体化と列強による侵食も進んでいた一九世紀後半、ヨーロッパ列強による勢力圏や植民地争奪の前線はバルカン、アフリカから東アジアに移行する。
列強による中国侵略の画期は一八四〇年のアヘン戦争と南京条約にある。|香港島の割譲を含む南京条約は典型的な不平等条約だが、フランスも同様の黄埔条約を締結した。イギリスはアロー戦争(一八五六年)と天津条約、北京条約で権益を拡大し、ロシアはアムール川左岸の割譲を含むアイグン条約(一八五八年)を締結。清と望厦条約(一八四四年)を結んだアメリカは、日本にもペリー艦隊を派遣して通商を要求する。アメリカの砲艦外交に屈した江戸幕府は日米修好通商条約(一八五八年)の締結に追いこまれた。
開国を強いられ不平等条約を押しつけられた日本には、二つの可能性が与えられていた。いずれかのヨーロッパ大国の支配下に編入され、植民地化の道を辿るか。あるいはヨーロッパ公法諸国の新規メンバーとして承認され、植民地領有国になるか。明治維新で体制を一新した日本は、尊皇攘夷から文明開化へ、そして富国強兵への道を走りはじめる。
維新直後から沖縄と北海道の国内植民地化を強行した日本は、続いて「日本列島の脇腹に突きつけられた匕首にも擬せられる朝鮮半島」への干渉を強めた。朝鮮を従属国と見なしていた清との対立は激化していく。
日清戦争(一八九四年)で小国日本に敗れ、腐朽化と弱体化をさらけ出した老大国の分割に、列強諸国は乗り出した。下関条約による日本の台湾獲得に続き、イギリスは香港島と九龍半島に加えて威海衛を、フランスは広州湾を、ドイツは青島を、ロシアは旅順と大連を租借地として得た。さらに長江流域はイギリス、広東省はフランスが、満洲とモンゴルはロシアの勢力圏となる。ロシアは東清鉄道附属地も密約で獲得していた。
朝鮮から清の影響力を排除することに成功した日本は、「朝鮮半島とその後背にある満蒙の大地」を次の獲物として狙いはじめる。三国干渉で旅順と大連を横取りしたロシアが、日本の敵となることは不可避だった。からくも日露戦争に勝利した日本は遼東半島の租借権と南満洲鉄道を獲得し、満洲支配の基礎を築くことになる。
『地図と拳』の物語は日清戦争後、日露の緊張が高まる満洲からはじまる。「序章 一八九九年、夏」では、参謀本部から特別任務を命じられ商人に偽装して満洲に潜入した陸軍の高木少尉、同行する通訳の細川による偵察行が描かれる。二人の目的は満洲の軍事的な地図を作ることだ。
西南戦争で戦死した父の形見の短刀を、高木は荷物の底に隠し持っていた。川船でハルビンに到着する寸前、短刀を川に捨てるよう細川に忠告されるが、どうしても捨てることができない。その短刀は臆病な高木の精神的な支えで、「これは自分が軍人である証なんだ」。
「捨てましたか?」と細川に問われて、高木は「小刀がなるべく見つからないよう、着替えの長衫に包んで鞄の底に押しこむ」。
細川はこの行為に気づいていないようだ。鞄の中身を検めながら、はたしてこの小刀に命を懸ける価値があるのだろうか、と自問する。
この行為は勇敢なのか、それとも臆病なのか。
少なくとも卑怯ではあろう。自分は今、ロシア兵だけでなく細川も騙そうとしている。
「認めよう。自分は命と小刀の価値を天秤にかけたわけではない。鞄に隠せば小刀が見つからずにすむのではないか、という可能性に賭けただけで、天秤に至ってすらいない」と高木は自答する。細川が警戒したように短刀は検問のロシア兵に発見されてしまう。ところが、捨てろという忠告を無視され、結果として騙されていた通訳の青年が「私のものです」とロシア兵に応じる。
連行された二人は、ロシア語に堪能な細川の弁明が功を奏したのか、なんとか無事に解放される。卑劣な自分の罪を被ろうとした通訳の青年を前に、高木は「危険だとわかっている軍刀を捨てることすらできなかったし、その軍刀を捨てることができなかったと白状することもできなかった。どこまでも臆病で、卑怯な人間だ」と自責する。
そんな高木に「奉天の東、李家鎮という村の付近に資源があるかもしれません。(略)李家鎮では土が燃えるんです。石炭が混じっているからでしょう」と、船内で中国人から得た情報を細川が告げる。
小刀をめぐるエピソードで示されるのは、軍人らしからぬ自意識家としての高木の性格だが、それだけではない。戦死した父の形見に執着し、逮捕と処刑の危機を招いた愚かな行動は、『地図と拳』の全篇を通して語られる日本帝国の運命を暗示しているからだ。一八九九年に高木と細川が満洲に潜行したのは、対露戦に備える情報収集が目的だったし、「第四章 一九〇五年、冬」では満洲の戦場で突撃し、戦死する高木の姿が描かれている。
『地図と拳』の作中では複数の登場人物が、日露戦争で戦死した「十万の英霊」のためにも、満洲を失うことはできないと口にする。たとえば「第七章 一九二八年、夏」では「第一回『日華青年和合の会』」の議論が描かれる。そこで三井物産の棚橋部長が「満蒙は日露戦争十万の英霊によって手に入れた土地です。我々には、この土地の資源を利用する権利があるはずです」と発言する。また細川が主宰する戦争シミュレーション会議〈仮想閣議〉で〈海軍大臣〉を演じる赤石は、もしも偶発的な日中衝突が起きたら、との仮定にたいして次のように述べる。
「現地で停戦合意がされようが破談しようが、支那軍が徹底抗戦の姿勢で挑んでくることに変わりはないし、そうなると日本人の多くは〈陸軍大臣〉殿と同じ考え方をしているから、結局内地の師団を派兵することになる。派兵すれば、派兵した分の元を取らなければならなくなるから戦争になる。一度戦争が始まれば、戦争を始めた分の元を取らなければならなくなるから日支は全面戦争になる。日露戦争の英霊に囚われて満洲に過剰な投資をした日本人には、この連鎖を途中で止めて損切りすることなどできない。どちらかの国が滅びるまで日支の戦争は続く」
「第十章 一九三四年、夏」の戦争シミュレーションの正否を、もちろん本書の読者は知っている。一九三七年七月の盧溝橋事件に際し、日本政府は不拡大方針を掲げながらも内地師団の動員を決定し、ずるずると日中戦争に入っていく。対中戦争の行きづまりから対米開戦に追いこまれた日本は、一九四五年にポツダム宣言を受諾し中国を含む連合国に無条件降伏した。たしかに「どちらかの国が滅びるまで日支の戦争は続」いた。
作中の細川による戦争シミュレーションにはモデルがある。猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』では、首相直轄の総力戦研究所による模擬閣議が対英米戦をシミュレーションし、昭和一六(一九四一)年八月に結果を提出した。報告書には、ほぼ正確に日本の敗戦にいたる過程が先取りされていた。しかし政府は「対米戦は敗北する」というシミュレーション結果を無視し、舵を失った船さながらに嵐の海に流されて難破した。この史実を下敷きにして作者は、戦争構造学研究所の〈仮想閣議〉による対中戦争シミュレーションを設定している。
西南戦争で戦死した父親の形見を捨てるわけにはいかない。この高木の執着は、高木を含む「十万の英霊」の形見ともいえる土地、満洲は日本のもので放棄などできないという国民世論として、対米戦争の敗戦に帰結する二〇世紀前半の日本を突き動かした。満洲を焦点とした日本の膨張と失墜を描いた物語全体のモチーフが、序章のエピソードには込められている。
明治維新と西南戦争から日清、日露戦争を経由して第二次大戦の敗戦にいたる日本は「勇敢なのか、それとも臆病なのか。/少なくとも卑怯ではあろう」。日露戦争十万の英霊を裏切れないという建前ではじめた日中戦争と第二次大戦で二三〇万という戦死者を出した。徹底抗戦を回避しての無条件降伏とは、膨大な戦死者への自己保身による裏切りに他ならない。しかも自己保身は、敗戦を「終戦」と自己欺瞞することで理念的なレヴェルにまでも及んだ。
序章の小刀をめぐる挿話に、『地図と拳』の第一のモチーフが込められているとすれば、第二のそれは青龍島という小島だろう。「第五章 一九〇九年、冬」で物語られるのは、大学で気象学の研究をしていた須野青年が、二年前に満鉄歴史地理調査部から「黄海にあるとされる青龍島という小さな島が実在するかどうか調査してほしい」と依頼された事情だ。
ロシア人が作成した地図には描きこまれているが、実在が確認できない小島の謎に須野は憑かれ、「私はオケアノスを目指す一人の船人なのかもしれぬ」と思う。オケアノスとは「ギリシア神話に登場する海神」で「世界の果てはオケアノスという大海」だ。義和団の乱のため帰国を余儀なくされたロシアの測量隊は、地図の黄海の箇所を「大清一統輿図」から引き写したと考えられる。中国の地図には存在しない島が地図に書き加えられたのは、その際のことではないか。「ロシア人はなぜそんなことをしたのだろうか」。
宗教的理由、詐欺師による金儲け、作家の空想、伝聞の間違い、機器の故障、軍事的理由など、様々な経緯によって、人々は架空の島を夢想してきた。須野はそれらの理由をひとつずつ検証し、退けていった。その作業は、これまで人類が、未知の世界を夢見た歴史を追いかける作業だった。
大学で気象学は学んだが測地学や地図作成の知識はないという須野に、「君は満洲という白紙の地図に、日本人の夢を書きこむ」のが仕事だと細川は応じる。満鉄の男の縁で知った高木夫人の慶子と結婚した須野には子供が生まれ、命名を依頼された細川は明男と名付ける。須野明男、逆に読むとオケアノスだ。『地図と拳』の後半も複数の人物の視点から描かれるが、物語の中心になるのは須野明男だ。小刀と小島をめぐる伏線は、物語の結末で明男によって回収される。
高木と細川、高木の元妻と結婚した須野と息子の明男。これらが日本人側の視点人物として第一の系列をなしている。大学で建築学を学ぶ明男の友人で共産党活動家の石本と中川、甘粕正彦を敬愛する憲兵の安井なども、この系列に属する人物だ。
元号が大正と改元された年に、須野は満鉄本社勤務を命じられて日本を離れることになる。「辛亥革命によって清は滅び、中華民国が誕生していたが、彼らも広大な満洲の統治に苦心していた」。
満洲はまだ、誰のものでもなかった。広大な白紙の地図を、馬賊がゲリラ的に埋めていた。台頭した馬賊が別の馬賊に敗れ、勢力圏は目まぐるしく入れ替わった。日本が、支那が、そしてロシアや諸外国が有力な馬賊を懐柔しようと試み、それに成功したり失敗したりした。
細川は満鉄を動かして、かつての満洲調査で情報を得た「土が燃える」田舎町に「虹色の都市」を建設しようともくろむ。「仙桃城には満洲民族と漢民族がともに暮らしています。そこに日本人とロシア人、朝鮮人とモンゴル人が加わります。仙桃城では、国家や民族、文化の壁を越えて、様々な立場の人々が手を取りあって生活します。どのような形になるかわかりませんが、満洲の地に新国家が建国されたとき、仙桃城はその規範の都市になるのです」。
虹色の都市の最後の一色を問われて、「死者です」と細川は応じる。満、漢、日、露、朝、蒙の六民族に、「この地における争いの歴史によって犠牲になったすべての人々」を加えた七色の、つまり虹色の都市。こうして炭鉱開発と同時に建設がはじまる新都市の理念は、満洲国の建国理念「五族協和」の原型ということになる。
『キメラ――満洲国の肖像』では「英語などでの満洲国についての叙述」が、「日本が中国東北に一九三二年に建てた傀儡国家(puppet state)。溥儀を名目上の統治者としたが、すべての実権を日本の軍人、官吏、顧問が独占した。これにより、日本は、ほぼ半世紀にわたって中国、ロシア(ソ連)の双方と競った満洲(Manchuria)の征服を成し遂げた。数多くの国が承認したにもかかわらず、その本質は傀儡国家であり、第二次大戦における日本降伏とともに潰滅した――などと説明されることが多い」と要約されている。連合国側の視点からは、日本帝国主義による計画的な中国東北部侵略の結果として捏造された傀儡国家が満洲国ということになる。
七三一部隊の人体実験や死にいたる強制労働をはじめ、満洲の植民地支配の実情を知る者は「傀儡国家というよりも、アウシュヴィッツ国家、収容所国家とでも概念づけたい慄然たる衝動に駆られる」と山室信一はいう。「しかし、にもかかわらず、こと満洲国に関するかぎり、それはけっして単なる傀儡国家、植民地国家ではなく、欧米の帝国主義支配を排してアジアに理想国家を建設する運動の場であった、満洲国建設は一種のユートピア実現の試みであった、とする見方が、一九四五年以降も牢固として存在しつづけてきた」。こうした満洲国観は、いかなる根拠もない妄想的な自己正当化なのか。
植民地民衆を蹂躙する傀儡国家としての満洲国、「王道楽土、五族協和」のユートピアとしての満洲国。対立する二つの満洲国観のうち、細川の「虹色の都市」構想が後者を体現していることは明らかだろう。「第七章 一九二八年、夏」以降の章で、作者は仙桃城の興亡に託して満洲国の運命を描いていく。その後、細川は「十年後の未来を予測する」目的で戦争構造学研究所を設立し、明男の友人で共産党員として弾圧された石本を研究員に誘う。
一九三一年の柳条湖事件と関東軍による満洲制圧、満洲国の樹立にいたる時期のことは、「第八章 一九三二年、春」と「第九章 一九三二年、秋」で描かれる。建築学科の学生として仙桃城を訪れた明男、孫悟空の娘で地元の抗日パルチザン隊員の丞琳は、町のダンスホールで客と踊子として出逢う。丞琳たちは日本資本の炭鉱を襲撃し、その報復として憲兵の安井は付近の村人を大量虐殺する。その直前に虐殺現場から追い払われた明男は、なにが起きようとしているのか疑念を抑えられない。
「第十章 一九三四年、夏」では、仙桃城を本拠とする戦争構造学研究所の設立記念祝賀会の模様が描かれる。所長に就任した細川は記念講演で、かつての満洲偵察の旅について触れる。「僕が満洲に初めてやってきたのは、今から三十年以上前、まだロシアの留学生だったころです」「僕たちは二人組で、満洲という広大な土地の軍事的な地図を作るために潜入工作をしたわけです」。では、地図とはなにか。
国家とは法であり、為政者であり、国民の総体であり、理想や理念であり、歴史や文化でもあります。ですがどれも抽象的なもので、本来形のないものです。その国家が、唯一形となって現れるのは、地図が記されたときです。
「国家とは地図である」と細川は語る。かつて細川と高木は地図を作るため満洲に派遣された。地図を作るのは満洲を日本にすることだ。朝鮮や台湾のように併合するか、海外植民地として属領化するか、あるいは傀儡国家とするかはともかく、新しい地図は日本の領域を拡大するだろう。少なくとも、そのための一歩ではある。
「なぜこの国から、そして世界から『拳』はなくならないのでしょうか」と自問し、細川は答える。「答えは『地図』にあります。世界地図を見ればすぐにわかることですが、世界は狭すぎるのです。(略)人類が戦争をするのはこのためです」。
コロンブスによる西インド航路の探索が新大陸への到達に、そしてカリブ諸島や中南米の植民地化に帰結したように、地理上の発見と新たな地図の作成はヨーロッパによる植民地主義の展開と不可分だった。太平洋を探検しハワイに到達したクックも、アフリカ大陸の横断に成功したリヴィングストンも、当人の意図は別として植民地主義に加担する結果となったし、リヴィングストンを救出したスタンリーの場合は、ベルギーのレオポルド二世によるコンゴ植民地化の尖兵だった。
『地図と拳』の物語の舞台廻し役で、須野や明男や石本をはじめ多数の人物の運命を操って満洲に集めた細川だが、「その大地に眠る豊富な天然資源は日本の経済的発展を約束するものと目」し、「満蒙こそ日本の死活を決する特殊地域として認識」していた点では当時の日本人の大多数と変わらない。だから「国家とは地図である」との信念のもと、満洲の地図を作ろうとした。あるいは「満洲はまだ、誰のものでもなかった」と考える須野を満鉄に誘い、空白の地図に理想を描くように仕向けた。
細川の「虹色の都市」構想は日本人の主導性を不可疑の前提とする点で、帝国主義的支配という満洲の現実に理想の糖衣を被せたものにすぎないと、現地の人々は批判するだろう。指摘するまでもないだろうが、満洲が「誰のものでもな」いとは、中華民国、ロシア、日本、その他の国家のいずれもが実効支配していないことを意味するにすぎない。
満洲には満洲で生活する人々が存在し、その土地がその人々のものであることは疑いない事実だ。たとえば李家鎮には、細川たちが訪れる以前から暮らしている者たちがいた。李家鎮の住民を物語に引き入れるキャラクターとして、高木・細川や須野と同じく地図と無関係ではない人物、クラスニコフが最初に登場する。
クラスニコフは大学で地理学を学んだ測量士だったが、「測量に行った先で主教に出会い、それまでの道を捨てて神父になることを決めた」。満洲での布教活動を予定していたが、ウィッテ大臣の意向で参謀本部が編成した測量隊の一員として、一八九六年に満洲に赴く。
呼び集めた測量士の前で大臣は、「我々は鉄道を使って都市を作る。(略)鉄道が都市を作るのであれば、その鉄道を作るのが地図だ」と語る。「その言葉を聞いて、発奮しない測量士はいないだろう。測量をしていると、不遜にも自分が世界を創造しているのだと錯覚する瞬間がある。距離を測り、白紙の地図に線を引く。その線が世界となって現前する」。
中途で測量を終えたクラスニコフは、奉天に近い小集落に粗末な教会を建て布教をはじめる。ハルビンで報告書を渡した少佐から「我々は、黄ロシア構想のために、満洲へロシア人を入植させなければならない。そのために、各地に教会を建てる必要がある。君は満洲に残って布教をするんだ」と命じられたからだ。
日本よりも一歩先に、ロシアが満洲の地図を作成していた。その地図によってシベリア鉄道は満洲まで延長されていく。ロシアもまた「国家とは地図である」ことを確信していた。
クラスニコフの教会がある李家鎮の支配者は元役人の李大綱で、「東北に桃源郷がある」という噂を流して各地から流れ者を集めていた。「第一章 一九〇一年、冬」では義和団の乱に巻きこまれたクラスニコフが、孫悟空と名乗る若者を救う。李大綱の道場で修行を重ねた若者は、銃弾を撥ね返す躰と未来を予知する千里眼を獲得していた。孫悟空は李大綱を殺害して町の支配者になる。クラスニコフ、李大綱、孫悟空、丞琳などが物語の視点人物として、ロシア人や中国人からなる第二の系列をなしていく。一五歳で母を失った丞琳を引き取って育てたのは、教会のクラスニコフ神父だった。
親しい中国人が日本の憲兵に殺されて、「神の声が聞こえなくなった」クラスニコフは教会を閉じ、六分儀とぼろぼろの手帳を持って荒野を彷徨うようになる。「神の声が聞こえなくとも、神が作った世界を知ることはできます(略)だから私は測定するのです」。
「第十一章 一九三七年、秋」で、建築家として満洲に赴任した明男に、神父に同行していた丞琳が五年前の虐殺事件の真相を突きつけ、「私は絶対にあなたたちを許さない」と告発する。「許してもらえるとは思いません」と、かろうじて明男は答える。
日本軍の犯罪を知って絶句している明男に、「私は今、四十年前に中断していた宿題を終えようとしています」とクラスニコフは告げる。この老人にとって、もはや地図は国家ではない。ガリレイからニュートンにいたる自然科学者たちは、神の理性を再確認するために世界の合法則性を探究した。神が最高の理性的存在であるなら、神の創造物である世界が理性的でないわけはない。
こうして国家=地図の等式は失われ、老人は神=地図の新たな等式を発見した。その神はロシア帝国と一体だった、かつての神ではない。老人が新たに作ろうとしている地図も、国家の形としての地図ではないだろう。
父の須野や細川にとっての「地図」が明男には「建築」となる。学生時代の「明男は仙桃城周辺に残った農村や田園をそのまま保存し、別区画に都市部をつくる」都邑計画を構想していた。この構想からもわかるように明男の建築思想と、近代化と都市化に邁進する植民地主義や産業主義の路線とは齟齬がある。
建築家として満洲に赴任した明男の仕事は総力戦体制という条件に阻まれ、あらためて提出した李家鎮公園の設計案が満鉄に採用される。「西洋式の点対称な構造に、日本と支那の回遊式を取り入れ」た公園の「景色にはかつて小さな農村にすぎなかった李家鎮という村と、発展した『煤都』仙桃城の二つを繋げる含意もある」。
公園のテーマは「地図」である。公園はそれ自体が仙桃城のミニチュアとなっている。中央に位置する広場には鶏冠山を模した盛り土の丘があり、その後ろに沈みゆく太陽となる巨大なアーク灯が置かれている。
明男の公園構想は、土着の人々が主人公だった田舎町の李家鎮と、日本人が建設した新興産業都市の融和と統一という願望が込められている。この設計を認可したのは、侵略戦争に邁進する日本の傀儡国家ではない、「王道楽土、五族協和」を掲げた満洲国だった。「第十四章 一九三九年、冬」に、公園はようやく完成に近づく。しかし何者かによってモニュメントの板金が盗まれてしまい、設計者には不本意ながら未完成の状態で公開がはじまる。板金には「虎臥」と刻まれていた。それは「仙桃城の自由闊達な発展を祈る言葉であると同時に、日本人は『虎臥』を『こぶし』とも読む。日本人は、この街にふるってきた自分たちの拳を忘れてはならない」「モニュメントの中に、怒りによって突きあげられた拳の形が見えたのは、すっかり設計が終わってからだった。それは彼女の、丞琳の拳だった。/悪くない、と明男は思った」。
土着の抗日パルチザンだった丞琳たちの隊に、共産党から黄宝林が派遣されてくる。隊は八路軍に編入され、黄の支配下に置かれることになる。「丞琳は一目見た瞬間からその男が嫌いだと思」うが、「黄宝林はすぐに仙桃城八路軍の心をつかんだ。彼の『私たちの土地を取り戻しましょう』という惹句に心を奪われたのかもしれない。黄宝林は毎日、土地革命の話をしていた」。
共産党員の黄は、自然発生的に組織された土着のパルチザンに規律性と計画性を持ちこんだ。指導者としての黄に心服する隊員もいたが、丞琳のように黄の作法に抵抗を覚える古参兵もいた。
五味川純平の『戦争と人間』では、共産党員の弟で反戦運動に挺身していた標耕平は兵士として戦地に送られるが、運よく八路軍に合流して抗日活動に参加できる。このような日本人コミュニストや八路軍の描かれ方と、『地図と拳』のそれは大きく異なる。壊滅寸前の共産党でKの名で活動していた中川は、拷問に屈して同志を売り、徴兵されて中国戦線に送られる。「青年だった自分の理想が、夢が、仲間と交わした熱い議論が、Kの名が、支那の夜空に煙となって溶けていく」と、戦場で中川は思う。
また八路軍の黄は、人格改造的な整風運動を部隊に持ちこむ。「『整風』を経験した党員の心はずたずたに引き裂かれた。(略)壇上に立たされた党員は自己批判を行い、他の党員はそれを責めたてた」。こうして「『日本鬼子から自分たちの土地を取り戻す』という仙桃城八路軍の願いは、黄宝林への個人崇拝や、党の教義に対する絶対的な信仰という形に置き換わった」。
そして黄は仙桃城への総攻撃を命じる。「丞琳にはわかっていた。黄宝林は、自分にとって都合の悪い存在である、仙桃城という都市と古参兵をぶつけ、どちらも一緒に消してしまおうと考えているのだった。自分の息のかかった本軍はしっかりと温存して、この先の国民党との戦いにも備えるつもりだ」。
「第十六章 一九四四年、冬」で、突入してきた八路軍と日本軍の戦闘がはじまる。公園のモニュメントの下で倒れていた丞琳を、兵士として戦闘に参加していた明男が救う。
「終章 一九五五年、春」では、四三歳になった明男は仙桃城を再訪する。戦闘と掠奪のため廃墟と化した町で、クラスニコフが遺した李家鎮の巨大な地図を拡げてみると、そこには青龍島も描かれていた。明男の父、須野を悩ませた黄海の小島をめぐる謎は解明される。ロシアの地図に存在しない小島を描きこんだのは、一八九六年にロシア帝国から満洲に派遣された青年測量士クラスニコフだった。
描かれた青龍島の内部には李家鎮の古い地図が貼られ、『地平線の向こうにも世界があることを知らなかったあなたへ』とロシア語で記されている。「この地図は――そして青龍島は、李家鎮の住民に向けて描かれたものだった」と呟いた明男に「きっと、彼らが存在すると信じていた島なの。伝説の龍が住む理想郷」と丞琳は応じる。
「なるほど」と明男はうなずく。「中世の西洋の地図には、未踏の地のどこかに、かならずアダムとイヴの楽園が描かれていたと聞いたことがあります。青龍島は李家鎮の住民にとっての理想郷で、神父にとっての楽園だった」
こうして謎の小島をめぐるモチーフは着地点を見出し、『地図と拳』の物語は終わる。他方の高木少尉の小刀をめぐるモチーフはどうだろう。
「第十七章 一九四五年、夏」で明男は、復員船の船内で偶然に細川と再会する。「日本は戦争に負けて満洲を失う。研究所の調査と会議で、僕は何年も前からそのことを確信していた」と語る。「満洲に建てたものはすべて無駄になるし、日本を復興するためには大量の建材が必要になる。僕は君に謝らなければならない。李家鎮公園で『虎臥』の板金を盗んだのも僕だ」。
ロシアとの戦争に備えて満洲を調査し、日露戦争を体験した細川は、満洲という白紙に理想の国の地図を描こうとした。壮大な計画の中心には、「虹色の都市」を無から創造するというプランが存在した。しかし帝国主義の圧倒的な力学を前にして、細川は計画の挫折を予感しはじめる。
高木少尉と小刀をめぐる序章の挿話は、明治維新から第二次大戦の敗戦にいたる近代日本の運命を寓意していた。細川の主宰する〈仮想閣議〉の戦争シミュレーションで浮き彫りになったのは、「損切り」を決断しえない結果、時間稼ぎの無意味な追加投資を重ねて事態を悪化させ、最後には倒産の憂き目を見る無能な経営者にも類比的な日本国家だった。
戦争構造学研究所でシミュレーションを重ねた結果、日本の敗戦を確信した細川は「巨大な不要物に使う建材を節約する」ために、隠然公然と満洲への投資を抑えるための活動を開始し、膨大な建材を横領しては密かに日本に送っていた。来たるべき敗戦と日本の再建に備えて。ある時点から細川にとって満洲は、理想を描きうる空白の地図から「巨大な不要物」に変質していた。
明男は反論する。自分が満洲で建設したもの、たとえば李家鎮公園が不要物だとは思わない。「建築は人間の過去を担保」するからだ。満洲を追われた「あなたにとっては意味のない建築かもしれない。でも、生まれたばかりの子どもにとってはどうでしょうか」と。これに細川は「君は人類の話をしている。そして僕は日本人の話をしている」と応じる。
別れ際に細川は忠告する。上陸の際に米軍の持ち物検査があるかもしれない、「見つかって不味いものを持っているなら、今のうちに海に捨てておけ」と。港が近づいてきたとき、明男は「軍刀を佐世保の海に向かって放り投げた。軍刀はきらりと太陽に反射して、そのまま海の底に消えていった」。
ハルビンの船着き場で高木少尉が捨てられなかった小刀を、「もう戦争は終わったんだ」と呟きながら明男は海に投じる。日露戦争で血にまみれた小刀とともに、満洲という呪縛からも日本は解放されたことを作者は暗示している。
しかし、本当に「戦争」は終わり、満洲の呪縛は消えたのだろうか。一九三六年に満洲国に派遣された商工省高官の岸信介は、ソ連やドイツを模倣して統制経済の実験を試みた。それが近衛内閣による国家総動員体制の構築に有益だったことはいうまでもない。
完全に新しい炭鉱都市を構想していた細川と岸が、どこかで顔を合わせていたとしても不思議ではない。その場合、日中戦争が開始された時点で日本の破滅を予測していた細川は、戦争政策の最高プランナーの一人だった岸とどんな会話をすることになったのだろうか。
満洲から帰国した岸は、東條内閣の一員として対米開戦に向かう。敗戦後はGHQにA級戦犯容疑で収監されるが、ソ連の脅威を意識しはじめたアメリカが占領政策を転換し、政治的な復権が許された。密かにCIAのエージェントとして活動していた岸は、一九五七年に首相就任、六〇年には国民的な反対運動を押し切って日米安保条約改定を強行し辞任する。
このような特異な経歴から「昭和の妖怪」とも呼ばれた岸信介だが、日本帝国復権と対米従属を反共の一点で自己矛盾的に統合した政治路線は、孫の
安倍晋三に継承された。安倍は暗殺されたが、安倍派は今日も永久与党と化した自民党の最大派閥だ。
満洲国の高官だった人物の孫が、史上最長政権を築いたという事実がある。満洲侵略を含む戦前昭和の帝国主義日本を肯定する政治勢力が、二一世紀の日本を支配している以上、満洲の呪縛は今日もなお消えていないというべきだろう。
またポストコロニアリズム研究からは、「漢江の奇跡」として語られる韓国の高度経済成長と満洲国の関係が検証されはじめている。ソクジョン・ハン「植民者を模倣する人々――満洲国から韓国への統制国家の遺産」を、鈴木貞美は『満洲国 交錯するナショナリズム』で次のように要約している。
彼(ソクジョン・ハン――引用者註)は、儒学を国民統制の道具とすることを、満洲国軍の副官として反共産活動に活躍した朴正熙が第二次大戦後の韓国で、いかに応用したのかを明らかにしてゆく。その「満洲国」の経験は、朱子学が李氏朝鮮時代に沁み込んだ文化基盤に支えられ、第二次世界大戦を越えて、韓国で復活した。つまり、一九六〇年代半ばから七〇年代を通して韓国に高度経済成長を現出させた朴正熙政権は、いわば「満洲国」の亡霊に守られていたのだった。
韓国で民主化運動が勝利しても、軍事独裁政権の流れを汲む保守勢力はいまだに国民の半数の支持を得ているし、朴正熙の娘の朴槿恵は二〇一三年から一七年まで大統領職にあった。韓国でも満洲国の亡霊は消えていない。
また、日韓両国にわたる満洲国の亡霊が合体して生じたのが統一教会といえる。一九六〇年代はじめから統一教会はKCIAと密接な関係があり、岸信介の支援で日本に進出してきた。安倍晋三の暗殺事件以降に暴露されてきたのは、今日まで続く自民党と統一教会の癒着だった。
満洲を、あるいは満洲への野望を象徴する小刀が佐世保の海に沈められても、満洲の亡霊はいまも日本で、あるいは韓国で無視できない力を発揮している。
五味川純平は「戦争と軍国主義」に反対して弾圧された反戦活動家や、遊撃戦で日本軍を苦しめた中国共産党を肯定的に描いた。しかし、こうした戦後民主主義的な構図はすでに失効している。日本人の加害性を容赦なく描き尽くした船戸与一が、かろうじて肯定性を託したのは、満洲の原野をノマド的に放浪する敷島次郎のキャラクターだった。しかし次郎もインパール作戦で死亡する。
『地図と拳』の作者が未来を託しているのは、コスモポリタンである明男と、外来の共産党員さえ拒否した土着民の丞琳だろう。いわば明男はナショナリズムを上に、丞琳は下に突き抜けている。地図と地図が、国家と国家が永続的に抗争し続ける「拳」の世界を超える未来のために、明男と丞琳は廃墟の仙桃城で再会することになる。
《ジャーロ No.88 2023 MAY 掲載》
■ ■ ■
★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!
ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。
お気軽にフォローしてみてください!
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
