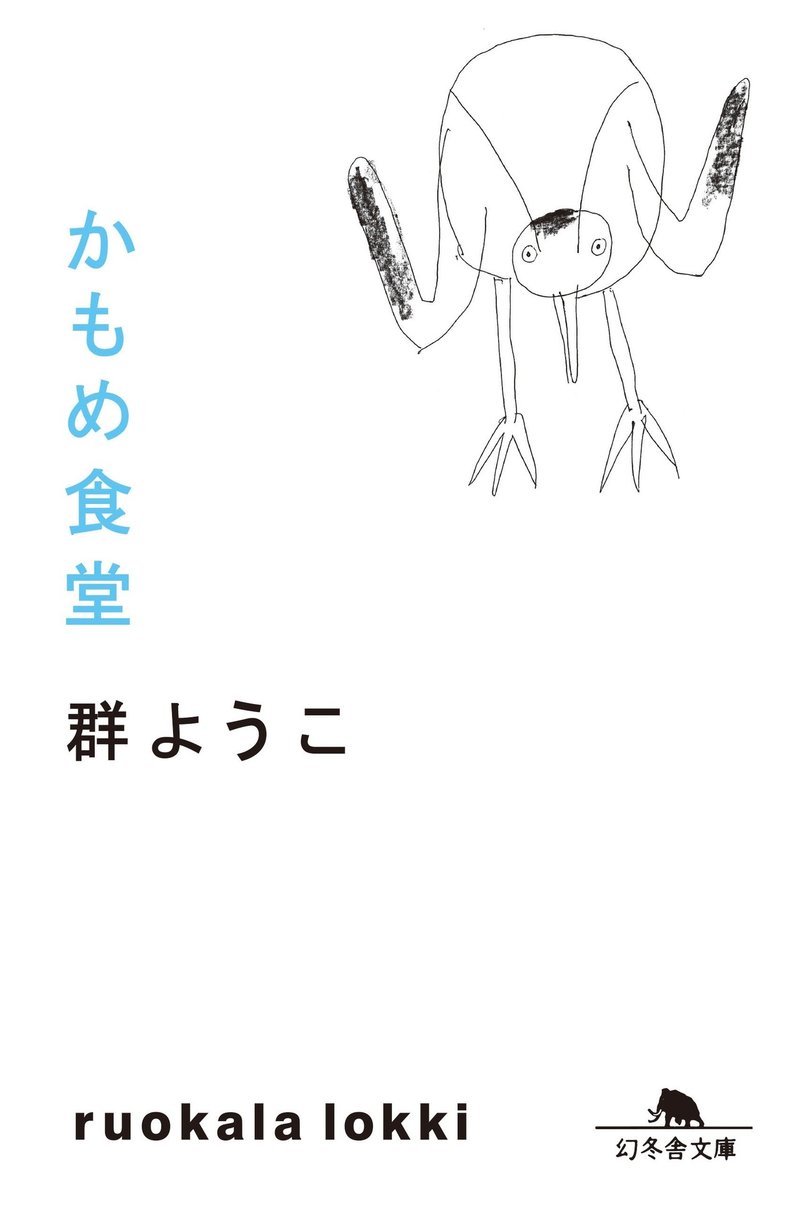かもめ食堂 1┃群ようこ
「かもめ食堂」はヘルシンキの街なかにひっそりとある。
大きな看板も出しておらず、ドアのところに「かもめ食堂」という日本語と、フィン語で「ruokala lokki」と小さく書いてあるので、それとわかるようになっている。
以前、ここは地元の太った名物おばさんが経営している食堂だった。彼女が急死してから、半年以上、店は閉められたままになっていて、周囲の人々はいったいどうなるのだろうかと気にしていた。
そしてある日、店の中を片づけていると思ったら、しばらくして東洋人の女の子がいつも一人でいるようになった。
近所のおじさん、おばさんは興味津々だった。
「『かもめ食堂』って書いてあったけど、行ってみた?」
「窓から中をのぞいたら、子供がいたんだ。女の子だ。他に誰かいるのかと見ていたんだけど、誰もいない」
「たまたま親がいなかったんじゃないの」
「いや、いつ見ても一人なんだ」
「おばさんの親戚かしら?」
「そんなはずはないわ。ほら、あの太った息子二人しか子供はいないはずよ」
「それはそうねえ」
「子供一人で置いておくなんて。さすがに東洋人は子供でもよく働くわね」
「もしかしたら無理矢理に働かされているんじゃないかな」
「それにしてはあの女の子、いつも元気で楽しそうよ。聞いたことがない曲だけど、鼻歌なんか歌ったりして。でもそういえば店の大人の姿は見たことないわ」
「朝から晩まで店にいるし、学校にも行ってないみたいだよ」
「児童虐待じゃないだろうね。元気に楽しくするしかないって、あきらめているんじゃないだろうね」
まじめに心配する人も出てきた。謎の「かもめ食堂」はおおっぴらではなく、ひっそりと周辺の噂になっていた。が、誰一人、「謎の東洋人の女の子」であるサチエをつかまえて、
「あなたはどうしてここにいるの? どこから来たの?」
と聞く人はいなかった。
みな関心を持ち、おかしいなあと思いつつも、遠巻きにして静かに眺めるだけである。フィンランド人は、見知らぬ人にはフレンドリーではない。多くは人見知りだ。店の前を行ったり来たりして中をのぞき、偵察隊と化してみんなに結果を報告する。
「店は開いていたけど、客は入っていなかった。店にいるのは今日もあの子供だけだよ。あの子が注文をとって料理を作るみたい。フライパンや鍋を持ってきて、それをじっと眺めたりしていたもの。でもちゃんとした料理が作れるのかしら。あれは『かもめ食堂』じゃなくて『こども食堂』だわ」
サチエの知らないところで、周囲の人々からは「こども食堂」と呼ばれていた。
サチエはいつも一人で、客が来ない店の中で日がな一日、グラスを麻のクロスで拭いたり、掃除をしていた。日本人がオーナーでありながら、扇子やら日本人形やら富士山の写真など、日本を象徴する飾り物が一切ないので、外からはどんな店かはとてもわかりにくい。
外国でわざわざ日本をアピールするのは、ものすごく野暮ったいとサチエは考えていた。さりげなく地元にすっととけ込んだ、お店をやりたかった。どこの国の人間だっていいじゃないか。だから他の国で、日本人を必要以上にアピールするのは、サチエにとってはものすごくださいことだったのである。
いくら暇でもじっとしていられない性格のサチエは、何か仕事を見つけては体を動かしていた。棚の食器を並べ替えたり、床のしみをていねいにこすり取ったり、そんなことをして一日を過ごしていた。
作業をしながら、ふと人の気配を感じて窓のほうに目をやると、不思議そうに外から中を見ている人々と目が合う。目が合って、入ってきてくれるのかなあと期待すると、相手はそのままふっと通り過ぎてしまう。誰もドアを開けて入ってこようとしない。
駅のそばでチラシを配ったり、新聞や観光客相手のガイドブックに広告を出せば、まだ気付いてもらえたかもしれない。
でもそれは嫌だった。気付いてもらえる人に気付いてもらえればいい。
大げさな宣伝や広告を打つのは、サチエの性分には合わなかった。
客数ゼロの日が延々と続き、それでもサチエはここヘルシンキで自分の店を持てたことがうれしく、嬉々として体を動かしていた。
しかし店内はどんどんきれいになっていく一方で、売り上げは全く変化がなく、ゼロのままだった。
サチエは三十八歳になったばかりだ。
地元のフィンランド人に「子供」といわれていたのは、小柄でかわいらしい顔立ちのせいである。
彼女の父は古武道(こぶどう)の達人で、幼いころから自分の道場に一人娘のサチエを連れていき、熱心に指導した。そこには世界各国から、武道を習得しようという、白い人、黒い人、黄色い人たちが集つどっていた。道場の壁には、
「人生すべて修行」
という父の筆による書が掲げてあり、これは父の口癖でもあった。
運動神経のいいサチエは、敏捷な身のこなしで、みんなに一目置かれていた。とにかく技の形をすぐ覚え、これが男の子だったら、ものすごい技の使い手になるだろうといわれていた。
しかし当のサチエにとって武道は、好きだけれど趣味のようなものにすぎなかった。というよりも、父がサチエの才能を見抜き、より高度な技を求め始めたので、このままでは抜き差しならぬ状態になると、小学校の高学年のときに不安に陥ったのである。
このまま武道ばかりやっているのは嫌だ。
それでも父の指導は熱心になり、周囲も、がんばれ、がんばれという。そういわれればがんばって、子供武道大会で優勝したりしたものの、いつもこのままでいいのかなとそればかりを考えていた。
頃合いを見計らって、そろりそろりと父の顔色を窺いながら、武道から距離を置こうとしたとき、サチエの母親が買い物帰りにトラックにはねられて亡くなった。サチエが十二歳のときだった。
このときも父がいったのは、
「人生すべて修行」
だった。
葬式でも父は涙を見せず、サチエにも、
「人前では泣くな」
といい渡した。
陰ではたくさん泣いたが、いわれた通り、人前で泣き顔を見せた覚えはない。母の死をきっかけに、サチエはこれまで武道に割いていた時間を、母がやってくれていた家事に費やすようになった。
学校に行く前に父と自分の弁当を作り、学校から帰ると晩御飯の支度をする。それまでは父親にばっかりくっついていたものだから、家事はみんな母親まかせだったのが、自分がやってみると、それなりに面白かった。
活発なサチエが、中学校に入学早々、学校のフェンスに向かって跳び蹴りをくらわすところを、クラスメートに見せたのはいいが、制服のスカートをひっかけて、破いてしまったことがあった。
その直前に、父は武道大会で優勝して賞金をもらっていたし、お母さんも死んだし、新しいスカートを買ってくれるかなあと期待していたが、
「だめ」
のひと言で片づけられてしまった。
学校の家庭科の先生に、つぎの当て方を教えてもらいながら、自分でやってみたが、はじめてだったのでうまくいかず、一目で、
「ここにつぎが当たっています」
とアピールしているスカートになってしまった。自分の不注意とはいえ、若い娘にとっては辛いスカートを穿いて登校し続けなくてはならなかった。
しかしその心中を父に見透かされ、
「物を大切にして何が恥ずかしいものか。堂々としていろ。人生すべて修行だ」
といわれた。
サチエもそのうち慣れてしまい、つぎのことは何とも思わなくなったが、話を聞いた同級生のお母さんが気の毒がって、その子のお姉さんが穿いていたスカートをくれた。サチエのサイズよりも、二段階くらい大きかったが、それをウエスト位置で黒の太いゴムひもで縛り、ずっと穿いていた。
裁縫はこの程度だったが、料理はどんどん上手になった。料理上手の母親が料理ノートを残してくれていて、それを見ながらアレンジして、煮物、焼き物はもちろんのこと、和菓子まで作った。
サチエが道場に来なくなったので、最初はぶつぶつ文句をいっていた父親も、妻亡き後、熱心に家事をしてくれる娘に対して、そのうち何もいわなくなった。
遠足の日、お弁当を作らなければと起きたサチエは、台所で物音がしているのに気がついた。
どうしたのかと行ってみると、ふだんは瓦を割ってみせたり、弟子たちを投げている父が、その手でおにぎりを作っていた。
「お父さん」
声をかけると、彼はびっくりしたように振り返り、
「いつも自分で作って自分で食べているんだろう。おにぎりは人に作ってもらったものを食べるのがいちばんうまいんだ」
大きな鮭、昆布、おかかのおにぎりを見せた。他には卵焼きも鶏の唐揚げも何もない。サチエはそれを遠足に持っていって食べた。
他の子はお母さんが作ってくれた、華やかな色合いのお弁当だったが、父が作ってくれたシンプルなおにぎりは、不格好だったけれども、サチエにとってはとてもおいしかった。
それから父は、中学校の三年間、遠足と運動会の日のお弁当だけは作ってくれたが、それはいつもおにぎりだった。
* * *