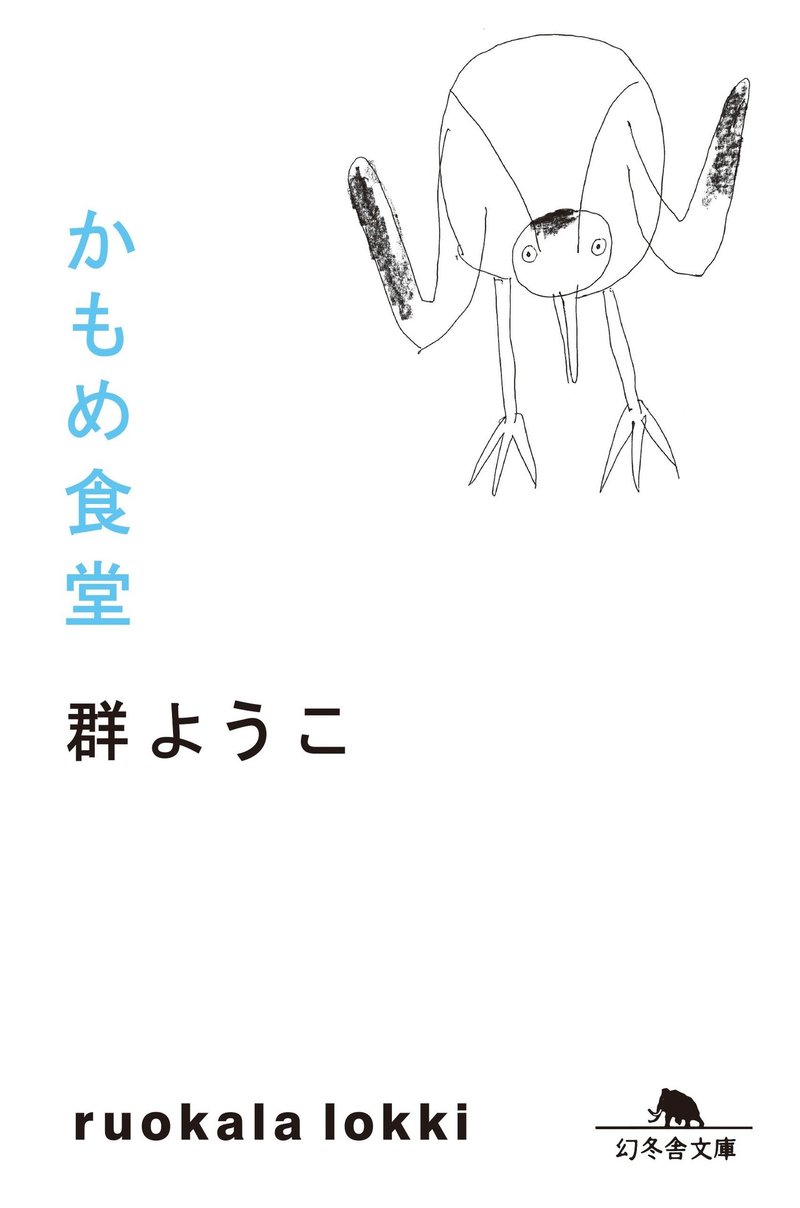かもめ食堂 4┃群ようこ
いちばん最初に誰が気が付いて来てくれるだろうかと、サチエはグラスを磨きながら、日がな一日待っていた。実は周辺の人々はみな気が付いていたのだけれど、最初の一歩が踏み出せなかったのである。
ある日、厨房の中で、同じ皿なのにどこか大きさが違うような気がしてきて、じーっと見比べていると、静かにドアが開いた。
はっとして顔を上げると、そこにいたのは、へたくそな手描きのニャロメが描かれたTシャツを着て、半ズボンを穿いた青年だった。サチエはうれしいというよりも、びっくりした。何も宣伝などしなくても、ドアを開けて入ってきてくれる人がいたからであった。彼は、サチエの顔を見て、ぱっと顔を輝かせた後、にっこり笑いながら、
「コニチハー。カ、モ、メ?」
とドアを指差しながら語尾を上げた。
「ヨー(はい)、かもめ。lokki」
「アア、ソウデス。ワタシ、ヨメマスタ」
ちょっと怪しい日本語で彼は話しかけてきた。
「ニホンゴ、ベンキョ、チョットシマシタ。ドコデ? シミンコウザデ。ニホンジンノオクサマガ、オシエテクレマスタ。ニホンノジ、エート、エロガナ、トテモカワイイデスネ」
「えろがな?」
サチエは首をかしげた。
「エー、アー、マルイデスネ。『か』『も』『め』」
空に指で書いた。
「ああ、ひらがなですね」
「ア、ソウデス? ヒーラガナデスカ。アア、センセイ、イッテマシタ。ヒーラガナ、カタカネ、カンズ。オモイダシマシタ。ワタシノナマエハ、トンミ・ヒルトネンデス。ドゾヨロシク。アナタノオナマエハ、ナニデスカ」
地元の人にしては珍しく、おしゃべりな青年であった。サチエは彼の覚え間違いを訂正し、コーヒーを淹いれてあげた。彼はカップを前にして熱く語りはじめた。
トンミくんは一年前、たまたま日本のアニメーションを見て興味を持ち、少しでも日本語を理解しようと、ヘルシンキの市民講座で、短期の日本語のクラスが開講されたのを機会に、そこで勉強したこと。ぜひお金を貯めて日本に行って、ガッチャマングッズをたくさん買いたいのだといった。
「はあ、ガッチャマンねえ」
「ガッチャマン、スバラシイデス。コンドルノジョー、ケン、ジュン……アアッ……」
青年は胸の前で両手を組み、うっとりした顔で身もだえした。
「でも、あなたが着ているのは、ニャロメのTシャツですね」
サチエはクールにいい放った。
「コレ? デスカ。ハイコレハ、ニャロメデス。ガッチャマンデハアリマセン。ガッチャマンノツギニスキデス。ハイ、デモコレハ、ニャロメデス」
「どこで買ったんですか」
「ドコデ、カッタ? ハイ。ニワデカイマシタ」
どうやらフリーマーケットが開かれ、そこで買ったらしい。Tシャツをよく見ると、ニャロメは太字のマジックインキみたいなもので描かれ、もちろんへたくそであった。白いTシャツが寂しいので、適当にニャロメを描いたといった感じの、どうでもいいTシャツであったが、彼はとても気に入っているらしく、襟元はよれよれに伸びていた。
「ガッチャマンハ、ダイスキデス。ウタモスバラシイデス。『ラレラ、ラレラ、ラレラーッ……』」
調子っぱずれの声で彼は歌いはじめた。アニメーションには疎いサチエにも、それは明らかに勘違いしているのがわかった。
「それは『誰だ、誰だ、誰だー』じゃないですか」
「『ジャナイデスカ』ッテ、ナンデスカ」
この構文は彼にはちょっと難しかったようだ。
「あなたは、間違えています。わかりますか」
「マチガエテイマス。アア、ハイ、ワカリマスタ。エッ、マチガエテイマスカ? ドコ、ドコ?」
彼が焦ったのを見て、ついサチエは曲を口ずさんでしまった。
「オオオオオー」
トンミくんは感動で再び身もだえした。そして背負っていたデイパックの中からあわてて紙とボールペンを出して、
「マタ、マタ、ウタッテクダサイマセ。オネガイシマス」
と目を輝かせた。サチエは、
「誰だ、誰だ、誰だー」
と歌い、彼は、
「dareda dareda dareda」
と書きとめた。書き終わるとぱっと顔を上げ、期待の目でサチエの顔を見る。
「ごめんなさい。ところどころしか、歌詞を知らないの。あのね、私はここと、『地球はひとつ、地球はひとつ。おーガッチャマン ガッチャマン』のところしかわからないの。ごめんなさい」
彼はきょとんとしていたが、事情を理解したようで、がっくりと肩を落とした。サチエはおぼろげな記憶をたどりながら、小声で歌いはじめたが、やはり全部を覚えているわけではなかった。
「ミンナ……、ゼンブ、ワカリタイデス」
悲しそうな顔をした。なまじ歌ってしまったために、期待を持たせてしまって、サチエは彼が気の毒になってきた。
「ガッチャマンノウタ。シリタイデス。ワカラナイノハ、トテモオオキナ、カナシイモンダイデス」
トンミくんにとってはトテモオオキナ、カナシイモンダイと聞いて、主題歌を口ずさんでしまった自分をとても後悔した。彼は困ったような顔で、じっとサチエを見つめている。
「ごめんね。少し時間がかかるかもしれないけど、調べて正しい歌詞を教えます」
そういってやっと納得してもらった。
結局その日は、厳密にいえば客ではない、トンミくんしかお客は来なかった。おかわりのコーヒーも店の持ち出しになった。
「サチエ……チャン。ワカリマシタ。ココスキデス。マタクル。サチエチャン、サヨウナラ」
彼は合掌をして店を出ていった。
「はい、ありがとうございました」
店を出て見送ると、トンミくんは何度もこちらを向いて大きく手を振り、自転車に轢(ひ)かれそうになっていた。
次の日、彼はゲイシャチョコレートを持ってきて、サチエにくれた。パッケージにいかにも外国人が描いた芸者の姿が印刷されている。
「キートス(ありがとう)」
サチエに喜んでもらったとわかったトンミくんは、満面の笑みを浮かべて、満足そうに何度もうなずいた。彼が店にいることで、地元の人も少し安心して入りやすくなったのか、ぽつりぽつりとお客さんが来るようになった。
彼らは椅子に座って、きょろきょろと店内を見渡し、どこをどう見ても、サチエ以外に店の人間がいないので、
「やっぱりあの女の子が、一人でやってるんだわ」
と小声でささやき合った。
トンミくんは日本語が少しわかるとあって、地元の人々に対して、日本通として優越感を持っているようだった。しかしそれは地元の人々にとっては、何の尊敬にも値しなかった。
「かもめ食堂」のメニューは、ソフトドリンク、フィンランドの軽食。煮物、焼き物などの日本食、夜はアルコールも出す。味噌汁、そしてサチエの一押しであるおにぎりが、おかか、鮭、昆布、梅干しと揃っている。
しかし客の注文はほとんど、ソフトドリンクとフィンランド料理ばかりだった。注文をとるときは必ず、
「おにぎりもいかがですか」
と勧める。
なじみがないフィンランド人が、それはいったいどういうものかとたずねるので、握ったものがあればそれを見せ、ないときは説明する。
それを見たトンミくんは、
「なかなかおいしいですよ」
と横からしゃしゃり出てくるのだが、それを聞いておにぎりを注文する客は一人もおらず、みんなに、
「いや、結構」
と見事にきっぱりと断られた。
自称日本通のトンミくんが、珍しく自腹を切っておにぎりを注文したことがあった。おかかと鮭の二個セットだったが、鮭はともかくおかかのほうは、飲み込むのに難儀しているようだった。
それでも日本通のプライドにかけて、
「トテモオイシイデス」
というしかなく、涙目になっていたのを、サチエは見逃さなかった。
それでも彼女は、おにぎりに固執した。作る人が心をこめて握っているものを、国は違うとはいえわかってもらえないわけがないと信じていた。客にお勧めを拒否されても、彼女は腐ることもなく、にこやかに客と接し続けていた。そんなサチエを、トンミくんはうっとりと眺めていた。
青年の「かもめ食堂」への日参は続いた。彼は厨房で忙しく立ち働いている彼女に、あれやこれやと話しかける。
「だめ。今は忙しいの」
ふだんはふんふんと彼の話を聞いてあげるサチエだが、仕事となるとそれに没頭した。一喝されると、
「アア……ハイ……スミマセン」
としゅんとして店の隅に座っている。そして客足が途切れたのを見計らって、なんだかんだと話しかけてきた。
「オトウサン、オカアサンハドコデスカ」
「お父さんは日本にいますよ」
「ニホンデ、イルデスカ? フィンランドニヒトリデスカ?」
トンミくんは不思議そうな顔をした。
「そうですよ」
「サビシクカナシクナイデスカ」
「いいえ」
きっぱりとサチエはいった。
「デモ、オンナノコヒトリ、アブナイデス」
「女の子? 誰のこと?」
「サチエサンデス。オンナノコデス」
「ああ、まあ、広い意味ではねえ……」
「ヒロイイミッテナンデスカ? ソレハドウイウコトデスカ」
彼は必死の目つきになった。
「あ、あの、私は女だということです」
「ソウデス、ソウデス」
真顔で大きく何度もうなずいた。
「ガッコウハ……、イキマシタカ?」
「行きましたよ。東京の大学を卒業しました」
「…………」
うっと言葉に詰まった。
「ア……」
明らかに彼が落胆しているのを見て、サチエは、
「私、いくつ、何歳に見えますか?」
と直球を投げた。
「イクツ、イクラ、ナンサイ……。ナンサイデスカ?」
「はい、私が何歳だと思いますか?」
彼はだんだん顔を紅潮させながら、小声で、
「十五歳」
といった。
「十五歳?」
サチエはげらげらと笑った。トンミくんは口を真一文字に結んで緊張した顔をしている。
「私は三十八歳です」
明らかに彼の瞳孔が開くのがわかった。一瞬、くらっときたらしく、壁に頭をぶつけた。
「サンジュウハチサイッテ、サンジュウハチコ、サンジュウハチネントオナジデスネ」
涙目になっていた。
「そうです」
「フエ~ン」
彼は何ともいえない声を出しながら、サチエの顔を見つめた。
「スコシカナシイデス。デモガンバリマス。ナカナイデス。キョウハサヨナラデス」
彼はがっくりとうなだれて、荷物を持って店を出ていった。その後ろ姿を見送りながら、サチエは、
「早いとこわかったほうが、彼のためにもいいし」
とつぶやきつつ、もう店には来てくれないかもしれないと思った。
* * *