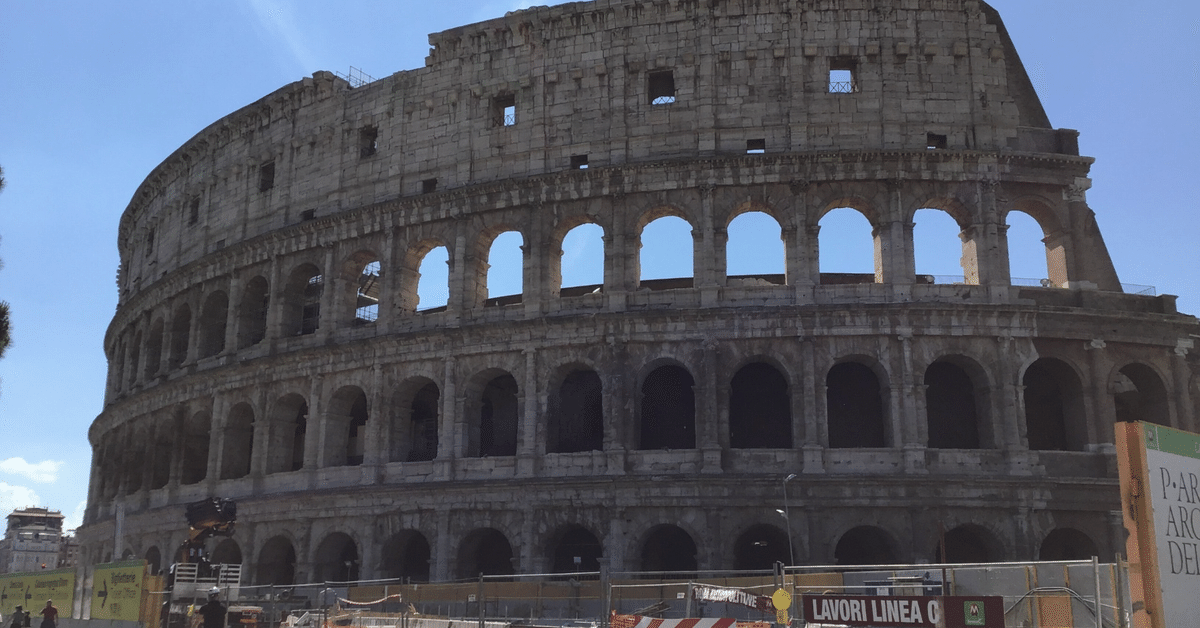
ローマ帝国とポルトガル(6)信仰
00.はじめに
ここでは、ポルトガルの歴史についてお話しした際のメモ書きを公開しています。今回はローマ時代を扱った部分です。なお、メモ書きは、アンソニー・ディズニー著『ポルトガルとポルトガル帝国の歴史』に基づいて作ってあります(ほぼ翻訳になってしまっていて、反省ですが)。関心のある方は、Anthony Disney, A History of Portugal and the Portuguese Empire(2009)をご覧ください。
前回は、現在ポルトガルと呼ばれる地域の社会的側面について言及しました。
前回の記事
今回はローマ時代の文化的側面、とくに信仰について見ていきます。
1.ローマの神々の定着
キリスト教が国教となるまで、ローマ帝国はさまざまな神々が祀られていました。つまり、多神教だったわけです。現在ポルトガルと呼ばれる地域でもまた同様にさまざまな神々が信仰の対象となっていました。ローマ帝国の進出以前には、北部にはケルト人、南部にはフェニキア人やギリシア人、カルタゴ人が到来し、それぞれに文化的な影響を与えていました。その点については信仰についても同じです。
ローマ帝国が進出すると、現地に根付いた信仰はローマ帝国の文化的影響を受けていきました。ケルト人が持ち込んだ神々がラテン語で表記されるようになったり、現地で信仰された神々がローマの神と同化したりしたのです。たとえば、戦士の神でルシタニア人の間でひろく信仰されていたトゥレバルナという神は、最終的にはローマの女神ウィクトリアと同一視されるようになります。

Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343373による
また、ユピテルは現在ポルトガルと呼ばれる地域でも信仰を集めました。最初は都市で、やがて周辺地域で信仰されるようになりました。ユピテルは、ローマ神話のもっとも中心的な存在で、天空をつかさどる神とされます。英語読みでは、ジュピターともいいます。ローマ帝国において、ユピテルは神話の最高神というだけでなく、国家的もっとも重要な信仰対象でした。ローマでは、執政官の就任や将軍の凱旋には、必ずユピテルに報告するため神殿に参詣したとされます。

Dodo (トーク · 投稿記録) - 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38992による
国家的に重要な神であったユピテルに対する信仰は、現在ポルトガルと呼ばれる地域でも重要なものとなっていったようです。ユピテルを祀る祭壇は、市街地だけでなく、非常に小さい定住地、ほとんどローマ化されていないポルトガルの中部と北部の内陸にまで広がっていたといいます。
2.皇帝崇拝
また、ローマ帝国では、ユピテルに対する信仰と重なって、皇帝を神のようにあがめる皇帝崇拝も盛んでした。初代ローマ皇帝アウグストゥスは生前から崇拝されていましたが、死後神格化されました。すると、アウグストゥスの後継者たちも同じように崇拝の対象となります。
現在ポルトガルと呼ばれる地域でも同じように、アウグストゥスと皇帝一族の像と祭壇が、アウグストゥスによる平定後から作られて、重要な町に置かれていきました。このような皇帝崇拝はとくに1世紀、2世紀に盛んでしたが、3世紀には衰微していったとされます。
3.オリエントの神々に対する信仰
このようにローマの信仰と現地の信仰がまじりあっていく一方で、現在西アジアや北アフリカに含まれる地域ではじまった信仰も現在ポルトガルと呼ばれる地域で影響力を持っていきました。
アナトリア半島に起源があるという地母神であるキュベレーは、ローマ市で信仰対象となり、やがて現在でいうところのポルトガル南部アルガルヴェ地方で信仰者を集めました。

ChrisO - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4678601による
また、ローマ帝国時代にエジプトの神々であるセラピスやイシスも信仰の対象となっていたとされ、とくに後者はブラガ周辺まで広がっていたとされます。さらに、後200年ごろには、古代イランの神ミトラの密儀な宗教がポルトガルに到達したといわれています。
4.キリスト教
そうした東方で生まれた信仰の中で、もっとも影響力が大きかったのは、キリスト教の存在です。キリスト教はのちにポルトガル王国が存立する基盤になるからです。
あえて強調するまでもなく、キリスト教は紀元前1世紀にローマ支配下のパレスチナで誕生した宗教です。
キリスト教はユダヤ教の一派の洗礼者ヨハネの影響を受けたイエスによってはじめられました。イエスは、神の愛が貧富の区別なくすべての人に与えられる絶対的な愛であるとし、神の愛を信じて隣人を愛するよう説きました。キリストはやがて処刑されますが、やがてその教えを守ろうとする共同体がエルサレムを中心に生れ、伝道活動が行われるようになりました。

Edal Anton Lefterov - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15165689による
伝道活動は当初、キリスト教徒は迫害を受けました。しかし、その後、ローマ帝国の支配が混乱した3世紀頃から帝国内でキリスト教徒が多くなっていき、313年のミラノ勅令でキリスト教が皇帝から公認されました。これによって、ローマ帝国におけるキリスト教の地位が高まり、公にも普及していきました。さらに、392年にはテオドシウス帝がキリスト教をローマの国教と定め、その地位が確立しました
もっとも、現在ポルトガルと呼ばれる地域におけるキリスト教の普及がいつからはじまったのははっきりしていないようです。歴史家のディズニーは、同地域では、キリスト教徒のコミュニティが、3世紀初めまでに出現していたと述べています。
はじめキリスト教の改宗者は一般の自由人、奴隷、そのほか地位の低い人々に限られていましたが、次第にエリート層の住民もその中に加わっていきました。
やがて3世紀までには、少なくとも5都市(ブラガ、シャーヴィス、ファロ、エーヴォラ、リスボン)に司教が置かれていたようです。詳しいことはわかっていないようですが、司教というキリスト教徒を統括するような役職者がいたということで、現在ポルトガルと呼ばれる地域でキリスト教徒がそれなりの人数で、組織的に活動していたことはわかります。

そして、その後、ミラノ勅令(313年)が発布されると、現在ポルトガルと呼ばれる地域における信者の数はさらに増えたに違いありません。実際に同地域ではこの時期からキリスト教式の墓地も出現したとされます。
さらに、4世紀末には、イベリア半島西部におけるキリスト教はかなり強力な宗教となったと考えられています。
392年、皇帝テオドシウス一世はカトリックを国教であると宣言して、多神教も一斉に禁止しました。それによって、これまでローマがもっていた宗教的寛容性は失われました。現在ポルトガルと呼ばれる地域もまたその影響を受けなかったとは考えられません。ディズニーは、同地域におけるケルトやオリエントなどさまざまな地域の影響を受けて成立していた多神教的世界観は、キリスト教の陰に隠れてしまったと指摘してます。
ローマ帝国とポルトガル(7)につづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
