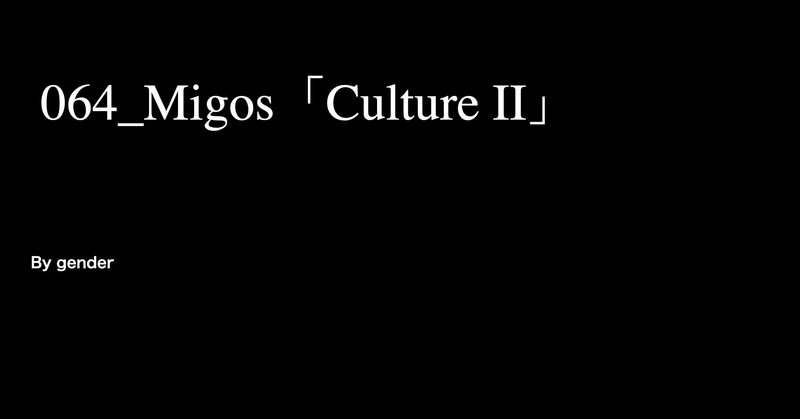
064_Migos「Culture Ⅱ」
広島行きのぞみの新幹線の自由席の座り心地がなんとなく悪い。3人シートの通路側。真ん中は空いていて、窓側には長い黒髪の美しい女性がビールを飲みながらずっと景色を眺めている。自分にとってはいつになく、居心地が悪いものとなってしょうがない。それは今の自分の気持ちを反映しているからだろう。実家の広島に帰るのは、いつも億劫で暗澹たる気持ちになる。それが父の存在によるものだということもよくわかっている。
こうやって父を説得するために帰るのも、もう3回目になる。いつになったら、わかってくれるのだろう。これまで真之介との結婚を認めてほしいと何度も何度も訴えてきたが、父の態度はいまだに頑なだ。母も「お父さんがああ言うんじゃね」という曖昧な態度。なんともやりきれない。
地方の新聞社で社会部部長をやっていた父の言うことは、いつまで経っても型にはまったものであり古臭い。まるで新聞の隅っこでいまだに遺跡のように昔から残る古臭い社説のようだ。
「男はちゃんとした会社勤めでないとダメだ。起業家か自営業なのかよく知らんが、正直あの弟が何をやっているかわからん」
父は彼のことをそう切り捨てた。
でも今は、多様な働き方が叫ばれている時代、会社勤めだけが偉いとかそういう時代じゃない。彼は自分で人材派遣業のクラウドサービスを起業して、今もちゃんと実績を出している。確かに真之介の態度も良くないところはあったことは認める。でも、彼はいつでも誰に対してもフランクな態度だし、そうやってフラットに人脈を増やしてきたから、一概に彼の人となりを批判する気に私はなれない。
彼は文字通り父と対照的な型にはまらない性格である。中学で型通りの教育に違和感を覚えて不登校になり、フリースクールに通って大学検定を取って、米国の大学で勉強して日本に帰ってきてから今の仕事を起業した。自分の可能性を信じて突き進む姿勢は見ていて立派だとは思う。ただ、間違いなく父とは合わない。
昨年秋、彼をはじめて広島の実家で両親に会わせた。その時から、父の機嫌がよくないなと言うのは感じ取れた。一応緊張している体の真之介に対して、腕組みをして深く息を吐く父。まず真之介の格好が良くなかった。彼は仕事柄、カジュアルで自由な格好でいることが普通で、夏などTシャツに短パンなどの格好も多い。今回は一応、親への挨拶ということで、申し訳程度にグレーのジャケットは羽織ってきたけれど、インナーはシャツにネクタイではなくて、白いTシャツ、足元はシルバーのラインの入ったハイテク目の白スニーカーだった。
「こんなんでも十分っしょ」
行きの新幹線でこともなげに彼は話していた。私の両親に会うことに対しても特に緊張した様子もない。新幹線の中の方が、なんか仕事が捗るから」と言って、私の横でBOSEのヘッドフォンで重低音のヒップホップを流しながら、ノートパソコンを取り出して仕事をしていた。(彼はいつもそうやって仕事をしている)
しかし、やはり私の不安は的中した。彼にとっては、ジャケットを羽織るだけでも、だいぶキッチリ目な格好なんだと思うのだけど、明らかに父に対しては逆効果だった。
「黒のスーツにネクタイ、革靴で来るのが当たり前だろう」
まるで父が就活の面接官のように、目で訴えかけているようだった。真之介は街で決まりきった型通りの就活生の格好を見ると、「あんなカラスみたいな格好をした奴らは、うちの会社では絶対に取らない」と豪語していた。
父母と私たちが対面している居間のテーブルの上には、彼がGINZA SIXで選んだ派手目なスイーツが所在なさげに佇んでいる。おそらくこれも父の嗜好に合わなかったのだろう。(後で、母からも「お父さんには、下町の老舗の羊羹とかお団子とかそういう和菓子の方がよかったわね」とこぼしていた)
話が全く盛り上がらない。
「仕事はなにをされているのか」必ず出る話題だが、特に彼の仕事の話になると、父は苦虫を噛み潰すような表情を浮かべた。彼の言っている話がとても理解できないといった印象だ。「男は仕事してナンボだ」特に仕事に対して一家言というものを父はいつも持っていて、いつも、男=仕事という頑固たるイデオロギーを掲げていた。
私は子供の頃から、いつもきっちりとシワのない濃いグレーのスーツに、曜日によって決まったネクタイを着けて、朝7時決まった時間に必ず家を出る父を見送っていた。
「これからは仕事なんて、それぞれ自由なやり方でやっていけばいいんですよ」
渋谷のコワーキングスペースで仲間と話す時の語り口と同じように、カジュアルに仕事について話す真之介の言いぶりを気に入る訳が無い。
ブブ。真之介のスマホが震える。
「あ、すいません、ちょっといいすか。どうも、仕事の電話みたいで」
真之介は母に目配せで、台所で話していいか、という合図をした。母親は台所の引き戸を開けて、真之介を促した。彼は台所でポケットに手を突っ込んで立った姿勢で、ハンズフリーのイヤホンを耳にはめて、中空に向かって話し始めた。
「すいません、綾瀬です。いやー、今、ごめんなさい、ちょっと東京にいなくて。ええ、この前はありがとうございました。すげー、盛り上がりましたね」
父は呆れたように、お茶を飲みながら庭を見つめる。母も困った顔をして、私の顔を見る。台所で上機嫌で景色ばんで話す真之介の声が、居間にまで響いてくる。たぶんうちの家の堅苦しさから一瞬でも抜け出したからだろう。母と父と私は家族なのに、今は間がもたない。
「そーなんですね、いくら俺らの頭脳で考えるよりも、あの人たち頼った方が良くないすか。コージさんとか頼って、ド派手なイベントやりましょ。ねえ、その方が良くないすか。ふんふん、大丈夫っしょ、さすがに。ええ、もうやってきてんの。こっち何もしていないのに。誰が言ってきてんの。あっちの?マネージャー?マネージャーが言ってきてんの?嘘!よく言うよ、ええーって感じだよね。」
「まあ、わかりました。そこは、うまくやりましょ。印上さんとこれまでやったことない形のものやってきますよ。いいじゃないですか。あーっいいすね、だからやりましょうよ。そこから一個も僕らのパイプできなくてもいいですから。お客さんに対して一個もマイナスな話ないじゃないですか。こうやってやる話であれば。小出さんとこの下でこのリモートワーク世代での生き残るノウハウみたいな。そう言うのが、どっちかというとあっちも嬉しいみたいな。」
「あ、そうなんだ。それなら印上さんにうちのお客さん紹介しますしね。モチベーションクラウドでってそっちの会社で使ってないのかかな。年間まあ、数百万の話であれば、こっちで買っちゃえばいいわけだし。その先24もあるわけでしょ。それって戦略的投資じゃないですか。それらをまあ、山田さんとかがジャッジしたとしてですよ」
彼が台所で話している内容が、私たちのいる居間に筒抜けだ。話が盛り上がってるようだ。彼の声が次第に大きくなっているのに対し、私たち3人の抱く感情は冷ややかだった。(いつも彼は夢中になると、だんだんと話す声量が増してくる)私は立ち上がって、台所にいる真之介の服の裾を引っ張り、もういい加減電話はやめて、というジェスチャーをした。真之介も本当にあっと我に帰ったような表情をした。自分が彼女の両親の実家にいることを思い出したようだ。こういう悪気のないところは天然だなあ、と感じる。
「すいません、長話しちゃって」
一応申し訳なさそうな態度で真之介が戻ってきても、父はお茶を飲みながら、可愛げのない老猫のようにすんとしている。
「ちょっと、先方と仕事の話をしていたんですが、すげー盛り上がっちゃって」
彼は居間のテーブルの前に座り直そうとするが、再び正座することが億劫だったようで、あぐらをかく格好になった。
「あれが仕事の話か」
父はふーっと息を吐いた。時代は変わったな、とでも言い出しそうな口ぶりだった。友達と話しているようにしか聞こえなかったのだろう。その言葉に、父が何かをいろいろとを諦めたような、そんな感情が込もっている気がした。GINZA SIXで買ったスイーツは、いつまでたっても手をつけられることなく、テーブルの上に置かれたままだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
