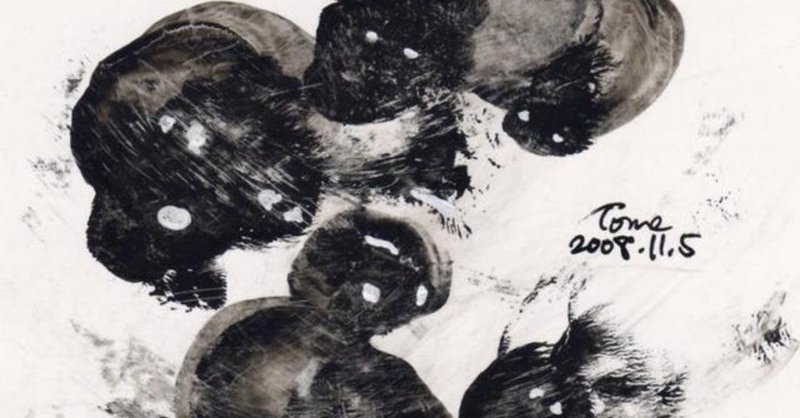
榛葉英治『城壁』(文学通信)を読んで
直木賞作家である榛葉英治(しんばえいじ)による、日中戦争における南京攻略、およびその占領下での日本軍の蛮行を描いた長編小説。
『城壁』は、多くの資料を下敷きとはしているが、あくまでフィクションとして書かれた"文学"である。したがって、その描写にどれほどの迫真性、真正性が感じられようとも、例えばこの文章を、"南京における日本軍の蛮行を明らかにするための客観的物証"として読むことはできない。
しかしながら、読者の多くは、この作品を読みながら、確信を抱くに違いない。「これは、なんとしてでも未来へと継承していかねばならない、とても大切な作品だ」と。
では、例えば僕たちは、この作品の何処にーー決して歴史的な資料とはなり得ないこの"文学"としてのテクストのいったいどのような点に、そうした確信を抱くのだろうか。
『城壁』のポリフォニー
『城壁』の語りの特異性は、その企図された多声性にある。企図された、というのは、そもそもあらゆる文学作品はポリフォニックな場であるわけだが、特にこの作品は、そうした多声性を、その語りの構造においてあからさまに可視化しているからである。
例えばこの作品において、語り手が寄り添う――つまりその内面や心理が直接語られる人物(俗にいう、視点人物)は、目まぐるしく変わる。章ごとに変わるだけでなく、同じ章の同じ場面でも、先ほどまでAの心中を描写していたかと思えば、今度はBの思いを叙述したりする。
そしてその各々が、日本軍が今まさに南京を蹂躙するその場に存在し、その同一の出来事を経験している…のではあるが、その受け止め方は、文字通り、各人各様である。
なんの躊躇いもなく中国人を殺し、あるいは強姦を楽しむ寺本伍長。
日本に残した妻や子どもを思い、寺本らによる中国人女性の陵辱に付き合いながらも、罪悪感に"最後まで"苛まれる鈴木上等兵。
彼らを率いる江藤少尉は、
戦場でない場所で、武器をもたない無抵抗な人間を殺すことは考えてもいなかった。彼はいまはじめて、戦争とは何であるかという考えにつきあたった。日本人と中国人は、なぜ、戦わなければならないのか(p56)
と懊悩する。
日本軍による中国人の虐殺の現場を目にし、それに憤りながらも、嘘八百の国威発揚の記事しか書くことのできない新聞記者たちの葛藤。
また、日本軍による蛮行からなんとか中国人を助けようと奮迅する国際委員会のメンバーも、ヒトラーを敬愛するドイツ人、協働しながらも心底では彼を軽蔑するアメリカ人教授、現実のあまりの残酷さに神への信仰が揺らいでしまう、同じくアメリカ人の神父、等々。
南京大虐殺事件という同一の出来事に対峙する眼差しは、まさに多角的に記述されていくのである。
あるいは、以下のような人物造形にも、ある意味での多声性を読むことは可能だろう。
「おい、射ってしまえ。生かしといても仕様がないぞ」(p11)
「ちき生ッ! お前らの仇はうってやるからな。待っていろ。つらかったろうなあ」(p25)
引用した二つのセリフは、どちらとも、倉田軍曹という人物のものである。前者は、道を歩いていた中国人の女性を殺した後、その死んだ母親の腕の下にいた赤ん坊を撃てと命令する、およそ人間性の感じられない、非道なものである。対して後者は、リンチを受け殺され、晒された日本兵の遺骸を目の前にして、「涙をこぼし歯がみをし」ながら発された"義憤"の言葉である。この対照性。そして後に、倉田軍曹は、80人の捕虜の虐殺を命じる。
交錯する視点の効果
繰り返すが、『城壁』は小説である。つまり、フィクションである。よってそこに描かれた内容は、決して、"南京における日本軍の蛮行を明らかにするための客観的物証"にはなり得ない。
しかし、そこに交錯する数多の視点ーーあまりにも多くの人物の眼差しを描き、時に矛盾する個々人の心中を克明に記述する書き方は、読み手に、とある一つの可能性を与えることになる。
それはつまり、
数多くの視点や思いが描かれることで、そのうちのどれか一つに、読み手が自己を同一化、あるいは投影し得る可能性が高くなる
ということだ。たとえその対象が、全273ページ中のたったの一文にすぎなかったとしても。
例えば、寺本伍長の語るかつての女性遍歴や猥談、それを聞きながら心浮く取り巻きに自らを重ねる読者もいようし、日本に残した恋人を思う江藤少尉に己を見る読者もいるだろう。
そして、その瞬間、読者は、その物語世界における当事者となる。つまりは、『城壁』の語り手が対峙した、あるいは対峙しようとした、南京の出来事…それを直接には経験せずとも、確かにそこに生起した何かしら尋常ではない出来事を、いや、それを物語化しようとする意思を、分有する主体となるのではないだろうか。
普遍性への昇華
こうして『城壁』の読み手は、その物語世界、あるいはその世界の先にある、決して現実としては経験し得ないけれど、確実に生起した恐ろしい出来事…あるいはそれと対峙しようとする眼差しの、当事者となる。それだけでも、このテクストの読みへと参入することの意味はあるだろう。
しかしながら、多角的視点とは、裏を返せば出来事の拡散でもある。散り散りに分裂していく出来事は、そこに生じる当事者性を、一過性の刹那的経験として霧消してゆく可能性も否定はできない。
ところがこのテクストには、その拡散を収斂するための仕掛けが用意されているのだ。
山内静人は東京外語の志那語科を出て、A新聞の東亜部にはいり、すぐに中国に渡った。南京支局へきてからは家族を郷里において、支局のこの二階で独身生活をしていた。胸に手を組み眼をつぶった彼は、学生時代に読んだダンテの〈神曲〉の「地獄編」を思い出した。ミケランジェロの絵でも見た気がする。人間が折り重なって死んでいる絵だ。苦悶している顔や手もあった。(p79)
あの二人の青年はどうなるだろう? 裏通りを難民区のほうへ歩きながら、ミルス神父は江藤少尉と黄夫婦のこれからの運命について考えていた。それは世界中の若者にも通じる道であった。(p241)
この二つの記述に共通することは何か。
それは、このテクストが語る出来事を、普遍的な経験へと止揚していこうとする意志である。
後者は「世界中の若者にも通じる道」と、今、ここで起きている出来事を共時的に敷衍し、そして前者は、それを西洋という遠く離れた地の、しかもルネサンス期というはるか昔の時代にもつながることとして、通時的に一般化しているのだ。
テクスト『城壁』は、読者をその出来事(について語る物語)の当事者として巻き込み、そして、そこでの経験を、人類に普遍的な出来事へと昇華する構造を有している。
出来事を語る物語の多声性(...そこに展開されるモザイク状の視点の一つは読み手のそれでもある…)は、個々個別の断片であることをやめ、一つの、人類史的な地平へと織りなされてゆくのだ。
文学を通して戦争を読むということ。
その営みの持つ意義や可能性の一つを、『城壁』は教えてくれているのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
