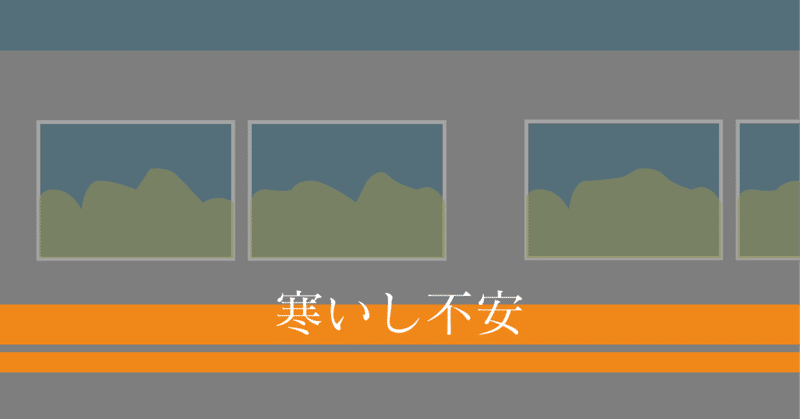
寒いし不安 な夕
降車駅が近づく。線路の緩やかなカーブに合わせて床が傾き、バランスが崩れた。網棚に掛けようと慌てて振り下ろした手は空をかすめ、危うく前の座席のスーツの男に突っ込みそうになる。が、すんでのところで後ろに半歩下がることで最悪の悲劇は回避することができた。これが今日起こったことの中で一番よいことかもしれない、というほどのついていない1日。
停車間近まで列車の揺れは収まりそうになかった。本に挟んである、薬局でおくすり手帳を忘れたときに渡されたシールを乗車前のページから今のページに移して、本を閉じる。10ページほど進んだことになっているが、目が上滑りするばかりで内容はあまり入ってこなかった。とにかく外界と目を合わせないために必死に視線を落とし込むためだけに開いている本、いつものことだ。
最近のイヤホンは性能も良くなり音漏れしにくくなっている、と誰かが言っていたけれど、であれば列車が風を切り線路を打ち付ける音の中でも耳に届くこの打ち込みのドラムの音は、彼の耳元では一体どれほどの音量で鳴っているのだろう。
10センチほど開いた窓からは、窓ガラスを通さないまっすぐな光の玉がいくつも駆け抜けていくのが見える。本当はあの光と逆の速さでこちらが動いている、というのは幼稚園生の頃から知っているがいまだに実感がわかない。いや、それどころか距離による遠近感を考慮すると、光の玉がそう見えているよりずっと速く我々を乗せた箱は動いているのだ。同じ箱に乗って同じ方向に動いているだけで、我々は我々になってしまう。先ほど突っ込みそうになったスーツの男も、その両脇の老婦人と青年も、皆知らぬ者同士だというのに同じ列車に乗っているかぎり。もし今この車両が横転でもして全員死んでしまったとしたら我々はひとくくりに、この列車の乗客だ。しかし、考えてみれば地球だってこの瞬間に崩壊してしまったなら、我々はみなひとくくりに地球の生命か。地球の崩壊は現実的にあり得ないとしても、東京くらいならこの瞬間に吹っ飛んで無くなることも全くあり得ないことではないかもしれない。私が私として私のままこの生を終えるには、ただ私だけが死を迎える瞬間に巡り会う必要があるのだ。こんなに人がいるのにそんなことできるのだろうか。
昔から、空が暗くなると息を合わせるように思考も暗くなった。これはよくないと思い、家にいるときは意識的に明かりを点けたまま寝たりもしたが、かえって悪夢にうなされる始末。人工的な明かりじゃだめなのだろうか。白夜の地域に滞在してみたい、寒くないならば。ここより寒い地域がこの国内にもあることが信じられない。一体そこで人々はどうやって暮らしているのか、想像もつかない。いや、イヌイットみたいな人たちがワカサギ釣りをしているようなところは容易に想像できる。本当に想像できないのは、ここより寒いところの人たちがこことそう変わらない生活を営み成立させている姿だ。
降車扉が開き、寒空に積もった雪がなだれ込むように人が出ていく。扉付近に立ち止まりになったお客様が出口を狭めているためにうまく流れ出ず、車内の人々は、振動で前に進む人形のような小刻みなステップで少しずつ進む。私もその中のひとり。
外の空気に開放されたとたん、我々だった塊は個々に霧散していく。とりあえずまず、ホームの先にある自動改札のところまでは。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
