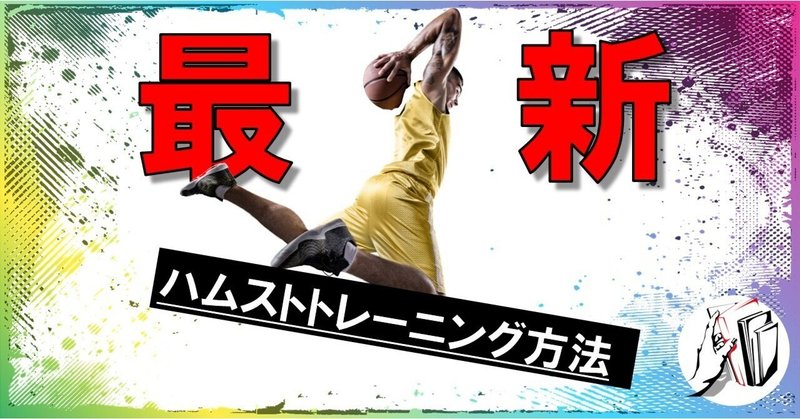
理学療法士・ピラティスインストラクターが考えるハムストトレーニング方法
1.はじめに
サッカーやスプリント競技で多く見られる疾患の一つに、ハムストリング損傷(ハムストリングスの肉離れ:以下HSI)があります。
ガクトレでも過去このHSIについてのブログをいくつかまとめておりますので、そちらも是非参考にしてください。
損傷の程度にもよりますが、少なからず一定期間は競技復帰に時間がかかってしまう事と、パフォーマンスの低下は予想できます。
そのためケガをしないための予防が重要となり、そのトレーニング方法が上記に添付してるブログ内に記載してます『ノルディック ハムストリングス エクササイズ:以下NHE』となります。
NHEは2008年の「Strength & Conditioning Journal」にも研究され掲載となっていたので、現場で導入されていたのはおそらくもっと以前からかもしれません。現在では海外のプロサッカーチームでも導入されているほどメジャーで、偏心的にハムストリングスの筋力を向上させるトレーニング方法となっています。
ですが、NHEが初めて導入されてから長い年月がたちますが、これまでにその方法やバリエーションには変化が起きなかったのでしょうか?
今回は2023年に掲載されていた海外の論文をもとに、NHEのバリエーションの違いがもたらす影響についてまとめていきたいと思います。
2.HSIについて
サッカーなどのスポーツで多くみられるHSIですが、Kerkhoffsらによると参加時間1000時間当たりのHSIの発生率は、非接触スポーツでは0.87で、接触スポーツでは0.92~0.96の範囲と報告がありました。
またHSIは再損傷のリスクもあり、特定のシーズン中または最初の損傷から2年以内に14~63%とされています。つまり、一度でも損傷の経験があるプレイヤーは再損傷のリスクがあるため、予防がかなり重要であるということです。

このHSIの予防として行われているエクササイズがNHEとなります。その予防の効果は高く、アスリートのケガのリスクを50%も低下させることができると報告されています。
もちろんNHEだけではなく、HSIのリスクファクターとしてハムストリングスの柔軟性低下や体幹筋力の低下など様々な因子があるため総合的なアプローチがもちろん重要ですが、NHEだけでもリスクを50%も低下させる影響があるためとても効果が高いことが伺えます。
このHSIですが、ある文献では損傷のメカニズムによって、異なる2つのタイプに分類わけできると記載されています。
1つ目のタイプはスプリントなど瞬間的なハムストリングスの収縮動作に関与しており、2つ目のタイプはハイキックなどのハムストリングスの伸張動作によって引き起こされるものと分けられて紹介されていました。
これは、スプリント型とストレッチ型のメカニズムが異なるためであり、この文献によるとストレッチ型のハムストリングスの損傷の回復期間は、スプリント型の損傷の回復期間に比べて著しく遅いとの報告もされていました。
この研究では異なる損傷タイプをMRIにより観察した研究報告でした。中でも興味深かったのが、修復期間の違いだけでなくスプリント型では遠位のハムストリングス、ストレッチ型は近位のハムストリングスに病理学的変化がみられていたという損傷タイプで損傷の部位も異なるという点です。
この件についてはまた別の機会に調べていきたいと思います。
少し話がそれたのですが、この様々な様式で損傷を受けるハムストリングスですが、今回参考にした文献はNHEの単一した方法ではなくバリエーションを変えることでどのような影響があるのか?をまとめたものでした。
以下にまとめていきたいと思います。
3.NHEのバリエーションが与える影響
Ⅰ:研究の概要
この参考にした研究の対象は17~31歳のエリートアスリート、22名です。
過去NHEについて様々な研究報告がありましたが、そのほとんどが偏心的なNHEに焦点を当てています。(この研究ではNHEeccと記載してました)
通常NHEeccはゆっくりと制御されたテンポで行うのですが、対照的に高速ストレッチ-短縮サイクル(こちらはNHEsscと記載されていました)が、ピーク時に膝の屈筋力に及ぼす影響力を調査したのもです。
Ⅱ:方法
参加者にNHEsscを行ってもらうのですが、そもそもこのバリエーションを知っている参加者がいなかったようなので、入念な習熟セッションから始まりました。
NHE中のピーク膝屈筋力は、事前に設定されたデバイスにて計測されています。

Ⅲ:結果
結果としてNHEsscは従来のNHEeccと比較して、パフォーマンスの向上に貢献しさらにピーク時の膝屈筋力が13%も大きくなりました。
結果は以下の表にまとめてありました。


通常筋と腱が長くなった時に、より損傷を受けやすくなりますが、従来のNHEeccではエクササイズ中膝関節の角度が伸びた状態では筋力発揮が不十分な場合があり、活動終わりの筋活動が大幅に低下すると考えられています。
そのため、結論としてはこのNHEsscは従来のNHEeccの段階的なトレーニング方法としてHSIのより効果的な予防だけでなく、スプリントやジャンプのパフォーマンス向上など、運動能力向上にも関与します。
ただ、この論文内にも記載がありましたが、今回はNHEの速度に関する研究でしたが、さらにNHE中の異なる下肢の角度も影響すると考えられます。股関節が屈曲した状態でのNHEはスプリントのスイング後期を反映していると考えられるためです。
今後、速度以外のバリエーションが及ぼす影響について調べてみたいと思います。
また、今回NHEsscの高い予防とパフォーマンス向上の効果は理解できましたが、実際どれくらいの速さで行えばいいのかというようなところは明確な記載はありませんでした。例えばメトロノームでどのくらいというような。。。
この論文内でもNHEsscもしくは速いNHEというような記載しかありませんでした。効果が期待できる反面、負荷としてもかなり高くなることは予想できるためまずは標準のNHEeccからはじめ、徐々に速度を上げて負荷を上げる方法がいいかもしれません。
4.まとめ
・HSIはその損傷タイプでスプリント型とストレッチ型の2タイプに分けられ、それぞれ損傷部位も異なる。
・従来のNHEよりNHEsscは膝屈筋力のピーク値が13%大きく、ケガの予防だけでなくスプリントのパフォーマンスなどにも影響を与えます。
最後にこの記事を読んで少しでも参考になりましたら、スキまたはフォローをよろしくお願いいたします♪
理学療法士・ピラティスインストラクター 辻川 真悟
参考・引用文献
・Speed Matters in Nordic Hamstring Exercise: Higher Peak Knee
Flexor Force during Fast Stretch-Shortening Variant Compared
to Standard Slow Eccentric Execution in Elite Athletes
Jesper Augustsson 1,* , Tobias Alt 2 and Håkan Andersson 3
・Askling, C.; Tengvar, M.; Saartok, T.; Thorstensson, A. Sports related hamstring strains--two cases with different etiologies and
injury sites. Scand. J. Med. Sci. Sports 2000, 10, 304–307.
・Askling, C.M.; Koulouris, G.; Saartok, T.; Werner, S.; Best, T.M. Total proximal hamstring ruptures: Clinical and MRI aspects
including guidelines for postoperative rehabilitation. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2013, 21, 515–533.
・Alt, T.; Roos, T.; Nolte, K.; Modenbach, D.; Knicker, A.J.; Jaitner, T. Modulating the Nordic Hamstring Exercise from ‘zero to
hero’—A stepwise progression explored in a high-performance athlete. J. Athl. Train. 2022.
・van Dyk, N.; Behan, F.P.; Whiteley, R. Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention programmes halves the rate
of hamstring injuries: A systematic review and meta-analysis of 8459 athletes. Br. J. Sports Med. 2019, 53, 1362–1370.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
