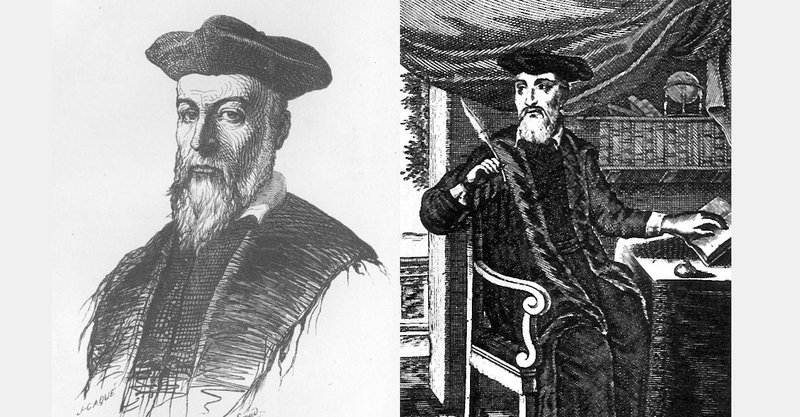
ノストラダムスが日本に来た日
昨日、唐突にSNS上に出まわり、今日になって新聞などでも報道された五島勉氏の訃報は、多くのひとびとにある種の衝撃を与えましたが、その衝撃というのは以下のようなものだったようにも思えます。
当時もう中学生だったけど怖く泣きそうだった。「あんなのウソだよ」って教えてくれる人もいなかった。99年8月になった時、関係者一同とっ捕まえてノコギリ引きにするべきだ、と思った。「ノストラダムスの大予言」の著者・五島勉氏が90歳で死去していた | 文春オンライン https://t.co/I3OZyRETIr
— 唐沢なをき (@nawokikarasawa) July 21, 2020
1973年に刊行された『ノストラダムスの大予言』によって、おおいにあおられた「1999年7の月、空から恐怖の大王が下りてくる」という終末予言は、日本中の少年少女のトラウマとなって、長く深く刻み込まれてきました。
実際、私なんかも、小学校高学年の頃に友人から、当時出版されていたノストラダムス紹介マンガで見せてもらった、
若き獅子は老人に打ち勝たん、
いくさの庭にて、一騎討のはてに、
黄金の檻のなかなる、双眼をえぐり抜かん、
酷き死を死ぬため、二の傷は一とならん、 (澁澤龍彦訳)
の不気味な詩の内容は、それが的中させたというアンリ二世の最期の場面の凄惨さも手伝って、大人になるまで頭から離れませんでした。
こうした経験をしたひとは、それこそ何万人、何十万人、へたをすれば何百万人にものぼったかもしれません。
それだけに、1999年7月というのは、だれもかれも、その実現は否定しながらも、どことなく落ち着かない、「もしかして……」という気味の悪さを抱えながら待ち、直面し、そして通り過ぎたと思います。
もっとも、いざ過ぎてしまえば拍子抜けもいいところで、長年にわたり不安をかき立てられていた純朴な、元も含めた少年少女たちは、とはいえ本気で怒るわけにもいかず、かわいく照れ笑いを浮かべて忘れるしかありませんでした。
引用した唐沢なをき先生の発言も、青少年時代の感覚をとりもどしての、最後の苦笑だったのでしょう。
そうして、ふってわいたように日本中を席巻したノストラダムスフィーバーは、四半世紀を経て鎮静化していったわけですが、ところでこのノストラダムスは、はたして1973年の『ノストラダムスの大予言』でもってふってわいたものだったのでしょうか。
実は、五島勉以前にも、ノストラダムスという人物と、その予言が紹介されたことはありました。
ノストラダムスとは
と、その前に、ノストラダムスという人物の基本データをまとめてみましょう。
ノストラダムスこと、ミシェル・ド・ノートルダムは1503年に生まれ1566年に没した、フランスの医師であり、占星術師であり、著述家です。
南仏のプロヴァンスにあるサン=レミという町の、それなりに裕福な商家に生まれた彼は、学問に長じて、大学を遍歴して医学博士号を取得した後は医師としての活動を行います。
16世紀中盤のペストの流行では各地で診察を行い、その際に訪れたサロンという町で伴侶を見つけ、終生住み着くことになります。
彼が予言者として名をあげていくのは、このサロン定住以後、1550年を過ぎてからのことで、有名な『予言集』も1555年に初版が刊行されています。
医師としての業績に、それらの刊行物も合わさり、カトリーヌ・ド・メディチをはじめとした王侯貴族の支持をとりつけ、ここに予言者ノストラダムスが誕生しました。(ちなみに、ノストラダムスは本名のノートルダムのラテン語読みです)
その後国王シャルル9世より王宮侍医としての称号を与えられ、多くの財産を遺して逝去したとされています。
まず抑えておきたいのは、ノストラダムスがフランス人であったということと、活躍が16世紀の半ば、つまりルネサンスの時期にあたるということの2点となります。
なぜなら五島勉以前のノストラダムス紹介者は、ふたりがふたりともにフランス文学者だからです。
澁澤龍彦による紹介
澁澤龍彦(1928-1987)は、シュルレアリスム作家や絵画、西洋の古代から近代にいたるオカルティズム関連の書物や知識など、多方面にわたる紹介者として知られる翻訳家であり、エッセイストですが、その専門をマルキ・ド・サドとするように、基本的な肩書はフランス文学者となります。
その澁澤龍彦に1960年から翌年にわたって推理小説専門雑誌「宝石」に連載した、オカルティズム関連のエッセイをまとめた単行本『黒魔術の手帖』があり、収録された「方位と予言」が一編まるまるノストラダムスの紹介にあてられています。
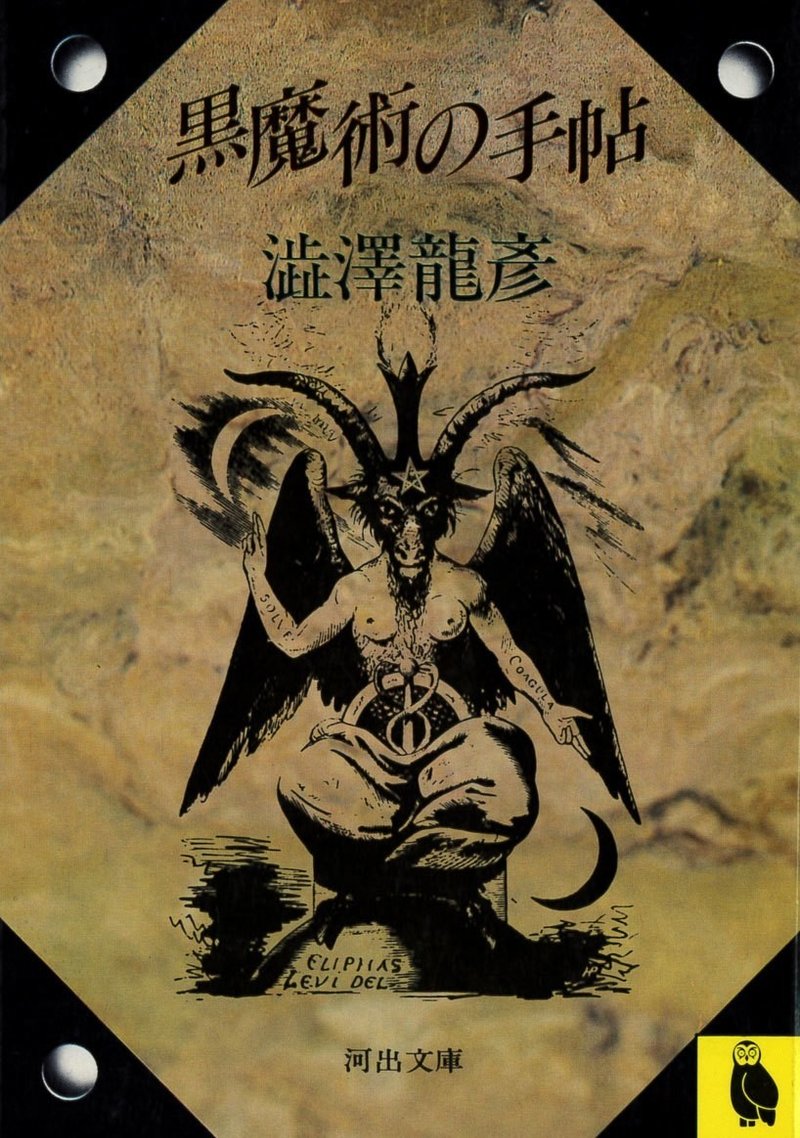
(河出文庫旧版、1983年)
ここでの澁澤龍彦の語り口はとてもユニークです。
サブタイトルの「方位と予言」が示すとおり、まず占星術と同時に発達していった天文学の話題を取り上げ、古代から近代にいたるまで、星の運行はほぼモノサシとペンによって机上で計算されて推測され、望遠鏡が実用化されたのも1663年以降だと明かします。
だから、つい中世やルネサンス期の占星術師のかたわらに望遠鏡を置いてみたくなるが、それはまちがいだと切って捨てて、19世紀に描かれたノストラダムスの肖像画を俎上にあげます。
そして天文学と占星術が密接にかかわって出来上がった、黄道十二宮と七惑星の運行で、複雑に計算される方法を概説していくのです。
そのうえで、改めて、占星術師ノストラダムスの紹介がはじめられます。
澁澤が書きたかったのは、水晶玉のかわりに望遠鏡で星をのぞいて運命をいいあてるような、神秘的かつ直感的なオカルティズムではなく、ひとびとの知の積み重ねのうえに成り立つ、歴史的な存在としてのオカルトであり、その対象のひとびとであったのでしょう。
もっとも、そうして積み重ねられたなかで、どうしてもあらわになってくるほころびに興味の中心があったのはまちがいがなく、あくまでも「歴史的事実」(澁澤の頃の、という留保はもちろん必要です)にのっとってノストラダムスの業績を追いつつ、1555年に出版された『予言集』からいくつかを取り上げて、その的中を語っていきます。
この記事の冒頭に書いたアンリ二世の死や、その子である3人の王子の無残な死のひとつひとつが挙げられていきます。
ただ、このエッセイでは、あくまでノストラダムスの予言の対象範囲は、彼の存命中(少なくとも面識のあった人物)に限られており、予言者や占星術というものも、歴史の、それまであまり語られてこなかった1ページとして取り上げられているにすぎません。
それが変化を見せるのは『妖人奇人館』に収録された「ノストラダムスの予言」です。
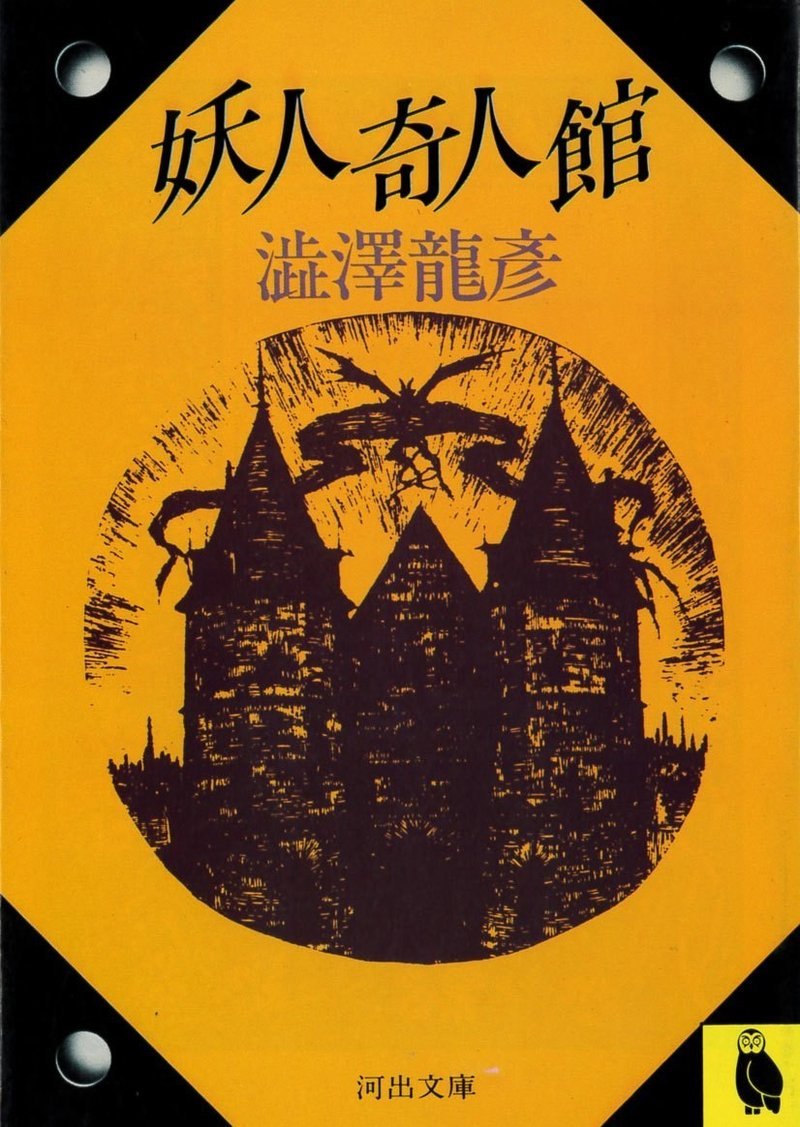
(河出文庫旧版、1984年)
こちらは1966年から1969年まで季刊雑誌「別冊小説現代」に連載されたエッセイをまとめたもので、単行本は1971年に刊行されたとあります。
掲載された雑誌のカラーに合わせてか、前の連載から5年以上を経て、澁澤の趣味が変わったのか、この一編では、ノストラダムスの予言は、彼の死後の、ナポレオンの登場、第一次世界大戦の勃発、スペインでのフランコ政権の樹立、ヒトラーの台頭とその最期、さらには1956年のハンガリー動乱までをもいいあてた……という説もあるという風に、その神秘性を誇張する風に終始しています。
そして文末には、
千九百九十九年七月
空から恐怖の大王舞い下りけん
アングレームの大王復活し
その前後にマルスが支配せん
おなじみの四行詩も鎮座しております。
もっとも、この一編での澁澤の文章は、ずいぶんと皮肉めいておりまして、こうした予言の拡大解釈を笑っているように思える部分も多くあります。
特に「恐怖の大王」の直後の一文、
予言とか占いに熱中する傾向があるのは、なにもノストラダムスの生きていた、十六世紀の愚昧な民衆ばかりではない。二十世紀のわたしたちだって、神秘や謎は大好きなのである。そうでなければ、週刊誌にあれほど各種の占いの記事が出るわけはないし、占星術の本があんなに売れたりする道理もないのである。
これには既に、『ノストラダムスの大予言』を読んで右往左往するひとびとへの警鐘が、先まわりしてこめられているような気もしてきます。
渡辺一夫による紹介
五島勉より12年以上前にあたる、1960年の澁澤龍彦の記事が、ノストラダムスの紹介のはじめてかといえば、そんなことはありません。
日本におけるノストラダムス紹介は、第二次世界大戦終戦直後の1947年に渡辺一夫(1901-1975)によって書かれた「ある占星師の話 ミシェル・ド・ノートルダム(ノストラダムス)の場合」を嚆矢とします。
渡辺一夫は辰野隆や鈴木信太郎に教えを受けた、日本のフランス文学者の第二世代にあたる人物です。東京大学、明治大学、中央大学、立教大学でフランス語を教え、ヴィリエ・ド・リラダンやフローベール、ボードレールの訳業にたずさわり、特にフランソワ・ラブレーの「ガルガンチュワ/パンタグリュエル物語」全5巻の翻訳は生涯にわたる事業となりました。
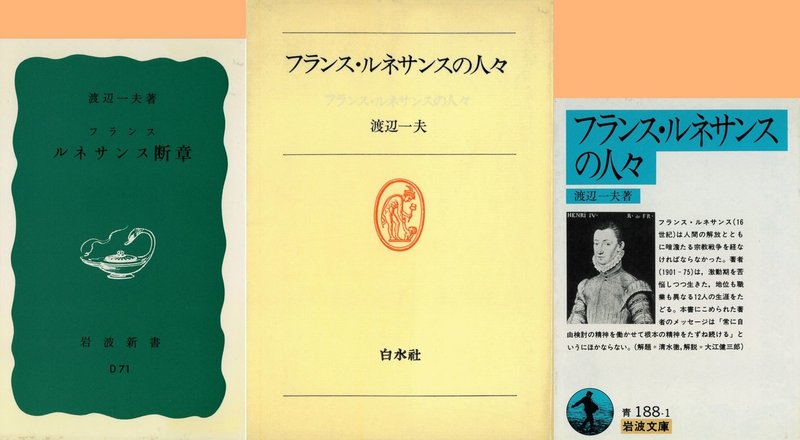
(岩波新書1950年、白水叢書版1979年、岩波文庫版1992年)
「ある占星師の話 ミシェル・ド・ノートルダム(ノストラダムス)の場合」の収録はやや複雑な経緯を踏んでいます。
雑誌「人間」の1947年11月号に掲載されたものが岩波新書に『フランス・ルネサンス断章』として収録、その後白水社で1964年『フランス・ルネサンスの人々』というタイトルになり、1971年に『渡辺一夫著作集』(筑摩書房)に収められ、岩波文庫のベースとなるにいたっています。
ちなみに、それぞれの版では、加筆訂正が行われています……
この最初の単行本である『フランス・ルネサンス断章』は、後に教え子のひとりである大江健三郎がその講義録である『日本現代のユマニスト渡辺一夫を読む』で語っている、
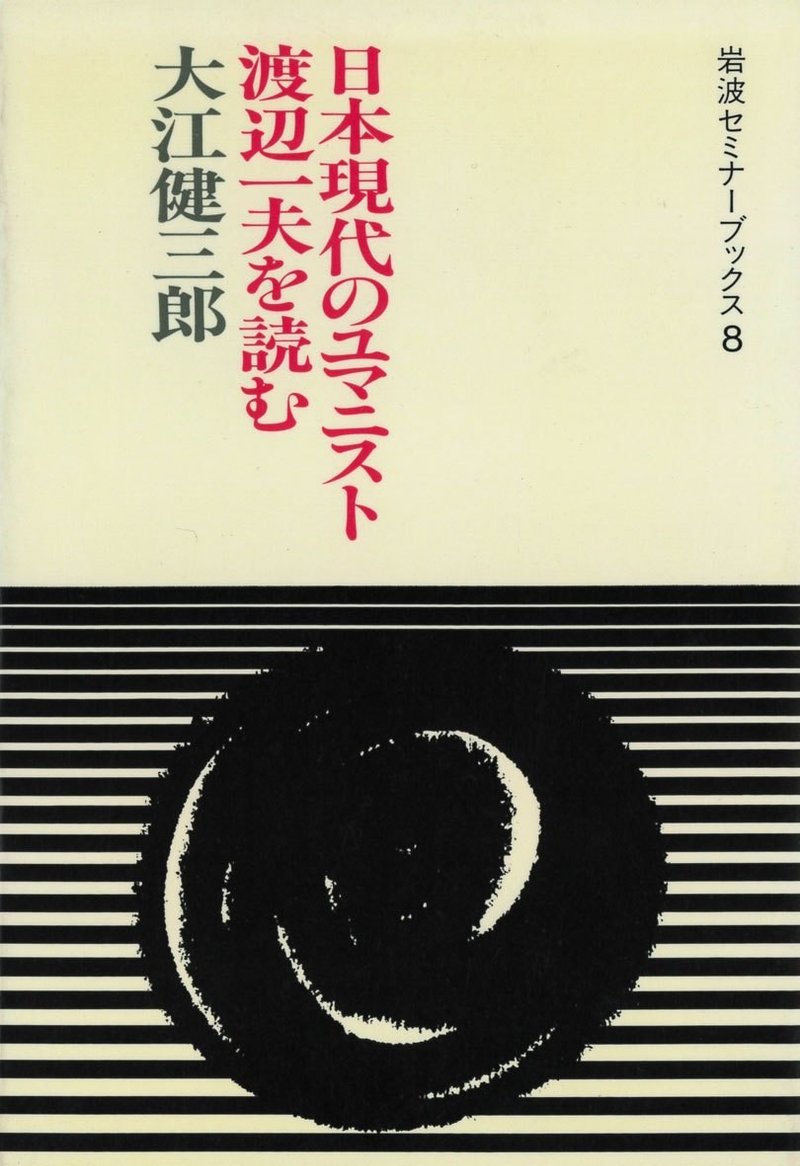
(岩波セミナーブックス、1984)
「僕たちの世代の者が、高校生としてこの版に深く影響を受けて、仏文科に進もうとした。それは幾人もの同級生に確かめた」という言葉を信じるならば、ある世代に働きかける力を大きく持っていたということができるでしょう。
フランソワ・ラブレー(1483?-1553)を専門として取り扱っていたその渡辺一夫は、その同時代・ルネサンスを生きた特徴的なひとりとしてノストラダムスを取り上げております。
もちろんその興味関心は、
ノストラダムスが、今でもなぜフランスで有名であるかと申しますに、それは、彼が占星学によって、いろいろな事件を予言したと伝えられているからです。我々人間には、未知なもの未来のことに対する恐怖不安の念があります。これは昔も今も変わりますまい。そして、人間は、複雑な因果律の結果として生ずる事件を、事件が起らぬ前にあらかじめ知ろうとして、いつの世になっても、予言や占いにすがりつこうとする現象が見られるようです。特に未知の世界が現在よりも多く残され、また未知の世界探究の方法も確立していなかった時代には、占術予言の流行は盛大であり深刻だったに相違ありません。しかし、ノストラダムスのように、占星学者として、その名が後世にまで残り、ゲーテのファウスト博士の道連れにもされようとした例は決して多くはないでしょう。
と、特異な占星術師としての部分に向けられています。
けれども、その描き方は堅実の一言に尽きるといえるでしょう。
生年から、家系をさかのぼっての父母の家族構成とその影響、幼少年期の学業、青年期の大学と各地への遍歴の記録、医師となってからの赴任の実績など、事細かくその足跡を追っていきます。
そして、予言者として頭角を現してきてからのノストラダムスについても、当時王侯貴族にもてはやされた事実を述べるに留まり、果たして稀代のペテン師であったのか、それとも真の大占星術師であったのかについての判断は控えています。
ただ、他の紹介者にない特徴として、渡辺一夫は予言の詩篇のフランス語原文をあげ、自ら翻訳したうえで、
老いたる獅子に、若きは打ち勝たん、
いくさの庭のなか、一騎討のはてに。
黄金の檻のなかにて、双眼をえぐり抜かん、
二つの破片の一つは。而して死せん、酷き死。
右の訳詩は、前記A・ワードの読み方に従ったものであるが、第三行および四行には、別な訳もつけられるし、単に浅学な筆者のみならず、フランスの学者でも、この原文を合理的には説明できないようである。
とその問題点を指摘したり、
ピエール・ピヨブの研究によると、ノストラダムスは、まずフランス語で文章を作り、それをラテン語に訳し、さらにフランス語に再訳して、文体をひきしめ、表現に陰影を与えようとしたらしいとのことである。
と制作の方法を考察したりと、ルネサンス期のフランス語を専門とする学者としての知見を披露してくれています。(フランス語原文は省略し、旧字旧仮名は新字新かなに改めています)
しかし、渡辺一夫はそうしてノストラダムスを断罪することを目的としているわけではありません。
キリスト教徒が新旧の教派争いで次から次へと同じ信奉を持つはずのひとびとを火あぶりに処していた、暗い時代でもあるルネサンスにおいて、こうした自身の真意をぼかしつつ、そして庇護者に取り入る術は一個の市民として必要なサバイバル能力であったと分析・解釈しているのです。
そこには神秘のベールを持ち上げ、過酷な時代に、ひとりの人間がいかに工夫をして生き抜いていこうとしたかを調べようとする、等身大の相手と向き合おうとする意思が強く見えます。
戦前から、驚異的な占星術師として、名前だけがひとり歩きする状態だったノストラダムスを紹介するにあたっては、バランスに気を使った非常に誠実な手法が施されていたように思えます。
けれども、そうして、改めて、日本におけるノストラダムスの紹介から受容を見ていくと、一度は剥がされた神秘的なベールが、やがて一枚また一枚とかけなおされて、やがて、伝説に満ちた大予言者として再登場することとなるのは、不可解なような、それでいて当然なような感じがしてきます。
ここまでお読みいただきましてありがとうございます! よろしければサポートください!
