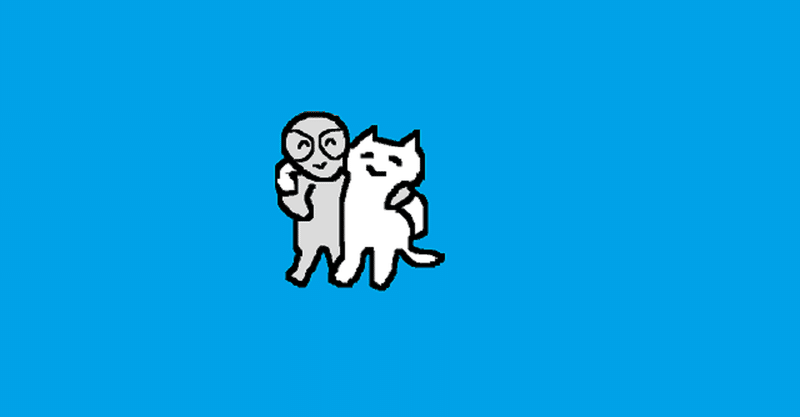
ホロックスみーてぃんぐの感想と◯△駅前
漫画ジャンプ+の新しい漫画であるホロックスみーてぃんぐを1話読んで来ました。YouTubeの文脈を絵にする文化にはクリアすべき壁がまだ多そうで大変だと思う。ヘッダ画像をお借りしています。
本当は違うnoteを書こうと思ってたんですけど、色々と思ったし漫画の感想をnoteに書くことに割と躊躇いがない、といいますかnoteというプラットフォームにおいて娯楽文化の感想を残しておくことにはそこそこ意味があると思っているため書いています。
○△駅前
まず最初に思ったのは○△(まるやま)という言葉に意味があったのだということ。○△とはかつてホロライブの公式インターネット番組?の題に使われた名前で、番組名は「○△駅前」だった。
○△駅前には人外の猫又みたいな人が経営しているゲーセンみたいな店があって、MCN(マルチチャンネルネットワーク)の三人が固定で店員みたいな立場で猫又に従っていて、同様にMCNの仲間からかわるがわる一人ゲストに呼んで悩みを聞いて一緒にゲームで遊んで解決する内容だった。
ぼくはライブストリーミング形式のYouTubeコンテンツよりも、過去に収録されてプロの手で編集されたムービーに割と興味があるため、○△駅前は楽しみにしていて実際楽しんで見てて、木曜日にプレミア公開で更新されるんだけどだいたいオンタイムで見ていました。見れなければその日か次の日には見ていたような気が……
制作会社かMCNを運営しているカバー社がゲストを決めてたっぽいので、固定の3人とそこまで頻繁に関わり合わないYouTuberがゲストに来ることがありました。下世話な言い方をすると、その普段話さない人同士がどのように話すんだろうみたいな部分を重点的に見ていた。
「普段こんなこと言うわけないから(一応固定メンツの3人のライブストリームをそこそこ見ている自負があったから性格は解っていたつもりだった)、ここからここまでは台本だったのかも知れないけどうまく再現できなかったから残りの二人が笑ってたんだな」とか……です。
番組作り
そのような穿った見方を抜きにしても、いわゆる個人が個人の裁量でのみ展開する普段のストリーミングとは違って、大人が介入して造っているんだな感をそれなりに楽しんでいた。比べるなとか言われるかも知れないし比べるつもりで例示するわけじゃないけど、超人女子戦士ガリベンガーVとかプロジェクトVと同列の感覚で見ていた。あと同MCNで言えばポル伝とかもあります。
あえて比べるなら上記はポル伝を除くと既にテレビ業界で一定の成果を残したコメディアンとかを司会に招いているパターンが多いんですけど、○△は一番YouTuber側がテレビ業界の文脈に寄り添い、コメディアン側(猫ですが)がYouTube側の文脈に合わせていった感じが一番強い番組だったと思えます。
つまりMCNの他のメンツと同じ感じでコメディアンを扱うようになっていった感がある。かといって異様に馴れ馴れしいとか暴言をはくとかじゃないので、一定の品性は保っていたはずですがこれを贔屓目と言われれば強く否定する気はございません。そして別に贔屓しているつもりもない。
でもそれはプラットフォームがYouTubeだったからであり、チャンネルもカバー社所有のメインアカウントだったからでもあったかも知れない。
ホロックスみーてぃんぐ
そこへいくとホロックスみーてぃんぐは思いっきりアウェイだと思う。
○△の説明をこれほどまでした理由は○△が地名としてホロックスみーてぃんぐの舞台として再登場したからです。だからそれらを知っている人にとっては地続きのコンテンツであり、知らない人にとってはなんのこっちゃとなり得る。ぼくも○△駅前を見ていた頃、どういうネーミングだよと思っていた。
少年ジャンプ+みたいなスパファーとかチェンソーが乗るような雑誌(現代はアプリ/電子プラットフォームを雑誌と呼ぶ時代だ)は多分ハードルがめちゃくちゃ高いように感じられる。
比べるって悪い文化だみたいな感じのことを上の方で述べましたが、現代文化とは対象年齢が下がれば下がるほど比べられること前提みたいな造りになってしまっている感じがする。そこで比べる対象がそのような究極な位置にいる漫画だから色々な前提条件を知っていると見方が変わる漫画を載せるのは編集社の意思決定的に大変な気がする。
だから確か一年以上前ぐらいに、本誌少年ジャンプのアンケか何かを実施して、「ホロライブって知ってますか?」「知ってるなら誰が好きっスか?」みたいな解答欄を造っていたのでしょう。意思決定の材料となる市場認知度を以前から調査していたわけです。
そして多分その中で、普段YouTuber見ますか?とかYouTube見る時間はどんくらいっすか?みたいなのもあった記憶がある。後は葉書の中の必須項目である個人情報と突き合わせて(雑誌のアンケートって、両面とも何ら隠れていない葉書を遣って本名とか年齢とか個人情報を書かせているのだろうか)、雑誌の読者層とYouTuberの視聴層の趣味とか年齢が割とかぶっていないことが大体わかればゴーサインが出そうな気がする。
ぼくはホロックスみーてぃんぐを読んで、その結果ありきで一話目だったらそれはこのような内容になるでしょうと思いました。結構説明が多くて、漫画の登場キャラクタたちは配信に比べるとなにか違う感を抱くのかも知れないけど初めて読む読者に対して説明がなければそれはまずい……といいますか「編集者が存在(介入)する雑誌社」で連載する意味がない。商業漫画とは担当の手が入る。手が入るから自然と説明もできる。
で普段しないからしなけりゃいいのにうとうとしていたという事故があり手が滑ったら、ジャンプ+の下の方には感想欄があるんですね。そこであまりポジティブじゃない感想群を目にした。
林子平のインタビューをこの前見たので、+のどこかに感想があることは知っていたんだけどそんなすぐあるとは思わなかった。人の感想とかチャット欄とかはなにかの感想を得る際にぼくは必要としていないため、見なくて良かったんだけど見てしまったがために冒頭述べたようにこの文を書く事になりました。
林子平のインタビューでは編集者(すくなくとも林子平自身は)書かれた感想に必ず総て目を通すとも話された。
そしてぼくはつまらないと思うことはなかった……といいますか、どんな一話目だろうと物語って「旗色を判断するには一話目じゃ早すぎる」ため、どれほどつまらないと思ったところでそれはもう肌が合わなかったんだろうと解答を下し、他の誰かの判断に変な影響を与えないように感想欄に「つまらない」とか書くぐらいだったら何もせずページを閉じて他のことをするんじゃないだろうか。それはぼくがどんなに面白かろうがその逆だろうが、備え付けられた感想欄に感想を書くという系列の行為を絶対しないからってだけだからなのだろうか。
だけど、じゃあどうしてぼくはつまらないとは思わないのか?という疑問についても同様に自分の中で分析したくなったのでしょう。だからこうして書き残すことになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
