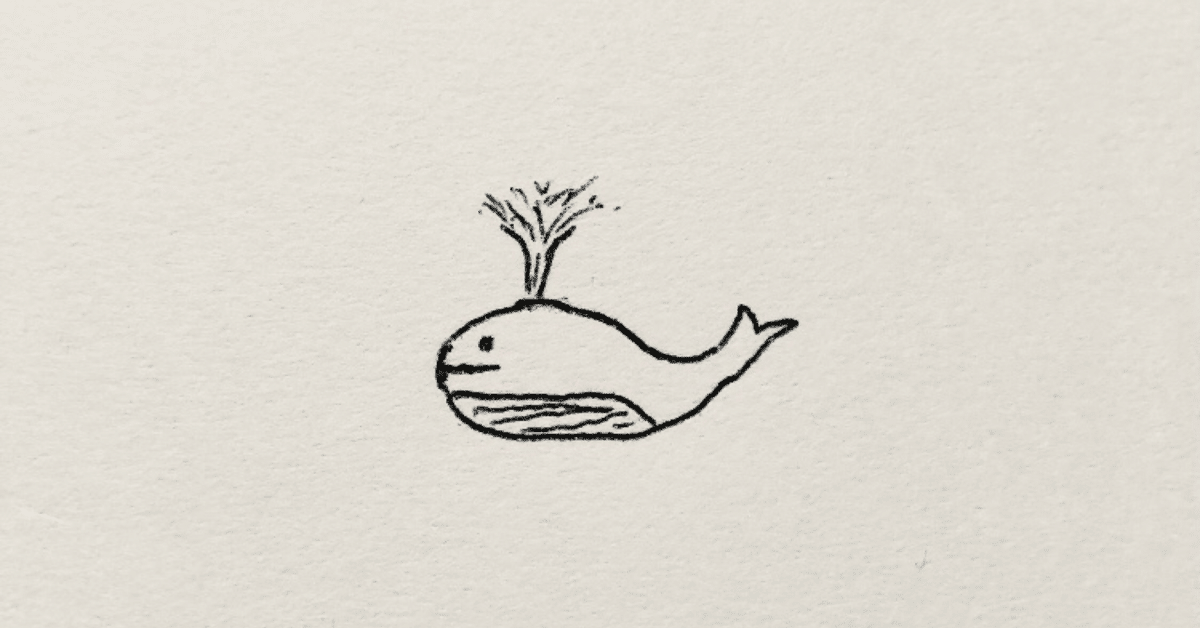
掌編小説(12)『別れを刻む空』
胸に浮かんだ円盤にそっと触れてみる。
増幅した振動が口をついて溢れ出ると、憂いを帯びた僕の声は、雨雲のすきまに吸い込まれていった。
彼女の声は美しかった。その声を生む心盤も当然、美しい。
明け方の空を切り取ったような、やや白みがかった千草色の心盤。陽の光を受けるとそれは目の醒めるような青い揺らぎを地に映して、清廉で凛とした、彼女の人格そのものを世界に表していた。
それに比べて僕の心盤ときたら、透明なのか濁っているのかも判らないくらいに黒檀で、どう見たって性格の悪さがそのまま表れているような気もして、心底、決まりが悪かった。ただ、そんな僕の心盤でさえも、彼女からすれば「生真面目なところがそのまま出ている」らしく、そう言ってもらえたことが少なからず、僕にとっては救いとなった。
出会いといえばありきたりで、彼女はたまたま同じ学校に通うクラスメイトだった。絵に描いたような優等生である彼女と、物理的にも存在感的にも、いるんだかいないんだかわからないような僕。唯一の共通点である「読書が趣味」ということを除けば、まったく不釣り合いで、似つかわしくない二人。これは往々にして面と向かって言われることが多かったので、あながち間違いではないのかもしれない。彼女はいつも否定してくれたけれど。
彼女の心盤に触れたいと、少し前から思うようになった。
「他人の心盤に安易に触れてはならない。心盤はその人の心そのものだから」
子どもの頃から言われ続けてきた世間じゃ当たり前の一般常識とも言える決まりごとが、僕にとってこれほどまでに耐え難い枷となるなんて思いもしなかった。
彼女の心に触れたとき、いったいどんな風にして僕の心は震えるだろうか。そんなことばかり考えていた。
そして言い換えるなら、それは焦りだった。
四月の進級を迎える前に、彼女は海の向こうに行ってしまう。父親の仕事の都合ってやつだ。
「国をまたいだ転勤だなんて、ほとんど転職みたいなものじゃない? 笑っちゃうよね」
彼女が教室でこぼした言葉の中に、ほんのわずかなノイズを感じたが、僕はそれに気付かないふりをした。
春休みを思う存分に満喫しながら、なんてことはない平凡な毎日を過ごした。そこには、残された時間を意識したくないという双方の暗黙の了解があった。あわよくば、このまま都合の良いタイムリープか何かでふたりの時間をどこかに閉じ込めてしまえたらと、願ってみたりもした。
それでも別れはやってくる。だから、「無駄な努力なんてない」とか言っていた担任のことは今後一切、信用しないと心に誓った。
さよならの朝。二人で散歩に出かけた。
川沿いの遊歩道にあるベンチに、並んで座る。ついに開くことのなかった桜の蕾。苛立ちを抑えようとした僕は、川面に小石を投げ込む。すぐに彼女から、驚かせてしまった鯉に対して謝罪をするように言い渡された。
風の匂いばかりが春めいていて、せめて最後の日くらい一緒に桜を眺めたかった僕の気持ちは、さっきの小石以上に沈む一方だった。これは「春なんて来なければ良い」と、よくわからない嫉妬のような感情を持った僕に対する罰なのかもしれない。
「もう行かなくちゃ」
立ち上がる彼女を見ないようにして、あと何回聞こえていないフリが通じるだろうかと、無駄な抵抗を試みる。
たった二回であえなく打ち切られた最後のわがままを、彼女はいつものとおりに笑って許してくれた。
「ほら」
僕を立ち上がらせてから、彼女は小さくて暖かな手で僕の手を握った。そして、僕の人差し指を自分の心盤にあてた。
僕の尖った指先が君の心に触れる。心盤の表面に、白くて細い筋が刻まれる。
君の鼓動のピッチに合わせて、心盤はくるくると規則的な回転を繰り返す。
さよならを伝えるはずの僕の口は、彼女の心に不意をつかれて「またいつか」とつぶやいていた。
***
このお話は、3月20日の『LPレコードの日』にちなんで、『レコード』をテーマにして書きました。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
