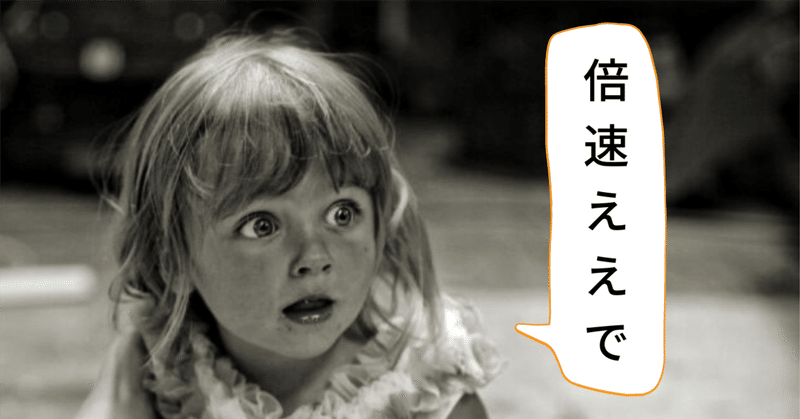
タイパ思考の今後を考える(2)
前回は、タイパ(タイムパフォーマンス)をテーマにしました。かけた時間に対して得られることを追求するタイパに関連し、「徹底してタイパのよさと効率的な便益を訴える」ことと「自分の価値観に合ったスローな時間の充実を訴える」ことが、買い手に向き合う上で今後ポイントになるのではないかと考えました。
9月14日の日経新聞記事「倍速ニッポン(中)Z世代、最速で学びたい 情報の耐えられない薄さ」でもタイパについて取り上げられていました。一部抜粋してみます。
「長時間授業を聞いているのは苦痛。倍速の方が集中できる」。セイコーホールディングスの2021年調査ではオンライン講義を倍速視聴する学生は半数を超える。「内容を短時間で理解して、もっと先のことを学びたい」。「オンデマンドの授業はバイト前や空き時間に倍速で見る」。タスクを無駄なく詰めるタイムパフォーマンス(タイパ)意識が透ける。
じれる学生の気持ちをくみ、工夫するのは兵庫教育大学の小川修史准教授。動画投稿サイト「ユーチューブ」を参考に、オンライン講義は従来の1.3倍速で話す。「えー」「そのー」など間延びするワードは編集でカット。学生から「頭に入りやすい」と評判だ。
少しでも早く結果をつかみたいのは1日の生活も人生も同じ。若い世代が前のめりなのは未来に確信が持てないからだ。
「新卒入社後3年を我慢したところで、成長できる確証はない」。都内の25歳女性は前職のエンジニアを5カ月で辞め、待遇もよい大手コンサルタント会社に転職した。必要なお金は早めに稼ぎ、できるだけ早くリタイアするという。「60%の力で60歳まで働くより、100%で40歳まで仕事する方を選ぶ」
脱・年功序列にカジを切ったNTT。社員11万5000人の人事制度を見直し、基準を満たせば年次や年齢を問わず昇格・昇給できるようにする。ある管理職は「(若手社員は昇進待ちの)長い行列に並ぶことを"コスパが悪い"と考えている」とみる。「社長を含め抜てき人事を一度も見たことがない」(40代社員)という環境では、タイパ、コスパを追う彼らをつなぎ留められない。
半導体製造装置のディスコは、総合職新入社員が技術を学びつつ興味ある部門で働ける制度「アプリケーション大学」を設けている。1~2年後の「卒業」の際は希望部署とマッチングして配属先を選べる。「配属のミスマッチが減った。自己責任でやりたいことに挑戦できると好評」。キャリアは自ら選びたい。漫然と「待つ」のは不安だ――。そんな気持ちに応える仕組みが欠かせない。
平成不況や災害の痛手にからめ取られ、グローバル競争にもまれる日本。「Z世代」が抱える将来への不安は切実だ。明治大学の藤田結子教授は「少しでも早く成長して安心したいとの意識が強い」と指摘する。
「最小の労力で最大の成果を取る」スキルを重視するZ世代。人生100年の曲折を最短距離で急ぐだけでは見えない景色、得られない経験もあるが、「最速世代」の登場は日本の企業、社会の停滞を打ち破る原動力にもなる。
同記事からも改めて感じるのは、「何をパフォーマンスと捉えるかの大切さ」です。
決まった情報をインプットする情報伝達型講義を、隙間時間を有効活用して動画で受けるのは、テクノロジーの進化の恩恵でありまさにタイパのよさにつながります。どの速度が自分に最適かも人によって違いますので、1.25や1.5など倍速の度合いを選ぶことで、自分にとって最も良いタイパが実現すると思います。(ちなみに、周囲には2倍までOKという人もいますが、個人的には1.5倍を超えると理解が落ちて逆にタイパが悪くなる感覚です。個人差だと思いますが。)
一方で、考える時間を圧縮するのは、タイパが良くなるとは限らないと思います。例えば、あるお題に対して一定時間を使って考えるよう、教授が問いを出すとします。この問いに対して考える時間をスキップして解答の確認に急いだり、何らか考えたからといって残り時間をスキップして教授の解説動画に進んだりすることもできます。しかし、果たしてそれで効果が上がるのかは疑問もあります。一定時間を使って考えることに意味があると判断した上で、そのような設定にしている可能性が高いからです。
検索エンジンは言うまでもなく便利なツールですが、使い方によっては思考力の減退を招くという指摘も聞きます。ある課題やテーマに対して、自分で仮説を立てるプロセスをスキップしてその課題やテーマについて書かれた情報を見にいくことで、分かった気になるためです。他の論点や可能性が埋没しているのを気がつかないまま、情報を見に行ったと同時に、その課題やテーマについての思考が終わるかもしれません。
普段仕事をしている中で、各社の多くの方と関わる機会があります。若手の方ほど、同記事のようなキャリアでのタイパの追求や、自分がそうなっていないことへ焦っているという話を聞くことも多いです。そのことに対する個人的な意見としては下記です。
・自分のキャリアにとって明らかに無関係・NGな仕事であれば見切りをつける
・明らかに無関係・NGと言えなければ、しばらくの間続けてみる
明らかにNGとは例えば、社会に害悪を与えるのを是としている会社で仕事を続けることです。法令を踏み外した仕事のやり方を強要するような職場であれば、そのことに気づいた時点でおかしいと声を上げるか、それも難しい環境なら見切りをつけるのが適切です。
他方、明らかに自分のキャリアにとって無関係・プラスにならないと言えるかどうかについては、難しい問題です。自分の専門外の業務だと思っていたものの、やっているうちにそのノウハウを活用することで自分の専門領域が開眼した、ということがあるからです。
また、どんな仕事であっても、他者との協業で成り立っています。自分のキャリアとして深掘りしていく領域外の仕事については、いずれ協業者に委ねることになります。協業者が、自分がしない仕事をどのように見たりどんなことを考えたりするのかを知っておくのは、協業者と一緒に仕事をしていく上で必ずプラスになると思います。管理部門の専業で採用された人が、入社後にあえて現業部門でしばらく配属になるのは、そのことを体系的に運用しているケースと言えます。
少しでも早く成長したいという、焦る気持ちはよくわかります。そのうえで、どんな仕事であっても現状をよりよく改善できる工夫はないのか、一定期間没頭して取り組んでみることも貴重だと思います。
一方の企業側としては、上記事例にあるような、各人材に適用できる成長環境整備の追求もこれまで以上にすべきでしょう。要件を満たしていない人材を無理やり抜擢するのは的を外していますが、要件を満たしている人材の昇格を行列待ちの慣習に合わせるために待たせるのも、的を外していると思います。
<まとめ>
タイパに適っているかどうか、分からないうちは続けてみるのも有益かも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
