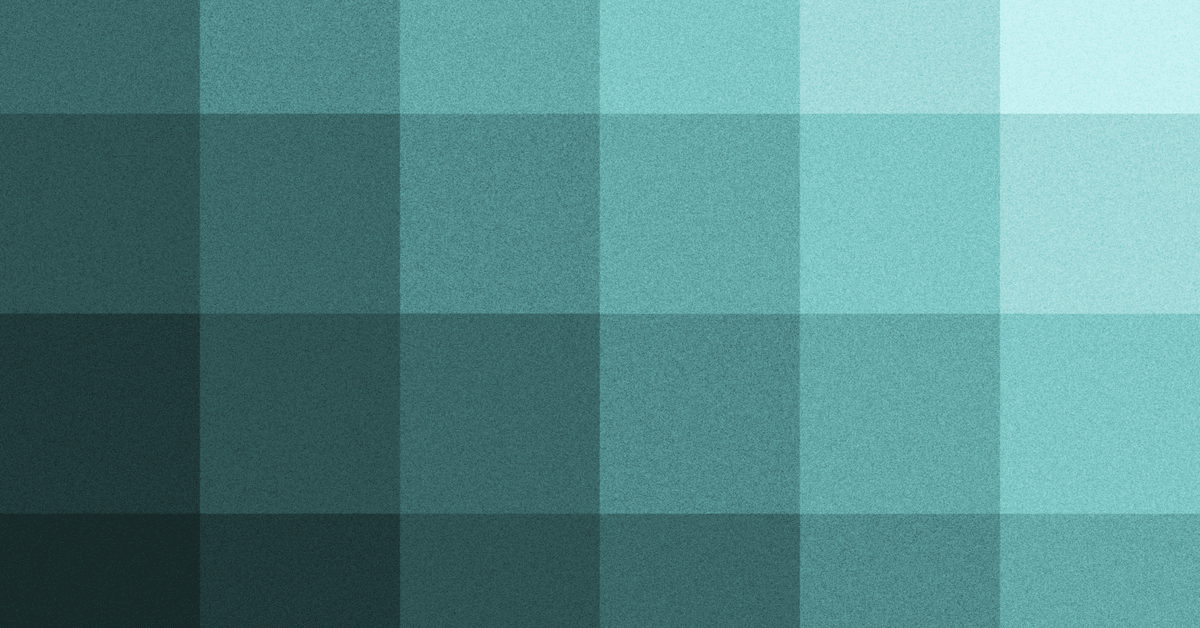
アート思考を考える
「イノベーション創出を実現する「アート思考」の技術」(長谷川一英氏著)という書籍を読みました。組織がイノベーションを起こしていくうえでアート的なアプローチの重要性が高まっているという話を耳にする機会が増えました。同書では、そのことについて分かりやすく説明されています。
「アート思考」に近いイメージを持つ言葉に「デザイン思考」があります。これらに「論理的思考」を加えた3つについて、同書では次のように説明されています。
・論理的思考:物事を体系的に整理したり、道理にそって筋道を立てて考えること
・デザイン思考:商品やサービスを使うユーザーの視点からビジネス上の課題を見つけ、解決策を考えること
・アート思考:自らの関心・興味に基づき、常識を覆す革新的なコンセプトを創出する思考
デザイン思考の5つのプロセスとしては、次のように説明されています。
1.共感:ユーザーを観察し潜在ニーズを探る
2.定義:ユーザーのニーズを定義する
3.概念化:解決するアイデアを出す
4.プロトタイプを作成する
5.テストを繰り返し、精度の高い製品にする
経営学者のドラッカー氏は、企業にはマーケティングとイノベーション2つの基本的な機能が存在すると言いました。私なりの解釈になりますが、デザイン思考は「マーケティング」で力を発揮するのではないかと思います。
上記5つのプロセスは、お客さまが求めていること(=どのように考え、感じ、行動するか)をもとにして、それに応えるアイデアを形にして届け、喜んでもらうプロセスそのものであると感じます。そして、このデザイン思考を10年ぐらい前から日本企業が本腰を入れて取り入れるようになったと言われます。
そのうえで、このデザイン思考では、これまでにない革新的な製品を創るのは難しいと同書は指摘します。これまでにない商品・サービスは、ユーザーが想像することができないからです。
また、ユーザーという他者起点でアイデアを出す行為は、他の人も同じアイデアにたどり着く可能性があり、参入障壁が低くなってしまうとも同書は指摘しています。
同書で紹介されている「3つの思考法の違い」の一部を、以下に抜粋してみます。デザイン思考に対し、アート思考は0を1にするような大きな「イノベーション」で力を発揮すると言えるのではないかと思います。
<起点>
論理的思考:事実関係・事象
デザイン思考:あなた(顧客・ユーザーなどの潜在ニーズ)
アート思考:私(自らの興味・関心、自由な発想、感性)
<特徴>
論理的思考:誰もが納得できる結論を導く、普遍的、客観的
デザイン思考:顧客・ユーザーのニーズに対して問題を解決する、他律的
アート思考:既存の価値観・常識を覆し問題を提起する、自律的、主観的
<必要な要素>
論理的思考:フレームワーク・冷静な分析
デザイン思考:ユーザーモード、人間中心の視点、観察、プロトタイプによる試行錯誤
アート思考:自分モード、突き詰める力、思考を飛躍させる力
<得意領域>
論理的思考:経営計画、生産計画、効率化
デザイン思考:ユーザーにとって有用なものの創出、1→10や1→100のイノベーション
アート思考:革新的なコンセプトの創出、未知なるものの創出、0→1のイノベーション
そして、2016年時点のユニコーン企業(評価額が10億ドルを超える、設立10年以内の未上場のベンチャー企業)のうち、21%でアート系の教育を受けた人が創業者になっているそうです。
掃除機で有名なダイソン社の創業者ジェームズ・ダイソン氏もその1人です。長年イノベーションの起きていなかった掃除機の業界に、吸引力の落ちないサイクロン掃除機というイノベーションを投入したと同書は説明します。「透明なカップにゴミが溜まっているのを見たい人などいない」と言われながらも、「ゴミが溜まっていくのが見えるのは面白いはず。そのことにより吸引力の高さをビジュアルとして頭の中で描ける」として開発を進めたというわけです。
先日、ある中小企業様を訪問しました。今まで自社で取り組んだことのない新規事業を考えているのですが、責任者に適した人材が内部に見つからず、また立候補を募っても集まりそうにないことから、適材をヘッドハントで外部調達しようとしているということでした。
稲盛和夫氏は、次のような話をしていますが(日経ビジネス、22年11月28日より)、同社様の人選に通じるものがあります。これまでにないようなイノベーションのアイデアを具現化する過程では、論理的思考より、アート思考が得意な人の活躍の場が大きいということを彷彿させます。
これまでやったことのない新製品を開発しようと思ったとき、よい大学を出た賢い部下を集めて話をすると、技術的に非常に難しいので、なかなかやる気になってくれません。
新しい開発に挑戦しようと燃えて会社に帰ってきて、皆にも同じように燃えてもらおうと思っているのに、部下たちは燃えないどころか、冷や水をどんどんかけるのです。こういうことが何度もあったので、私は開発を始めるときには、頭のよい冷静な開発者を呼ばないことにしました。それより、『それはおもしろそうですね』と言う、少しおっちょこちょいな人がまわりにいたほうがよいと思うようになりました
上記にある、アート思考の特徴から感じるのは、「主語を自分にすること」「自分モードによる主観」の大切さです。自分発の優れたアイデア、それも人間や社会の本質からずれていないアイデアが思いつくかどうかが、これからの企業や人の競争力を分けていくのだろうと思います。(簡単ではありませんし、私はあまり得意ではない自覚もありますが、、)
続きは、次回以降取り上げてみます。
<まとめ>
自らの関心・興味に基づくアート思考は、今後ますます重要性が高まる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
