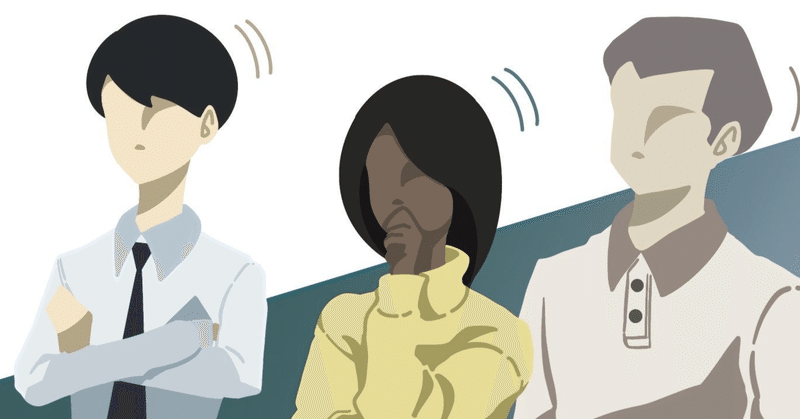
評価は納得感(2)
前回は、「評価というのは、結局納得感があるかどうかである」ということについて考えました。そして、評価という取り組みを行う際のポイントとして、「事実を曲げない」ということを挙げました。
ポイントの2つ目は、評価の取り組みだけで物事を解決しようとしないことです。
前回の内容で、評価とは、「あるべき姿(ありたい姿)と現状とのギャップを明らかにすること」だとしました。その続きが大切です。つまりは、フィードバックと行動計画の実行後のPDCAです。
・評価結果を本人に的確に伝える
・ギャップ=問題に対する認識を共有する
・問題に対してどのように向き合い、何に取り組んでいくのか、課題形成する
・課題解決につながる行動計画をつくり、取り組み意思を確認する
・成果が出るよう、行動計画の取り組み開始後の進捗を確認し必要な軌道修正をする
これらを適切に行なえるかどうかが、評価した意味があるかないかを分けることになります。
また、もっと組織的・長期的な視点で考えると、様々な取り組みとの関連づけが必要になることが見えてきます。例えば、本人がより持ち味を発揮できる仕事への担当替え・配置転換がそうです。他にも、キャリアビジョンと本人の仕事との一致、高い組織貢献をした人への優先的な賃金等の還元、本人の仕事がどのようにお客さまや社会に役立っているのかの周知、などがあります。
評価とこれらの合わせ技で、前回取り上げた人事制度の3つの運用目的「事業(業務)の推進」「人材の育成」「適切な処遇」が実現されます。評価の取り組みだけでこれらを満たそうとすると無理があり、評価が歪むことにもなります。他の取り組みといかに関連付けられているかを常に確認するとよいと思います。
3つ目は、評価で目指すのは「納得」であり、「満足」ではないということです。
検索で出てくるオンライン辞書をいくつか参照すると、「納得」「満足」についておおむね次のように説明されています。
納得:他人の主張、言動・行動に対して理解し、もっともであると認めること
満足:望みが達せられて不平のないこと。十分満ち足りていること。また,そのさま
自分のパフォーマンスや現状について、自分を評価する人(=会社)の考えや意見などを聞き、「言われてみれば、確かにそうかも」と思ってもらうことが、「納得」のイメージです。言われた内容に対して、喜ぶかどうか、ほっとするかどうかなどを、直接問題としないわけです。「本人に満足してもらうかどうかはどちらでもかまわなくて、納得してもらうことを目指す」ということです。
しかし、評価や評価結果のフィードバックの視点が、利害関係者の「満足」に向くと、運用が歪み始めます。「この評価結果だと本人が不満を持ちそうだから、このまま進めることの悪影響を考えて、マイナスの度合いを少し和らげておこう」「こんなに良い評価結果ばかりだと上の人たちが嫌がりそうだから、少し調整してバランスをとっておこう」などです。
仕事に限らず、社会活動・組織活動は様々な立場の人がいて成り立っています。関わるすべての人がみな満足という状態は、基本的にないでしょう。ましてや、評価の取り組みだけで自分が関わる相手すべてに満足してもらうなど、無理があります。しかし、自分にとって注目度の高い特定組織や特定個人に目が行き過ぎると、評価で満足する状態をかなえようとしがちです。
実際に、「評価基準に沿って評価したら、やたら高い点、低い点が出た。これでそのまま進めてよいのか」といった話は、時々聞くことです。会社の各人に対する期待値を大きく超えている、大きく下回っている、それが事実であるなら、そのまま結果を活用するのが基本と言えます。
よいことはよいと言い、よくないことはよくないという事実を見つめた上で、どう改善するかを考える。そのメリハリがあることは、組織の閉塞感を打破できる一助にもなると考えます。
仮に、ある個人が自分に対する評価結果にどうしても納得しない場合は、その個人と、その個人を取り巻くその他大勢との、両方を想像してみるとよいと思います。
(その他大勢に評価結果を直接見せるわけではないとして)仮にその評価結果を見たとしたら、その他大勢の目線も自分と同様、当該個人に対する評価結果が妥当だと納得しそうかどうかです。もしそう思えるなら、当該個人の自身に対する客観視がずれているということです。そのような場合は、その他大勢の納得感を優先させるべきだと思います。
<まとめ>
評価の取り組みで、相手を直接満足させることを考えない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
