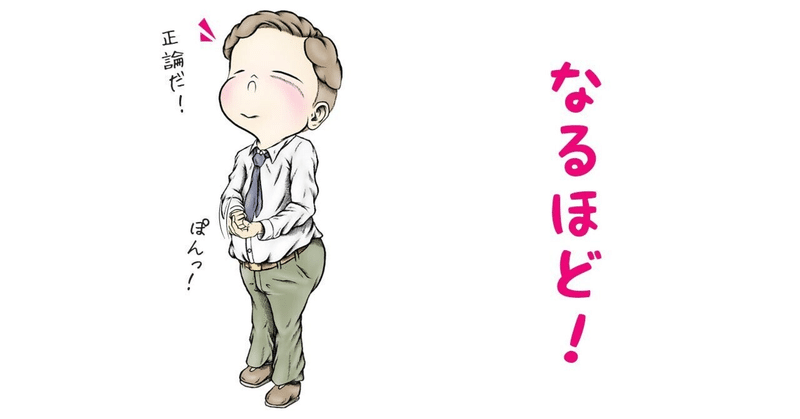
評価は納得感
先日、経営者複数人とお話をしていて、人事評価による評価結果の決定について話題になりました。皆さんとの間で同意したのは、「評価というのは、結局納得感があるかどうかである」ということです。
人事制度の運用を何のために行うのか。私は、その目的を大きく3つの実現のためだと説明しています。
・事業(業務)の推進
・人材の育成
・適切な処遇
そして、人事制度の一環として行う評価は、あるべき姿(ありたい姿)と現状とのギャップを明らかにすることです。プラスのギャップとマイナスのギャップの、両方の可能性があります。
今期期待されていた成果に対して、結果としての現状がちょうど期待に応える大きさだったのか、期待を上回ったのか、下回ったのか。期待されていた役割発揮や行動に対して、期待通りか、期待以上の動きをしたのか、期待以下の行動レベルだったのか。それらを見える化して、本人含めた当事者間で確認する取り組みです。
ギャップを明らかにすることで、今の仕事のやり方をそのまま進めていけばよいのか、あるいは、もっと別のことにもトライできる状態なのか、やり方を変える必要があるのか、などがわかってきます。そして、必要に応じて仕事のやり方を見直すことで、業務が推進され、本人の育成にもつながっていきます。
自分で自分を完ぺきに客観視できる人はいません。自分の考える成果の度合いや役割発揮の度合い、強みや課題について、他者からのフィードバックや他者との対話を通じて気づくことがあります。その取り組みを一定期間ごとに組織的に行おうというのが、人事評価です。
その意味では、本人による自己評価と会社の判定した評価結果のズレが大きい人ほど、人事評価を実施する意義があると言えます。本人のズレた認識を修正し、適切なパフォーマンス発揮に向けて行動を修正する機会になるからです。また、ズレがほとんどなく、自分を限りなく客観視できている自律人材にとっても、現状認識しズレがないという確認を行うことは大切です。
この評価という取り組みを行う際の、ポイントを3つ挙げてみます。ひとつは、ギャップの結果を操作しないことです。言い換えると、事実を曲げないということです。
いろいろな企業様から、例えば次のような話を聞くことが時々あります。
「評価のルールと手順に則って結果を出したら、高い評価結果の人がやたら多くなった。よって、調整をかけて評価の平均値を(下方に)調整しないといけないかも。また、何人かの人は、周りと見比べて評価ランクを1つ下げることも考えるかも」
この話には、納得感がありません。あるべき姿(ありたい姿)と現状との間にある、本来のギャップの存在を、過小に見立てようとするものです。
「会社として、各人の仕事の成果や成果を生み出すための役割発揮・行動の度合いについて、事実情報に忠実に、そして、各人に求める基準に忠実に、判定した結果がこれである」と言いきれるかどうか。
ここが揺らいでしまうと、聞いている方は話の内容に納得感がありませんし、明らかにしたギャップから仕事のやり方を変えていくこともできなくなります。事実をひん曲げて目的を達成しない取り組みに多くの時間と労力を割く評価であれば、評価をしないほうがまだましだと思います。
上記の例のように、評価結果の全体的な傾向が、会社として想定するものと大きく異なることで、運用に別の弊害が出るような場合もあるかもしれません。そのときは、適正な運用ルールになるよう改正することを社員に伝え、改正するまでは社員に約束したルールに沿って評価し結果を伝えることが、筋だと言えるでしょう。
続きは、次回以降考えてみます。
<まとめ>
評価は、事実に忠実に行う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
