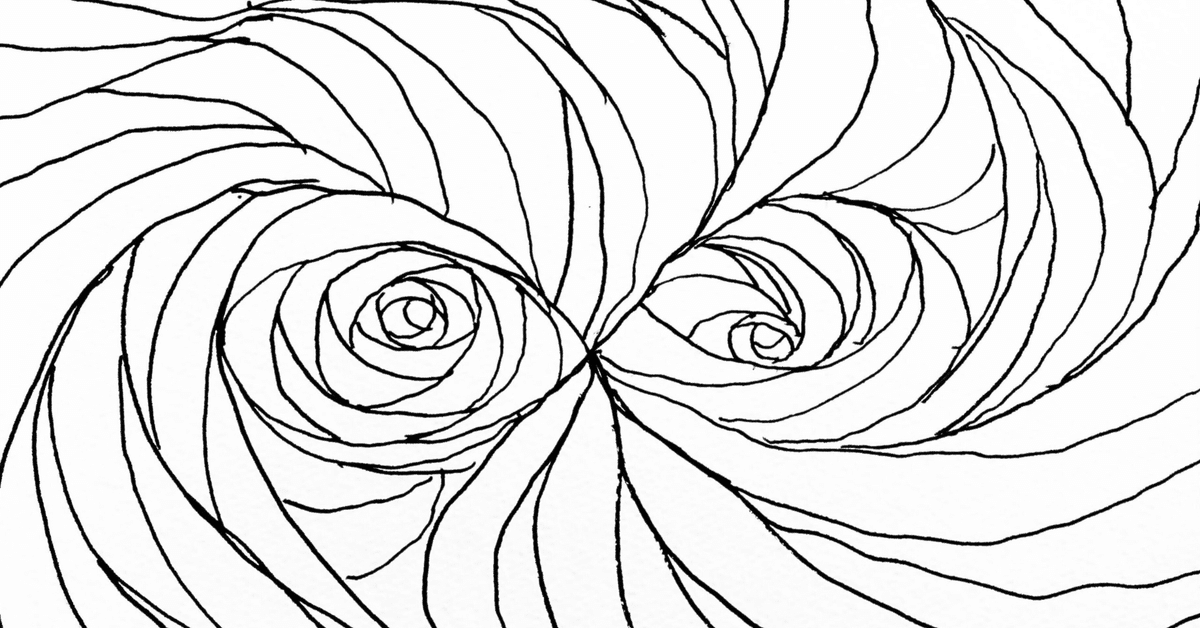
ヱリ子さん思考日記~2023年2月「いつか循環の中でバタつきパンを食べられたなら」
【循環するひと、表現するひと】
「循環者」と「表現者」について水面下で考え続けている。作家大木芙紗子さんの「にんじん」(https://www.instagram.com/p/CokQugeh4co/)という掌編を読んでからだ。物語では、人参が苦手だった兄がスキー場の事故で死に、残された母はわざと大量に作った料理を腐らせて捨てる儀式に依存し、主人公の弟はヤクザの下っ端として親分たちの靴を舐め、その味から母の腐乱した料理を想起する。兄弟を育てている身としては条件反射的に重いものが残る掌編だが、後になってこの母も弟もきっと「表現者」なのだろうと考えるようになった。
中年になってくると、色々なかたちで喪失を体験した人たちに出逢うが、なんとなくだけど、既存の共同体や群れの中に存在する自己を守ることで癒されようとする人と、喪失の悲しみや孤独を抱きしめている自己を他者に表現することで共同体や群れとの共感を試みようとする人がいる気がしている。前者は喪失の悲しみを深く秘匿し「いつもの顔」を表層的に保つことで、自己の表面を社会と擦り合うように調整する訓練を自らに課し、それを繰り返すことで解決を試みる「循環者」であり、後者は何らかのかたちで喪失を他者あるいは自分自身にアピールする表現を獲得することで、解決ではなく共感を求めてゆく「表現者」のように思える。古今東西、芸術家や作家など、表現者が何かと波乱万丈な人生になるのは、「循環者」のように元に戻ってゆく手法からズレてしまうからではないか。「循環者」は自分軸ではなく共同体軸で思考しているのだから、循環に戻れるのも必然だ。そして、癒されたあかつきには「皆のおかげでここまで立ち直れた」などと気持ちのいい言葉を本心から紡いだりする。「表現者」は、喪失を表現する手段を獲得してしまえば、時間は止まったままになってしまう。
悲しみを癒すためにはその感情を表現することが大切とよく言われるが、それは「循環者」に限定して向けられるべき忠告なのかもしれない。けれど、「私は、本当は自分の言葉で文章を書きたいの」と言っていた「表現者」の友人が、喪失を胸に深く沈めたまま何食わぬ顔で「循環者」をやっている姿が、わたしはほんとうは一番悲しい。
【揺れる】
井戸川射子さん芥川賞受賞作「この世の喜びよ」を読んだ。以来、第一子の子育ての記憶が浮かんでは沈む日々を送っている。あのどうしようもなく独りぼっちだったという手触りと、何らかのチャクラが開くように幼少期に実母から受けた言動の数々がぴたりと紙を重ねるように「今」という時間に被さってくる恐怖と、ひたすら続く不眠と、乳の痛みと、そういうあれこれが24時間365日水攻めのように顎下十センチまで迫っていることを知りながら、それでも子の一瞬一瞬の成長にこのうえない多幸感を覚えるあの日々に、確かに「この世の喜び」はあったのだと信じられる作品が、この世にあってよかったと思う。マドラーでかき混ぜるとレモネードの底に溜まっていたレモンピールがぐるぐるとガラス瓶の中を舞いはじめるように、わたしの中にはたくさんの記憶の断片が浮いていて、その中でああ本当にあれは幸せだったなと思える瞬間の断片たちだけが、「わたしが選ばれし記憶です」と言って眩しい光を放ちはじめるようだ。
小川の畔でベビーカーを押していると、たくさんの桜の花びら達が私たち親子と歩調を合わせるように水面を流れてきたこと、ブランコに揺られながら空を仰ぐと高いポプラのてっぺんが見えるような気がしたこと、暗くなるまで練習した竹とんぼがふらふらと中空を舞って幼子の顔が輝いたこと、夜道に歌を歌いながらユサユサとおんぶして歩いたこと。わたしの幸福な記憶は、「揺れる」あるいは「揺られる」行為と結びついているようだ。子育て中のあの頃のわたしが、世界に優しく包まれていたとは思わない。ただ、世界に揺られていたこと、揺らされていたことを心地よく思い出すのである。
小さい頃、両親の間でわたしは「好きなものがなにもない子供」ということになっていたのだが、わたしは世界に揺られること、揺られている自己を見つめることが幸福だったのかもしれないと、ふと思ったりする。かくたる個性もないまま、アレを見ればアレもいい、コレを見ればコレも素敵だと思って、もう長い間揺られている。
兄はわたしに似ず、「好きなものがたくさんある子供」ということになっていた。プラレール、亀、ザリガニ、キンケシ。大阪弁はどこへ引っ越しても強要されたし、「ほんまにチョケやなあ」という母の言葉にはパブロフの犬のように「おどけ者の子供」であることを強いられたが、先の記述で言うところの恐らくは「循環者」である兄は、その環境にもすんなり馴染んでいた。それでも、30センチほどの水槽の中の数匹のタナゴがはたはたと右へ行っては左へ返り、また右へ行っては左へと翻るさまを、三時間も四時間も眺めていた兄の後ろ姿を思い出すとき、今では敏腕営業所長をやっている彼もまた、本当はただ揺られることが好きだったのかもしれないとわたしは小さく考えてみたりする。
【バタつきパンと野原】
本の中でしか出会ったことのない憧れのものはたくさんあるが、中でもずっと叶うことのないまま焦がれているのが「バタつきパン」だ。どの絵本と具体的に言い当てることはできないが、ある時代の絵本ではバターのことを「バタ」と表記していた。石井好子さんのエッセイ「パリの空の下オムレツのにおいは流れる」でも、確かバターのことはバタと表記されていて、わたしはこの本を俄然好きになった記憶がある。
それで、憧れてやまないのがバタつきパンである。まず小さな丸テーブルに、白地に赤が入った大ぶりのチェック模様のテーブルクロスが敷かれていて、そこにほかほかのポタージュスープが置かれている。スープ専用のまんまるで重たいスプンでポタージュを啜っていると、焼き立てのバタつきパンが登場する。ロールパンなのだが、生地は極めてリーンで、皮はフランスパンのようにパリッと音を立てんばかりに香ばしく、中は真っ白でふわふわ。ここにバタとパンのどちらが主役かわからないくらいに、四角いバタをたっぷり塗って食べるのだ。咥内の温かさでバタはこっくりと黄色く溶けだして、すぐにじゅわっと広がる。そういうパン。バターもマーガリンも好きだけれど、いつか完璧なバタつきパンが食べてみたいなと思う。
もう一つ、絵本の中でしか出会ったことのないものが、野原だ。絵本の中では、野原が身近だ。動物たちや子供たちはよく野原で出会ったり、野原をてくてく歩いていたり、野原で喧嘩になったりするけれど、たいてい地方都市や都心に住んできたうえに出不精のわたしにとって、野原はいつまでも遠いままだ。駐車場の一メートル四方程度の叢のほうが、ずっと近い。
フキノトウが伸び菜の花やオオイヌノフグリが咲き乱れる、そんな野原はいつだって遠く、それに人っ子一人いない寂しい場所のように想像してしまう。いつか、野原に行ってみたいものだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
