
【読書日記】読書の方程式|インプット・アウトプットが10倍になる|速読・多読より学びの量
本書のテーマは「10倍読書」
速読でもない多読でもない
自分の中に「視点」と「法則」を増やして
あなたなりの「結論」を持つことです。
新年明けましておめでとうございます。
安全・安心と絆でつながる
キャリアコンサルタントのタルイです。
本年もよろしくお願いします。
せっかくなので新年の抱負を
書きたいと思います。
『10倍読書』
これは今より読書量を
増やすことではありません。
読書の質を高めて
インプットとアウトプットを
10倍にしたいのです。
限られた読書時間の中で、
どれだけ学びの量を増やせるか?
これは多くのビジネスマンにとっての
課題でしょう。
▼本書から学びました。
著者が提唱する10倍読書とは
一体何か?
結論は以下の図です。

カンタンに書くと
「視点」とは著者のモノの見方のことで
「法則」とは著者のノウハウのことです。
インプットは視点読書✖️法則読書で
アウトプットとは
「本の感想を述べる」ことではなく
インプットした学びを
いかに組織の力や社会への
共有の仕方について
解説されてます。
ここまでを読んでアナタは
こんなことを考えませんでしたか?

速読とは一般的に
「写真を撮るように本の情報を脳に送り込む」
「眼球の動きを鍛えて一定の時間内に文字を多く読む」
といった技術ですね。
著者は速読について
「文字情報を写真のように記憶しても、
眼球を速く動かして読んでも、
言葉の意味を知らなければ意味がない」
と、懐疑的です。
また、多読についても
「ビジネス書で重要なのは2割しかない。
だから、そこだけ拾い読みすればいい」
といった時短テクを駆使する人は
月30冊以上はビジネス書を読んでいる
猛者である
と著者は指摘します。
私も以前は、
ビジネス書はひらがなを読まない
キーワード読みをしておりました。
漢字と数字とカタカナは読むけど
ひらがなは読まない。
この方法で本を読むことで
通常よりも速い読書をやってましたが…
この本でキーワード読みは
読解力を失う間違ったやり方だと知り
やめました。
またコロナ自粛中は
毎日1冊ペースで多読してましたが…
通常活動に戻った今は時間的余裕もなく
読書は週2〜3冊程度に落ち着きました。
しかし、
本を速く読むことと
多く読むことをやめても
元々、noteで「読書日記」という形で
アウトプットするのが
週一回程度だったので
実質的に支障は出てません。
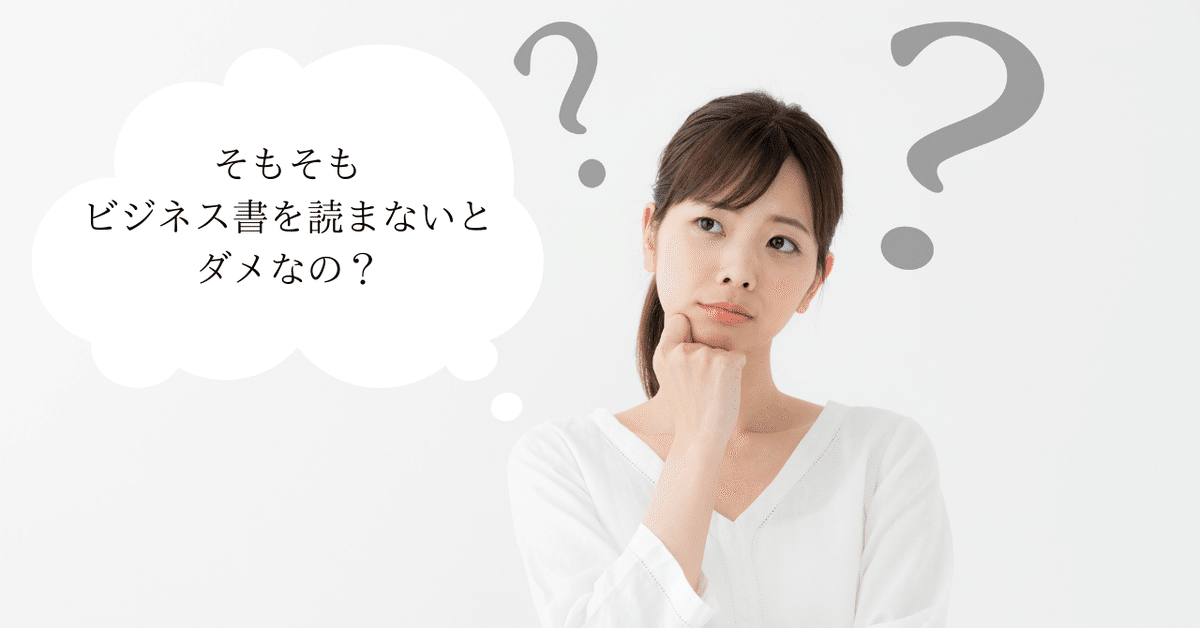
この記事の核心をついてきましたね!
この疑問には最後にお答えいたします。
では今年も
張り切っていってみましょう!
◆著者は「外資コンサル」と「広告代理店」をハイブリッドキャリアを持つ羽田康祐さん

羽田康祐[ハダコウスケ]
株式会社朝日広告社ストラテジックプランニング部プランニングディレクター。産業能率大学院経営情報学研究科修了(MBA)。日本マーケティング協会マーケティングマスターコース修了。外資系コンサルティングファームなどを経て現職。「外資系コンサルティングファームで培ったロジック」「広告代理店で培った発想力」のハイブリッド思考を武器に、メーカー・金融・小売り等、幅広い業種のクライアントを支援。ハンドルネームはk_bird
ちなみにですが、
私は頭の良い人とは
3タイプいると考えてまして
●コンサルのようなロジカル(論理的)な頭の良さ
●広告プランナーのようなラテラル(発想力)な頭の良さ
●お坊さんのような客観性に優れたクリティカル(本質理解力)な頭の良さ
これで考えると著者の羽田康祐さんは
ロジカルとラテラルとクリティカルな
トリプルで頭が良い人です。
とっても稀有な人材です。
▼羽田康祐さんの肩に乗っているインコに注目ください。
セキセイインコとオカメインコを
自宅で飼っているそうです。
インコが肩に乗る理由は
とても飼い主に懐いている証拠と
聞いたことがあります。
ワンピースのロブ・ルッチが頭に浮かびました。
▼目次にも注目してください。
目次
第1章 ビジネス書は、成長を加速させるエンジン
第2章 10倍読書の四大原則
第3章 視点を増やす「視点読書」―10倍読書“前篇”
第4章 法則を増やす「法則読書」―10倍読書“後篇”
第5章 10倍読書のアウトプット術
第6章 ミスマッチを防ぐ!10倍読書の選書術
この記事では第1章〜第4章までの内容から
「四大原則」「視点読書」「法則読書」の
3つをピックアップしてみました。
◆10倍読書の『四大原則』とは
その一、「読書量」より「学びの量」
前述しましたが、
速読と多読は読書量を目指すものであって
速く、多く本を読めるようになることが
目的です。
これをサッカーに例えると
「速く走れるようになる」
「多くボールが蹴れるようになる」
これは手段であって
「限られた時間の中で
多くの得点を重ねること」こそが
サッカーの目的です。
その二、「フローの情報」より「ストックの情報」
著者は世の中の情報には
2種類あるといいます。
・フロー情報
流れ去る情報、SNSのタイムラインに流れてくるニュースなど
・ストックの情報
あなたが「考えるきっかけ」になる情報。
フローの情報は「最新であること」ですが
時間が経てば価値は減っていきます。
一方で、ストックの情報は
「時代や分野を超えて変わらない法則」
が潜んでいるので、
価値が落ちません。
これが蓄積すると
「仮説力」が身につきます。
ストックの情報✖️思考を巡らすこと✖️その蓄積(=時間)
その三、「視点読書」「法則読書」の2回読みをする
一冊のビジネス書を2回に分けて読むことです。
1回目:著者が置いている「視点」を発見しながら読む
2回目:著者が想定している「法則」を発見しがら読む
2回に分けて読む理由は
視点と法則を一度の読書で
学び切ろうとすると
結局は一つも
身につかなくなってしまうからです。
なるほど🤔
一回の読書ごとに
目的を決めて読むことで
集中が持続できるということですね。
その四、同じ分野の「固め読み」をする
固め読みをすることで記憶力と読書スピードが上がります。
▼下記は有名なエビングハウスの忘却曲線です。

人が何かを学んだ時、
・20分後には42%忘れる
・1時間後には56%忘れる
・9時間後には64%忘れる
・1日後には67%忘れる
・2日後には72%忘れる
・6日後には75%忘れる
・1日後には79%忘れる
このデータだけを見ると、
人の記憶力はニワトリ並みなんだなー
と勘違いしそうですが、
この実験データは
「子音・母音・子音」からなる
無意味な音節を覚えた時の記憶のデータ
なのです。
固め読みのように
何かを覚えるという時には、
既に知っていることと関連付けたり
紐づけできるかによって
記憶の残り方が違ってくることは
あなたも経験があることと思います。
ちなみに私も固め読み派です。
最近は感情について本で読書を固めてます。
◆視点読書と法則読書

10倍読書の手順を書きます。
もう一度この図を見てください。

10倍読書とは
視点(どの側面に焦点を当てるか?)を置いて
法則(ああなれば→こうなるだろう)と考え
結論(自分なりの仮説)を立てる。
この習慣が身につけば
確実に観察力が身に付きます。
実際の流れが本書に解説されてました。
著者の別の本より文章を引用します。
人は誰でも疑問や問題にぶつかった時、つい性急に「答え」を求めがちです。しかし「答え」を学んだところで、「どのようなものの見方や考え方をすれば、優れた答えにたどり着けるのか?」と言う「答えの出し方」を学ばなければ、一生ものの学びにはなりません。
この文章に対して視点と法則を見つけましょう。
まずSTEP①
「この文章には、どのような視点が隠されているか?」
「答え」の視点と
「答えの出し方」の視点
が見つかります。
以下のSTEPは図解の通りです▼

そしてこちらが視点と法則をメモしたものです。
答えとは抽象化すると知識の視点。
答えだけを学んでも、一過性の学びにしかならない
故に、知識とは一過性の消費にしかならない
答えの出し方は「思考プロセス」の視点
答えの出し方を学ぶことができれば
一生ものの学びになりやすい
故に、思考プロセスは一生ものの学びになりやすい
おぉ!これは見事な三段論法ですね🤔
さらに2つを並べると…
「知識」は一過性の
「消費」にしかならない
だが、
「思考プロセス」は
将来に活かせる「投資」になる。
「知識」と「思考プロセス」で
対比の構造文を作って
さらに「消費」と「投資」で韻まで踏んでます。
かっこいいフレーズです😆
これぞまさに
「1から10」を生み出す工程
10倍読書になってますね。
著者も触れてますが
「抽象化」にこれだ!という正解はないそうです。
幅広く応用できる意味に置き換わっていたらOKです。
羽田康祐さん、
ありがとうございます!
早速、この視点と法則を活用した「10倍読書」実践します。
ここまで自分の言葉で抽象化できれば
幅広い応用ができますね。
例えば、自分で本を書くときも
参考文献としてパクリの域ではなく
自分の言葉にしてる感は出ますね😁
◆(まとめ)なぜ、ビジネス書を読まなければいけないのか?
序文の質問の答えです。
ビジネス書は、成長を加速させるエンジン
さらに著者は以下のメリットも挙げています。
ビジネス書を読むと「体系化された知識」が身につく
ビジネス書を読むと「解釈力」が身につく
ビジネス書を読むと「思考力」が身につく
ビジネス書を読むと「応用力」が身につく
ビジネス書を読むと「将来に向けた投資」が身につく
この5つは私も同感です。
ちょっとだけ補足させてもらうと
私がビジネス書を読むのは
ネットとかの情報ですと
エビデンス(確証)の怪しい情報も多いので
ビジネス書はその道の専門家の方が書いております。
いちいちネット記事の確証を探すくらいなら
校閲の入ったビジネス書を読んだ方が早いとも考えてます。
最後に私がビジネス書を読む理由をまとめます。
ビジネス書を通じて著者との対話ができる
人は同じ環境で同じ人間ばかりと行動してると
確実に成長は鈍化します。
自分だけの視点や
自分と似たような視点の環境で
凝り固まってしまうと多様性を見る力を失います。
今回も本書を通じて
著者とビジネス本を通じて対話できたことで
著者の視点と法則は大変勉強になりました。
もう一点、私がビジネス書を読む上で大切にしていることは
読書とは字の如く、「読んで書く」こと
つまりビジネ書を読んだだけでは
「読書」ではないと考えております。
これからも
noteの読書日記を通じて学んだことは
社会へと共有していきたいと考えております。
文字数の都合で省きましたが
第5章の「10倍読書のアウトプット術」では
インプットした学びを
組織の力や社会への共有の仕方について解説されてます。
第6章の「ミスマッチを防ぐ!10倍読書の選書術」は
「思っていた内容と違った」
「自分が求めているレベルと違った」
このような「ミスマッチ」を防ぐ方法が書かれてます。
気になる方はぜひお手に取ってみてください。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
感想はスキとコメントで
お知らせいただけると嬉しいです。
いただいたサポートは毎月
児童養護施設支援団体に寄付させていただいてます。

この記事が参加している募集
記事がお役に立てたら100円サポート願います。 noteで頂いたサポートとAmazonアフィリエイトは児童養護施設を退所する子どもたちの就労支援団体ブリジッフォースマイルさんに毎月寄付させていただきます。https://www.b4s.jp/action/contribution
