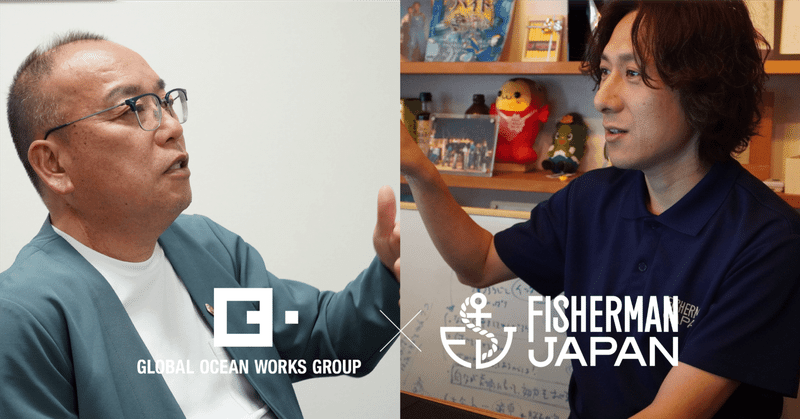
水産業の将来を憂う「田舎者」同士がタッグを組んだ!鹿児島・垂水と宮城・石巻。地方から生まれる「世界進出」と「構造改革」
2022年春、日本の水産業の変革を試みる2つのグループが手を組みました。鹿児島・垂水を拠点にブリの養殖から海外輸出まで手がける多角経営企業「グローバル・オーシャン・ワークスグループ(GOW)」と、宮城・石巻の地からチャレンジを続ける漁師団体「フィッシャーマン・ジャパン(FJ)」。南北約2000キロの距離を超えて実現したコラボは急速なシナジー効果を生み出し、海外進出や構造改革など「課題だらけ」の日本の水産業に新しい風を吹き込もうとしています。コラボの背景には個性豊かな両トップの「出会い」がありました。どのように意気投合したのか? これからどこを目指すのか? グローバル・オーシャン・ワークスグループの増永勇治CEOとフィッシャーマン・ジャパンの津田祐樹に聞きました。(聞き手はフィッシャーマン・ジャパン安達日向子)
鹿児島と宮城。進取の気性に富んだ両トップの出会い
――まずは鹿児島県が拠点の増永社長と宮城県に住む津田さんがなぜ出会ったのかを教えてください。
津田:僕はサステナブルシーフードの国際認証、「ASC認証」を取得した水産物の取り扱い量を日本で増やしたいと思っていて、インターネットで認証取得企業の一覧をチェックしていました。そうしたら認証を受けている企業の中にグローバル・オーシャン・ワークスを見つけたんです。「この会社、すごくおもしろそう!」と思いました。ブリの養殖でASC認証を取っているのは大手ばかりですが、こちらは独自の資本で認証を受けていました。しかもいろいろな取り組みをしているし、アメリカに販売拠点も持っているとのこと。「すごい!」と思いました。そこで知人を通じて増永さんにつないでもらい、実際に初めて会ったのは2021年の12月でしたね。

増永:そうでしたね。私もその頃からフィッシャーマン・ジャパンのことは知っていて、会いたいなと思っていたんです。とてもかっこいいウェブサイトを持っていますよね。拝見して感銘を受けました。私も日本の水産業のイメージを変えたいなと常日頃思っていましたし、水産業を子どもに誇れる産業にしたいと思っていたんです。この人たちはそういう試みを実際にやっている。おまけに私が足を運ぶ勇気を持てなかった東日本大震災の被災地でそれをやっている。かっこいいなと思いました。
津田:僕が鹿児島まで行き、増永さんに営業担当の外木場さんも加えて3人でしっぽりと酒を飲みましたね。今までどんなことをしてきたか、これから何がしたいのかなど、深くお話をさせてもらったのを覚えています。

「まず動く」で意気投合
――初めて会った時、お互いにどのような印象を持ちましたか?
津田:とにかくこの人はやばいなと思いました。増永さんの半生、漁協との「闘争」の歴史を聞きましたので。我々の張りぼて感がばれてしまうと(笑)。フィッシャーマン・ジャパンは有言実行というかビッグマウスというか、先に虚像を作ってから頑張ってそれに追いつくというところがありましたから。
僕は何かの分野のプロフェッショナルではありません。魚屋をやっていましたが、目利きや包丁さばきではかなわない人が五万といました。だから僕はみんなの力を頼って生きてきました。人と人をつなげ、新しいものを生み出すのです。強いて言えば、人と人とをつなげることのプロフェッショナルでありたいと僕は思っています。そういう風にしてフィッシャーマン・ジャパンはみんなを巻き込む形でやってきました。だから逆に驚きなんです。増永さんは一人で、しかも鹿児島という日本の端っこで、グローバル・オーシャン・ワークスという会社をここまで大きくしました。このエネルギー、バイタリティーは本当に真似できません。
増永:そう言ってもらうとかっこよく聞こえますけど、いろいろな人に助けられて今の私があります。私が津田さんと初めて会った時に感じたのは、石巻には全体として「変わらなければいけない」という雰囲気があることです。これはうらやましいなと思いました。あとは何と言っても、津田さんとだったら長く話していたいなと思いました。当時の私は養殖業者さんの中に長く話せる相手がいませんでしたから。やっぱり出会いがすべてですよね。津田さんと出会えたことにも何らかの意味があると思っていて、それを大事にしたいです。まあ、特に津田さんのような変わった人とはずっと付き合っていたいですね。
津田:そんなに変わってますか?
増永:変わってますよ(笑)。初めて会った時も、「このあとアフリカに行きます」とおっしゃっていましたよね。世の中が新型コロナで大騒ぎになっている時期でした。この行動力は才能だと思いました。

津田:僕はあまり考えないタイプなんです。考えた通りに世の中が動くならもっと考えるんですけど、実際には世の中はコントロールできません。だから、思いついたらとりあえず行ってみる、やってみる、言ってみる、というのをモットーにしています。
増永:まず動いたほうが楽なんです。「成功」も「失敗」も、動くからこそ経験できます。失敗したらその経験に基づいて修正したらいいだけの話です。
人のつながりを大事にWin-Winの関係を構築
――その出会いを経て、2021年末にはグローバル・オーシャン・ワークスの養殖ブリを使ったサンドイッチ(「ブリのテリヤキBLTサンド」)を、フィッシャーマン・ジャパンが運営するフィッシュサンド専門店で販売しました。そこからさらに、道の駅「たるみずはまびら」内の「海鮮こだわりの店 よかもん市場」にフィッシャーマン・ジャパンの売り場を作ってくれたり、海外輸出をバックアップしていただいたり。関係性がどんどん深まっていったと思います。何がきっかけだったのでしょうか?

津田:実はすごく絶妙なタイミングだったんです。2014年にフィッシャーマン・ジャパンを立ち上げてから、ずっとやりたかったのが海外輸出でした。これには「金儲け」とは別の理由がありました。これだけの高学歴社会です。大学でレベルの高いものを学んだのに、卒業したら田舎に帰って雨合羽を着て長靴をはいて、という気持ちには当然ならないと思います。石巻に優秀な人を巻き込むためには、石巻で先進的なことに取り組める環境をつくればいい。「輸出を頑張れば海外に行きたい若者が集まるんじゃないか」と短絡的に考えていました。でも、「言うは易く行うは難し」で、なかなかブレイクスルーを起こせませんでした。2021年に石巻出身でアメリカに留学経験がある村上日奈子がフィッシャーマン・ジャパンに入り、本格的に対米輸出を目指そうというタイミングで、アメリカに拠点を持つ増永さんと出会うことができました。本当に図々しいんですけど、「乗っからせてください!」とお願いしました。

増永:お会いした時に「石巻にはいい魚やいい加工場がいっぱいあるんです。資源が豊富なんです」と津田さんがおっしゃっていたので、「じゃあうちも輸出できる商品を探しているから、やってみませんか」ということですよね。そもそもサンドイッチの時にかなり感銘を受けていました。私たちにはできない販売方法を持っていらっしゃると。だからアメリカでもいい結果が出るだろうと思っていました。あとは、今後どう広げていくかですよね。
――グローバル・オーシャン・ワークスとしてフィッシャーマン・ジャパンに期待していることは何ですか?
増永:ビジネスライクな商売だけの付き合いにはしたくないですね。人と人のつながりを大事にしたいです。お互いのいいところを見つけて伸ばし、悪いところを補うWin-Win(ウィンウィン)の関係性が築けると期待しています。そんな仲間が石巻と鹿児島だけじゃなくて、たとえば四国にも北海道にもいるという形になればもっといいと思います。具体的に期待しているのはブランディングの部分ですね。私たちは「やっていることの割にアピールが下手だ」と言われることが多いです。石巻ではありませんが、ぜひフィッシャーマン・ジャパンの方に手伝ってもらえないかと思っています。

津田:もちろんです。団体を立ち上げる時、「フィッシャーマン三陸」とか「東北フィッシャーマン」という名前にすることも検討しました。でも、海はつながっているし、結局やりたいのは日本の水産業を変えることだろうということで、今の名前になりました。だから三陸や宮城には全然固執していません。むしろようやく鹿児島と連携することができて、自分たちのビッグマウスに少しだけ近づくことができそうでありがたいです(笑)。
増永:ついていきます(笑)。
命と向き合った経験が原点に
――直接会って話す機会はそれほど多くなかったと聞いています。それでもこうしてインタビューしていると、なんだか息が合っていますね。
増永:心が通じ合っていますからね(笑)。
津田:はい(笑)。
――二人とも人生において「命」というものと真剣に向き合う機会があったんですよね。
津田:29歳の頃に東日本大震災を経験して、人間って結構すぐ死ぬんだなと思ったんです。それまでは死ぬことなんて全然考えてませんでした。でも、身のまわりの人の死に直面して、「後であれをやっておけばよかったと後悔だけはしたくないな」とすごく思いました。

増永:命って大事ですからね。もう20年前のことになりますが、私は癌になって「もう死ぬ」と言われましたが、たまたま助けていただきました。それをきっかけとして、命の大切さや、せっかく助けていただいた命で自分は何をすべきなのか、ということを考えるようになりました。後悔だけはしたくない。そう思いました。
――水産業に賭ける思いがあまり強くない、というのも意外な共通点かと。
津田:僕は今も水産業が苦手です。でも、日本の水産業には課題が山積していて、そういう課題があることを知ってしまった以上、解決する責任があると勝手に思っています。
増永:手前味噌ですが、養殖業界が置かれている現状を変えようと声高らかに言うのは私くらいなので、それが私の使命かなと思っています。なぜ水産なのかということはあまり考えたことがないですね。
海外への扉を切り開く
――連携は始まったばかりですが、将来的にはどんなビジョンを持っていますか?

増永:世界に出たいですね。まずはアメリカです。今アメリカのマーケットに行っているのは、築地や豊洲で水揚げされる季節性のある一部の魚種か、ハマチに代表されるような養殖魚です。今後も人口は伸びていきますし、魚は蛋白源として注目されてくると思います。「伸びしろ」はかなりあるはずです。ただし、グローバルスタンダードの魚でなければ通用しません。先日、白人のシェフに日本の魚を使ってくださいとキャンペーンしました。ちょうど3月で長崎産のキジハタがとてもいい時期だったので、薦めてみました。そうしたら「絶滅危惧種なので使わない」と言われたんです。世界で通用するのはどんな魚なのか、私たちはもっと勉強しなければいけません。私たちは可能性も持っているけれど、変わる必要もあるということですね。
アメリカで経験を積んで、それからアジアや中東、ヨーロッパへも一緒に進出したいです。私たちがチャレンジしていれば、水産業をよくしようと思っている若者たちがついてきてくれるんじゃないかな。
――フィッシャーマン・ジャパンが海外輸出で狙うのはやっぱりアメリカですか?
津田:その通りです。悔しいけれど、アメリカが世界で一番の大国です。世界に情報を発信する上でもアメリカで認められることが重要でしょう。増永さん、アメリカの販売拠点である「インターナショナル・マリン・プロダクツ(IMP)」にフィッシャーマン・ジャパンのことをプッシュしてもらえますか?

増永:昔のIMPは、日本代表として日本の魚の良さを全米に伝えるんだという自負を持っていました。でも時間が経って組織体制も変わるうちに、そうした企業風土が崩れてしまっていた。そのため私はIMPを自分のグループに引き入れました。今、IMPの組織を変えようとしている最中です。フィッシャーマン・ジャパンと一緒にやっていくということについても、私のメッセージがまだ浸透していない部分があると思っています。そんな中で先日、先ほどもお名前が挙がったフィッシャーマン・ジャパンの村上日奈子さんに米国へ行ってもらいました。もっと苦労するかと思ったのですが、彼女はIMPの中に仲間をたくさん増やしてきてくれたようです。私が言うよりも直接行ってもらった方がフィッシャーマン・ジャパンの良さを理解してもらえると実感しました。
津田:ありがとうございます。これからも足繁く通いたいと思います。

水産業の課題に“一斉蜂起”?!
――先ほど「水産業は改革が必要だ」という話がありました。日本の水産業の課題をどのようにとらえていますか?
増永:日本の水産業はたくさんの課題を抱えています。代表的なのは漁業権の問題です。昔は必要だったと思いますが、今の時代には合っていません。漁業権を持っている人たちを守りながら、新しい決まり事を作っていくことは可能です。たとえば新規参入業者にチャンスを与える。ライセンス制にして厳しい基準を与える。クリアできなければ資格を剝奪する。そういう制度設計に取り組むべきでしょう。他産業のテクノロジーが入ってくればその産業は伸びていきます。もう一つは構造改革です。たとえば、輸出を促進するための全国規模の協議会はありますが、そういう団体にどれだけ実効性があるのか。スピード感が求められている現状において、無駄なものは省くべきです。

津田:世界の人口が増えている中で食糧が不足してきています。こうした状況において水産業にはすごいポテンシャルがあると思っています。考えてみてください。穀物は人が育てるものです。野生の牛を食べている人もほとんどいないでしょう。一方で海産物は資源を適切に管理するだけで勝手に増えてくれます。人間は「足るを知る」だけでいいんです。
世の中では今、GAFAなどのIT産業が注目されています。しかし、食糧危機が起きた時、強いのは食べ物がたくさんある国です。そういう意味では本来、海に囲まれた日本はとても有利なはずです。それなのに、日本の水産業では適切な資源管理ができていません。乱獲の結果として近海の魚の数が減り、水揚げされた魚のサイズも年々小さくなっています。これではまずいでしょう。先ほど増永社長が先ほどおっしゃったキジハタの話もそうです。こういう課題があるということを多くの人が知りません。僕たちが拡声器のようになって言い続けなければいけません。
増永:無駄のない魚の獲り方をするためには、船1台あたりの漁獲量を決めた方がいいのではないでしょうか。それをしないから、訳の分からない競争が起き、小さいのも大きいのも獲ってしまう。いい時期に、いい型の魚を決められた量だけ獲るようにしないと。
津田:その通りです。でも、そこには痛みが伴います。少なくとも数年間は業者が我慢しないといけないでしょう。その期間は国が将来への投資だと思って、業者に補助を出す必要があります。諸外国ではやっていることですが、日本ではまだその必要性が理解されていません。政治や業界団体に直接呼びかけてもだめなので、僕は世論を動かしたいです。クリエイティブの力も使って。フィッシャーマン・ジャパンとして僕らがやっていきたいのはそういうところですね。
増永:日本中にいい人がいるし、いい物があるはずです。漁師は世界中にもいますし。津田さんなら、日本だけでなく世界中の漁師を束ねていけますよ(笑)。
津田:ありがとうございます(笑)。水産業には改革が必要なところがたくさんありますが、一つの地域だけが動いても変えるのは難しいでしょう。増永社長がおっしゃる通り、日本中におもしろい水産業者がいるので、一斉蜂起のようなイメージで、北の石巻と南の鹿児島から、連携して同時に声を上げていければと思っています。
増永:一緒に頑張りましょう!
津田:ありがとうございます!

会社紹介
【グローバル・オーシャン・ワークスグループ】
「世界がもとめる食の未来を創る」を理念にかかげる水産総合商社。主力商品のブリを中心にイシガキダイ、タイ、カワハギ、シマアジなど豊富な魚種の養殖事業を展開。サステナブルな養殖業であることを示す「ASC認証」を取得するなど、近代的な養殖体制の整備に取り組んでいる。一方でグループ傘下の商社「インターナショナル・マリン・プロダクツ(IMP)」(本社・米国ロサンゼルス)を拠点に輸出拡大にも力を入れる。
【増永勇治(グローバル・オーシャン・ワークスグループCEO)】
25歳の時にウナギやハマチなどの加工や飼料を扱う会社に就職。鹿児島をシリコンバレーのような水産業の集積地にしたいという夢を抱いて退職したが、大病を患って一時療養生活を送る。病気を克服し、38歳で起業。以降、鹿児島・垂水を拠点とした水産業の雄としてGOWを急成長させている。
【フィッシャーマン・ジャパン】
東日本大震災の被災地である宮城・石巻の若手漁師や水産業者が2014年に設立したチーム。被災地だけでなく日本の水産業全体の変革を目指し、人材育成や新規事業の開拓、業界のイメージ改革に挑んでいる。
【津田祐樹(フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング代表取締役社長)】
宮城・石巻にある鮮魚店の二代目。東日本大震災で同級生が亡くなったのをきっかけに、地元水産業の復興をけん引しようと決意。若手漁師らと共にフィッシャーマン・ジャパンを設立した。現在は販売部門の株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングの社長を務め、地元産品の海外輸出や海洋環境の保全に取り組んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
