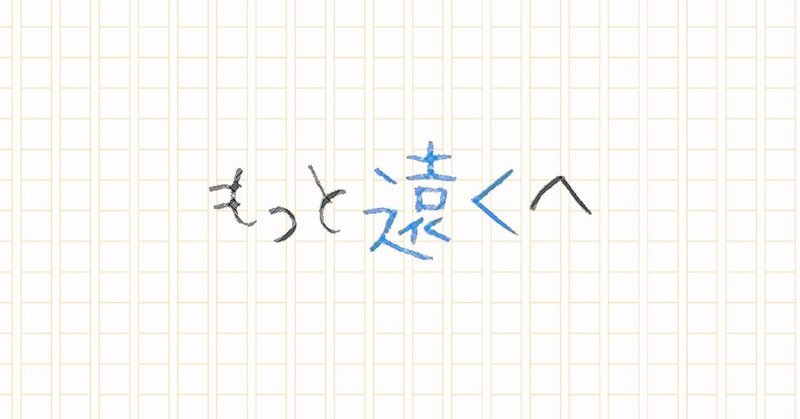
初稿の連載小説「もっと遠くへ」2-2
2-1はこちら↓
https://note.com/fine_willet919/n/nffe9df010f5a
本音という猛獣が鉄格子の中で暴れ出し、その様子をじっと観察する。人が人と共に生きる(共存する)と言うことはすなわち、これをずっと檻の中に閉じ込めておくことであると理解したのは、僕が記憶している限り、小学校の二年生、八歳頃ごろだったと思います。
僕は鹿児島の田舎で生まれ育ちました。東京に出てきてから鹿児島の場所を聞くと、大概の人間がその場所を言い当てることができます。
それは、一番端にあるからだと思っており、これが県に挟まれた真ん中あたりであれば、答えは違ったのかも知れません。
父親は、地元で建設業を営んでおり、僕から見れば、ひい爺さんが会社を起こし、父が三代目でした。父は、昭和の人間でありながら、九州男児でもあり、子供の頃の僕にとっては厄介な男でした。
帰宅するのは、大体十八時頃で、風呂が沸いていないと、すぐに腹を立て、怒りの矛先が母親に向きました。
もちろん僕にも向けられるわけで、そんな日の食事はテレビの音が無ければ、蟻の足音さえ聞こえるのではないかと思えるほどでした。
父の手を始めて見たのはその時でした。誤解がないように加筆すると、まじまじと見たのが、という事で、爪は薄黒く汚れ、真ん中からぱっくりと半分に分かれてしまいそうな縦の線が入り、隙間がない程膨らんだ指一本一本は、キャッチャーミットのようで、そこには無数の傷がありました。
野球グローブであれば、替えどきもいいところで、自分の掌と比べれば、違う動物と見間違えてしまうほどの物でした。
ですが、可哀想などという気持ちには少しもなりませんでした。ただ、何をすればこうも違うものになるのか些か疑問だったのです。
父はよく物を大事にしろと言っていました。
当たり前のことです。物を大事にできない人間は、人も動物も、大事に出来ないのです。
そんな父は、よく物を壊していました。説得力がないとはまさにこの事です。
夕食が気に入らなければ……
また、自分が見たいテレビを観れなければ……
また、風呂の温度が適温でなければ……
また、誰も構ってくれなければ、
まさに子供のような父でした。だから、自分の手も傷つけてしまうのだとその頃の僕は理解しました。
「仕事っていつもどんなことしてるの」
一瞬、テレビの音にかき消されそうになった僕の忖度を、父はなんとか救い上げ、持っていた焼酎をゆっくりと机に置き、僕を見ました。
「仕事か」
いつもの口調と何も変わりません。
自分がこの家で一番強い、と過信している人間の口調です。ですが、口元は確かに緩み、目は鉛筆で描いたように細く、何より、僕には楽しそうに見えたのです。
「今度の土曜、行ってみるか」
懸命に、面倒だなと言った表情をして見せるのですが、それが本心からくるものでないことは子供の僕にも手に取るようにわかりました。
父は本音を隠せない人間だったのです。
***
続きは8月25日(金)です。
お待ちください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
