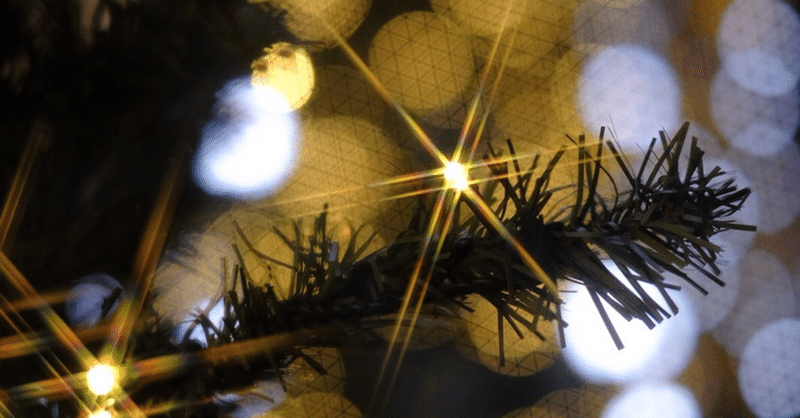
『孔雀とナイフとヒエラルキー』第2幕
聖夜
1
十二月二五日、クリスマス。学校が冬休みに入っていたので、私は普段より遅い起床となった。この日、午後から友美の家でパーティーが開かれる。私は楽しみな気持ちと億劫な気持ちが混ざり合って、ブルーな気分になっていた。
「そうか、今日か」
私は部屋を出て、リビングへと出た。そこにはストレッチをしながらテレビを見ているパジャマ姿のお母さんの姿があった。お母さんはどうやらこの日、仕事は休みだったらしい。
「お、由香里おはよう」
「おはよう」
お母さんは既に朝食を食べていた。私は自分のご飯の用意を始める。パンを袋から出してトースターにして入れる。そうしていると、お母さんが話しかけてきた。
「そういえば、今日はクリスマスだね」
「そうだね」
「楽しんできなね」
「わかった……」
この日、友美の家でのパーティーに私も出るということは、数日前にお母さんに伝えていた。お母さんは、せっかくだからと前日にお菓子を買ってくれた。それは友美に渡すための物で、とても嬉しかったのだが何だか気が重くなった。パンをトースターで焼き始める。リビングに出て、改めてテーブルの上に置かれたお菓子が入った袋を見つめる。上手な説明はできないが、面倒くさいという漠然とした感情があった。私は、彼女と一応は友達である。だけど、そこまで深い間柄でもないと思っていた。
どうしてか、私は深い間柄の友達を作ることがいつからかできなかった。それは、見えない力関係や、読み取りきれない気持ちの数々がそうさせたのだとは思う。後になって考えれば私は、ただ純粋な友達が欲しかったのだ。気兼ねなく接せる、普通の友達。その人が私にはいないように思えた。どうしてそんな思考になったのか。もしかすると、錯覚や幻想、理想が幾らかはあるのだと思うが私の生の気持ちが願ったのだ。友達が欲しいのだと。
焼き終えたパンを皿に出す。バターを塗る。私はパンにはバターを塗って食べるのが好きだった。食べながらテレビを眺める。内容は先日から世の中をざわつかせているいじめが原因の事件だった。お母さんもテレビを見つめていた。コメンテーターやキャスターたちが相変わらず合っているのか、的外れなのかよくわからないことを言っている。改めて事件の内容を聞くと、男子生徒が複数の同級生からいじめられたことが原因で、いじめていた同級生をナイフで刺したのだった。幸い、刺された相手は軽傷だったようだが、男子生徒は警察署に連行された。その様子が、堂々と報じられている。世間や大人にはよほど衝撃だったようで、いろいろと騒いでいるみたいだった。お母さんも口を開けてその様子を見ていた。
「こんなことがあるのね」
「そうだね」
私は、こんなことがあり得る世界なのだと前々から思っていた。私たちはみんな、誰かに向けて鬱憤や不満、怒りを抱えている。だから、いつ、誰が、耐えきれなくなって何をしてもおかしくはないと思っていた。ただ、私の周りでそれが起きてないだけであって、世の中では頻繁に起こっているのだと感じていた。
パンを食べ終えて、服を着替えて、荷物をまとめた。パーティーは午後からなのでゆっくりと準備をする。あと一時間ほどで家を出ればいい。私は少しの間、部屋でゆっくりすることにした。好きなアーティストの音楽を聴いたり、動画サイトで流行っている動画を見たりした。そうしているうちに時間になったので、家を出ることにした。外は寒そうだったのでコートを身に纏う。リビングに出ると、テレビは東京とかで開かれているクリスマスイベントのことを伝えていた。綺麗なクリスマスツリーが画面に現れる。私は一瞬だけそれを見て、お母さんを探した。
「お母さん?」
「はい、何?」
洗面台の方から声がする。程なくして、お母さんがリビングに来た。
「じゃあ、行ってくるね」
「うん、気をつけて。あと、あれ、忘れないでね」
「あ、危なかった」
私は慌ててテーブルの上に置かれたままの袋を手に持った。それから、玄関に出てしゃがんで靴を履く。靴を履き終えて、立ち上がる。後ろを振り返ると、お母さんが立っていた。
「じゃあ、行ってきます」
「行ってらっしゃい!」
私は扉を開けて、外へ出た。階段を降りて、駐輪場へ向かう。予定の時間はまだ余裕があった。私は自転車の鍵を開錠する。それから、前面に取り付けられているカゴの中に袋を入れた。私は自転車に跨って、ゆっくりと漕ぎ出した。
友美の家は私の家から遠かった。そのため、街の中心部を抜ける必要があったので、私は中心部へと繋がる大通りに入った。道は少しだけ混んでいて通り抜けるのに時間がかかった。交差点に入り信号待ちをしていると、横の広場に大きなクリスマスツリーが飾ってあった。すぐそばでは子供たちが楽しそうに遊んでいる。私にもああいう時期があった。無邪気な心で友達と遊んでいられた、楽しい時間。ところが、今はどうだろうか? 私が純粋に楽しいと思えることは気づけば年月を経て減っていた。もっと言えば、その時間はこれからもどんどん減っていくのだろうなと諦めているところがあった。そう考えただけで、私は少しだけ悲しくなった。そう考えている間に信号は青になった。私は再び自転車を漕ぐ。
友美の家を探し当てるのは大変ではなかった。彼女から教えてもらっていた住所を地図アプリで検索をかけて事前に付近の様子をチェックしていたからだ。それと、友美の家は広かった。
石崎友美の家は、言うなれば西洋風のお屋敷だった。ブランコが一つ置かれている広い庭。季節の花が咲いている花壇。車が三台くらいは入りそうなガレージ。建物は二階建てで、広さはざっと見てバレーボールのコート二面分くらいはあるように思えた。
私は敷地内に入って、自転車が何台も置かれている場所に自分の自転車を並べた。この自転車たちはおそらく、友美が誘った仲間たちの物だろう。私は鍵をかけて、荷物をカゴから出して肩にかけた。玄関まで歩いて、インターホンを鳴らす。すると、すぐに応答があった。
「はーい」
「あ、佐野です」
「あー由香里! 今鍵を開けるからそこで待っていて」
友美の声だった。初めて彼女の家を訪れたせいなのか、なぜだか緊張してくる。程なくして、ドアの鍵が開けられた。扉が開くと、普段の私服とあまり変わらない姿の友美がいた。
「由香里! 待っていたよ」
「おじゃまします」
「どうぞ、どうぞ」
私は家の中に入った。玄関からして私の家よりも広かった。足元を見ると十人分くらいの靴が置かれており、横の方にも目を向けると数十足は入りそうな靴箱があった。靴を脱いで上がるとすぐに広い階段があった。周りには大きな花瓶や絵画が置かれている。私は彼女の住む世界はこんな所なのかと思った。
「広間は向こうよ。ついてきて」
友美の後ろを歩く。廊下にも高価そうな物がいくらか置かれていた。私は壁に掛けられていたバナナの絵を見つめる。この絵がいくらなのかは私にはわからなかったが、絵を見てお菓子を渡すことを思い出した。
「友美、ちょっと待って」
「どうしたの?」
彼女が足を止める。
「渡したい物が、あるんだ」
「なになに?」
気になるとでも言いたげな顔をして体ごとこちらを向いた。私は袋からお菓子を取り出して、彼女に見せた。
「このために用意したお菓子。どうぞ」
お菓子を差し出す。すると友美は嬉しそうにそれを受け取った。
「ありがとう! 嬉しい!」
「よかったよ。喜んでくれたようで」
彼女はそれを大事そうに抱えて、再び歩き始めた。私もついていく。
程なくして、広間へと入った。その広間はとても広く、モダンなデザインと家具で印象が統一され、洗練されていた。まるで、ドラマのセットのような空間で、私はまたしても驚いた。周りを見回すと、既に何人かの客人がいた。顔を見ると、真希ちゃんたち、バスケ部のチームメイトや、知らない顔の人もいて彼女の交流の広さを改めて意識した。
「本番はこれからだから、呼んでいる子がみんな来るまで待っていてね」
友美はそう言って、広間から出て行った。お菓子は彼女がそのまま持っていってしまった。みんなで食べることを想定していたのだがなと正直思った。おそらく、何かの準備をしに行ったのだ。私は誰も使っていないソファーにとりあえず座る。しばらく、窓の外を眺めていると、真希ちゃんが横に座ってきた。
「やあ、来たのね」
「まあね」
彼女は手に持ったガラスのコップを口につけて、中のジュースを一気に飲む。「ぷはあ」と言ってから彼女は小さい声で喋り始めた。
「このパーティー、色々な人がたくさん来てるけど、本当に友達だから来た人って何人いるのかな?」
その話に私は思わず小さな声で、聞き返した。
「どういうこと?」
「彼女さ、自分から声をかける方じゃん」
「それはそうだけど、それが何?」
「本当は、みんな逆らえないだけな気がしててさ。私だって、出ておかないと彼女に避けられるような気がしてさ……」
「それは、そうかもね……」
真希ちゃんの話に反論の余地はほとんど無かった。実際、これまで友美の意にそぐわないことをした人たちはみんな無視などをされていた。もしかすると、このパーティーに来ないという選択をした人たちはこのグループから外されてしまうのかもしれない。そんなことを考えると恐ろしいという言葉が浮かんできた。その瞬間、扉が開く音がした。私を含め全員が入り口の方を振り向く。そこには友美の姿があった。この部屋に静寂が訪れる。
「じゃあ、時間になったからパーティーを始めようか!」
彼女は拳を上げて朗らかにパーティーの始まりを宣言した。それに続いて、今度は私たちが「おー!」と言って、拳を上げたりした。
こうして、波乱のクリスマスパーティーが始まった。
2
いざ、始まってしまえばパーティーはとても楽しいものだった。友美が用意してくれた肉やパスタ、スイーツの数々は美味しくて、ついつい食べこんでしまった。それはこの場にいる全員に言えることで、みんな「美味しい」と口を揃えて用意されたものを食べていた。
「どう、美味しい?」
友美が明るい調子で声をかけてきた。
「美味しいよ」
「良かった。用意した甲斐があったよ」
「どうやって、こんな量を用意したの?」
「週一でお手伝いさんが私の様子を見に来るんだけど、昨日来てくれたから手伝ってもらった」
「へえ、そうなんだ」
「二人で用意するの大変だったから、喜んでもらえて嬉しい」
「え、二人?」
私は思わず質問していた。この時、友美の表情が一瞬だけ曇ったような気がした。それでも、彼女はすぐに明るい調子に戻ってこう答えた。
「私の両親、仕事が忙しくてさ。いつも家に居ないんだよね。だから、普段は一人で過ごしているんだ」
「そうなんだ、知らなかった、よ……」
「いいの、由香里には今まで全然言ってなかったもん。そんな、暗い顔しなくても大丈夫だよ」
私はいつの間にか暗い顔をしていたようだった。その訳は、彼女も大変なのだなと思ったことと、それまで彼女がこの事を伝えてくれなかったことのショックが混じったからかもしれない。それと同時に、ああ、私は彼女に頼られていなんだなと直感的に思った。ちょっぴり傷ついた。直後、彼女は別の友達に呼ばれて向こうへと行ってしまった。
この頃の私は友美のことを不信に思う反面、心のどこかで頼ろうとしていたのだと思う。それはなぜか。なぜなら、私は独りだと思っていたからだ。いくら表ではいろんな交流や仲間がいようと、裏にどうしても満たされない気持ちがあった。私は寂しかった。
パーティーが続いている中、私は幾人かとの新しい出会いがあった。
「こんにちは。はじめましてかな?」
「はじめまして……」
「あ、私は桜木かりんっていうの。友美の中学の同級生」
「はぁ」
「よろしくね!」
「よろしく……」
桜木かりんはとてもお洒落な人だった。流行の色味のニットにダメージジーンズ。ニット帽に少し長めの黒髪。手にはドリンクの入ったグラス。同い年の高校生には見えなかった。彼女はすぐに私の横にあったソファーに座り込んだ。すると彼女は、私にも座るように促した。
「座ったら?」
「じゃあ、遠慮なく」
私もソファーに座る。かりんさんはグラスに入ったドリンクを一気に飲むと、私の方を向いた。私はなんだか照れた。
「友美は学校ではどうしているの?」
彼女に質問に私はどう答えて良いのか分からず、少し考えた。不自然に間が空く。少し焦って、私は答えを絞り出した。
「ええと、そうですね。彼女は普通に頑張ってますよ。友達のこととか、勉強のこととか」
かりんさんはそれを聞いて、神妙な表情で窓の方を見つめる。目は遠くを見ていた。
「そうか、友美、やっぱり頑張っちゃっているのか……」
「頑張っちゃってるとは、どういうことですか?」
友美が用意していた広間中に設置されているスピーカから、流行りのクリスマスソングが流れている。私とかりんさんにとっては場違いだったのだが、逆にそれが良かった。かりんさんは言葉を選ぶような感じで答えてくれた。
「彼女さ、私たちからしたら普通じゃないじゃん。両親のことなんか特にそうだって本人が昔言ってた。それで……」
「それで?」
「それで、普通になりたがっているの彼女は。だからこそ、友達を欲していんだと思うんだ」
「そうだったんだ…… 」
「でもさ、彼女は友達を欲している割には、友達のことを位づけしたり、突き放したり、ねちっこく攻撃したりしてた」
「どうして……」
「私にもよくわからない。でもそのせいで、倉持さんって人が相当傷ついてた」
「待って、倉持って、倉持咲のこと?」
この質問をした時、かりんさんはとても驚いたような顔をしていた。
「そう。あれ、友美と同じ高校だっけ?」
「そうです。友美は、倉持さんには近づくなって言っていました……」
「そうか……」
彼女はまた遠い目をした。何か思うところがあるような言い草だった。そういえば、私は友美と倉持咲がどうして面識があるのかを全然知らない。そう思った私は思い切って、彼女に尋ねた。
「あの、友美と倉持さんの間に何があったんですか?」
かりんさんはそれから一分ほど言葉に詰まった。周りは私たちの会話に全然気付いてる様子はなく、私たちの間にはただ静寂があった。やがて、彼女はひそひそ声で事情を話してくれた。
「昔は、友美も倉持さんも仲が良かったんだ。だけどさ、二人の間になにか大きな出来事があったみたいで、それから友美は彼女のことを周到に攻撃するようになった。仲間外れにしたり、無視したり」
「そんな……」
「それで、倉持さん、その事が相当こたえちゃったみたいで、病院に通うようになったみたい。そして、倉持さんはなぜか折りたたみ式のナイフを持ち歩くようになったの」
「折りたたみ式のナイフ?」
かりんさんはジェスチャーで手のひら程の大きさだと教えてくれた。
「倉持さんは、何かに怯えるようになって、それから少し荒っぽくなった。中二の時なんかはたまに机とか椅子を蹴っ飛ばしてた」
「そんなに」
「一見すると怖いでしょうけど、あれは彼女にとって必要なことになってしまったんだと思う。ああやって、物に当たっておかないと心の平穏が保てない感じ」
私はなんて言えば良いのかわからなくなった。今度はこっちが返す言葉に詰まる。それを見たかりんさんは立ち上がって、水を持ってきてくれた。
「ありがとうございます」
「いいの。こっちこそいろいろ話してごめんね。せっかくのパーティーの場でするような話題じゃなかった。ごめんなさい」
「いいえ。でも、おかげで友美と倉持さんの関係が少しはわかった気がします。少し前から気にはなっていたので」
「それなら、良かったよ」
彼女の表情は心なしかさっきよりも明るくなっていた。直後、向こうのほうからかりんさんの友達らしき人たちがやってきて「ねえ、ケーキ食べない?」と彼女を誘った。彼女は「喜んで」と返事をする。すると友達たちは「じゃあ、向こうで待ってる」と言って離れていった。
「じゃあ、また今度お話ししましょう」
「はい」
「ありがとうね」
「こちらこそ、ありがとうございます」
別れの挨拶を交わして、かりんさんは友達たちのいる向こうの方へと歩いていった。
私は大きなテーブルの上に並べられているケーキを一つとって、ソファーへと腰掛けた。ケーキをフォークで切り分けて、口へと運ぶ。私はケーキを食べながら考えてみた。友美はどうして、友達を求めておきながらいじめたりしているのだろうか。どうしたら彼女のことw助けられるのだろうか? もっと言えば、友美のせいで傷ついてしまったという倉持咲のこともどうしたら助けられるのか。助けるという言葉はもしかしたら上から目線な表現だとすぐに思い返す。じゃあ、どうやったら二人は仲直りできるのだろうかと改めて考える。私には友達と呼べる人はいないが、あの二人に何かをしてやりたいと浅はかながらに思った。どうしたら良いんだろうか。つい考えてしまう。二人を仲直りさせたところで、私には何の得もないのに。それでも、そうしなくちゃと心の中で感じた。だけど、私にはそれを実行に移す勇気はなかった。その場の勢いで、考えてはみたが、まず私にはこのことに踏み込む覚悟がないことに気づいた。それから、もし、それで私も無視されたら、今度は私が友美のピラミッドから蹴落とされてしまう。そうなったら、今度は私の方が辛くなるかもしれない。怖かった。私はこの時、自分が誰かに嫌われることが怖いことに気付いた。私は何もできそうにないと思った。やるせなくなって、ケーキをソファーの上に置いて、ため息をした。
それからパーティーは一時間ほど続いた。お客さんたちはいまだに騒いでいる。隣に家が無いだけあって、近所に迷惑になっているのではないかという不安はあまりなかった。私も気持ちを切り替えて、パーティーを楽しんだ。ケーキーをもっと食べてみたり、真希ちゃんらと他愛もない会話をしてみたりした。それでも、このパーティーへの違和感は払拭しきれなかった。そういえば、友美はどこにいるのだろうか。少なくとも十分前からこの広間には居ない。興味本位で私は友美を探してみることにした。広間を出て少し歩いて、部屋を探す。静かなリビング、散らかったキッチン、どれも私の家から比べれば羨ましくなるほどに綺麗で広かったが、そこには居なかった。仕方なく私はこれまた大きな二階へとつながる階段で上へと上がることにした。
「おじゃまします……」
二階へと上がると、廊下の途中で扉が七つ程あった。おそらくのこれらの扉のどれかの向こうに友美はいる。私は扉を一つ一つノックして確かめることにした。
一つ目の扉はハズレだった。特に反応がない。二つ目を叩いてみたが、これも応答なし。三つ目も四つ目もだめだった。
「どこだろう……」
五つ目の扉を叩く。すると、扉の向こうから、
「誰?」
と声がした。
「あ、由香里だけど。どこにいるのかなと思って探してた」
「あ、ごめんごめん。今、パーティー最大の見せ場の用意してるから、下で待っていて!」
彼女は扉ごしにいつも通りの明るい声で話していた。
「わかった。じゃあ、下で待ってる」
私はこの時、倉持さんのことも話して見ようかと考えたが、いざ実際に話しかける勇気はなかった。元来た道を歩き始める。彼女は何をしているのだろうか。でも、みんなを楽しませようと準備をしているのだということは理解した。
下へと戻ると、みんなはまだまだこれからと言わんばかりに思い思いに盛り上がっていた。様子を見ていると彼女らはこの刹那を精一杯生きているのかもしれない。不思議とそう思える。私もそれに混ざろうと思って、輪に入った。とても楽しかった。しばらくすると友美が戻ってきた。手には大きな何かを抱えている。
「じゃあ、クリスマスパーティー恒例のビンゴ大会を始めるよ!」
彼女は大きな声で高らかにこう告げた。
3
「ルールは簡単。ビンゴが三つ揃ったらプレゼントを差し上げます。景品の内容はいつも通り先着順。一番最初にビンゴを三つ揃えたら一等賞」
彼女の昔からの仲間たちは、ビンゴと聞いて歓声をあげた。私たちも勢いで歓声をあげる。だけど「恒例の」と言われても私にはいまいちピンと来なかった。そう思っていると、かりんさんが私の方へと来て、ひそひそ声で喋りかけてきた。
「ビンゴ大会は昔からずっと、やっててね。かなり盛り上がるの」
「そうなんですね」
「これ、景品がかなり豪華で、一等賞が最新の高級コスメ」
「本当ですか?」
私とかりんさんが話している間にも友美はビンゴ用の小さなガラガラをテーブルの上に置いた。
「今から、これからカードを配るね」
友美はビンゴのカードをその場の全員に配りはじめた。一人一人、丁寧に渡して回る。私が友美の様子を眺めていると、かりんさんが肩を叩いてきた。
「じゃあ」
そう言ってかりんさんは私の隣からいなくなった。次第に友美は私の方へと近づいてくる。
「由香里もどうぞ」
友美がカードを差し出す。彼女の顔は笑っていた。私は彼女の顔をほんの一瞬見つめる。その表情には曇りな無かった。
「ありがとう」
私はカードを受け取った。
友美がこの場にいる全員に用紙を配り終えるとすぐにビンゴゲームが始まった。
「23番!」
友美がガラガラを回して、出てきた玉に書かれた数字を読み上げていく。豪華な景品が貰えるからなのか、室内は静かな熱気に包まれていた。
「だめね」
「あ、リーチ」
静かなこの空間に密かに声がする。ここにいるほとんどが真剣そのものでビンゴに挑んでいる。かく言う私もつい熱が入ってしまっていた。
「次、33番!」
友美がガラガラを回す。
「ああ、当たらないな。悔しい」
思わず声が出てしまった。周りの声も次第に大きくなっている。室内の熱気が盛り上がっているのが感じられた。そうしている間にも友美はまたガラガラを回した。
「45番!」
全員が用紙上の45番の数字を探す。すると、向こう側にいた誰かが手を挙げた。
「ビンゴ出た!」
その後、次々と「ビンゴ出た」の声が聞こえてきたが、ビンゴを三つ揃えた人はなかなか現れなかった。私に至っては、そもそもビンゴが一つも出せていない。決着がつかない中、会場の熱気は最高潮に達している。友美の顔を見ると、楽しそうだった。
「それじゃあ、次行くよ!」
友美がガラガラを回そうとした、その時だった。どこからともなくチャイムが鳴った。
「あれ、どういうこと?」
友美が不思議そうな顔をした。彼女はすぐに「少し待ってて」とみんなに言ってからこの部屋を出ていった。このタイミングで誰かが来たのだろうか? 私は少し変に感じた。それは、ここにいる全員が同じ考えだったようで、ひそひそ声で「どういうこと?」と言っていた。時刻は午後四時。こんな時間にから参加するとは珍しいなと思う。私は友美が誰かを連れて戻ってくるのを待つことにした。
友美が出ていってから何分かが経った。もうそろそろ戻ってきてもいい頃合いなのに、彼女がなかなか戻ってこない。ここにいる全員が待ちぼうけしていた。待っている間、私はあることを思い出した。
『そういえば、友美が毎年クリスマスにパーティーをしているのだけど、今年はあなたも来る?』
少し前に聞いた倉持咲の言葉が頭を過ぎった。彼女はこれまでこのパーティーに来ていたのだろうか。少なくとも今、ここには居ない。そう思った時、私はあることに気づいた。
「え、ちょっと待って!」
「由香里!?」
私は急いで広間を出た。数時間前に通った、玄関までの道を急ぐ。もし、倉持咲がこのタイミングで来たとしたら、友美はどんな反応を示すのだろうか? そう考えたら、二人は喧嘩をしてしまうような気がして、私は急いで誰が来たのか確かめたくなった。
玄関まで走っていると段々、声が聞こえてきた。
「入れてよ!」
「だめ、来ないでよ!」
ああ、そんな。本当に来てしまったのだろうか。友美と誰かが言い争う声がする。玄関の前まで来ると、そこには友美と倉持咲の姿があった。
「何してるの!」
私は慌てて声をかけた。友美と彼女がここで言い争っているのを止めたかったからだ。
「由香里……、来ないで!」
だが、咄嗟に友美は私のことを拒んだ。
「どういうこと?」
私は思わず強い口調で友美に訊ねた。
「これは、私と倉持の問題なの! 由香里には関係ないことなの!」
彼女もまた強い声で言い切った。それに対して私は、これ以上は言えなかった。私にはこれ以上二人と言葉を交える勇気がなかった。それが、後々に命取りになることも知らずに私は、ここで言葉を止めてしまった。
二人の諍いは私の目の前でなおも続いた。
「なんで、私を拒むの?」
「あんたが気に食わないから!」
「どうして?」
倉持咲はついに彼女の方に近寄って両肩に手を置いた。だが、友美はそんな彼女の言葉に答えもせず、彼女の手を握り払う。そうして、彼女を突き飛ばした。
「きゃっ!」
倉持咲は大きな音を立てて一瞬にして床に倒れ込んだ。私は突き飛ばした友美の方を見る。友美の顔はどこかぎこちなく、でもスッキリしたような表情をしている。一方で倉持咲は半ば泣きそうな顔をして、倒れ込んだままだった。私はついに友美のことが理解できなくなった。どうして、ここまで執拗に倉持さんを拒むのか。その行動が私にはもう理解できなかった。自分の顔がこわばるような感覚に襲われた。すると、友美はこっちの方を向いた。
「何か、あるの?」
その目はどこか虚無のようなものを包んでいた。私はそれが怖くて、またしても何も言うことができなかった。
「ああ、ああ、あああ!」
すると、背後から倉持さんが起き上がって、友美を背中から蹴りつけてしまった。友美はその場に倒れ込む。それから倉持さんは周りに置かれていた雑貨品を手で払い除けたり、持ち上げて床に叩きつけたりした。彼女の目はどこか悲しそうだった。
悲しげに暴れる倉持さんを私は見つめた。向こうは私の視線には気づかない様子だった。一方で友美も倒れ込んだままそれを目にしていた。それから彼女は急に泣き出して、玄関を飛び出していった。
「待って!」
私は声をかけた。それでもこの声が倉持さんに届くことはなかった。
程なくして友美が起き上がった。
「友美……」
「なに?」
彼女のその言葉には怒りや苛立ちの思いが含まれていた。
「ううん。何でもない……」
私にはそれ以上言うことができなかった。
友美は辺りを見回す。私もそれにつられて周りを見た。倉持さんが散らかした物が散乱している。それはまるで、友美と倉持さんの関係性を示しているように思えた。すると、彼女は私にこう告げた。
「今日のパーティーはおしまい。帰って」
その言葉には棘が含まれていた。
「待ってよ」
「いいから、帰って!」
そう言って彼女はみんながいる方へと一人で向かっていった。彼女の背中には孤独が付き纏っているように見えた。
一人になった私はその場に座り込んだ。それから一息、深呼吸をした。
「なんで、こんなグチャグチャなんだろう……」
顔を上げて何も無い天井に向かって呟いてみる。もちろん、何も答えは返ってこなかった。
4
散らかったままの玄関で、私は天井を眺め続けた。何もない虚空だ。それはまるで、今の私たちの心をそのまま表したようなものだった。
「はあ……」
ため息を吐いてみる。何も起こらない。ふと、足元を見つめてみても何もない。あるのは、割れた花瓶の破片や、落ちたままの額縁の類だけのように見えた。外から入ってくる夕日が私や破片たちを照らし出した。
すると、光に当たって、銀色に光る物に気がついた。私は思わずそれを手に取る。
「これは……」
それは、掌くらいの大きさの折り畳み式のナイフだった。興味本位で刃先を出してみる。刃が夕日に照らされて輝いている。これが、かりんさんの言っていた、倉持さんのナイフなのだとすぐにわかった。おそらく、さっきの喧嘩で倉持さんが落として気がつかなかったのだろう。友美はみんなのところへと行ったままだ。
もし、彼女がこのナイフを見つけたら、何をするのだろうか? 私は、理屈は無いはずなのに少し怖くなった。このナイフは直接、倉持さんに渡すべきだと思った。だから、それを刃先を畳んでポケットに隠そうとした、その時だった。
「ねえ、それは何?」
後ろを振り返ると、そこには友美が立っていた。
「な、何でもないよ」
思わず、右手に持ったナイフを背中に隠した。しかし、友美はわたしの右手を何も言わずに掴んだ。
「やめて!」
彼女は私の叫びをものともせず、私からナイフを取りあげた。彼女に握られた右手が痛かった。それから友美は、謝ることも無く、廊下を歩き始め、階段を登っていった。私は何も言うことができず、ただ立ち尽くした。
友美と倉持さんの喧嘩から三十分ほどが経って、私は荷物を持って、友美の家を出た。その時、彼女の家からやけに冷たい空気が、私の心に流れ込んできた。それは友美が持つ負の感情がそう感じさせているのか、それとも、石崎家全体が持つ空気なのかは判別はつかなかった。
あの後、改めて、かりんさんに聞くと、友美の両親は共働きで、あまり家にいることは少なく、今では、彼女のことを置いて、海外にいるとのことだった。彼女の家族が家に居ないことと、彼女の言動にどういう関係性があるのかは、わからない。だけど、それは誰か、あるいは友美自身が何とか乗り越えなくてはいけないことのような気がした。
帰り道、自転車を漕いでいるとイルミネーションが目に入ってきた。カラフルに点滅する大きなクリスマスツリー、袋を担いだサンタクロースの格好をしたおじさん、それに群がる子供たち。その時、私は、世間はクリスマスだったことを思い出した。思い出したけれど、それを喜べる気にもなれなかった。
思わず、自転車にブレーキをかける。何も考えずにぼーっとしてみたら、案外それだけで、気持ちが落ち着いた。
空はすっかり暗くて、星がところどころ見えている。この時の私の気持ちもこんな感じだったのだろうか。後になって考えてみたが、この頃の私の気持ちはぐちゃぐちゃになっていて、今でも上手に表現ができないでいる。
この後、私はお母さんのためにチキンを買ってから家へと戻った。
家で私が買ったチキンを食べていると、またしてもお母さんが「何かあったでしょ」と聞いてきた。「なにも、ないよ……」と私が返すと、心配そうな顔で話をやめた。そこまでは、いいのだが、私にとって意外だったのは、この後、お父さんがいつも以上に早く帰ってきたのである。
「ただいま」
疲れ切った調子でそう言ったお父さんを見て、私は驚いた。
「ねえ、どうしたの? いつもより早く帰ってきちゃって……」
「あ、ええとな、今日はクリスマスだし、せめて今日くらいは早く帰ろうかと思ってな。あ、あとこれだ。これを由香里に渡したかったんだ」
弱々しい声と共にお父さんは小包を差し出した。
「何これ?」
「クリスマスプレゼント」
私は、どうにも苦しい気持ちになって、それを受け取るなりすぐに部屋へと直行した。
「おい、由香里?」
「由香里?」
お母さんとお父さんの声が聞こえたが、それに答える気にもなれず、自分の部屋のドアを閉じた。いつのまにか息が苦しくなっていたが、この時の私はこうすることを選んだのだ。
プレゼントを傍に置いて、ベットの上に飛び込む。気持ちはぐちゃぐちゃ。かと言って、気持ちを落ち着ける手段はない。
「どうして、こうなるかな…… 」
自分の中に在るピラミッドが崩れはじめている。
みんなが必死に立てたピラミッドは、いずれ意味が無くなって取り崩されてゆくのだろうけど、私の中のそれは倉持さんという突如現れた存在に壊されようとしている。一方で、私自身は、変われずにいる。さっき、二人が喧嘩をした時、止めに入れていたらよかったのにと、この時思った。気がつくと眠りについていた。
目が覚めた時には真夜中の二時だった。開ききってない目で辺りを見回す。
「変な時間に起きちゃったな……」
眠気がとれていく。フラフラしながら立ち上がって少しストレッチをする。目を向けると傍に置いたままだったお父さんからのプレゼントがあった。
せっかく貰った物だから、開けないのももったいなかったので、包みを開ける。中には小さなオルゴールが入っていた。木でできていて、全体に温もりが感じられた。ゼンマイを回して、音を鳴らしてみる。流れてきたのは優しい曲だった。私にはこれがなんの曲かはわからなかったが、一瞬で好きになれた。この時、思わず自分が笑顔になれたことに気がついた。それから、誰に向かってでもなく、つぶやいてみる。
「ありがとう、お父さん」
いつか、この言葉をちゃんと言おう。そう思った。
それから、友美や倉持さんのことを考えてみた。二人が仲直りすることはできるのだろうか? しばらく考えてもこの状況を乗り越える手段は見つからなかった。
「考えても、仕方ないのか……」
私は一つの賭けに出ることにした。ただ、今すぐはどうにもできないので、私はまた眠りについた。
気がついたら、夜も更けて朝になっていた。
リビングに出るとお母さんが、いつも通りにテレビを見ていた。
「おはよう……、その、昨日はごめん」
昨日のことを謝る。昨晩は二人を心配させてしまった。本当にごめんなさい。
「良いのよ。気にしてないからさ。あと、お父さんも同じだから、心配しないでね」
お母さんの返事は意外なものだった。嬉しくなる。
朝食を済ませてから、私は頼れそうな人を探した。少し考えて真希ちゃんなら頼りになりそうな気がしたので連絡を入れた。すると、すぐに彼女から返信があり、昼過ぎから会うことになったので、私は時間が来るまで家で待った。
時間が来たので、待ち合わせの場所で数分ほど待っていると、真希ちゃんが現れた。私服姿の彼女がこちらまで駆けてくる。私の前まで来ると彼女は申し訳なさそうに聞いてきた。
「ごめん、待たせた?」
「全然」
「それなら良かった」
私と真希ちゃんは早速、近くの座れるベンチを見つけて座り込んだ。それからこの日の本題を話し始めた。
「今日、来てもらったのはさ、倉持さんと友美のことなんだ」
「うん。それで?」
「二人に仲直りしてもらいたいから、どうしたら良いか一緒に考えてくれない?」
「わかった。かなり難しいと思うけど、由香里ちゃんがそうしたいなら手伝うよ」
「ありがとう!」
私は真希ちゃんに向かって手を合わせた。
私と真希ちゃんはどうしたら二人を仲直りさせることができるのかを考え始めた。だけど、仲直りできそうな手立ては簡単には見つからなかった。
「どうしよう、出ない」
近くの自販機で買った温かいお茶を飲む。真希ちゃんもさっき買った温かい紅茶を一口飲んでからため息をついた。
「あの二人を隔てる壁は思った以上に大きそうね」
真希ちゃんが言った。私は二人を仲直りさせるための方法を書いたメモを眺めながら彼女の言葉にうなづいた。
「でも、由香里ちゃんがここまで人のことを考えてるの初めて見た」
「え、そう?」
「そうだよ」
彼女の言葉に私はハッとした。たしかに、これ程以上に他人のことを考えていたことが無かった。
私はただ、クラスの中にあるヒエラルキーのことや、自分を守ることしか考えていなかった。だけど、今はこうして、真希ちゃんと一緒に友美と倉持さんのことを考えている。私は、倉持さんが現れたことで何かが変わったのかもしれない。そう思えた。
「ねえ、何も浮かばないならまずは本人らに話を聞いてみたらどうかな?」
しばらく考えた結果、真希ちゃんはそう提案してくれた。たしかに、まずはそこからだと思った。
「そうだね。でも、倉持さんにどう話を聞いたら良いかわからないし、そもそも連絡先や家も知らないよ」
「大丈夫、倉持さんの家なら知ってる人がいるから、その人に聞けば良いと思う」
「本当! じゃあ、その人に連絡をとってもらって良いかな?」
それから彼女はすぐに連絡をとってくれた。私は次の日にその人と会うことになった。こうして、私の戦いが始まった。
次回、第3幕
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

