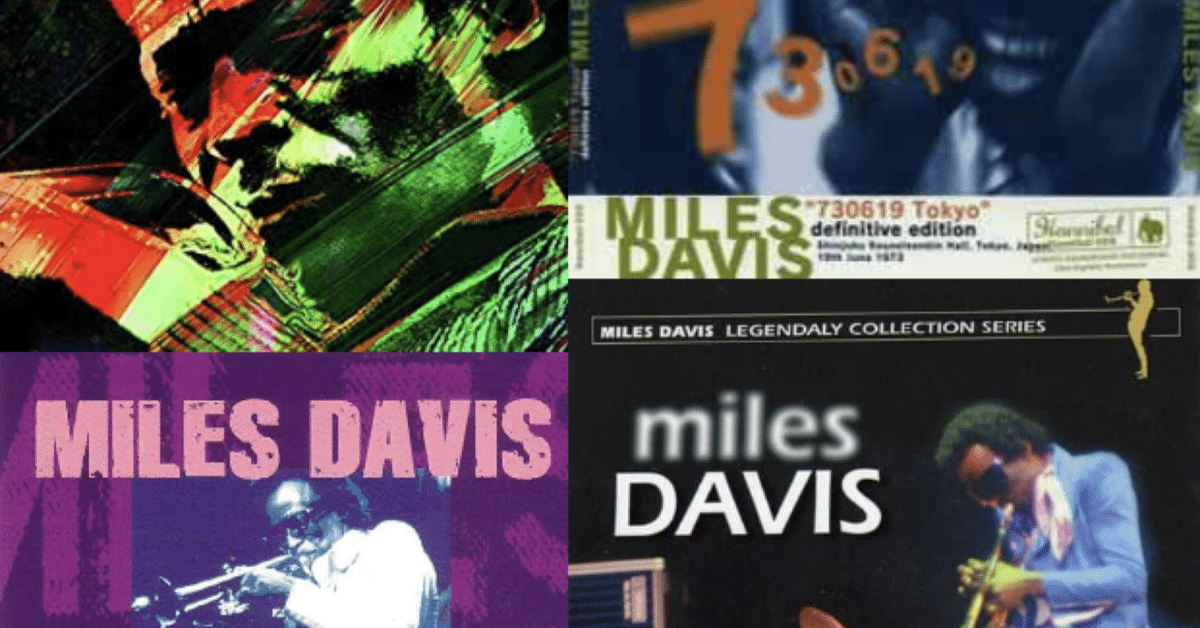
1973年6月19日のマイルスを聴く
personnel
Miles Davis (trumpet,organ)
Dave Liebman (tenor sax,soprano sax,flute)
Michael Henderson (electric bass)
Al Foster (drums)
Reggie Lucas (guitar)
Pete Cosey (guitar,percussion)
James Mtume Forman (percussion)
ブートをさらにブート化したコピー合戦に、新規音源発掘と謳っておきながら実際は既発音源の別ソースといった殆ど詐欺に等しい商売まで、ブートの世界は「出したもん勝ち」的な言い訳がまかり通っている。しかしながらそんな玉石混淆を見分けるのが困難な世界においてさえも「名盤」と呼ぶべき作品は存在するのは確かだ。
例えばビートルズであれば『ULTRA RARE TRAX』、ローリング・ストーンズでは『Nasty Music』などがある一定の世代から懐古の念をもって受け入れられている。これらが一体どんな理由で「名盤」として受容されているのだろうか。
やはり共通項としてあると思われるのが「音質の良さ」、「音源としての価値」、そして「パフォーマンスの良さ」。もっとも、古典的名盤として取り扱われているブートも、高音質が当たり前となった今の耳で聴いてしまえば大した感動は得られないだろう。音源としての価値についても、その後一年に二枚、三枚と発掘が進んでいけば段々と薄れていく傾向にあると思う。
それをさておいても名盤が名盤たるゆえんは「先陣を切った」、その一点にあると思われる。他がどうかは知らないが、マイルスでいえば80年代に『Double Image』(1969年ローマでのライブ)が出るまでロスト・クインテットの「ロ」の字も知られていなかったし、今回紹介する『Unreachable Station』も発表されるまで、初期アガルタ・パンゲア・バンドの姿望は音の悪いブートのみで殆ど雲霧を掴みに等しかった。
今では73年モノのブートもさして珍しいものではなくなったかもしれないが、73年東京、日本の観客が驚愕2割、困惑8割で迎え入れたこの貴重な模様をマトモに知るすべは無かったのである。どうりで中山康樹氏も喜ぶわけだ。
因みに音の悪いブートとは、Jazz Mastersから出ていた『Black Satin』のことである。マイルスブート草創期には大いに役立ったレーベルではあるが、いまや郷土資料館に入るレベルで古典中の古典である。現在でも稀にオークションサイト等で出回っているのを見かけるので要注意。

① Turnaroundphrase
先陣を切るのは何時もながらアル・フォスターのドラムス。75年までに段々とヘヴィーさを増していく彼のドラムであるが、この段階においてはシンバルのバシャバシャ感が一層強く、これはこれで絶品。
それと共にレジー・ルーカスとマイケル・ヘンダーソンのリズムセクションが絡み合っていくが、この段階、特にレジーのカッティングはどことなくまだ硬い印象を受ける。
一方で変わらないのがマイルスとデイヴ・リーブマン。1分前後に訪れる本日一発目のマイルス、遥か天空から見下ろすアブストラクトなフレーズは75年以降と比べても大きな遜色はない。
続いて訪れるリーブマンのソロも十二分に強力。74年にバンドを脱退してしまう彼だが、それも大納得、この段階にして殆ど完成され切っていたのだ。
対して大看板、ピート・コージーはどうか。う~ん彼もレジーと同様と見る。ディストーションとワウをバリバリに掛けまくり、しまいには大きな箪笥と見紛うシンセにギターを繋げてしまうという宛らサイバーパンクじみた妖しさがこの段階の彼にはまだ足りない。
そして聞いて驚くなかれ、これは『Pangaea』のA面《Zimbabwe》と同じ曲を弾いているのだ。75年時と比べ妖しい魅力に欠けるといっても、それ即ち演奏が悪いというわけではない。むしろオリジナルに近い、あるがままの「原色のPangaea」を存分に楽しむべきだ。本音源の見どころはその一点にあるといっても良かろう。
② Tune In 5
アルのドラムと共に意気揚々と訪れるのが《Tune In 5》である。「どっからどこまでが一つの曲なの?」という問題が出てくるが、さもありなん、この当時のマイルスに曲名など大した問題ではない。”Call it anything“なのである。どうしても気になる場合は拙稿『Agharta』 Preludeの謎をご覧いただきたい。
さて、マイルスとリーブマンが続いて出ると次第に熱気は冷め始める。タンバリンのような物を叩いているのは恐らくピート・コージー。75年までカウベルやカリンバといった小物は彼の領分であった。
そしてアルのドラムが一連の締めとばかりに再び盛り上がってくるとコージーのソロに入る。ここでも気迫迫る演奏で魅せたりはしないものの、これはこれで悪くはない。
マイルスとリーブマンもこの流れをもう少し持たせる。ここでもリーブマンのソロが炸裂する。70年代以降の電化地獄にあって、従来のジャズ的フィーリングを残したサックスセクションは必然的に箸休め的存在に収まってしまっていたが、ことリーブマンは違った。マイルスに対して食い下がり、ギターセクションに対しても食らいつく。少なくとも73年バンド前半期において、リーブマンはギターに対して圧倒的優位な立場にあったと見る。
③ Right Off
リーブマンのソロ中、不自然に挟まれた観客の拍手が明けると玄関で靴を脱ぐ暇すらないとばかりに強力なマイケルのベース・リフが始まる。この曲は前年度から演奏されていることもあって、特にアル、レジー、ムトゥーメ、マイケルのノリ様は素晴らしい。
ドラムがシャッフルビートに突入してからのコージーのソロは非常にブルージー。本来の彼はチェス・レコードでマディ・ウォーターズといったブルースの巨匠と仕事していただけあって、ここでのインプロは実に「らしい」。時代が進むごとにこのフィーリングが薄くなっていくことを考えると、このテイクは一周回って貴重だともいえる。
④ Funk
間断なく横入りするマイルスのソロから幕を開ける“Funk”のセクション。『Agharta』の一曲目《Prelude》の原型である。しかし『Agharta』 Preludeの謎でも取り上げた通り、『Agharta』収録の《Prelude》とは《Agharta Prelude》と《Funk》というあくまで異なる二つの曲のメドレー。ここで登場する《Funk》とは《Prelude》の前半22分部分を指す。実際に説明すると大して複雑でもない話なのだが、うーん、何ともややこしい話。
演奏から漂う雰囲気から察するに、《Funk》はこのライブが初出。ということもあって殆ど《Right Off》の即興の一部分といった感じがある。実際74年初頭までこの曲は《Right Off》とセットで演奏されていた。
しかしながら注目すべきは30分辺り、リーブマンのソロがもうそろそろ終わるぞという頃にレジーがさりげなく弾いているリズム・ギター。これはかなり74年以降のバッキングと近しいものがある。この段階においては即興の一部とはいえ、そもそも曲自体の構造はシンプル極まりない。後に通じるスタイルは初出段階でおおよそ完成していたといえよう。
⑤ Tune In 5
ムトゥーメのポコポコパーカッションで微睡の瞬間を迎え始めたころ、マイルスの指示で再びバンドの熱気は盛り返す。《Tune In 5》はアルのバシャバシャドラムから幕を開ける一曲。おそらくマイルスも「そろそろ潮時か」とでも思ったことだろう、シンプルで上手くノリやすいこの曲は終幕間際、しばしば単独で登場する。
⑥ Ife
記念すべき”Agharta=Pangaea Band“の初陣であるこの舞台、やや大人しい印象を受けるのはこの“Ife”の仕業でもあるだろう。『Agharta』にも『Pangaea』にも登場するこの楽曲だが、グチャグチャグーギャンが基調である両作においてすらもスローな部分を担っていた。
言わずもがな、72年から75年にかけてのマイルスの音楽性は、ジャズの寸胴鍋にオーネット・コールマンとJ.S.バッハとシュトックハウゼンとJBとスライ・ストーンの脛骨をぶち込んでじっくりコトコト21時間煮込んだような音楽である。やれ”シュトックハウゼン”、やれ”オーネット・コールマン“やら登場する具材一つ一つは難解なようだが、やっていることとしてはシンプルであり、音楽主義的でもあり、時にジャズ的ですらある。単にその基層的な発想が爆音とノイズでかき消されているだけなのである。
そういう訳もあって、このバンドの本領はスローが平常運転な“Ife”においてこそ発揮されるのだ。序盤7分間はマイルスの独断場、その裏で何やら密やかに暗躍するピート・コージーとムトゥーメのパーカッションが見どころ。互いの顔と演奏をよく見合い、それに応える、こういう所が実にジャズ的なのだと言いたい。
ソロはリーブマン→コージー→マイルス→リーブマン……と入れ替わり立ち替わりで熱気を増していく。マイルスのバンドに名手多しと言えども、彼らほど決定的な存在は居なかったと改めて実感させられる。
6月19日の”Ife“の演奏時間は22分間。長い、ひたすらに長い。全編通して耳をそばだてて聴くのは相当な注意力を必要とするだろう。しかしダルな瞬間があったかと思えば、ハイな瞬間もある。この絶妙な”焦らし”で聴者を飽きさせないのもまた一つの魅力であるといえる。
⑦ Agharta Prelude
「じゃ、せーので」のメロディーで始まる『Agharta』で言うところの《Prelude》後半部分を指す楽曲である。マイルスとJBの影響関係は言わずもがなとしても、マイルス、《Talking Loud》を若干意識して書いたのか?
JBの方とて《Cold Sweat》にて《So What》のリフを引用しているので、う―ん、持ちつ持たれつつの関係であることを伺わせる。
当然だが73年の段階ではこの曲、『Agharta』のそれとは全然異なる。マイケルもチョッパーベースを弾かないし、何よりリーブマンという強力なソリストが居る。ソニーもソニーで悪くはないが、リーブマンのドス黒くてノイジーなサウンドはここでも炸裂している。
⑧ Zimbabwe
セカンドセットにはやや大人しめな曲を選ぶ傾向にあるこの時期のマイルスだが、ここではその「で、どうする?」の度合いが一層色濃い。似たような「で、どうする?」が味わえるブートとしては同年10月13日ボストンのライブもあるが、偶然の一致か、セカンドセットで、さらに演奏曲目も一致しているというのが面白い。《Ife》、《Agharta Prelude》、《Zimbabwe》、これら三つに共通している点としては「スローになりやすい」点であろう。
もっとも《Ife》などといった場合においても、バンド自体が練度を上げていった1975年に入ると「ガガガガッ‼‼」で知られる1月22日東京公演の様に全くスロー化しないケースもある。しかしこれは73年である。ムトゥーメとコージーの出番(どちらもパーカッション役)も必要以上に多い。
40分ごろに登場するソロはレジー・ルーカス?彼がリズム以外を担当すると、この道50年一筋で豆腐のみを作り続けてきた職人がハンバーガー屋に暖簾替えするが如くの悲惨な有様に陥るのは今や周知の事実。だが不思議な事にここでの彼のソロのヘタウマ具合は場の雰囲気と不思議とマッチしている。絶妙なアラビアン感と、楽曲自体の怪しい雰囲気、意外なベストマッチがあったものである。
一時間三十分の演奏は一転して、ムトゥーメの静謐なコンガにて幕を閉じる。『Pangaea』における《For Dave》然り、73‐75年マイルスは地獄絵図のような瞬間もあったかと思えば、「わびさび」を思わせる瞬間がある。これが意外にも興味深い。
総評
入門度 ★★★☆☆
音質的には十分薦められるが、このバンドのベストな状態を捉えた音源とは言い難い。
テンション ★★☆☆☆
節々で盛り上がる箇所はあるものの、うまくコントロールできていない印象がある。しかしスローな展開も見ものといえば見もの。
音質 ★★★★★
FMブロードキャストがマスターという事もあり、バランス・音質共に完璧に近い。70年代マイルスのブート多しといえどもここまで綺麗な例は珍しい。
パーソネル ★★★☆☆
レジー・ルーカス、ピート・コージなどの面子が未だ真価を発揮しておらず、バンド全体の練度は高くない。しかしデイヴ・リーヴマンのソロをじっくり楽しめる。
レア度 ★★☆☆☆
リーヴマン参加の公式ライブ盤は『Dark Magus』と『Bootleg Series Vol.4』しか存在しないことを考えれば希少であると言えなくもないが、ブート界隈ではもはや食傷気味。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
