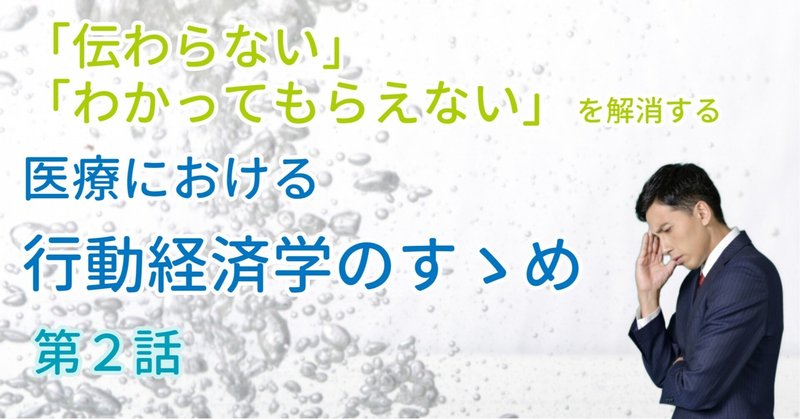
製薬企業が医師とより良いコミュニケーションを取るために有効な「行動経済学」
こんにちは。株式会社ユカリア データインテリジェンス事業部の城前です。
前回の第1話では、医療における「行動経済学」に私が出会った経緯と、それが「製薬企業の方」と「医師」の間でのコミュニケーションの改善にも応用可能なのではないか?という考えをお示ししました。
第1話はこちら
今回の第2話では、具体的な例を挙げながら、コミュニケーション改善のためにできることを考察していきたいと思います。
①製薬企業の方と医師のコミュニケーションを阻害しているものは何か
コミュニケーション改善の方法を考えるにあたって、まず最初に、コミュニケーションを阻害しているものは何なのかを考えていきます。
第一話で取り上げた2冊の書籍の中で挙げられている行動経済学のトピックと、弊社のコンサルティングプロジェクトの中での事例を元にすると、例えば以下が挙げられると思います。
製薬企業の持っているバイアス
医師の持っているバイアス
一方的なコミュニケーション
プロセスの細分化
②製薬企業の持っているバイアス
医師が製薬企業のMRに対して感じる違和感の一例としてしばしば挙げられるのが、「生存期間の延長」を医薬品の絶対的な価値と捉えているように受け取れる話法です。
「この薬はエビデンスにより、有意に生存期間を延長することが明らかになっています。」「なので、当社の製品をご採用ください。」というディテーリングが行われます。

製薬企業としては、生存期間の延長をその医薬品の最大の価値と捉えているからこそ、このような発信がなされるのでしょう。しかし、一人ひとりの患者のことを個別に考え、最善の治療を模索している医師は、2つの理由から、単純にこの説明に同意することはありません。
まず、生存期間が長いほど患者さんが幸せであるという前提自体が全ての患者さんにとって正しいとは限らないからです。人によって価値観は多用であり、残された時間をどんな状態であっても長く生きたいと考える方もいれば、たとえ時間が短くなったとしても好きなことをやり切って生を全うしたいと考える方もいます。
医師はそういった患者さん一人ひとりの価値観を大事にしながら治療方針を検討しています。
次に、薬のエビデンスは臨床試験による統計的な処理に基づいており、参加者一人ひとりの個別性は考慮されないためです。例えば、高齢者や合併症のある患者はそもそも臨床試験の参加対象から除外されます。しかし、特に生活習慣病や慢性疾患の患者さんの多くは、まさにそういった属性の方です。
医師は「自身の受け持つ患者」にその薬が効くのかどうかを知りたいと考えています。エビデンスの対象から大きく外れた属性の患者さんも多く抱えているため、エビデンスをもって即採用とはなりづらいのです。
医師に提案を受け入れていただくには、製品を起点とした価値訴求だけでなく、その医師の受け持っている個別の患者を起点にした価値訴求を行うことが有効であると考えます。
医師への的確なヒアリングや投げ掛けを通じて具体的な個別の患者像を捉え、その患者への処方検討を通じて、医師と一緒にその薬の処方の有効性を考えていく、そんな姿勢のMRを求めている医師が多いと感じます。
③医師の持っているバイアス
製薬企業だけでなく、医師の側にもバイアスは存在します。
書籍の中では、
非専門医よりも専門医の方が、治療選択にあたって、効果が低い治療をあえて患者に推奨する傾向がある
女性医師の方が男性医師よりもリスク回避的であり、ガイドラインに沿った治療を行う率が高い。また、患者の死亡率が低い
といった研究データが示されています。また、経験則として医師の頭の中には
「以前、似たような患者で○○ということがあったから、この人にも同じことが起きるのではないか」
という気持ちが生じることがあるとされています。

医師も一人ひとり、それぞれの経験や性格に基づいたバイアスを持っています。
詳しい解説は書籍に譲りますが、バイアスには、現在バイアス、確証バイアス、正常化バイアス、後知恵バイアスといった様々な種類があります。
もし、医師の言葉と処方行動の間に違和感を感じるようなことがあれば、医師の処方検討における思考回路を丁寧にヒアリングすることで、バイアスの存在を疑ってみてもよいかもしれません。
④一方的なコミュニケーション
特に限られた時間内のコミュニケーションでは、
一人が一方的に話す
相手のことを分かった気になって、すぐに解決策を押し付ける
といった会話が起きがちであると言われています。
書籍の中では、それが医師と患者の診察時の会話の例として挙げられています。
医師は限られた時間内に大量の患者を診察しなければならないため、
「いかに短時間で患者の状態を把握するか」
「いかに短時間で質の高い解決策を示すか」
という思考に追い込まれることがあります。
それが行き過ぎると、相手の話をじっくりと聴く余裕が無くなり、「わかりました」と話を遮り、「それなら、○○すれば良いですよ」と前のめりに解決策を提示するようになります。
このような話し方をすると、相手は「自分のことを理解してもらえていない」「主張を押し付けられた」と感じ、不機嫌になったり、不信感を抱くようになります。
このような会話のパターンは、製薬企業と医師の間のコミュニケーションでもよく見られるものではないでしょうか。
弊社がこれまでに行った医師へのインタビューでも、自身の患者の課題を十分に理解していないMRが食い気味に「それでしたら弊社の薬をぜひお使いいただけないでしょうか」と宣伝してくるのを、内心冷ややかに思いながら「検討します」と回答したエピソードを話す医師がいました。
アフターコロナの現在では、WEBでの極めて短時間のコミュニケーションが増えていると聞きます。
製薬企業にとっては医師とじっくり話し込みをすることが難しい、厳しい状況かと思いますが、確りとした前提状況の理解が無い中での処方依頼には効果が無いとする医師の声が多いのも事実です。
面談目的をヒアリングと提案で切り分けるなど、医師の状況や考え方の理解に一定の時間を割く営業上の工夫は重要なのではないでしょうか。
⑤プロセスの細分化
書籍の中では、長期間にわたる治療のプロセスにおいて、患者からの同意取得事項があまりに多く、その一つひとつが別々のタイミングで行われることによる弊害が指摘されています。
本来は疾患治療の全体観を捉えて意思決定するべきところが、一つ一つ細分化されることにより、時に患者にとって望ましくない結果を招いているということです。
いわゆる、「木を見て森を見ず」という現象です。
一例として、子宮がん患者がある時点での治療方針として、医師の推奨する化学療法に反して放射線療法を希望した例が挙げられています。
治療選択の結果、当初の医師が懸念したとおり、患者は下肢のリンパ浮腫と蜂窩織炎による入退院を繰り返し、日常生活が著しく阻害されるような状態になってしまいました。
後に化学療法の方がよかったと反省したものの、後悔の残る結果となってしまったそうです。
行動経済学では、人は本来考えるべき範囲よりも狭い範囲で意思決定をしがちであるとされており、この傾向はメンタル・アカウンティングと呼ばれています。
これと似た現象は、製薬企業と医師のコミュニケーションにおいても発生しているのではないでしょうか。
コロナによる環境変化もあり、昨今は営業場面において、認知向上や接点数の増加を目的としたKPIによる評価を重視する傾向があります。
その結果、メール発信・開封件数、WEB面談件数、オンラインウェビナー開催件数といったKPIに紐づく、医師向けの大量のメール、WEBコンテンツ、ウェビナーが溢れています。
そういった情報過多の中、医師からは、
数が多すぎて、どこに自身の求める情報があるのかわからない
マス向けで、自身のニーズにピンポイントで刺さる情報が無い
といった声も聞かれます。
これは、KPI向上という個別最適化を追求しすぎた結果、医師に価値を提供するという全体観を踏まえた本来の目的が十分に果たせていない例と考えられます。
医師に寄り添った発信を行うためには、マス向けの画一的な発信にとどまることなく、コンテンツのチューニングや、発信時のチャネルや表現方法の最適化も重要となってきます。
そういった取組みを行うためには、医師への定性的なヒアリングにより、いま具体的にどんな患者に対してどんな課題を持っているタイミングなのかを解像度高く把握する営業・マーケティング活動も、合わせて行っていく必要があるのではないでしょうか。
次回の第3回目は、
「製薬企業の方が医師を通じてその先にいる患者さんに良い影響を与えるには?」
という観点から、医療における行動経済学の活用方法を考えていきます。
よろしくお願いします。
ユカリアでは、
独自の電子カルテデータベースと専門家(医療従事者・アカデミア)ネットワークを強みとした、製薬企業様のマーケティング・営業活動をご支援する調査・コンサルティングを行っています。
詳細や事例にご関心のある方は、以下までお気軽にお問合せください。
株式会社ユカリア データインテリジェンス事業部
お問合せ窓口:pharma.biz@eucalia.jp
【製薬企業の方へお知らせ】
■ 無料の分析情報提供サービス Patient Visualizer(ペイシェントビジュアライザー)
薬剤のポジショニング・市場規模・患者像・競合品とのスイッチ状況 の把握に役立つ分析データやレポートなどの情報をご覧いただける情報提供サービスです。よろしければ、情報収集のため会員登録のうえご利用ください。
■製薬企業向け 営業活動支援サービス
弊社のご提供しているコンサルティングサービスの概要をまとめております。独自のアセットを活用し、製薬企業さまの営業活動のPDCAをトータルでサポートいたします。
