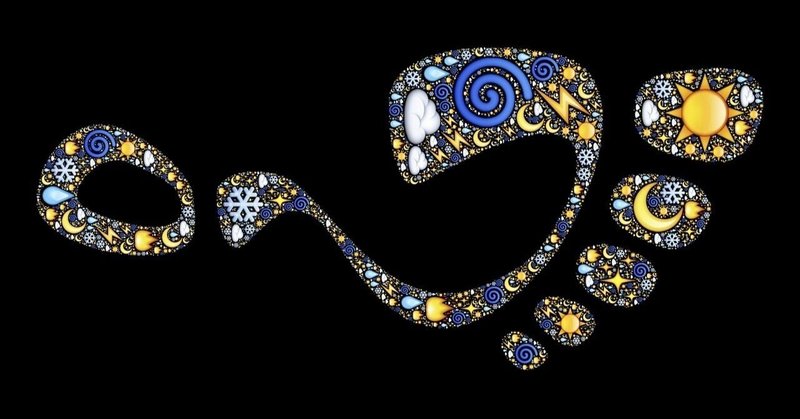
【コラム】「あるある」「あるない」「ないある」「ないない」 #021
このタイトルは何を言ってるんだ?(アタマおかしいのか?)と自分でも思う、な😏
きのうのコンサルティング習得講座6ヶ月目の内容から抜粋&シェア。
■事実と認識と
「実際にそうである」ということと「そうだと思っている」ことは違う。
実際には違うのに、そうだと思い込んでいることを『思い込み』という。
もっと背景からだと『先入観』『バイアス』というのもあるし、曲がってくると『偏見』なんかもそうかな。
いきなり話が全然関係ない方に行ってしまった・・・
実際にそうである、を「事実」とする。
思い込みはネガティブなイメージがあるので「認識」としよう。
事実「ある」ことを「認識」できているのが【あるある】だ。(そういうこと「あるある」ではない)
真逆の、事実「ない」し当然認識もでき「ない」ものが【ないない】。綺麗さっぱり存在しないと思ってもらえればいい。
【あるある】はあることが当たり前なので、実のところ普段意識していない。「水道の蛇口をひねったら水が出るかもしれないし、出ないかもしれない。今日はどうだろう」とか「通勤に使う交通手段に想いを巡らせる」ということはしない。
あることが当たり前すぎるので、もはや意識に上がってこない。が、
指摘されるとたちまち事実「ある」認識「ある」と判断できる。
【ないない】はそもそも何もないので、考えることもイメージすることもできない。人はないものをどうにかすることはできない。空想であっても「ある」ものならどうにかできるかもしれないが、全くないものを扱うことはできない。
なのでここでは【ないない】のことは考えなくていい。
■人の心理は、困ったとき「ないある」に目を向ける
【ないある】は事実「ない」ものだが「ある」と認識しているものだ。
最もわかりやすいのは未来のイメージ。今は事実「ない」。しかしこうしてやろう!などと考えたりイメージしてその通りに運ぼうとする。誰の目にも見えていないものが、その人には見えている・・・・「ある」ということがある。
子供なんかも【ないある】のいい例で、まだ生まれていなければ事実「ない」。認識も「ない」でも生まれてしまえば【あるある】に変わる。
『概念』は目に見えて実在するモノとしてはなさそうに思えるが、人間は概念を共通理解の存在として扱うことができるので、目に見えなくても事実「ある」と考える。
たとえばお金。紙の札は物理的に「ある」けども電子マネーや口座の残高9人で見えるものは「ただの数字」であって「お金」ではない。
「口」や「空」も同じ。口は部位を表す言葉ではない。私たちが口だと思っているものは口腔、舌、歯、歯茎、唇の総称で、物理的に口が指し示す場所はない。だが概念上は「ある」。空はどこからどこまでが空という定義がない。究極地面から離れればそこは空だといえる。
人間が概念を作り出すことができるのは、想像力や人間特有の脳の扱いを上手にしてきたからだ。これが「ない」ものを「ある」ことにする【ないある】の考え方になる。
事実は「ない」。しかしまず認識上「ある」ように考える。その「ある」はずのことを生み出すために行動なり手立てを講じる。上手くいけば事実「ある」にできたし、上手くできなければ改善したり試行錯誤を繰り返して「ある」にする。これが【ないある】の考え方だ。
そして人(類)は地道に【ないある】に取り組むが、人間心理では人は困ったとき、問題が起こったとき、ピンチの時に【ないある】をやろうとしてしまう確率が高い。
「会社の売り上げが下がってやばい!」というとき、なぜか大半の経営者は新規プランを立てたり、新しい計画や実行で乗り切ろうとする。そしてことごとく失敗する。
夫婦仲が悪くなったことに危機感を覚えると、危機感が強い方は今までやらなかったことをやろうとしはじめる。奥さんは会話を増やそうとしたり、家事をしなかった夫が家事を手伝うそぶりを見せたりする。そして大した効果が出ないばかりか、今更余計なことを・・・という感情を刺激してしまうことすらある。
マイナスの物事に対応するとき【ないある】はほぼ役立たない。
だから心理的に、ごく自然に【ないある】の状態に立たされたら、いち早く気がついてやめることだ。
やることは【あるない】にある。
■【あるない】が自分という物事を上手に運ぶキー
【ないある】がなぜ問題を解決できないかというと、ないものをあることにするには本来改善と試行錯誤が必要だ。ところがマイナスの状態では試行錯誤しているような余裕はない。
時間がかかり下手な結果を出せば泥沼にはまる。
なるべく上手に手早い結果を得る必要があるのに、心理は混乱してしまう。
【ないある】心理になっていることに気がついたら【あるない】に注目するといい。
【あるない】は事実「ある」のに、認識できていない(「ない」)もののことだ。たとえば強みや才能は自分では「当たり前の力」だと思っているので見逃していることが多い。自覚できていてもサイズ感がかなり間違っている。
性格や人間性も同じだ。そのような性格でも、どんな人間性でもいいところと悪いところがある。人は悪いところを拡大解釈しがちなので、いいところを見逃していることが多い。
性格悪い、についてはこちらの記事↓もどうぞ
マイナスの状態のとき【あるある】だけに頼っても上手く解決はできない。なぜならそもそもそれはできているからだ。できていて、なお、問題が起こっている。
なら解決の糸口は【あるない】にある。
ないものをあるにするのは難しい。
しかし、すでに事実「ある」ものを「え?あるんだ?」と認めるのはすぐにできる。あとは気がつくことだけだ。
どう気がつくのか?の方法論はいくらでもあるし、思い当たることもあるだろう。その方法でいい。わからなければ身近な人に聞けばいい。
それよりも【あるない】に注目するという視点、考え方が必要だ。
普段から【あるない】に注目しているということは、毎日のように【あるない】→【あるある】の量産体制が作られているということで、【あるある】の分量がどんどん増えることになる。
こうなると問題自体起きにくくなるし、起こったとしてもすでに「ある」もので解決することができるようになる。
心理的にも「新しいことでどうにか・・・」とならなくなる。
【あるない】の習慣が定着し、問題が起こったときに【あるない】対応できるようになったら、次は時間をかけて【ないある】に取り組む。
【あるある】分量の多い自分が【ないある】に取り組むことになる。認識の「ある」の分量が多くなっているので、その知見量から事実の「ある」を作りやすい状態になっている。
こういうことが歯車のように噛み合って動き出すと、物事の扱いが結構楽になる。
オンラインサロン【4ポジクラブ】やってます。
フォローやシェアをしていただけると嬉しいです。 よかったら下記ボタンからサポートもお願いします。 いただいたサポートは大切に松原靖樹の《心の栄養》に使わせていただきます!
