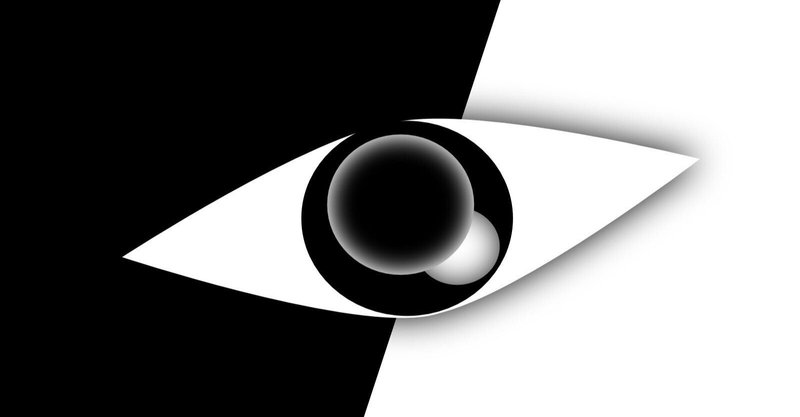
勉強会での「生きてる授業と死んでる授業」
先月,数人の先生たちが集まって、普段の実践について話し合う勉強会がありました。
その勉強会の個人的キーワードが今日のタイトルの「生きてる授業と死んでる授業」です。
1.大体の勉強会の流れ
今回は社会科の授業提案を頼まれたので、持っていった資料を発表したら、メンバーの一人が、(お歳は70のおじいちゃん先生。リタイアされても勉強会に顔を出してくれるレジェンド的存在)
「子供が見えてこない。子どもがこの授業でどう変容したのかが重要。我々は授業を通して子どもを変えることが使命だ。そういう生きた授業をしないと」と。
私が持っていった資料は昨年度校内研究で作成した指導案を今回の発表用にポイントを絞ったものに整理したものでした。
たしかに、当時の子どもの様子をもう少し伝えられる資料を載せればよかったと反省しましたが、それ以上に引っかかったのが、
「生きた授業」という言葉。
その後行った別の先生の指導案検討でも、
「子どもが見えない。指導案の書き方がなってない。」
その先生は、個人の変化に焦点絞り、授業の中で単元の中で、その子がどう変容していったかを注目するべきである、ということを言いたいのよ
と別の先生から教えてもらいました。
2.レジェンド先生の言葉を受けて
いったん整理しましょ。
先生たちが作る指導案。授業案?
授業の日に合わせ、見ていただく先生方に、
「こんな感じで今日の授業、単元についてかんがえてますー。45分ではこう流します。板書はこんな感じですー。」ってものを作りますが、(ざっくりですが)
ある個人を特定して、変容を捉えてそれを事細かに注目するってことをしてこなかった。してたかもしれないけど,レジェンド先生のご指導レベルまでの個人対応を指導案の段階ではしてきていない。
授業って指導要領に該当している内容、単元の目標を考えて子どもたちにどう落とし込むかってことに全力を注いできたけど、、
レジェンド先生の視点も盛り込んで指導案作るって
「無理っしょ!・・・・・いやできる・・・?」
指導案ってその教科の指導案であって、
一人の個人特定して変容を見とっていくって言う学級づくり的要素盛り込んでいくとか、、
どうまとめたらいいのさ、、、、考えすぎなのかもしれん。
3.できれば,その「目」はほしい
そもそもやらなきゃいけない必要性もよくわからん仕事に追われて、複数教科の授業準備も同時並行してこなしていって、、、より効率化が求められて、無駄を削いで、でも教育的効果は落とさずに、毎日子どもの前ではスイッチ入れて、突発的トラブルに対処して保護者対応して、先輩先生の立場尊重しながら、うまく自分の主張会議にねじ込んで、、、(後半はどうでもいいですが、)
個々の子どもの実態を常に把握し、変容を捉え続けることは担任として必要なスキル。それを指導案レベルに持っていくまで、私自身はついていませんでした。そしてそれを今後できるかって言ったらわかりません。必要性も今はわかりません。
でも授業参観者からすると,生きてる授業と死んでる授業は子どもを見るとよくわかります。レジェンド先生は、きっと紙を見ただけで
その授業が、生きてるか死んでるかが見えるんだと思います。
その目が欲しい。 よし。
#教育 #小学校 #授業 #学校教育 #若手教員 #授業づくり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
