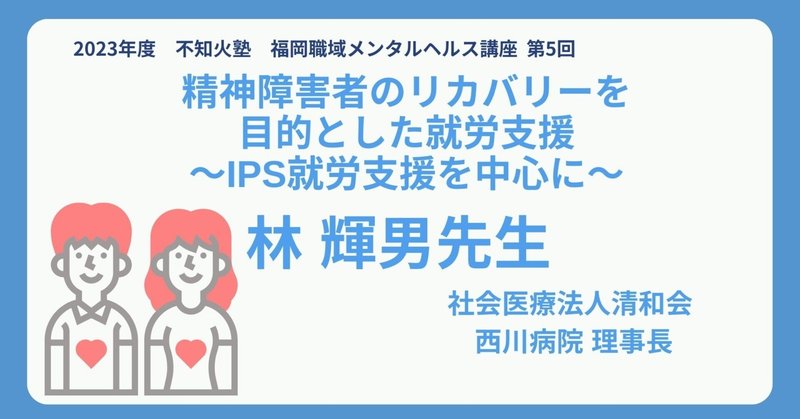
希望を提供することでチャレンジできる-IPS就労支援-
IPS就労支援という言葉をご存じでしょうか。
不知火塾 第5回目は、社会医療法人清和会 西川病院 理事長、林 輝男先生による「精神障害者のリカバリーを目的とした就労支援〜IPS就労支援を中心に〜」がテーマでした。
西川病院では「住む」「生活を営む」「働く」の三本柱を包括的に支援されています。
現行の就労支援とは異なるIPS就労支援について理解を深めてみませんか?
林 先生は、パーソナル・リカバリー、社会的リカバリー、臨床的リカバリーの3種類のなかで、精神科においてはパーソナル・リカバリーの支援が重要だとお話されます。
パーソナル・リカバリーとは、精神科の新しいゴールであり、当事者自身が決めた希望する人生の到達を目指すプロセスとのことです。
不知火塾についての詳細はこちら
次回は8月25日(金)
加藤 敏 先生(自治医大名誉教授)による
「職場メンタル不調者の外来診察・リワークデイケアの実際」です。
次回案内はこちら
精神障害者の就労支援

林 先生は、就労支援はリカバリー支援と強く関連していると述べられます。
統合失調症など重い精神疾患を有する人の60%以上が就労を希望している反面、10%~15%の人が就労できていないことを調査結果をもとにご指摘。
現在、一般的に行われている就労支援は、障害者総合支援法における就労福祉サービスだとお話しされます。
【現行の精神障害者就労支援モデル】
現行の就労支援のほとんどは段階的に就職を目指す、Train-placeモデルに基づいてデザインされているとのこと。
精神疾患に罹患した人は、ストレスに脆弱なため、指導員のもと集団で段階的な就労訓練を積んで、ストレス耐性を高めて就職を目指す方法(集団通所訓練型)と説明されます。
現行の精神障害者就労支援は、就労経験のない人でも安心して始めやすく、制度として確立、普及しているため、どの地域でも利用できるという利点はありますが、以下4つの課題について指摘されました。
本人の本来の希望に関わらず、均一な内容の就労訓練を一定期間、強いられるためモチベーションを保ちにくいことがある。
保護的支援環境が続くことで、当事者、支援者、あるいは家族の一般就労への意欲が下がる。
段階的訓練が一般就労を促進させる科学的な根拠はない。
障害者の就労ニーズ、雇用主の雇用ニーズの急激な高まりに対応できない。
IPS就労支援とは?

IPS(Individual Placement and Support)とは個別職業紹介とサポートのこと。
IPS就労支援はアメリカで始まり、現在世界20カ国で実装・普及、日本では一部の実践者が自主的に行っている段階だそうです。
現行の就労支援が段階的に就職を目指す(Train-placeモデル)のに対し、IPS就労支援は、希望者には誰でもいつでも支援を提供し、まず一般企業に就職して、最低賃金を超える給料をもらいながら、実際の職場で働くことで訓練する(Place-trainモデル)方法だと説明されました。
現行型(Train-placeモデル)は安全性を重視することに対し、IPSは動機付け(モチベーションアップ)を最重要視することを実際の患者との会話を例に説明されます。
モチベーションアップを重視することが長期的に予後が良いという臨床結果を紹介いただきました。
どの研究においても、現行型よりIPS就労支援の方が2倍強の高い一般就労率が示されているそうです。
一般就労率が高まる以外にも、入院期間が短くなる、外来通院期間が短くなるという効果についても示唆されました。
いかに動機付けが大事かを実感したお話でした。
IPS就労支援の実践

林 先生はアメリカの現地視察において、日本でもIPS就労支援ができる可能性を見い出し、精神科デイケアのなかにIPSチームを作られたとのこと。
IPS就労支援の8原則
IPS就労支援の導入~求職活動~就労継続のうえでの8原則について紹介いただきました。
①除外基準なし
②クライアントの好みやストレングスを尊重
③迅速な職探し
④一般就労を重視
⑤計画的な職場開拓と雇用主支援
⑥就労後の継続支援
⑦保障計画
⑧就労支援と精神保健サービスの統合
就職活動中、就職後、離職後のそれぞれの支援がありますが、特にIPS就労支援で重要視しているのは離職後の支援とのこと。
離職を失敗と捉えず、合わなかったことや良かったこと、次回の就職活動に活かすことを本人と振り返り、本人の自己理解を深める手助けをしていらっしゃいます。
IPS就労支援専門員は勤務時間の70%以上を地域で費やし、就職から定着支援、雇用主支援まで同じ支援者が行っているそうです。
IPS就労支援専門員は、就労の前だけでなく、就労後や離職後にも継続的にサポートを提供しており、企業にとっても安心感をもたらすモデルであると感じました。
具体例の紹介もあり、一人ひとりの個性に合わせた個別支援についての理解を深めることができました。
職場開拓とIPS就労支援における医師の役割
個人の特性に合った職場を見つけるために、職場開拓にもご尽力されています。
精神障害者を雇用することに対して、約半数の企業が前向きな回答だったとお話しされます。
また、IPS就労支援専門員1人の支援する人数が20人を超えると一般就労率が低下するというデータに基づき、20人を超えないように配慮されているとのこと。
現在に至るまで、約60%の方が一般企業に就職できているそうです。
IPS就労支援における精神科医の役割について、スタッフ援助、職場でのパフォーマンスと精神症状の関連性の評価、精神療法、薬剤調整の4つを挙げられ、実例を交えながら説明いただきました。
まとめーIPS導入の意義ー
精神疾患を経験した人の一般企業での就労を高い確率で実現できる(現行型支援の約2.5倍)。
街にすでに存在する企業一つ一つが社会復帰の場となるので、創造的な限界のない支援を展開できる。
職場の上司、同僚など、市民の障害理解が深まる(スティグマの解消に貢献する)。
当事者だけでなく、支援者にも「だれでも働ける」という意識が生まれる。
就労支援の課題と展望

就労を希望する人の約40%が目標を実現できておらず、現行型の就労支援や就労支援機関との連携方法の確立し、本人に合った支援を選択できるようにすることが、今後必要になってくるとおっしゃいます。
IPS就労支援の認知を広げ、学習機会を提供する場を増やす活動や、医療機関・福祉機関で広くIPS型の伴走型個別就労支援が実施できる体制の整備についても言及されました。
また、西川病院ではIPS就労支援で就職された当事者の講演会を全スタッフを対象に実施されています。
講座では、当事者講演会の様子を一部、動画で拝見しました。
当事者の声を動画で聞くことができ、あらためて「働く」ことは社会で認められることであり、当事者自身の希望する人生の到達に向けた確実な歩みであると感じました。
最後に、精神疾患を経験した人を支援することについて以下のように林先生は語られました。
例えば、身体障害を持つ人が働きたいときに支援者は車椅子を提供する、
精神疾患を経験した人に車椅子に匹敵するものは、希望であり、希望を提供することで、彼らがチャレンジできて前進できる。
最後の林先生の「希望」を提供するという言葉がとても印象に残り、自分自身も希望を提供できるような看護師でありたいと思いました。
貴重なお話をありがとうございました。
不知火塾についての詳細はこちら
次回は8月25日(金)
加藤 敏 先生(自治医大名誉教授)による
「職場メンタル不調者の外来診察・リワークデイケアの実際」です。
次回案内はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
