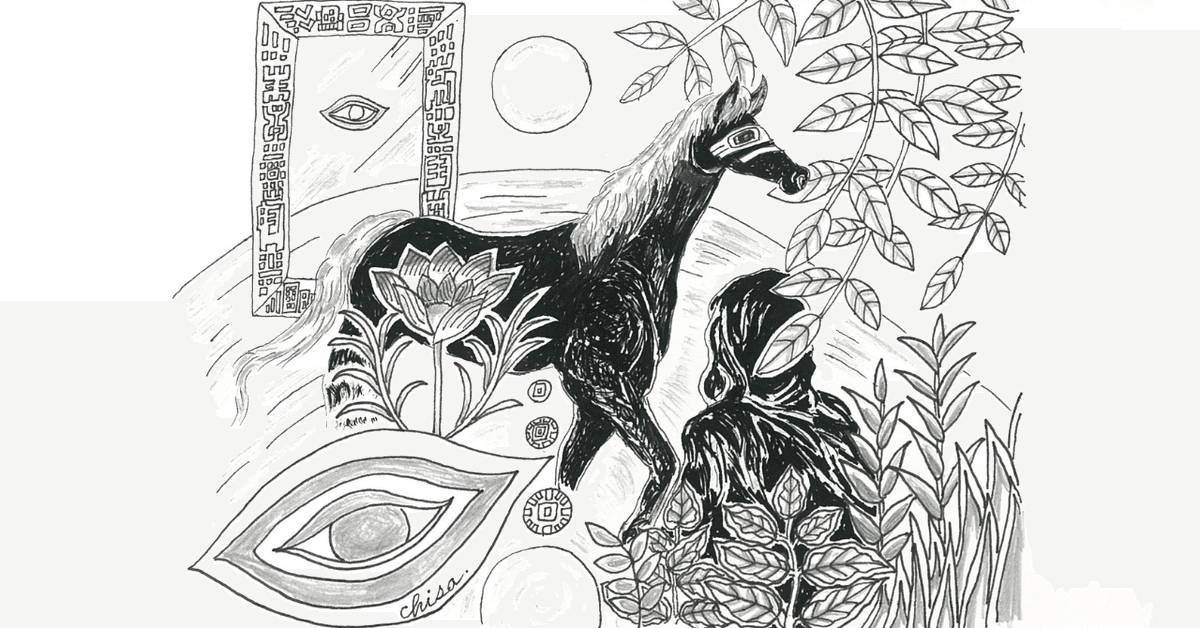
短篇小説【やがて滅びる国の民へ】中編
10
ヨギがその男に差し出せるものは白い封筒の手紙以外に無かった。
護身用の短刀も旅籠に置いてきていた。
夜明けの森の中で、今ヨギは「赤目」と向かい合っている。
その男は見た所20代後半位で長い髪を後で束ねていた。
目の周りは赤く隈取られ、鼻から下は白い布で覆われていた。
背は然程高く無かったが、がっしりとした体躯は一見して鍛え上げられた人間である事が分かる。
何故ここにいるのか、その理由を明かすのが一番安全であろうとヨギは考えた。
「この手紙は私の弟のテオが書いたのだと思う。私はそのテオに会いに来た」
黙って手紙に視線を落としている「赤目」の男にヨギが言った。
男の白い羽織の内側に革のホルスターが下げられているのが目に入った。
膝位までの長さの黒い銃身は、散弾銃の様なものなのだろうとヨギは思った。
男は手紙をヨギに返した。
「お前をこれから我々の集落に連れて行く。後に付いて来い」
男は丸池の畔から葦の茂る草むらに分け入って行った。
躊躇なく足早に進む男に付いていくのは大変だった。
ヨギは何度も下生えに足を取られ転びそうになり、鬱蒼と茂る灌木に男の背中を見失いそうにもなった。
それでも必死に道なき道を進む内に、辺りは完全に陽が昇って明るくなってきていた。
どこまで行っても同じ様な景色が続き、森は尽きる事が無かった。
リッケがこの森を国が丸々1つ入る程の大きさだと言っていたのをヨギは思い出した。
ヨギは先を行く男がさっきから何を目印に進んでいるのか不思議に思っていた。
彼等はこの森で迷ったりしないのだろうか?
それとも彼等にしか分からない道標があるのだろうか?
注意深く辺りを見廻しても、ヨギには森の変化が何も掴めなかった。
ポポイは危険は無いと言っていたが、ヨギにはやはり男が腰に下げている銃の存在が気になっていた。
反体制の危険な集団であり、目的も分からず、近隣の村を襲うという噂まで立っている。
そんな得体の知れない人間達の所へたった1人丸腰で行く事になった状況に、ヨギは改めて背筋の凍る思いでいたのだった。「赤目」達の判断一つで自分の運命は如何様にもなってしまう。
覚悟を持ってここまで来たつもりでいたが、ヨギは恐怖と不安で圧し潰されそうになりながらも、辛うじて歩みを進めていた。
やがて明らかに人の手が入った痕跡が木々のその間に感じられる様になってきた。先を行く男の歩みも心なしか緩やかになった。
ふと足元に視線を落とすと、草の間に石が埋め込まれ道の様になっているのにヨギは気が付いた。
木々が途切れ、太陽の光が大きな空間に勢いよく注ぎ込まれている。
どうやら「赤目」の集落に着いたようだった。
前方に漆喰の壁の家並みが見える。
広場の様な所には何人かの人々が輪になって何かの手仕事をしていた。
ヨギが傍を通り過ぎても誰も気にする素振りを見せない。
案内の男は尚も黙って歩き続け、振り返る事無くヨギを集落の奥へと誘う。辺りの家々からは炊事の煙が上り、子供達の笑い声や家畜の鳴き声が賑やかに聞こえてきた。それは森の外の光景と少しも変わらなかった。
そこには普通の暮らしがあり、自分達の世界と変わらぬ匂いがするのにヨギは少し安心した。
彼等は何の警戒も示していないし、少なくとも自分は招かざる客では無いのだとヨギは感じていたのだった。
石畳の道の傍らには小さな川が流れていて、それに沿ってしばらく歩くと集落の突き当りに大きな石柱を廻らせた館が建っていた。
その周りを一際大きな木々が取り囲んでいて、枝葉が石造りの館の半分を覆っている。
案内の男はその館の大きな門の傍で立ち止まっていた。
「ここだ。この中にお前を呼んだ者がいる。私はここから先には入れない。階段を上がって一番奥の突き当りの部屋に行け」
男はそれだけ言うとまた振り返らずに来た道を戻っていった。
周りは人の気配も無く、集落の賑わいもここまでは聞こえてこなかった。
館の扉は施錠もされておらず、押し開いてみると直ぐに広い吹き抜けの空間になっていた。
正面に鉄製の手摺りを備えた大階段が見える。
館の中も静まり返っていて人の気配が無かった。
天井の明り取りのガラス窓からはたっぷりと日差しが注ぎ込んできている。
ヨギがゆっくりと階段に近付くと、その足音が吹き抜けの空間に大きく響き渡った。
ヨギはまるで夢を見ている様な気がしていた。
階段を上りきると、片側に幾つかの扉が並んだ回廊になっていた。
反対側には大きな窓が並んでいて、ここからも眩しい程に陽が差し込んできていて辺りを白くぼんやりとさせていた。
歩き続けると突き当りに大きな扉があった。
様々な花や動物の彫刻が施された、見た事も無い様な美しい扉だった。
ヨギがその扉をゆっくりと押し開くと、部屋の中央に大きな鏡を背にして男が立っていた。
ヨギにはそれがテオであると直ぐに分かった。
黒いローブで全身を包み、目元には赤い隈取があったが、
ヨギを真っ直ぐ見詰めているその目を忘れるはずはなかった。
それは20年前に国境行きの列車に乗って去っていった時のテオと全く変わっていない。
15歳の少年のままの姿だった。
「よく来てくれたね。ヨギ。僕が分かるかい?」
その声もまるで少年の様だとヨギは思った。
「テオ・・・お前なんだな・・・・一体何から聞くべきか・・・・・」
ヨギは目の前の少年がテオである事に疑いを持たなかったが、
それが意味する所を理解する事は到底出来なかった。
「ヨギ、僕も何から話していいのか分からないよ。余りに話す事が多すぎて。ねぇ、覚えてるかい?ヨギが沼の底に沈めたあの3枚の絵の事?」
テオはゆっくりと黒いローブの頭の覆いを取った。あの頃と変わらない母親譲りの明るい赤毛に窓からの陽の光が当たる。
王都から遠く離れ、月夜に紛れて深い森に入り、丸池の畔で夜明けを迎え、「赤目」の青年に連れられこの館に辿り着いた。
この途方も無い道筋の不安と緊張で、ヨギは急激にこれまでに無い様な疲れを感じていた。
「テオ、お前は20年前にあの戦争に行ったはずだ。俺はとうの昔にお前は死んでしまったと思っていた。それがどうして今あの頃の姿のお前が俺の目の前に立っているんだ?」
信じられない光景を前にして、ヨギは混乱の極みにあった。
「ヨギ、本当に話す事が多すぎるんだ。とても話しきれない位に。多分全てを理解する事は出来ないだろうし、僕も全てを知っている訳じゃない。でもね、この森にはとても不思議な力が働いていて、時間も外の世界とは違う様に流れているんだ」
そう言うテオの表情が、本当に純真無垢そのものの様だとヨギには感じられた。
好奇心の塊の様だった少年時代のテオが信じられない事に今、目の前に立っている。
ヨギは部屋の中央の大きな鏡に映された、20年もの月日の労苦を経てくたびれた自分の顔を見て、世界の土台が音を立てて崩れていく様な奇妙な感覚を覚えていた。
11
テオの話はまるで長い夢の様だった。潰える事の無い、果てしない夢。
ヨギにはテオがこの20年の間、本当にずっと眠っていたのかも知れないと思った。
テオのその眠りに付く前の最後の記憶は列車が砂漠を越え国境の町に着いた夜だった。
3か月にも渡る新兵の訓練生活を終え、いよいよ明日は本物の戦場に向かうという夜。
摂氏40度の茹だる様な暑さの日中から、夜は一気に凍える様な寒さに耐える事になる。
過酷な環境と戦争への興奮から新兵の多くは眠れない夜を過ごしていた。
その時、町の外れの軍の宿営地に、強烈な閃光が2度瞬き、
その後直ぐに耳をつんざく様な轟音が響き渡った。
立ち昇る粉塵と黒い煙。
警報と人々の怒号が飛び交い、辺りは騒然とした雰囲気に包まれた。
テオの所属する部隊も直ぐに小銃を抱え表に飛び出した。
「敵襲だ!」
外では訓練期間中に最も上官の信頼を得ていたバリッチという少年が砂漠に向かって銃撃していた。
渇いたパンパンパンという音が闇に空しく響く。
「バリッチ!敵はどこだ!?」
テオが手にしてる小銃の安全装置を解除しながら叫んだ。
「分からない!敵は見てないけど、多分砂漠の方から来ているみたいだ!」
バリッチは崩れた壁を背にして頻りに辺りを見廻している。
兵隊と言っても皆つい半年前まではただの学生だった少年兵だ。
テオは目の前の情景が現実であるという事を、
上手く捉える事が出来なかった。
その時また閃光が瞬いた。テオがその時最後に目にしたのは、
宿舎の建物が吹き飛ぶ様子と、
すぐ傍にいたバリッチの体が爆風で引き千切られた光景だった。
そしてテオは長い夢の世界に落ちていく。
それは脈絡のない物語だった。
遠い記憶とまだ見ぬ未来がないまぜになった風景。
体の感覚があやふやで、深く落ちていっている様でいて、
ふわりとどこまでも昇っていく様でもあった。
眩しい光の明滅。轟音と静寂の繰り返し。
自分が生きているのか、死んでしまったのかも分からなかった。
とても長い時間が過ぎた様でもあり、たった今目を閉じた風にも感じられた。
そうして意識と無意識の狭間でどこまでもたゆたい、
朦朧としていく中でテオはいくつかの出来事に遭遇する。
その長い夢からテオが醒めた時、
それらはとても重要な意味を持っている様に感じた。
そこは白い壁と白い天井の部屋だった。
寝台に横たわるテオの傍に男が立っていた。
男はキラキラと眩しく光を反射する不思議な服を着ていた。
長い顎髭を生やし、頭髪は完全に剃り上げられている。
君はいくつもの未来を選ぶ事が出来る。
それは同時に存在するいくつもの世界だ
髭の男は口を開かずに話し掛けてきていた。
テオにはそれがごく当たり前の事の様に感じられた。
それから次々とテオの寝ている寝台の傍らに人々がやってきた。
皆口を開かずにテオに話し掛けて来た。
彼等の話は聞いた事の無い様なものばかりだった。
空に浮かぶ町の話。月にある海の話。遠い星に一瞬で行けるトンネルの話。眠ったまま何百年も生きていられる人間の話。
どんな病気も体を取り替えて治してしまう話。
大きな爆弾で人が住めなくなった星の話。
彼等はテオに何もかも教えてくれた。
それらの話は嘘の物語の様であり、
本当に起きた出来事の様でもあった。
何の為に教えてくれるのかはテオには分からなかった。
ただその話の全てが実に興味深く、酷く身につまされるものだった。
そしてどれ位の時間が経ったのか見当も付かなかったが、
その眠りから唐突に醒めるとテオは「神授の森」の「赤目」の集落にいたのだった。
「ヨギ、僕がその夢から覚めた時、外の世界では20年の年月が過ぎていたんだ。それから僕は彼等に教えて貰った話を1つ1つ思い出していったんだ。全部凄く大事な物だったからね。ヨギ、あの3枚の絵はね、彼等の故郷の景色なんだよ。彼等の住んでいた所はもう無いんだけどね。でも彼等の意識はずっとそこに残っているんだ」
テオは鏡を指差して「そこ」と言った。
ヨギにはテオの話の殆どが分からなかった。
それでも目の前に15歳のままのテオが立っている限り、
全ては本当の事なのかも知れないと思えてくる。
寧ろそう考えるしか今のヨギには選択肢が無かった。
「僕はとても長い旅をして、そこから帰ってきた。最後に僕に話を聞かせてくれたのは【最初の人】と呼ばれていた赤目の男だった。僕らの世界の戦争を終わらせて人々を解放すると言っていた。やがて滅びるこの国から、皆を連れ出す為に仲間を集めているとも言っていた。僕はこの新しい世界で彼の為に赤目として生きる事にしたんだ」
テオはまた頭に黒い覆いを被り、ゆっくりと部屋から出て行った。
「テオ、お前なんで俺をここへ呼んだんだ?何か用事があったんじゃないのか?」
ヨギが呼び掛けると、テオは回廊の窓の前で背を向けたまま立ち止まった。
「ヨギ、僕はこの世界を作り変える。あらゆる可能性の中から正しいものを選択するんだ。そうであったかも知れない過去と、そうはならなかった現在から本当の物語を救い出すんだ。ヨギにはそれを見ていて欲しい。知っていて欲しい。そして正しい未来で愛する人達と生きていって欲しい」
テオは窓の外の深い森をじっと眺めていた。
「テオ、お前は一体何をしようとしているんだ?」
ヨギがテオの肩を後から掴もうとすると、回廊の床が音を立てて湾曲した。
建物全体が波打っている様に揺れ動いている。
窓の外からは目を開けていられない程の眩しい光が入ってきていた。
床に倒れたヨギはそれでも必死に腕を伸ばしてテオの黒いローブの裾を掴もうとした。
「ヨギ、会えて良かった。トキさんと双子ちゃんに宜しく伝えてね」
テオは振り返らずに両腕を水平に押し広げながら言った。
その時ヨギの頭に王都の役人住居の景色が唐突に浮かびあがってきた。
見慣れた部屋の見慣れた食卓にはトキの姿と、
見知らぬ双子の女の子が見えた。
色とりどりのご馳走が並んだ食卓。病の影さえ見られないトキの笑顔。
窓から入ってきた緩やかな風が、僅かに揺らした白いカーテンの裾にヨギは触れられる様な気さえしていた。
次の瞬間、ヨギは腕を伸ばしたままどこまでも落ちて行った。
遠く離れていくテオの黒いローブの裾を睨みながら。
とてつもなく長い長い下降だった。
それはまるで世界の反対側まで突き抜けてしまいそうな程に。
どれくらいの時間が経ったのか分からなかった。
ヨギが目覚めるとそこはオシムで唯一の旅籠の狭い寝台の上だった。
12
まだ天井がゆっくりと遠のいていっている様に感じた。
体には強く浮遊感が残っている。
全身に汗を掻いていて寝台のシーツは濡れていた。
部屋は薄暗く窓には雨戸が降りている。
「ヨギ、起きたのか?」
部屋の隅から聞き覚えのある声がした。
「ポポイか?俺は・・・どうしてここに・・・」
ヨギは起き上がろうとしたが、激しい頭痛と体の強張りで満足に動けなかった。
「まだ休んでいろ。お前は2日ここで眠っていたんだ。森の丸池でお前は倒れていた。鳥達が一斉に北の国境の方角に飛び立っていったのが見えたので、迎えに行った」
ヨギは途切れ途切れの記憶を必死に呼び覚まそうとした。
しかしどこまでが現実で、どこからが夢だったのか判別が付かなかった。
ヨギはゆっくりと体を起こして寝台の縁に腰掛けた。
段々と部屋の暗さにも慣れてきて、扉の横で片膝を付いて座っているポポイが目に入った。
その時ヨギは言い様の無い違和感に強く捉われた。
何かがおかしいと思った。
上手く言葉に出来なかったが、周りの様子が大きく変わっている様に感じた。
「ヨギ、本当に大丈夫か?」
一点を見詰めたまま身動きをしないヨギにポポイが声を掛けた。
「ポポイ、君は目が見えなかったはずだ。黒い布を目に巻いて・・・・顔には入れ墨があって・・・・」
ヨギが呟く様に言った。
「この部屋も・・・様子が違う・・・僅かなズレだけど・・・・鞄、そこに掛けておいた鞄も無い・・・・ポポイ、君は本当にあのポポイなのか?」
ヨギは興奮して立ち上がったが、体に上手く力が入らずに床に膝を付いて倒れ込んでしまった。
「ヨギ、記憶と違っているのか?もしかして森に入る前に会った私は目が見えていなかったのか?」
ポポイが茫然として言った。
「世界がもう既に変わっているんだ。テオが・・・・作り変えたのか?」
ヨギは必死に記憶を掘り起こそうとしたが、頭に割れる様な痛みを感じてうずくまった。
「ヨギ!無理に思い出そうとするな!記憶が混濁して危険な状態にあるんだ!あの森から帰った者の中に同じ様な奴を見た事がある。今はとにかく休め」
ポポイがヨギを抱き起こして寝台に横たわらせた。
ヨギは呼吸も粗く、その頭の痛みに体を激しく痙攣させていた。
ポポイがヨギの両肩を持って懸命に寝台に抑えつける。
暫くの間ヨギは苦悶の表情で喘いでいたが、
やがて力尽きてまた眠りに落ちた様だった。
静まり返った部屋の中にはヨギの微かな寝息が聞こえてくるだけだった。
ポポイはそっと窓の雨戸を開け、外の様子を確認した。
夕暮れの村の様子に特に変わった所は無かった。
寝台のヨギも落ち着いている様子だった。
「ヨギに何かあったのか、それとも世界に何か起こったのか」
ポポイは音を立てずに部屋を後にし、
村外れに待たせていた黒馬に跨り森に向かった。
13
王都はその日、先王の命日を喪に服す為に静まり返っていた。
列車は全て運休。商店も全て休業。学校や勤め先も休暇になっていた。
人々の外出も制限され通りには人影が全く無かった。
市内巡回の任務に就いていたリッケは暇を持て余し欠伸ばかりしていた。
「おい、俺達何の為にこんな事してんだろうな」
腰に警棒をぶら下げた制服姿のリッケが、
近くに立っている仲間の警官に話し掛けた。
「この日を狙って赤目の奴等が何かしでかすかも知れないだろ。真面目に職務に当たれよ」
異様に大柄なその警官が周りの様子に注視しながらリッケに言った。
「でも、街中誰もいないんだぜ。こんな日に働いてるのは俺達ぐらいさ。パブすらやってねぇんだから、サボる事も出来やしねぇじゃねぇか」
リッケは鉄柵を警棒で叩きながら詰まらなそうにまた欠伸をした。
「おい、リッケ、お前本当に真面目に・・・」
その時リッケには遠くの建物の陰を過る人影が一瞬見えた様な気がした。
「おい、今あそこに誰かいなかったか?」
更に何人かの人影が町の広場の方に素早く消えていった。
ハッキリとは見えなかったが、黒いローブの様な物を着ていた様に見えた。
「おい、お前屯所に行って応援呼んで来い!俺は様子を見てくる!」
リッケがそう言って広場の方へ駆けだそうとしたその時、
目も眩む様な閃光が瞬き、耳を破る様な轟音が鳴り響いた。
激しい噴煙が通りを駆け、リッケも路上に吹き飛ばされた。
続けざまに爆発音が続く。余りの衝撃の強さに周りの建物のガラス戸が割れて吹き飛ぶ。
遠くの方から小銃の渇いた発砲音が聞こえてきた。
リッケは直ぐに立ち上がり広場へと走った。
「どうなってんだ!ここは王都のド真ん中だぞ!」
頭を低く保ちながら素早く建物の陰を移動するリッケの目に信じられない光景が飛び込んできた。ついこの前ヨギとここで眺めた王宮が巨大な瓦礫と化していた。黒い煙と濃赤の炎が立ち昇っている。
茫然と立ち尽くすリッケの目の前を馭者を失った馬車が暴走して通り過ぎていく。
「赤目の奴等か?戦争でも始めんのか!?」
広場の奥でまた小銃の発砲音がした。
リッケは人影の無い路地を抜け、旧市街の方向へ走った。
どこの通りも広場の騒ぎを聞き付けた群衆が右往左往していた。
途中で何人もの同僚とすれ違ったが、リッケは構わずに走り続けた。
そして長い坂道の麓に建つ役人住居に辿り着いた。
勢いよく3階まで階段を駆け上がると、ヨギの部屋の扉を勢いよく叩いた。
「トキ!俺だ!リッケだ!皆無事か!」
狭い廊下にリッケの叫び声が響き渡った。
ヨギが森に出掛けて行った時、留守は任せろと言ったのはこの俺だ。
リッケは嫌な予感で胸が圧し潰されそうだった。
やがて扉がゆっくりと開かれ、玄関口に小さな女の子が眠そうな目を擦りながら現れた。
「リリ!ママは?中にいるのか?」
リッケが室内を見廻す。そこに人の気配は無かった。
「ママはミミと一緒に行ったの」
女の子が手に持っている人形に話し掛ける様に小さな声で言った。
「どこに行ったか分るか?何か言って無かったかい?」
リッケが女の子の前に屈んで優しく言った。
「分んないの。赤い目のおじさんに連れられて行ったの。リリはベットの下にいたの」
女の子は人形をじっと見詰めたまま顔を上げなかった。
「何てこった・・・・」
西日が差し込む部屋の窓からは広場の黒煙が遠くに見えた。
リッケは小さな女の子を優しく抱き上げ、狭い廊下をゆっくりと戻って行った。
14
神授の森の東の窪地には、古くからこの地で暮らすロー族の集落があった。幾つかの先住民族の集落が森の中には点在していたが、
彼等ロー族は森の外とも交渉のある、比較的友好的な民であった。
王宮政府の干渉からは距離を置き、その暮らしは質素で旧時代のものであったが、ロー族には族長を中心とした強固な団結力があった。
族長の孫であるポポイは集落の若者の中でも特に秀でた人物で、
森の地理に詳しく外の世界にも明るい先進的な考えを持っていた。
ポポイと王都の警察部隊に所属するリッケは数年前から協力関係にあり、
森の部族が新たな時代に生き残っていく為に、
外界との通商を更に拡大する必要があると彼は感じていたのだった。
そのリッケの頼みで「赤目」に会いに来たヨギの森の案内を買って出たのだったが、先刻森から戻ったヨギの様子に只ならぬものを感じ、ロー族の精神的支柱である部族の占い師の所にやって来たのだった。
集落の外れの小さな沢の畔にひっそりとある、
クヌギの老木を組んだ丸太小屋がその占い師の住処であった。
如何にも賢そうな相をした黒馬に跨り、
ポポイはその馬上から動物の骨の様な短い棒を2度打ち鳴らした。
澄んだ金属音の様な音色が、沢の辺り一面に響き渡った。
ポポイが馬上で様子を伺っていると、丸太小屋の扉がゆっくりと開き中から杖を付いた老人が現れた。
「ポポイか・・・何かわしに用か?」
黒い布で目元を覆った老人はどうやら目が見えない様だった。
「アスイ導師、森の外の様子がおかしいのです。強い変調の兆しを感じます。導師が何かご存知無いかと思って来ました」
ポポイが黒馬の手綱を近くの木に結わい、ゆっくりと小屋に近付きながら言った。
「風に少し火薬が混じっておるな。鳥も騒いでおる。どれ、ちょっと玉を見てみるで、中に入れ」
アスイ導師はそう言うと部屋の中にポポイを招き入れた。
薄暗い室内には香が焚かれ、煙が充満していた。
天井や壁には乾燥した木々の枝葉が吊るされ、
至る所に鉢植えの植物が置かれていた。
生まれながらに目の見えないアスイ導師は、
ロー族に古くから伝わる「玉相見」の術を目では無く手で感じて占う。「玉」は他の者が見ても何も読み取れなかったが、
導師は手で触れるだけで色んな物が見えてしまうのだった。
「ポポイ、外はどんなじゃ?何か変わった事は起こっとらんか」
導師は床に敷かれた座布団に腰を下ろすと、卓に置かれた玉の覆いを取って両手をかざした。ポポイは何度かその玉を見た事があったが、
その度に玉の帯びている色合いが変わっていた。
今日は今までに見た事が無い深い緑に光っていて、
その玉の内部には煙が絶えず蠢いている様に見えた。
「導師、実は「赤目」の集落に行きたいという人間を4日程前に丸池まで案内しました。その者が帰ってきたのですが、妙な事を言っているのが気になるのです。記憶が混濁している様子だったのですが、世界が作り変えられたと言っていました。その者は以前の私は目が見えず、顔に墨を入れていたと言うのです。それで何か導師の玉に兆しが出てはいないかと思ったのです」
ポポイが導師の背後から不思議な光を放つ玉を覗き込みながら言った。
導師は微動だにせず、玉を両手で覆い、まるでその掌で玉の内部の煙を吸い込んでいる様にポポイには見えた。
静まり返った小屋の中に空気のうねりが生じた様に感じる。
充満していた香の煙も部屋の中をゆっくりと旋回しだした。
「ポポイよ。世界は常に変化しておる。それは目で見える変化だけじゃない。人の思いが色んな物事の成り立ちを曲げてしまう事もある。古くはたった1つの塊だったものが、数え切れない程の世界に分かれていったんじゃ。いくつも同時に存在する世界が、捻じ曲げられてくっついてしまう事もある。この兆しは大きな変化を生むかも知らん。誰も気が付かん内に、戻れん様になってしまうかも知らん」
導師が顔の黒い布を外し、玉を両手で掲げ額に当てた。
深い緑色に光っていた玉の内部が、次第に赤い煙で満たされていく。
その時、閉め切っているはずの小屋の中に凄まじいまでの突風が吹き、
乾燥した木々の葉が部屋中を舞い狂った。
「うぐっ!」
低く呻いて導師が前かがみに倒れた。
「導師!」
ポポイが素早く導師の体を支えると、
その両の手の中の玉に大きな亀裂が走っているのが見えた。
「ポポイ・・・・どうやらとてつもなく大きな力が世界を変えようとしているようじゃ。この急激な変化は世界を救うのかも知らん。あるいは滅ぼしてしまうかも知らん。お前はその集落から戻った者に供するのじゃ。王都で何かが起こっている。気を付けていきなさい」
導師は玉をゆっくりと卓に戻し、再び目を黒い布で覆った。
「導師、大丈夫ですか?」
「わしは大丈夫じゃ。ポポイよ、ロー族の長の血には昔から闇でも目が利く能力が備わっておる。この世界が闇に閉ざされても、お前の目で道を切り開くんじゃ。さあ、行け。お前を待っている者がおる」
アスイ導師は杖で立ち上がり、ポポイを小屋の外まで見送りに出た。
「ポポイ、これを持っていきなさい」
導師がポポイの手の平に小さな石の人形をそっと置いた。
「これは?」
その石には人の手によってか角が丸くなり、
ぴったりと手に馴染む感触があった。
「ロー族に古くから伝わるお守りじゃ。その石の感触をよく手に覚えさせておくんじゃ。それがこの世界である証になる」
ポポイはその石の人形をしっかりと握った。
「ありがとうございます。導師、どうかお体にお気をつけて」
ポポイは後ろ髪を引かれる思いで小屋を後にし、黒馬を走らせた。
15
ヨギが再び狭い寝台の上で目を覚ますと、
今度は部屋の簡素な食台にリッケと見知らぬ女の子が座っていた。
「パパ!」
女の子が大声で叫びながらヨギに飛びついてきた。
「ヨギ!気が付いたか!お前、いつ森から帰ったんだ?」
リッケが寝台の縁に腰を下ろして言った。
「リッケ、お前こそどうしてここに?」
ヨギがゆっくりと体を起こした。まだ頭に痛みが残っていたが、
随分と楽にはなっていた。
「ヨギ、落ち着いて聞いてくれ。俺にもまだ詳しくは分からないんだが、どうやら王都で反乱が起きたみたいなんだ。街中で激しい爆発があって、王宮も瓦礫になっていた。多分赤目の連中の仕業だと思うんだが何の情報も得られない。王都は今も戦闘状態だ」
ヨギはリッケの話を聞きながらも、目の前で自分に抱きついて泣きじゃくっている女の子を不思議そうに見ていた。
「リッケ、ちょっと待ってくれ。この子は?この子は一体どこの子だ?」
リッケが茫然とした目でヨギを見た。
「お前、何言ってんだ?冗談なんか言ってる場合じゃないんだぞ!爆発があって直ぐに俺はお前の家に走ったんだ。家にはリリしか居なくて、トキとミミは赤目に連れて行かれたって言ってるんだよ!リリは機転を利かして寝台の下に隠れていたらしいんだ」
ヨギはそれでも不思議そうに女の子を見ていた。
「リッケ・・・・俺は・・・どうかしちまったのかも知れない・・・覚えていないんだ・・・この子の事を。本当に俺の子供なのか?トキと俺の間には子供はいなかったはず・・・」
ヨギが両手で顔を覆った。その手は小さく震えていた。
その様子に只ならないものを感じたリッケは暫くヨギが落ち着くのを待った。
まだオシムの村には王都の混乱は届いていなかった。
リッケはリリを役人住居から抱え出し、通りで馭者を失っていた馬車を捕まえて王都を脱出した。市の至る所から煙が上がっていて、
赤目らしき黒いローブを着た一団と同僚の警察隊が銃撃戦をしていた。
昨日までの平和な光景が遠い過去の様だった。
まるで国境の果ての戦場の様だとリッケは思った。
とにかくリリを安全な場所に連れ出さなければと思いオシムの村に向かって馬車を走らせ、偶然にも旅籠でヨギを見付けたのだった。
「リッケ・・・信じられない話だと思うんだが聞いてくれるか?」
暫くして少し落ち着いた様子のヨギが寝台から窓辺に立っていたリッケに声を掛けた。
「ああ、勿論。話を聞かせてくれ。一体お前に何があったのか知りたいんだ」
リッケは食台の質素な木の椅子を寝台の傍に引き寄せて腰を下ろした。
ヨギはこの旅籠からポポイに連れられ闇夜に紛れ森に向かった時から、
事細かく順番に起きた事を話していった。
自分でも信じられない様な話だったが、
それが現実の事であるという実感がヨギには確かにあった。
テオが言っていた世界を変えるという言葉の意味する所。
既に自分の記憶とは違う世界になってしまっているという事。
混乱と恐怖に崩れ落ちそうな気持ちを奮い立たせてヨギはリッケに話し続けた。
小さなリリは父親に会えた安心感と疲れで眠ってしまっていた。
長い話が終わると暫くヨギもリッケもそれぞれの思索に耽って口を開かなかった。
小さな窓からは暮れかけた陽の光が弱々しく差し込んできていた。
その時、旅籠の外で僅かに馬の蹄の音がするのを2人同時に気が付いた。
リッケが素早く入口の傍に屈みこんで扉に耳を当てて外の様子を伺う。
ヨギは窓を日除けで覆い、リリを寝台に残して立ち上がった。
「ヨギ、いざという時はリリと窓から逃げろ。さっきも言ったがトキとリリの双子の姉のミミが赤目に連れて行かれたんだ。おそらく森の中だと思うんだが。森にはポポイもいる。奴ならきっと助けてくれると思うんだ」
リッケが腰から警棒を出して小声で言った。
部屋の扉のすぐ向こうに誰かが立っている気配がした。
リッケがヨギに黙って目で合図を送ったその時、外から聞き覚えのある声がした。
「そこにいるのはリッケか?ヨギもいるのか?俺だ。ポポイだ」
「ポポイ!」
リッケが扉を開けると黒い布を目元に巻いたポポイが立っていた。
「リッケ、どうしてここにいるんだ?」
ポポイは素早く部屋に入り扉を閉めた。
「王都で戦争が始まったんだ。王宮は粉々に吹き飛ばされて、街中で煙が立っている。多分赤目の連中の仕業だと思う。ハッキリとした情報は無いが、ヨギの嫁さんと娘さんが連れて行かれたみたいなんだ」
リッケがポポイに簡潔に説明した。
「そうか。導師の言っていた通りだな。ヨギ、その子は?」
ポポイが寝台で丸くなって眠っているリリを見て言った。
「これは・・・俺の娘・・・らしい」
ヨギが弱々しい声で答えた。
「そうか。お前の言っていた通り、世界が変わっていっている様だ。ヨギの記憶の中の世界とこの世界はいくつかの違いがある様だ。そしてそれは今後増えていくのかも知れない。今は何が起きているのか誰にも分からないが、とにかく安全な場所に移らなければならない。もう一度森に行こう。一先ずロー族の集落に身を隠すんだ」
ポポイはそう言って扉を開けようとしたが、
その動きを突然止めてしゃがみ込んだ。
リッケがゆっくりと窓から外の様子を伺った。
旅籠の裏庭の木に結わえた馬車の所に3人の男の姿が見えた。
3人とも白い羽織りを着ていて頻りに辺りを見廻していた。
「赤目か?」
ポポイが小声でリッケに言った。
「3人、いや、4人いる。王都の赤目達とは少し様子が違う様だが、赤い隈取が見える」
リッケが答えた。
ポポイが懐から短刀を抜いた。
ヨギの目にその刃先が鈍く光を反射させたのが見えた。
ヨギもリッケの隣から窓の外の様子を見た。
4人の男の中で一際がっしりとした男に見覚えがあった。
「あれは俺を赤目の集落に案内した男だ。間違いない」
赤目達は一向に旅籠に入ってこようとはしなかった。
「あの男に連れていかれた赤目の集落は平和そのものだった。ほんの数日後に王都を襲撃する様な雰囲気じゃ無かった。何かおかしい気がする・・・」
ヨギが何か意を決したように部屋の扉に近付いた。
「ポポイ、赤目達は本当に反乱を起こす様な連中なのか?俺にはとてもそんな風に見えなかったんだ。何か引っ掛かるんだ。俺は外の男に話しを聞いてみようと思う。どう思う?」
ヨギの話を聞いていたリッケが慌てて近寄る。
「馬鹿野郎!殺されるぞ。あいつらは銃を持ってるんだ。憲兵が血眼で追っているお尋ね者なんだ!とにかく隙を見て逃げるしかねぇよ」
リッケが声を荒げない様、必死に堪えながらヨギに言った。
その時、部屋の扉を外から2度叩く音が大きく室内に響き渡った。
ポポイもリッケも息を潜め臨戦の態勢を取る。
ヨギは寝台で眠るリリの傍に歩み寄った。
「やるか?」
リッケが警棒を構えながらポポイに言った。
「ああ、いつでもいい」
ポポイも短刀を構えて言った。
~後編へ続く~
illustration by chisa
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
