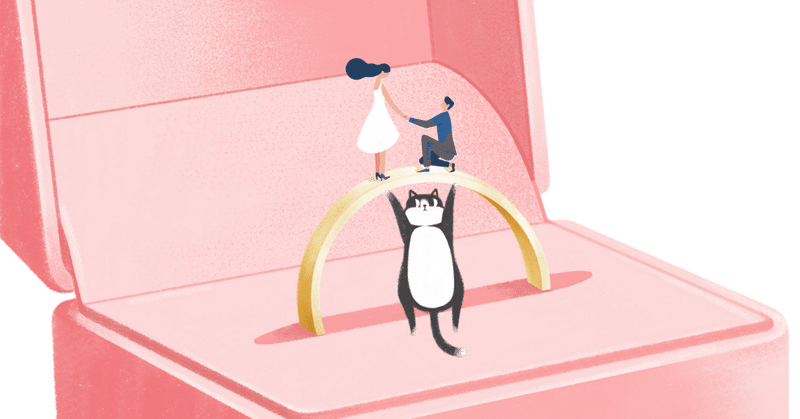
結婚制度から外れたパートナーの在り方と、生命保険の未来像について
自分だけの幸せを追求しやすいマッチングアプリの世界
パートナーや家族の在り方を考える上で、この本は極めて多くの示唆を与えてくれた。めっちゃ大雑把に要約するとこんな感じだ。
マッチングアプリ婚は世間の目が届かず、誰にも介入されずに自分の価値観で幸せを追求できるツールである。価値観が多様化する時代にこれで救済される人も一定数おり、10年以内にマッチングアプリ婚が半数を占めるようになるだろう。
では、具体的に救済されるのはどんな人たちか?
①年上女性の自立心と経済力に魅力を感じる男性と、甘えてくる年下を可愛いと思うカップル。70代女性でも全然あり、と考える若い男性はそれなりの数いるらしい。
②経済力はあって家事や介護(時には事業の手伝い)をしてほしい年上男性と、優雅な暮らしに憧れる年下女性によるパートナー契約。もはや雇用関係に近い。
専業主婦になってタダで家事・介護・家事手伝いをやれ、というエゴ丸出しな熟年離婚後の男性が本書には何度も出てくるが、契約関係だと割り切れば道が開ける可能性はあるはずだ。
③ADHDで他人と安定的な関係性を維持することが難しく結婚は非現実的。同性とのシェアハウスで寂しさを軽減しつつ、性的欲求と承認欲求をアプリで満たし続ける。
オーナー社長は事実上のパートナーを会社の役員にして報酬を払っていたりするので、成功している経営者は婚姻関係以外にも契約を結ぶ方法はある。
しかし、世の中の大半は儲かっていない経営者や会社を持っていない人間だ。そういった一般市民が模索する新しいパートナーシップは、社会通念と己の欲望とのギャップに苦悩する人間にとって救済になる可能性がある。
生命保険は結婚制度と結びついた商品である
一方で、今の生命保険は結婚制度に重きを置いた商品となっている。
生命保険の保険金受取人は○親等以内の親族、と定められているのが一般的だ。婚姻関係にがない人間にお金を残したいとなると、保険会社との個別相談の世界になる。同居や経済的な依存度など客観的な事実を集めての判断となるが、認められない場合もある。
また、未成年を受取人にする生命保険に加入するには親権者の同意が必要になる。たとえば、離婚したカップルがいて、子供の親権は母親が得たとする。この状況で父親が子供にお金を残そうと思って保険に加入しようとすると、別れた妻に親権者としての加入同意を取り付けないといけないのだ。
間に生命保険の担当者が入るとはいえ、かなりハードルの高い手続きではないだろうか。
こういったパートナーの王道パターンから外れたカップルというのは、将来のお金の話などをかなり真剣に考えている人が多い。これから増えてゆくことが予想されるので、生命保険がその受け皿を担うことができれば社会的意義のある商品を提供できるのではないか。
今の日本だと公正証書契約を結んで、結婚制度以外の方法で財産分与などを取り決める、といった方法がある。ただし、いろんな事項を事細かに取り決めなくてはいけないので、忙しい現役世代にとってはかなりの負担だ。
今の結婚制度は微妙にフィットしていない感はあるが、「諸々の権利関係をひとまとめのパッケージとして婚姻届一つで済ませられる」という手軽さは今も需要がある。
婚姻関係以外のパートナー向け保険の課題
では、生命保険がこのニーズに対応するにあたって課題となる要素は何だろうか。
【課題1】結婚制度以外のパートナー関係を結ぶ人間が、統計的にも明らかになり、しかも採算が見込めるぐらいのボリュームになること
これが最大の壁である。
婚外子率が2%といわれる日本の現状では、保険会社が動き出す可能性は低い。ここに「婚外子の社会的地位を認める法改正」が重なれば、GOサインを出す会社は増えるだろう(国からのお墨付きは、規制産業にとってはメチャクチャデカい後押しなのだ)。
これから増える予兆はあるが、いまはまだ「時期を待て」のフェーズである。
課題2:パートナー契約を装った保険金詐欺をどうケアするか
ホスト狂いの女性と推しのホストがいたとする。ホスト狂いの女性が自分を契約者・被保険者として、保険契約を結ぶ。受取人はホスト。女性はホストから婚約指輪をもらっており、いずれは結婚予定だという(ホストは営業のために婚約指輪ぐらいは普通に渡す)。
保険会社として、このケースは契約として引き受けてもよいだろうか?逆に認めるとしたら、どんな証拠が提出されたらOKが出せるだろうか。
同棲してたらOK?身体の関係があったらOK?女性がホストに貢いでいる金額が明らかに収入と比べて多額であれば、それも判断材料になるか?ホストの営業と区別がつかないのでいずれも信用できないとなると、それは職業差別になる?
少々極端な例だが、なぜ保険会社が婚姻関係以外の人間を受取人設定に慎重になるか、少し分かっていただけただろうか。
個人間の自由契約と、商売の間には見えにくい大きな溝があるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
