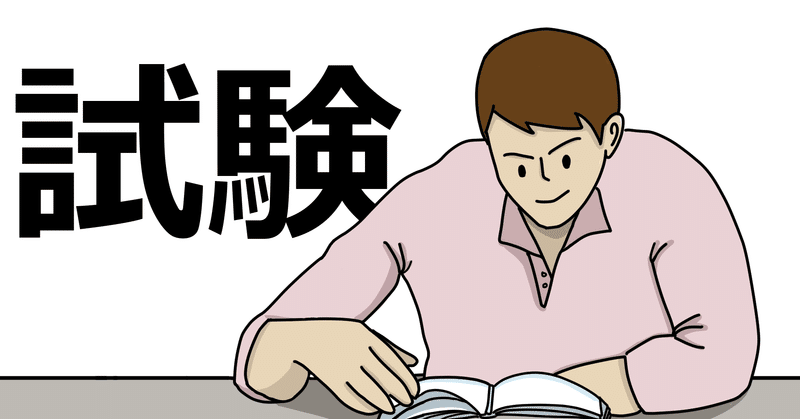
【4000字超】細胞検査士合格への道【これで合格できる】
どうも、だぴてぃ先生です!
僕も資格取得している細胞検査をするプロ「細胞検査士」の資格認定試験のための記事になります。
この試験の合格率はざっくりと1次試験で50%、2次試験で50%と、受験者の25%くらいしか受からないという、まあまあ難しめの試験になります。
とはいっても、日常的に細胞検査に従事していたり、触れているなら、正直そこまで困難な試験ではないです。
ただ注意しておきたいのは、どんな資格にも言えることですが「正しい努力をすること」。
これが出来ないと自分ではすごく頑張ったと思っても受からないです。逆に言えば正しい努力をすればそこまで根詰めなくても合格することができます。
僕は戦略的に試験を受けたので、誇れる勉強量がないってのが、今になっては「あの時もっと頑張っておけばよかった・・・」となっていますが😅
今は1次試験も終わり、これから12月前半の2次試験へ向けて受験者の皆さんが頑張っている最中だと思います。
ぜひこの記事が1mmでも参考になれば嬉しいです。
では今日は細胞検査士資格認定試験に合格するのに何が必要なの?ってことを、現役細胞検査士である僕の独断と偏見で書いていこうと思います。
難しいことは書きません。
というより本質はシンプルなので、難しく考える必要はないです。
では早速みていきましょう!
今日は結構マニアックな内容なので、スキの数だったりPVは度外視です。1人でも参考になってくれたら嬉しいなと思って書いています。
🔆細胞が好き
はい、これがないと合格は不可能って言ってもいいくらいです。
そもそもなんで細胞検査士になりたいんですか?細胞と触れていたから?業務上で仕方なくでしょうか?どちらにしてもまずは細胞に興味を持ちましょう。
細胞検査士は1日中顕微鏡に張り付いていることもあるくらい、常に細胞を見て、考えて、診断する職業です。
長時間触れているものは好きなものでないと、いつか自己崩壊を起こします。つまりそれは誤診や見逃しによって患者さんに不利益をもたらします。
なので細胞検査士として働きたいなら、何かしらの方法で細胞に興味を持ちましょう。全てはここからスタートです。
🔆わからないことは自分で調べる
これは細胞検査士に限らず、資格認定試験全般に言えることです。
まずは自分で調べる。どうしてもわからないなら人に聞く。
これができないと後述する「知識の掛け合わせ」ができないので、レベルの低い細胞検査士の爆誕です。
僕のチームにも受験者はいますが、やっぱり自分で調べてから聞いたメンバーと、最初から人に聞いたメンバーでは、知識の差が歴然です。
今の時代、Google先生に聞けば大体のことを答えてくれます。
でも医療に関しては(特に細胞検査というマニアックな分野では)ネットの情報は鵜呑みにできません。ネットで調べて、書籍でファクトチェックして自分の知識にする。
ちなみに試験合格とは関係ないですが、合格後の未来を見据えて、「自分で調べる」という過程ができないと起こる弊害の一部をご紹介しますね。
■弊害その1:人の時間を奪う
学生さん以外で細胞検査士を取得する方のほとんどが何らかの形で病理検査に従事しているはずです。
自分で調べる癖がないと、人に聞くことになります。でも現場の細胞検査士はそこまで暇じゃない。顕微鏡の前で暇そうに見える時はレポート所見を考えていたり、意識的に休憩しています。
そこで簡単に先輩に聞いてしまうと、最初は快く教えてくれると思います。でもそれが積み重なっていくと「こいつ、自分で調べもしないでいちいち聞いてくるなよ」となっていきます。
細胞検査士は1枚の標本を見るために5分前後の時間を費やします。難しい症例や異型細胞があった場合はそれ以上になる時も多々あります。
そんな時に勉強していない前提で聞かれると、はっきり言って感情的になります。愚痴りたくなります。
それは結果的にチームの生産性を落とすことにつながります。
業務時間中に勉強させてもらえるところは少ないかと思いますが、もし職場が育成にウェートを置いているなら、それをとてもありがたいことだと受け止めた上で、しっかり自分で調べるクセをつけましょう。
■弊害その2:成長度合いが止まる
試験合格後の話になりますが、自分で調べるくせをつけておかないと、惰性で仕事を続けることになります。
レベルの低い細胞検査士の出来上がりです。
成長の止まった細胞検査士ほど、厄介な存在はないと思っています。
なぜなら昔の知識に基づいて判断してしまっているので、所見に時代遅れ感もありますし、何より医学的な知識として間違っている時さえあります。
成長度合いは合格するために必須な条件ではないですが、合格後をイメージしておくことも、モチベーションを保つのに大切なことです。
細胞検査士の資格をとって現場で働くからには学習は一生涯です。
🔆スクリーニングを重要視
そもそも異型細胞が見つけられないとお話になりません。
よく試験勉強時に細胞像アトラスばっかりみている人がいますが・・・アレ、正直効率悪すぎです。
自施設に症例がないなど、制約がある場合はもちろんアトラスに頼らざるを得ないですが、病理検査室がある施設ではおそらく合格に必要な情報は大体得られると思います。
アトラスは家でもみれます。でも、顕微鏡は家にはありませんよね?だったら職場でやるしかないんです。
ここで重要なのが「スクリーニング(異型細胞を見つける作業)」です。これができない細胞検査士はそもそも合格できないようになっています。別名スクリーナーとも呼ばれる資格ですので、スクリーニングが一番大切なのは間違いありません。
見落としてしまっては勝負すらできません。まずは異型細胞を見つけて、そこから鑑別を絞っていく。これに尽きます。
■正常細胞を見まくる
よく落ちる人でやりがちなのが「異型細胞ばっかりを見る」こと。
確かに勉強していれば異型細胞見ている方がテンションも保ちやすいですし、何より「やっている感」が出ますよね。
でも・・・僕が知っている人はこれをやった人は100%落ちています。
これが落とし穴。
正常細胞の「正常」が何なのかわからないと、異型細胞を見つけにくいのです。
見るときの「カン」が働くのは、結局どれだけ正常細胞を見てきたか、ということが1番のファクターです。
■スクリーニングは体力勝負
長時間見ていれば誰だって疲れてきます。ここでバテてしまっては合格は無理。3時間は見続けられる体力を養いましょう。
と言っても人間の集中力は90分も持ったらモンスター級なので、うまく休憩や集中力のレベルを上下させる必要があります。
メジャーリーガーの田中将大投手は、ピンチになるとギアを上げて、バッターが打てない球を投げることができます。これは裏を返せば、普段はセーブして投げているということ。自分をコントロールできている証拠です。
体力とはマラソンみたいに持久力を要するという意味ではないです。
集中力だったり、長時間同じ体勢を取れる姿勢だったり、多角的に捉える必要があります。
🔆知識の掛け合わせができる
先ほど、わからないことは自分で調べると書きました。
自分で調べないと、知識の幅が広がらないんです。
人に聞いた情報は単発。自分で調べた情報は連鎖します。
これができると知識の幅が格段に変わってきます。
つまり、勉強効率が雲泥の差なんですね。
記憶力というよりは、勉強の仕方がうまいことで得られるものです。だからスペックは関係ないです。
むしろ自分はスペックが足りない・・・と思っている人こそ、自分で調べるクセをつけましょう。
どうしてもわからない、調べても出てこないことは先輩に聞いて、そこから自分で落とし込んで幅を広げる、関連する知識を肉付けしていくことが重要。
たとえば、病理では「胆嚢=GB」と略することがあります。
これはちゃんと勉強していれば「gall bladder=GB」ということは、略語を知らなくても想像することができます。
これが勉強していないと「ゲームボーイ」なんていうおもしろ回答が出てくることになるんです。
■学力は関係ない
僕は英語が死ぬほど苦手で、高校入試も主要5教科で英語以外50点オーバーだったのに、英語だけ「3点」っていうミラクルを起こしているくらい、苦手分野です。(⇦酷すぎますね)
それでも病理の組織型(一応解説しておくと病気のタイプみたいなもんです)は問題なく覚えることができます。
というかもはや英語じゃないとわからない時もあるくらいです。
これらは頭の中にある全て知識を掛け合わせているから。
わからないことが出てきても「これってあのことを言っているのかな?」という推測ができるようになります。
全てを暗記するのは不可能ですし非効率的。
合格を目指すなら、正しい努力を目指しましょう。
==============
いかがでしたでしょうか?
あまりにマニアックなので、参考になるところが少ないnoteだったかなと思います。
しかし、スクリーニングの下りを除けば、他の資格認定試験や受験などにも活かせるのではないかと思っています。
もし細胞検査士を目指している方で、どう勉強したらいいいかわからない。。。だったり、一緒に頑張れる仲間や先輩が欲しいって方は、オンラインでつながるっていうのも現代だからこそできることです。
僕のnoteサークル【えむてぃ】では、基本的にはチームマネジメントなど、どうやって生産的な仕事をしていくか、もしくは自分を向上させていくかっていうところをメインとしてやっていますが、これから病理プランというコースを作って、病理検査に従事するものが専門で交流できるプラットフォームを作ろうかなと考えています。(病理を勉強したい人でも歓迎です!)
今はメンバー募集中ですが、興味がある方はこちらまでご連絡くだされば詳細をご案内いたします。
Twitter⇨https://mobile.twitter.com/duppyclub(⇦タップで僕のTwitterアカウントに飛びます)
こういうのは有料でないと人間は動かないと相場は決まっていますので、月額制にはなります、ただ、月300円程度で考えています(1日うまい棒1本で参加できると思ったら破格ですよね)。
今月中には稼働させようと思っています。
最後は宣伝みたくなりましたが、今日書いたことを実践できれば合格は目の前です。
2次試験も頑張ってください!1次試験で落ちてしまった人は来年がんばりましょう!
だぴてぃ先生でした😌
⭐️ご覧頂きありがとうございます⭐
毎日更新するには読者のみなさんのフォローが励みになります!スキやコメント、フォローなど頂けると嬉しいです⭐サポートや購入はもっと嬉しいです!
さらなる情報発信の糧にさせていただきます!
✔️だぴてぃ先生のあれこれ✔️
▶プロフィール
▶運営サークルこちらから【えむてぃ】♻️
▶Twitterはこちらからどうぞ🐦
🌟関連記事🌟
この記事はこのマガジンに入っています😌
ぼくの経験とノウハウが詰まった記事たちです。
ぜひ覗いていってくださいね🍀
頂いたサポートは書籍やスタバ代とさせていただきます❗サポートはぼくの活力となります😆たくさん喜んで頂けるように日々がんばります⭐
