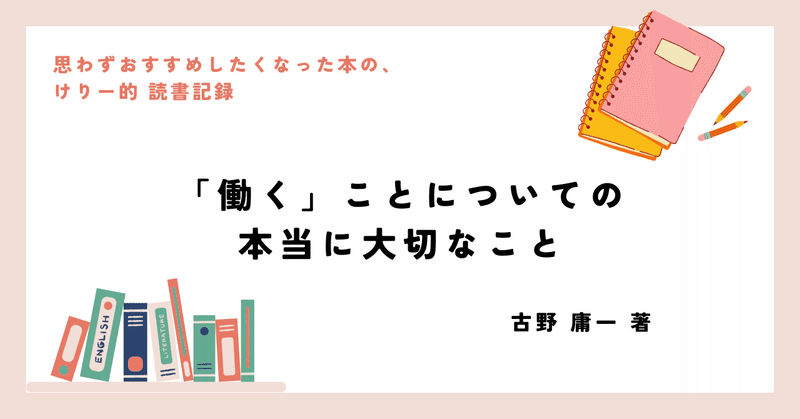
【本】「働く」ことについての、本当に大切なこと(古野庸一)
自分が自分の人生の主人公であり、世界はその舞台です。「働く」ことを通じて、「生き残る」ことだけでなく、「幸福になる」ことを試みることで、世界は自分の味方であると感じられると信じています。
私は、この考え方が好きだ。体現できる人に憧れる。
社会人としての、理想のように感じる。
当たり前のようにも思えるが、心からこう信じて仕事をしている人は一体どれくらいいるだろうか。
多くの人は、「幸福になる」ことを忘れていないだろうか。
日本人は、その勤勉さから「生き残る」ことへの意識は高いと思われる。日本の学校教育が勤勉で従順な人間形成を目指してきているのだから、それは至極当然かもしれない。
「自分や家族を幸福にすること」よりも「カイシャ・社会に貢献する」ことを良しとしてきた風潮があるのではないだろうか。自分や家族の幸福を優先するような人間は、ややもすると「自己中心的だ」「利己的だ」と捉えられがちではないだろうか。
100年後の未来からみると「おかしい」と思えること
「働き方改革」は、表面的には、女性の活躍促進であり、ブラック企業の撲滅であり、健康増進ですが、深層では働く意味、仕事の中心性、仕事と家族の関係性、仕事と幸福との関係性などの問題だと考えます。
近年よく話題に上がる「働き方改革」は、ワークライフバランスという単語も挙がるように、働くことと人生についての「是正」なのだと思う。
100年後の未来から見ておかしいと思えることを少しずつ是正し、人間らしい人生を送ることを追求する運動だと私は捉えている。
この本の中では、アリストテレスのいう「エウダイモニア」がキーワードとしてよく出てくる。
エウダイモニアとは「よく生きること」、「やりがいのある人生を生きる」ことである。
そして著者は、「豊かに働く」ことについて以下のように表現している。
目的や方向感を持ってコントロールできることをコントロールし、コントロールできないことを受け入れ、そして自分を受け入れることで生き残り、エウダイモニア的幸福感に浸りながら働いていける
将来に対して、目的あるいは方向感を持ち、今日、コントロールできることに集中し、コントロールできることを楽しみ、コントロールできないことを受容し、そして自分を受け入れる
2回(細かくいうとそれ以上)も繰り返し出てくるこのメッセージこそが筆者の最たる主張なのだと思う。
構成
【主題】豊かに働くこと・・・・・・・第6章
【前提】働く意味・・・・・・・・・・第1章
【目的】働くことと幸福の関係性・・・第2・3章
【方法】
・自分に合った仕事を見つけること・・第4章
・居場所を探し続けること・・・・・・第5章
以下に、私が感じた本書の内容をざっくりと記載していく。
(目次とは異なります)
第1章で 「働く」意味
・仕事の特性
・仕事の歴史
・働く目的
・働くことをたのしむ
などについて、根本的な問いに考えを深める章。
ちなみに、ここでは漁師とビジネスマンの話が出てくるのだが、私は最後にはっとする気づきがあったので、ぜひ一度考えてみて欲しい。
第2章 「生き残る」ことと「幸福になる」こと
・生き残る、幸福になる、とは
・働くことを通じて、生き残ることと幸せになることを両立させるには
・広義の幸福
について分析されている。著者自身の経験談も。
ここで印象的だったのは、
「明日に向けての準備が、今日の楽しみと繋がるように」という言葉。
生き残るための方策を、幸福になる手段として、目標に至るすべての過程を楽しむということだと解釈した。
今を楽しみ、未来を創る。
悲観は気分だが、楽観は意思。
私は、相田みつをさんの「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」という言葉が大好きだ。
幸福は、意志と自己克服によるもの。そう述べた著者と、通ずるものを感じた。
第3章 「働く」ことと「幸福になる」こと
・富と幸福
・幸福を決めるもの
富は必ずしも幸福をもたらすわけではない。
幸福をもたらすのは、人としてのあり方である。財産や、他社からの評価ではない。
幸福の感じ方は、遺伝によって左右される因子もある、というのは驚きであった。ただ、ここで大切なのはその事実を認識してどう行動するか、ということである。これは認知療法に近い。
「仕事は、最高の自己実現の場」であると私は捉えていたが、つまり幸福を感じる機会である、ということに本章で気づくことができた。
第4章 自分に合う仕事を見つけることをあきらめない
・「ジョブ」、「キャリア」、「コーリング」
・自分を知るためのアセスメント
・自分にあう仕事をさがす4つの作業
・Will Can Must という視点
・いい会社とはなにか
何ができるのか、何をやりたいのか、という2軸で仕事というものを捉えていたが、ここでは「社会のなかで自分がその仕事をするのにふさわしいか」という観点を知ることができた。コーリングつまり天職は、社会によって生かされているということを自覚し、社会のなかで自分の価値発揮を最大限にできるもの、ということなのであろう。
そして、何をするか(仕事)に加えて、どこでやるか(会社)も重要であり、場(どこでやるか)を選ぶための軸についての示唆を与えてくれている。
第5章 自分の居場所を確保し続ける
・仕事する環境を整える
・仕事人としての成長(ステージと見極め)
・経験を学びにする(気づきと内省)
・「スパイラル・キャリア」
人間は、繋がりによって幸福を感じる。居心地の良い場所で、自分に合うように仕事をデザインしていくこと(ジョブ・クラフティング)。仕事をデザインする、とは、仕事の内容、意味合い、人間関係をアジャストしていくということである。
そしてここでは、具体的なスキルや方策が示されている。
<能力を上げ続けるための、3つの問い>
①この1年で自分は成長したのか
②自分の強みを発見できたか
③その強みを磨くプロセスは自分にとって楽しいだろうか
これは、定期的に向き合うべき問いである。
私は毎年、建国記念の日に(単純に祝日なのでこの日を選んだ)、やりたいこと100個のリストアップと、ライフプランを考えている。ちょうど良いので、次回からはこの3つの問いも取り入れることにした。
第6章 より豊かに働く
・快楽を求めるだけが幸福ではない
・キャリアデザインとプランドハップン
・自分らしさ
・豊かに働くためには
ここで漁師とビジネスマンの話が再度出てくる。ここまで読み進めた上で改めて問うと、私は当初とは違う答えになっていた。考え方は個人によるので一概には言えないが、最初の問いについての捉え方に変化があるのは確かだと思うので、一度読んでみて欲しい。
快楽や喜びや充実や達成のようなポジティブな感情だけではなく、悲しみや苦しみ、妬みや怒りのようなネガティブな感情も味わいながら働く。
そのように豊か(エウダイモニア的)に働くことを提唱します
章の最後をこう締めくくっている。
人生を俯瞰して、まるでゲームの主人公の気持ちを眺めているように捉えることができたら、ネガティブさえも楽しめるのではないかと思う。
私自身は感情に揺り動かされやすいタイプで、ネガティブな感情への対処があまり上手ではない。顔に出てしまう。しかし、この最後の一文のように、「ネガティブな感情も味わいながら」働くことで、一歩引いて捉えることができるような気がする。
この先何十年も働きつづけるのだから、せっかくなら明日の準備を楽しめる自分でいたい。それが精神的な充実をもたらし、仕事もプライベートも楽しむ素地となるのではないだろうか。
働くことを通じて、「生き残り」と「幸福」の両立ができること。
これを、一人の仕事人として追求していきたいと思う。
人間は、生きて死ぬだけ。
そう考えると、人生をより味わうことこそが、
「よく生きる」ということなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
