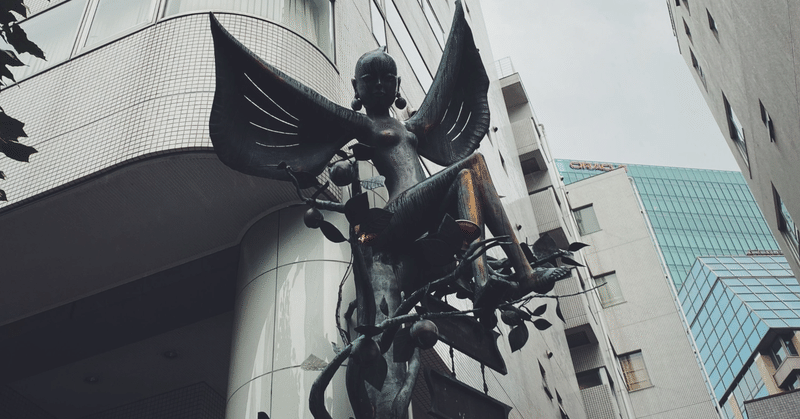
今村夏子「あひる」
初めての今村夏子。
あひるを飼い始めたら近所の小学生が家の庭に来るようになった。あひると遊びに、触りに、見に。絵を描く者までいる。「わたし」の両親はそんな子どもたちを気にかけて、庭から部屋にあげて宿題をする場を設けてあげたり、お菓子を用意したりするようになる。
「わたし」は資格の勉強を自分の部屋でしている。あひるを見にくる子どもたちの様子が手に取るように分かっている。あひるの名は「のりたま」という。
ある日の夕方、授業を終えて一番乗りでうちへ来た男の子が、
「のりたまっ」
と叫んだ。わたしはその叫び声に驚いて、思わず勉強の手を止めて二階の窓から顔を出した。
男の子はギョッとした顔でこっちを見上げたまま動かなくなった。縁側から出てきた母が、どうしたの、と声をかけるとまっすぐにわたしの顔を指差して、
「人がいる」
と言った。娘よ、と母がこたえた。
わたしが小さくおじぎをすると、向こうも同じように頭を下げた。
解説でも触れられていた箇所だが、ここを読んでぞっとした。
少年にとってこの家は「あひるのいる家」でしかない。二階に人がいるとは思っていない。子どもの狭い視界と世界の中で、元からいた住人の方が蚊帳の外に置かれている。幽霊と大差ないどころか、彼らにとって「わたし」は幽霊であっても差し支えがない。
構われすぎのストレスにより、一匹目のあひるは衰弱し、父の手によって病院に運ばれる。後日帰ってきたのは、違うあひるであった。二匹目も同じ道を辿り、三匹目がやってくる。子どもたちは変わらず「のりたま、のりたま」と言ってあひるを可愛がる。当然また三匹目も死に、庭に墓が作られる。そこに訪ねてきた少女が問いかける。
ねえねえ、のんちゃんね、一ぴき目が一番好きだったよ。ここにいないの?
ねえどこにいるの。ねえねえねえ。
子どもたちはあひるの代替わりを把握していた。父があひるの死を隠して新しいあひるを購入してこようが、子どもたちにとって個体が違うことは重要ではなかった。異常なのはこの家族なのか、子どもたちなのか。不思議な筆致で描かれた残酷でありながら現実的な絵画、というような話に私は唖然としながら読んだ。「おばあちゃんの家」「森の兄妹」でも似た驚きにうちのめされながら、子どもたちの寝た後、シンクの明かりだけを灯した居間で読み終えた。
言葉には出来ない何かの衝動が湧き上がってきて、私は「千人伝」という話を書き始めた。題名の通り千人続くかは分からないが、この世にいるようないないような人の話を、書き始めた。今も書き続けている。
入院費用にあてさせていただきます。
