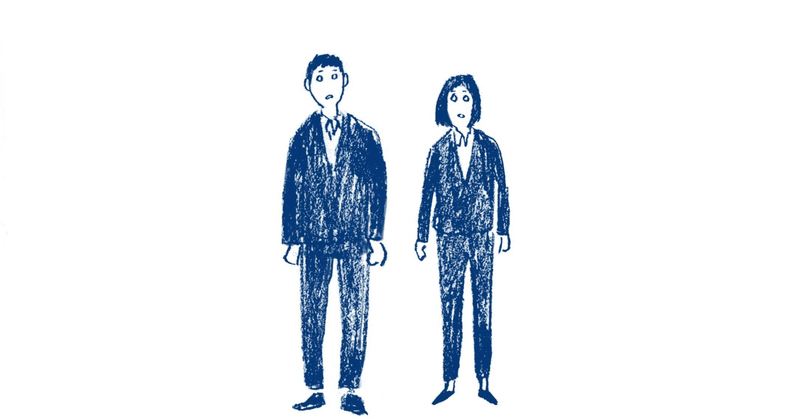
ステレオタイプを揺らす「労働小説集」ーミニ読書感想『私たちの金曜日』(三宅香帆さん編)
書評家・作家の三宅香帆さんが編者を務めた『私たちの金曜日』(角川文庫、2023年1月25日初版発行)が面白かったです。一見、ステレオタイプを反映したかに見えるタイトル。しかし実際は、そのステレオタイプを揺さぶる珠玉作品を集めた素敵なアンソロジーでした。
『私たちの金曜日』は、『僕たちの月曜日』と対になっている。このタイトルの差に少し引っ掛かりました。なぜ男性は月曜日で、女性は金曜日なのか?男性は「月曜日から仕事に向かって行くもの」で、女性は「金曜日を終えてからが本番」、そうした性的役割分業が目に浮かぶようなタイトルに感じたのです。
解説によると、編者の三宅さんもこの点には立ち止まっています(p235)。三宅さんに寄せられた依頼は「女性主人公を中心とした、日本のお仕事小説」。三宅さんは、この「お仕事」にツッコミをいれる。女性の労働が「お仕事」という軽い響きを持つ言葉に置き換えられる現状に違和感を表明する。
その上で、あえて、『私たちの金曜日』というタイトルを選び取ったと説明します。
前略)タイトルの話に戻るが、やはりいまだに女性の仕事は「金曜日」ーーつまり仕事以外のことをする時間と、仕事をする時間を、天秤にかけながらやっていることだと思われているのではないか。
そこまで考え、そのうえでやはり私はこのアンソロジーを「私たちの金曜日」と名づけたい。なぜなら私は、月曜日ではなく、金曜日の労働だとみなされ続けている、女性たちの働く姿をきちんと記録しておきたかったからだ。
このような思いで編まれた本書は、一言で言って強い。選び方も、並び順も、ビリビリと電撃を帯びるような、強い意志を感じるのです。
たとえば一番手の『社畜』(山本文緒さん)。この作品では、「コネ入社」として見下される女子社員が、本人は気にせず淡々と仕事をこなしていたところ、思わぬ形で意思表示の強い先輩女性社員を追い抜いてしまう姿が描かれます。
実はこの作品で一番ダメなのは、主人公たちの上に立つ典型的ヒラメ上司の男性社員なのだけれど、先輩の怒りはそこに向かない。女性だけで「争わされている」構図が、男性の読者としては申し訳ない気持ちになる。
そしてさらに印象深いのが、主人公のひょうひょうとした仕事観。先輩に泣かれたり、散々な目にあった後、友人とカフェで顔を合わせるラストシーンが心に残りました。
「ねえ、畑中。会社って面白いね」
妻子を養うため、自分のスキルを生かすため、そう言って働いてる人達が聞いたら卒倒しそうだなと思いながら、私はエスプレッソに口をつけた。ここではないどこかではなく、私の居場所はここだった。それはいつだって同じで、私は今立っているコートで打たれた球を、何も考えずに拾うだけなのだ。
打たれた球を、何も考えずに拾うだけ。それが、面白い。淡々として、だけどふっと笑うかのような主人公の言葉に、「たしかにな」と思うのです。仕事の醍醐味って、こういう無骨なものかも。
主人公が見据えているのは「労働」です。自己実現とか、スキルアップとか、そういうものとは異なる、労働としての仕事です。明日も明後日も、来た球を打ち返す。だけど単純作業だと辟易するわけではなくて、なんだか「面白い」。「女性主人公のお仕事小説」とは、全く違う毛色の物語がここにあります。
他の作品も、イメージ通りの「お仕事小説」は正直一つもない。いや、編者はわざと入れていない。読んでいて、「裏切られた」と感じる。それは心のどこかで、『私たちの金曜日』と聞いたら逆境で奮闘する女性の姿を描いたバリキャリ小説を期待している自分がいたからだと思います。自分自身のステレオタイプが炙り出されました。
編者は「私たちの金曜日」という依頼を巧みにすり替えて、『私たちの金曜日』という強烈なアンソロジーを送り出した。策士だなと思いました。
世の中で叫ばれる「市場価値向上」に疲れ、キラキラした仕事とは違うことに辛さを抱いた時。本書は凝り固まった視点を「ずらす」点眼薬になると思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
