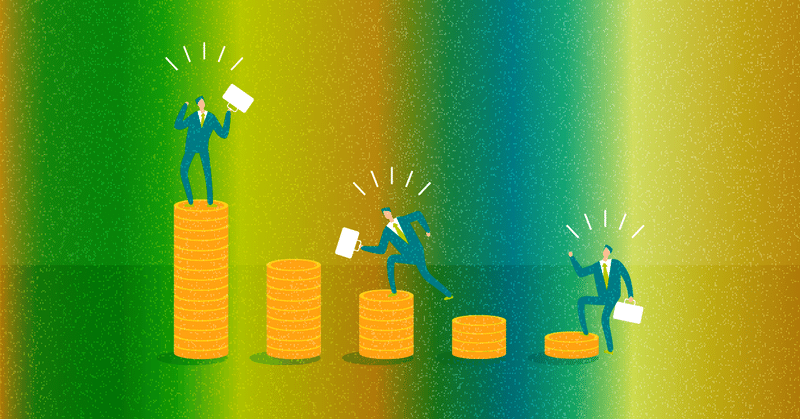
価値ある人間だから給料が高いのではないーミニ読書感想「給料はあなたの価値なのか」(ジェイク・ローゼンフェルドさん)
ジェイク・ローゼンフェルドさん「給料はあなたの価値なのか」(川添節子さん訳、みすず書房)がとても勉強になり、興味深かった。タイトルはもちろん反語だ。給料は「あなたの価値ではない」ということを、産業史的な視点、労働運動史的な視点、現代労働の国際比較などさまざまな観点から検討し、立証する。副題にある通り、給与にまつわる「神話」を解体する。「個人の市場価値」の向上がそこかしこで叫ばれるいま、必読の一冊だと言える。
では何が給料の高低に関わるのか。当然複合的なのだが、本書では「組織内の権力関係」と「株主資本主義の加速化」が大きな要因に挙げられている。特に後者の株主資本主義は目から鱗で、たしかにCEOなどの給与の高騰は「企業の利益は株主に十分分配されるべきだ」という言説の浸透と連動しているのが理解できる。
近年労働生産性は向上しているとされるのに、労働者の給料は上がっていない。そうした利益は株主資本主義に基づき、株主に還元されていると言える。
にもかかわらず「個人の能力が高度化するほど高い給料が受け取れる」という考え方は根強い。著者は自ら米国の労働者と経営者にアンケート調査をしているのだが、なんとどちらの側も給料の決定要因として個人の能力を上げる人が最も多かった。
本書ではさまざまな反証が用意されるが、分かりやすいなと思ったのはバーガーキングの給料。米国ではとても暮らしていけないのに、デンマークではそれなりにもらえるらしい。もし「単純労働だから価値が低い」のなら、両者の給料に差が生じるのは妙だ。少なくとも、暮らしていけないほど低い給料になる理由にはならない。
むしろ、給料格差の拡大を許容し、正当化するための言説として「能力主義」が活用されていると言える。この辺りの問題意識はマイケル・サンデルさん「実力も運のうち」にリンクする。今後、能力主義への懐疑や、拡大しきった格差への不満爆発につながるのではないか。
能力主義への反証として「個人の成果は、思うほど簡単に測れない」という指摘がある。これも豊富なケーススタディがあり面白い。特に警察など公的機関に成果主義を導入すると必ず不正や腐敗が起こるのは興味深い。一般的企業においても、チームの成果と個人の成果を切り分けるのは困難だし、そうすると結果的に「成果をかすめとる個人」がのさばる結果となる。このあたりの内容はジェリー・ミュラーさん「測りすぎ」の議論とつながる。
では、われわれ労働者は給料を上げるために何をすれば良いのか?という点では、本書の提案はそれほど強くはない。それほど強くはないが、少なくとも、本書を読むことで能力主義と給料の紐付けは当たり前ではなくなる。それを疑い、拒否する余地ができる。これはジェニー・オデルさん「何もしない」で触れられている戦略と同じ。「そう思わない」と反応し続けることがひとまず、この大きな潮流への抵抗力になる。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
