
“ちゃんとやっとけ”は指示ではない。京丸農園の事例から考えるユニバーサルな就労環境。
ようこそ、お越しくださいました。
どうも、えんどう @ryosuke_endo です。
自分の言葉や投げかけ方が本当に的確で他人が迷うことなく行動を開始できるのかどうか。こんな点を冷静に、客観的に振り返る機会を設けられている人は決して多くはないだろう。
logmiに掲載されていた京丸園(静岡)が行っている多様性のある就労環境についての記事からマジマジと振り返りながら自分自身の「できていなさ加減」に辟易とすることになった。
「仕事ができない子」ではなく、その「伝え方」に問題がある400年続く芽ネギ農園が気づかされた「農業の弱点」
ついつい言葉にしがちな「ちゃんとやっといて」とか「しっかり」とか「丁寧に」なんて抽象的で浮ついた表現で誰かに指示や依頼をしてしまうことの問題点について考えていきたい。
▶︎ “一緒ではないこと”を前提にすること
ぼくはあなたではない。同じく、あなたはぼくではない。
ここからいえることは、他人が自分の抱く価値基準や軸なんてものがあるのだとして、それを完全に理解できることなどありえない、なんて当然なものだ。
ただ、これを受け止め切れる人は決して多くはない。
上司と呼ばれる会社の偉い人は部下と呼ばれる人たちに向けて指示を出す。そんな場面は就労者であれば一度や二度のみならず自身でも体験済みだろうし、目の前で繰り広げられてきた光景であるはずだ。
おそらく上司側は部下に指示を出す上で長く就労している、ある程度の関係値が構築されている人たちに囲まれ、日々、自らが発している発言やメールなどのテキスト文で「伝えている」と力強く実感されていることだろう。
しかし、いくら自分に付き添う時間が長い人間がいたとしても完全に自分と一緒の思考を辿ることなどできないし、そこから同様の結論に至ることなど到底ありえない話だ。
なぜなら、上司は部下ではないし部下は上司ではないからだ。これは役割を指しての言葉ではない。あくまでも人格が異なる別の存在であるという意味で、この点を蔑ろに捉えてしまっている人はぼくに限らず、一定以上の割合で存在しているのではないか。
▷ “ちゃんと”、”しっかり”、”丁寧に”は甘え
同一人物でない以上、思考が同じくなることもなければ結論が一致することもない。方向性がわかっていたとしてもcm,mm,μmといった範囲で誤差が生じる。その誤差を発生させないようにすることこそが「指示を出す側の責務」だ。
小さな点に目を向けつつ、その誤差が発生することによって困ることになる自分や部署、会社のことを想定していれば、そもそもが前提から揃えていく、揃える必要があるものの、それをせずに「ちゃんとやっといて」とか「しっかりやってね」、「丁寧にやりましょう」といった抽象的な物言いをしてしまうことは、明らかに怠慢であり単なる甘えでしかない。
「その抽象的なものいいから汲み取ることも仕事だろう!」
そう言いたい人もいるだろうが、だからユニバーサルな就労環境にならないだけでなく、上司部下の間で起こる人間関係の不和を基点としたメンタル不調の増加に影響を及ぼしていると見ることも可能だ。

ユニバーサルな就労環境とは普遍的な就労環境だと言い換える。つまり、どんな境遇の誰が働いたとしても問題や課題もなくバリアフリーな状態で就労できる環境だ。
就労環境の「環境」には上司や同僚といった人員も環境因子として考えなければならない。
つまり指示を出す、もしくは指示を確認し合う同僚間で共通言語や前提認識といった事柄を共有し合える環境こそがユニバーサルな就労環境を構築することであり、それもせずに「汲み取ること」を求めるのは、あまりにも大上段に構えすぎている殿様みたいな態度だといわざるをえない。
▷ 自分のことばは誰になら通じるのか
「部下側に謙るようなことをやっていては事業に支障が出る」
そんな声も聞こえてきそうなものだが、正直、その思考自体が甘えなのだと断じざるをえない。別に偉そうに物を言っているわけではない。それでは通じない人たちに向けて同様の物言いをしてしまうのか、という問いだ。
車椅子に乗っている人がどこかしらのビルの上階にどうしてもいかなければならないのだが、階段しかない...と言った非常に困っていることが安易に想定できる場面で「車椅子に乗っているからだ」とか「ここには階段しかないので...」という物言いをするのか。
耳が聞き取りづらい人がいたとして、その人にわかるような物言いができない以上は画面でテキスト文で伝えたり、ゆっくり聞き取れているのかを確認しながら話すことを「時間がもったいない」だとか「そんなことをしている時間があれば他にやるべきことがある」といった様に血も涙もないような態度を貫くのか。
ぼくは「できない人がいるから」と何もかもができない人たちに合わせてしまうことは速度感を失っていくことにもなるため、すべてをできない側の人たちに合わせて進むべきだと述べるつもりはないが、社会構造的にできない・やりづらい側が少数派であったとしても、その人たちが望んで選択できる様な状態を構築することが必要だと考えている。
たとえば、会社での就労することを想定すると、就労が可能な人たちが意思疎通の場面において課題感やどうしようもない焦燥感を抱くことなく就労できる状況を生み出すことが必要なのだ。
上記した車椅子に乗った人が上階に用事があるのにいくことすら叶わないなんて状況は絶望的なわけだが、それを把握した人が数名でも手伝えば済む話でもある。
結局、自分のことばが誰になら通じて誰に通じないのかを把握する他にないのだが、それならばいっそのこと通じないことを前提にしつつ、前提から認識を合わせていく様なやり方をした方が結果的に時間の短縮になるはずだ。
▷ 仕事を人に合わせるの本意
冒頭で紹介した京丸農園の記事内で”「人を仕事に」ではなく「仕事を人に合わせる」”と表記されている箇所がある。別に無理やり仕事を増やそうって話ではないし、無駄な仕事を増やして人員の確保に努めようって話でもない。
ある一つの仕事があるのなら、それをユニバーサルに誰でもこなせるようにすることを目指すには何をしたらいいのかを考えることだ。
指示の出し方、ひいては”ことばの選び方・使い方”、業務設計や役割など、あらゆる事柄が普遍的であるのか。属人化することを悪いことだとは思わないが属性化することは悪いことだとぼくは考えている。
男性にしかできない、女性にしかできない。上司にしかできない部下の一部の年齢層しかできない。など、誰かに依存するのではなく、ある属性を持っている人たちにしかできないことが業務内で発生するからこそ問題なのだ。
上で記載している「仕事を人に合わせる」の本意はそんなところにあるはずで、何でもかんでも人に依存することが悪いと記載しているわけではない。
そんなことを考えると、子どもとの生活を送ることができる状態であるぼくは恵まれているといえる。普段の生活で自分のことばが通じるのか通じないのかを常に図られているからだ。
子どもたちはわからなければわからないというし、わからないまま誤解してしまうことも多々ある。たいてい、誤解している場合はこちらの認識が甘く、彼らにいい加減な伝え方をしてしまっていることに起因するため、説明力不足だったといわざるを得ない。
保育園や幼稚園に通っている子どもたちは難しいかもしれないが、小学生と共に就労をすることを前提にすると、自分の利用することばや説明が難しくてややこしいものになっているのかを検証することも可能だ。
そんなわけで、他者に向けてやさしくありたいと思う今日この頃である。かしこ。
ではでは。
えんどう
▶︎ おまけ
▷ 紹介したいnote
これからは合理的配慮がないところを「ノンユニバーサル〇〇」って名乗るようにしたらいいんじゃないかな
同じように取り上げてくれているnote執筆者の方々は一定以上おり、その人たちの大半は物珍しいことを目の当たりにしたというよりも普段の就労環境等に課題感や問題意識を持っている人たちが多い印象である。
トイレからユニバーサルデザインを考えてみる
街中でユニバーサルデザインを目にする機会は少なくない。しかし、誰でも理解と把握が可能な動線設計となると敷居が高くなる。だからこそ、色や図などと用いて判読性を高めようとしているのだが、この記事はその点をわかりやすく説明してくれている。
農福連携についての整理 モデル図など
農福連携といったことばを目にする機会は多くないだろう。本記事は図解にして説明してくれているため理解しやすい。この記事内で行われている図解もユニバーサルな試みだ。
▷ 紹介したい関連書籍
めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン!
もう、早速購入したのはいうまでもない。子どもたちとユニバーサルな取り組みについて考えるきっかけになると思ったのはもちろん、彼らと「自分のことばが誰に通じるのか」を模索する第一歩にしたいと思ったからだ。
▷ えんどうのTwitterアカウント
僕の主な生息SNSはTwitterで、日々、意識ひくい系の投稿を繰り返している。気になる人はぜひ以下から覗いてみて欲しい。何ならフォローしてくれると毎日書いているnoteの更新情報をお届けする。
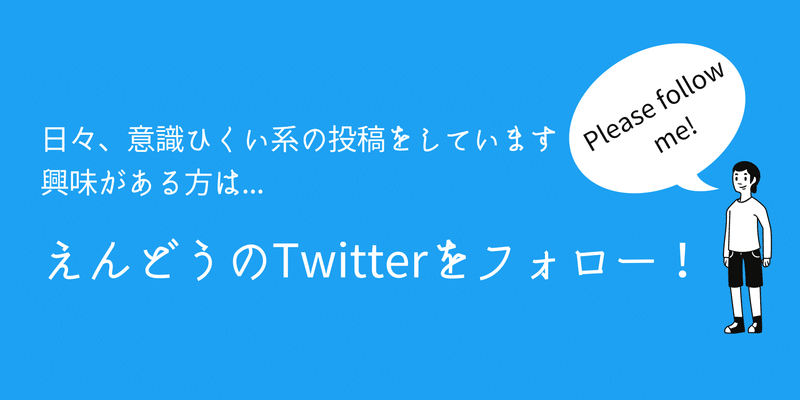
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
