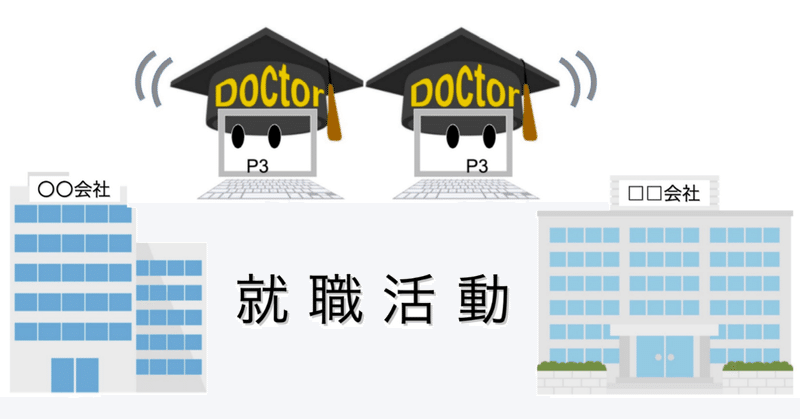
工学部 大学院生へ 〜 インターンシップ 〜
私の時代にはなかったインターンシップという制度.本当に素晴らしいと思います.思いっきり有効活用して下さい.世間の空気は,終身雇用は崩れており,もはや幻想である.めざせ!一億総個人事業主,企業家などといった非常に威勢の良いことばかりがもてはやされている.会社の歯車になってどうする?という人もいますが,どんなに大規模で優れた製品も,優れた品質のギアがなくては成り立ちません.全ての人が偉人である必要もないし,偉人なわけがない.凡人が幸せにゆる〜く生きていける社会が豊かな社会なのです.全ての人がすごいリーダーシップを持たなければならないというのもなんだか違うような気がしてます.力強いリーダーシップを発揮する人から,ぜひ自分のチームに加わって欲しいと言われるようになれば良い話です.iPad Pro単体ではその性能が100%発揮できない.そこにApple Pencilがあって初めて120%クリエイティブな活動ができる.そのApple Pencilたる人材を目指してもいいんじゃないだろうか.誰もがiPad Proにならなくてもいいのです.そう,人の数だけ生き方がある.ましてや100年に1度の〇〇(自然災害,技術革命,不況,パンデミック...)といった中で,かつてのロールモデルなんて一切通用しない現代.グローバルというなんだかよくわからない抽象的なものに,本来の日本の良さが食い荒らされないように,行動原理(自分の価値基準)を常に問い続ける姿勢が大切だと思っています.
ちょっと硬い入りなってしまいましたが,インターンシップではどういったことを見極めたら良いのか,少しでも学生さんの参考になればと思って,ポイントを書き記しておきます.
1.その会社の事業ビジョン
2.組織・体制
3.カルチャー・雰囲気
4.自分とのマッチング(得意領域,価値基準)
1.会社のビジョン(企業理念や創業者の意思/継承)
まずは,そもそのその会社は,どういった主旨で設立されたものなのか.何で社会貢献しようとするものなのか.創立された時代背景はどんな状況だったのか.そこには必ず何らかの物語があるはずです.
その会社が提供している製品やサービスはどういったものであるのか.単にホームページや製品カタログを拾うのではなく,もっと掘り下げて調査?考察?してみて下さい.どこかに創立者の本や所縁のお寺などが記されているかもしれません.あるいは,妄想してみてもいいかもしれません.例えば,ありきたりかもしれませんが,ある製薬会社の創業者のお母さんは,昔に看護師をしていて,その時の救急患者で運ばれてきた男性(将来,夫となる)のICU担当となって,献身的なお世話により,男性は九死に一生を得ることになるのですが,それと引き換えに看護師は当時は不治の病とされていた△△に冒され人知れず田舎の実家での自宅療養を余儀なくされる...あるいは,あるスポーツメーカーの創業者は,マンガ『プロゴルファー猿』の著者と古い友達で,小さい頃からスポーツが大好きな少年だったのだが,自分の上達スピードに納得がいかない.あるとき,友人の非常に手入れの行き届いたグローブ,ゴルフクラブなどを使わせてもらったら,なんて使いやすいんだ!?と衝撃を受けます.そして...などと空想するのがどんどん楽しくなってきます.(こんな話を面接でしたら,どういう反応をされるのだろう?うちの会社でエンジニアになるよりも,物書きになったら?と言われたらどうしよう...喜ぶのがっかりするの.どっち??)
そして,創業から今日までどのような変遷を経て,今に至っているのだろうか.決して平坦な道ではなかったはずです.幾度と倒産の危機や事業展開において様々な妨害にも遭ってきたはず.それをバネにどうやって事業活動が続けられたのか.そういった継承という一見地味なところにも思いを馳せてみる.(こういった視点で歴史書を読み返してみると,戦国武将とかが何に腐心したのか共感が持てて,新たな発見があるかもしれません.)
2.組織・体制
会社は,下の表に示すようにだいたいクロスファンクションと呼ばれるような組織になっていることが多いと思います.(これはあくまで一般論であり,会社によっては異なるということをご了承下さい)

縦串に製品○○という課があって,横串に製品を構成する主要コンポーネントがあるといった感じです.分かりやすい例として,自動車を挙げますと,製品1というのがプリウス.製品2はルーミー.製品3はRAV4.コンポーネントAはエンジン.コンポーネントBはボディ.コンポーネントCはトランスミッションといったもの.このどこの課に配属されるかによって,業務内容が異なります.製品の課に配属されれば,その車を開発する全体の取りまとめ的な立ち位置で開発をリードする.コンポーネント課に配属されれば,その要素技術に特化した技術開発を行うことになります.(繰り返しますが,分かりやすいようにトヨタ車名を参考例として記述していますが,あくまで例を示しているのであり,トヨタ社がこうであると言っているわけではありません)
まずは,自身が配属された課のロール&レスポンシビリティ(役割と責任)をよく聞いて,それに相応しい対応を考えて下さい.配属された課に応じた考え方や優先順位があったりします.この観点は結構大事で,自分よがりの考え方で業務を進めようとしても,たとえそれがグッドアイデアだったとしても上手くいかないことが多いような気がします.
3.カルチャー・雰囲気
『風通しが良く,みんなが自分の意見を言う会社であるかどうかを見極めよう』とよく言われるが,具体的にはどうやって見極めれば良いのか.
クロスファンクショナルな組織というのは,従来の製品の改良を進めるには,合理的でよくできた形態だと思います.しかし,全く新しい製品やサービスを生み出すには柔軟性に欠けるかもしれない.そこで,組織を超えて縦横無尽に動き回るタスクフォースチームが結成されることがしばしばあります.今だったら,DX(デジタルトランスフォーメーション)推進室とか,IoT推進室,SDGs検討室,AI(ディープラーニング)推進室といった特命チームが発足している会社が多いと思います.
このような特命チームに
①有望な人材がアサインされているか
②トップが強力にバックアップしているか
③特命チームに権限と予算が与えられているか
④特命チームメンバーが活き活きしているか
上記の4つを注意深く観察してみて下さい.このような特命チームにアサインされているような社員は,コミュニケーション能力が高いことが多いですので,時と場所をよく考えて,コンタクトしてみて下さい.4項目の特命チームメンバーの目の輝きがその会社のカルチャー・雰囲気を表していると思います.
4.自分とのマッチング
これまでの3つの事項は,会社のリサーチです.今度は,自分の内面をしっかりリサーチする.
自分がその会社に入ったら,給料とか出世とかではなく,別の指標(自分の価値基準)で,悔いなく過ごせるだろうか.そんなことは,実際に配属されてみないと分からない.その通り.もちろん,分からないことが多いです.たまたま自分の直接の上司が...ということもあるでしょう.でも,一生同じ課に配属で,一生同じ上司ということはありません.ですので,その会社で作っている製品が好きとか,提供しているサービスに意義を感じているといったことが有意義な人生を送る上で大切になってきます.その辺りの自分とのマッチング(どんな状況でも前向きに取り組めるか)が見極められたら,それこそがインターンシップに参加した意味です.健闘を祈ります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
