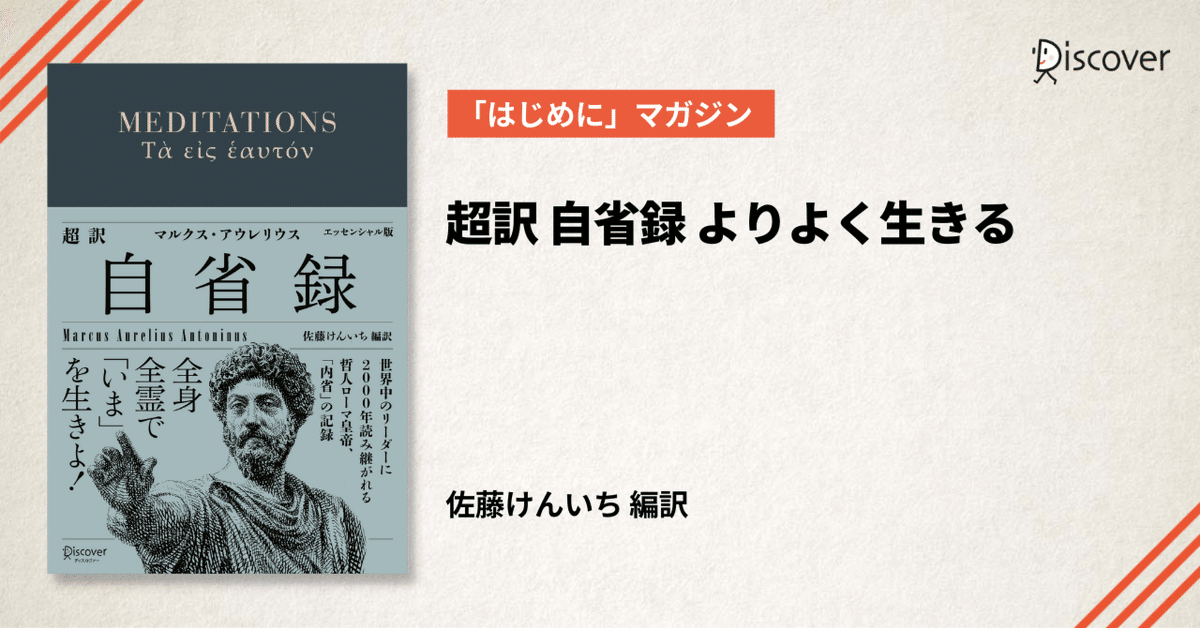
【「はじめに」公開】佐藤けんいち 編訳『超訳 自省録 よりよく生きる』
シリコンバレーの起業家たちが注目し、マンデラ元南アフリカ大統領、ビル・クリントン元アメリカ大統領など各国のリーダーが愛読してきた『自省録』。
哲学者でもあるローマ皇帝マルクス・アウレリウスによる人生訓が「超訳」となって読みやすくなりました。
このnoteでは冒頭の「はじめに」を公開します
はじめに
ローマ皇帝マルクス・アウレリウスと『自省録』について
マルクス・アウレリウスは、紀元2世紀に生きた実在のローマ皇帝だ。そして『自省録』は、彼が激務のかたわら就寝前につけていた「瞑想記録ノート」である。
彼はまた、古代ギリシアにはじまるストア派最後の哲学者とされている。
皇帝としてのマルクス・アウレリウス
マルクス・アウレリウス・アントニヌス(紀元121~180年)は、第
16代のローマ皇帝として「五賢帝」の最後に位置づけられている。五賢帝とは、ネルウァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウスと続く5人の皇帝のことだ。いずれも内政においては善政をほどこし、外政においても地中海帝国としてのローマ帝国の最盛期を実現した。
当時のローマ帝国の人口は、約6000万人強(紀元前25年時点)と推定されている。マルクス・アウレリウス帝の先々代にあたるハドリアヌス帝時代には、首都ローマの人口は100万人に達していた。最高責任者として、その頂点に立つのがローマ皇帝であった。皇帝の職務がいかに重責であったかが理解されよう。
ローマ市民にとって最高の娯楽であった剣闘士(グラディエーター)の試合では、皇帝の義務として観戦している最中にも未決済の書類を読んでおり、市民から笑われていたという。そんなエピソードがあるくらい、きまじめで仕事熱心であったらしい。
だが、五賢帝の最後となったマルクス・アウレリウスが39歳で即位したとき、すでにローマ帝国は全盛期を過ぎており、衰退の影が見え始めていたのである。洪水や大地震などのあいつぐ天災、戦地から兵士たちが持ち帰った感染症の蔓延(天然痘だとされている)、東方では大国パルティア王国との戦争、北方からの蛮族ゲルマン人の侵攻、そしてシリア属州においては信頼していた将軍の反乱など、さまざまな問題が押し寄せてきたのであった。
次々と押し寄せてくる問題の解決に奔走し、朝から晩まで激務に追われていたマルクス・アウレリウスだが、帝国を北方から脅かすゲルマン人との戦闘にかんしては、住み慣れて快適なローマから遠隔操作していたのではない。ほんとうは哲学者になりたかったマルクス・アウレリウスは、平和愛好家であったにもかかわらず、50歳代になっていた晩年の10年間の大半を戦地で過ごしている。自分自身が軍隊を指揮するわけではないが、最高責任者が「現場」にいることが将兵の士気向上につながると確信していたからだ。そんなところにも、誠実できまじめな性格が表れているといっていいだろう。
前線に設置されたドナウ河畔の陣中で書き続けていたのが『自省録』だ。だが、過酷な環境においての激務で神経をすり減らし、食も細っていた彼は、ドナウ河畔の陣中で病没する。享年59歳であった。
映画化されてヒットした『テルマエ・ロマエ』の原作は、ヤマザキマリによるマンガ作品(2008~2013年)であるが、哲学に心を奪われていた青年時代のマルクス・アウレリウスが登場する。まだヒゲを生やしていない、目の澄んだ若々しい青年として、主人公ルシウス(架空の人物)とかかわりあう設定になっている。時代背景は、マルクス・アウレリウスに目を掛け、後継者としていたハドリアヌス帝の治世だ。
ハリウッド映画『グラディエーター』(米国、2000年製作公開)には、リチャード・ハリスが演じる最晩年のマルクス・アウレリウスが、遠征先の戦地でオイルランプの火をたよりに瞑想し、『自省録』を執筆しているシーンがある。
『テルマエ・ロマエ』も『グラディエーター』もともにフィクションであり、事実関係は大幅に脚色しているが、マルクス・アウレリウスの人物を映像や画像をつうじて感じ取るには参考になるかもしれない。
『自省録』の著者としてのマルクス・アウレリウス
『自省録』の原文は、ギリシア語で書かれている。原題の「タ・エイス・ヘアウトン」とは、「彼自身のために」という意味だ。人に読ませるためではなく、あくまでも自分のために書き続けた「瞑想記録ノート」なのである。読者をまったく想定していない私的な文書なのである。しかも、このギリシア語のタイトルさえ自分自身でつけたものかどうかも不明だ。全12巻の構成じたい、いつそうなったのかも不明だ。そもそも、なぜこの記録ノートが廃棄されることなく筆写され、伝承されてきたのかも、ほんとうのところはよくわかっていない。
当時のローマ帝国の支配階級にとって、その支配下にはいったバルカン半島のギリシアは教養の源泉とみなされており、ギリシア語は教養言語と位置づけられていた。明治時代前半までの日本人にとっての漢文のようなものといっていいかもしれない。マルクス・アウレリウス自身も、子どもの頃から母語のラテン語のほか、ギリシア人の教師たちから、ギリシア語でさまざまな教育を受けている(*詳細は『自省録』の第一巻に回想されているが、本書では割愛した)。
ある意味では、マルクス・アウレリウスは、昼はラテン語世界、夜はギリシア語という「二つの世界」に生きていたといえよう。前者は、「役割」として演じていたローマ皇帝の公務で使用していたラテン語、後者は「隠れ家」であり「本当の自分」の世界とみなしていたギリシア語である。哲学が生まれたのは古代ギリシアであり、哲学用語を駆使するにはギリシア語のほうが都合よかったということもあるだろう。彼は、異なる二つの世界を行き来していたのである。日本語では、『自省録』というタイトルが定着してきた。精神科医で『生きがいについて』(みすず書房、1966年)という名著で知られる神谷美恵子氏による翻訳が、1956年に岩波文庫に収録され、現在に至るまで長年にわたって読み継がれてきたからだ。『自省録』というタイトルはじつにすばらしい。私もこの翻訳で読んできた一人だ。
だが、英語圏では『Meditations』というタイトルで普及していることにも注意を向けておきたい。「メディテーション」とは「瞑想」のことだ。まさにその通りであって、マルクス・アウレリウスは、朝晩の瞑想のなかで自省し、就寝前の瞑想で自分自身と行った対話をメモとして書き残したのである。文中での「君」という呼びかけは、「自分の分身」が「自分自身」に対して呼びかけているものだが、「理想」を追い求めていた青年マルクス・アウレリウスが、「現実」のなかで苦悩する中年マルクス・アウレリウスを叱咤しているのだと考えていいかもしれない。
しかも、瞑想を行うだけでなく、文字として「書く」ことが重要であった。これはマルクス・アウレリウスだけでなく、先行するエピクテートスやセネカといったストア派の哲学者に共通しており、「書く」ことは「スピリチュアル・エクササイズ」(=精神修行)として行われていたのである。「書く」ことはアウトプットであり、その意味については、のちほどまた触れることにしたい。
日本人にもなじみの深い内容
哲学というと敬遠しがちな人にも、ストア派の哲学は受け取りやすいのではないかと思う。なぜなら、実際に読んでみると気づかれると思うが、日本人にもなじみ深い内容が語られているからだ。
「すべてが瞬間ごとに変化していること」(=無常)や、「すべてがつながっていること」(=縁起)を強調したブッダの思想にも通じるものがあり、「いま、ここ」に集中するべきと説く禅仏教や上座仏教がルーツの「マインドフルネス」を連想させるものがある。老子や荘子などの老荘思想が説く「タオ」(=道)にもつうじる自然観がある。しかも、21世紀の現在にもつうじる宇宙観がある。
「仕方ない」ということばに体現された、きわめて日本的な運命受容と肯定の思想を見いだすこともできる。「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」という『葉隠』の思想を想起する人もいるだろう。個人的には、ミリオンセラー『生き方』(サンマーク出版、2004年)の著者で京セラの創業者でもある稲盛和夫氏や、合気道開祖の植芝盛平翁の思想を連想させるものがあると感じている。このほか、日本人の思想に近いものが多くあるので、みなさんもぜひ、そんな観点から読んでみるといいと思う。
マルクス・アウレリウスの時代は、キリスト教が公認される以前の時代であり、『自省録』にはキリスト教の影響は皆無といっていい。つまり、ストア派の哲学は、キリスト教が受け入れられる以前の「実践哲学」であった。だが、そうであるにもかかわらず、西欧のキリスト教世界で受け入れられてきたのは、ストア派の「実践哲学」がキリスト教徒にとっても有用だとみなされたからだろう。
激動の時代に迷える者の指針となる「実践哲学」
西欧世界では、『自省録』は写本をつうじて、ほそぼそとではあるが読み継がれてきたようだ。だが、本格的に注目を浴びるようになったのは、16世紀半ばに活字化されて以降のことだ。激動期の17世紀には、「新ストア主義」として『自省録』を含めたストア派哲学がリバイバルしている。
熱心な愛読者としては、17世紀スウェーデンのクリスティナ女王や、18世紀プロイセンのフリードリヒ2世をあげることができる。クリスティナ女王は、フランスの哲学者デカルトをスウェーデンに招致したことでも知られているが、プラトンが説いた「哲人王」を理想としていた。「ウェストファリア条約」(1648年)の締結を促進し、キリスト教徒どうしが血で血を洗う「宗教戦争」を終わらせるにあたって多大な貢献をしている。啓蒙専制君主であり、軍事の天才であったフリードリヒ大王は、『自省録』を自分の愛馬の鞍のポケットに入れ、戦場にはつねに持参していたのだという。
19世紀の「産業革命」以降の欲望全開時代には、マルクス・アウレリウスだけでなく、ストア派全体の人気は下火になっていたが、世界が激動期に入ってきた1970年代以降、ふたたび熱心に読まれるようになってきた。ストア派の実践哲学が、混迷する情況に生きる迷える者たちの指針となることが再発見されたからだ。
そのなかでも著名な愛読者としてあげるべきなのは、南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領や、米国のビル・クリントン元大統領、トランプ政権の国防長官だったマティス海兵隊退役大将(2018年12月末に解任)などだ。かれらの出処進退を見れば、『自省録』がどのように影響しているかよく理解できることだろう。
南アフリカで人種差別のアパルトヘイトと戦い投獄されたマンデラ氏は、獄中に差し入れられた『自省録』を繰り返し熟読したのだという。27年間にも及んだ獄中生活から解放後に南アフリカの大統領に選出された際には、怒りではなく和解こそが重要だと理解したうえで、人種間の壁を越えた国民和解に努めた人であった。クリントン元大統領は、大統領退任後には1年に1回はかならず読み直しているとインタビューで語っている。マティス米海兵隊退役大将は、「マッドドッグ」や「戦う修道士」という異名をもつ人だが、ペルシア湾やイラク、アフガニスタンでの任務の際には、つねに持参していたという。
現在の米国では、ベストセラー作家でメディア戦略家のライアン・ホリデイ氏によって、ストア派哲学の大衆化と普及が活発に行われており、シリコンバレーの起業家たちやアスリートたちのあいだでは、ストア派哲学の心酔者が増えているという。他人に振り回されることなく自分自身のことに専念し、目標に向けてセルフコントロールするマインドセットをつくりあげるうえで、ストア派哲学が大いに役に立つからである。それが、本当の意味でストイック(=ストア派的)な生き方なのだ。
「書くエクササイズ」は「セラピー」でもある
『自省録』は、「書く」という「スピリチュアル・エクササイズ」(=精神修行)として実践されたものであることはすでに記したとおりだ。就寝前の瞑想で一日の振り返りを行い、胸中の思いに対して自問自答し、最後に結論として自分を戒め、自分を叱咤激励することばを書く。このプロセスがセルフセラピー(=自己治癒)にもなっていることが、本文を熟読していると理解されることだろう。
おしゃべりであれ、日記に書くのであれ、なんらかの形で内面の思いを吐き出すことはデトックスであり、精神衛生上よいことは言うまでもない。そして自問自答と決意表明の内容を書き終えたあとは安心して就寝し、翌朝に目が覚めたら再び活力に満ちた状態で仕事に専念する。マルクス・アウレリウスもまた、そんな日々を繰り返し送っていた生身の人間であった。
本文を読んでいると気がつくと思うが、似たような内容が表現を変えながら、何度も繰り返し登場する。おなじような内容が多くあるということは、その都度、決意表明をしながらも、あらためてそうし直さなければならなかったことを意味している。厳しすぎる内容だと思う読者も少なくないと思う。だが、決意表明をしても、現実生活では実現できなかったことが多かったのではないだろうか。
マルクス・アウレリウス没後のことだが、帝位を継いだ長男のコンモドゥス帝が暴君となってしまったのは、その姉、つまりマルクス・アウレリウスの実の娘による暗殺未遂事件に大きなショックを受けたためだとされる。実の子どもたちでさえ、自分の意のままにならないのが人間の性(さが)であり、マルクス・アウレリウス自身もまた、その例外ではなかったのである。
つまり、マルクス・アウレリウスは「哲人皇帝」ではあったが、けっして聖人君子ではなかったのである。生身の人間だったのである。だからこそ、この本は聖人の教えとして読むべきではない。生身の人間であったマルクス・アウレリウスの肉声を聞き取ってほしいと思う。約2000年の時空間を超えて、現代に生きる人間にも響くものがあるはずだ。
編訳方針について
エッセンシャル版では、全体で487章ある長短さまざまな文章から、現代に生きる人にとって意味をもつと思われる180章を厳選して翻訳した。意味がよく伝わるように、原文にはない表現を補い、逆に削除している箇所もある。翻訳にあたっては、参考文献にあげた日本語訳と英訳には、たいへんお世話になった。
セレクトした文章にかんしては、可能な限り全文を収録するようにした。すでに見てきたように、『自省録』のスタイルは、結論が先にあるわけではないからだ。そのかわり、原文にはない「小見出し」を内容要約としてつけ、内容別に配列し直している。
できれば、みなさんにも「書くエクササイズ」をやってみてほしいと思う。アウトプットすることによって、自分の思いが整理され沈静化されるだけでなく、再び明日への活力も生み出されることになるだろう。「人生は短く、いつ死ぬかわからない」。だからこそ、過去でも未来でもない、「いま現在」を生きる気持ちが湧いてくるはずだ。それが本書全体を貫くメッセージでもある。
では、さっそくマルクス・アウレリウス自身のことばを読んでみよう。どのページからでもいい、見開いたページを読んでみる。そして自問自答してみるといい。「君」という呼びかけが、読者である「あなた」自身に向けた呼びかけと思うようになるまで。
2021年10月 佐藤けんいち
目次
はじめに
ローマ皇帝マルクス・アウレリウスと『自省録』について
I 「いま」を生きよ
II 運命を愛せ
III 精神を強く保て
IV 思い込みを捨てよ
V 人の助けを求めよ
VI 他人に振り回されるな
VII 毎日を人生最後の日として過ごせ
VIII 自分の道をまっすぐに進め
IX 死を想え
著者について
マルクス・アウレリウス
(紀元121~180年)
第16代ローマ皇帝。「五賢帝」の最後に位置づけられている。五賢帝はいずれも内政においては善政をほどこし、外政においても地中海帝国としてのローマ帝国の最盛期を実現した。しかしマルクス・アウレリウスが39歳で即位したとき、すでにローマ帝国は全盛期を過ぎており、衰退の影が見え始めていた。洪水や大地震などあいつぐ天災、東方ではパルティア王国との戦争、北方からのゲルマン人の侵攻などさまざまな問題が押し寄せる。彼は朝から晩まで激務に追われ、しかもゲルマン人との戦闘に関しては晩年の10年間の大半を戦地で過ごしつつ『自省録』を書き続けた。59歳でドナウ河畔の前線の陣中で病没。ハリウッド映画『グラディエーター』には最晩年の、ヤマザキマリの漫画『テルマエ・ロマエ』には青年時代のマルクス・アウレリウスが登場する。
編訳 佐藤けんいち(さとう けんいち)
ケン・マネジメント代表。1962年京都府生まれ。一橋大学社会学部で歴史学を専攻、米国レンセラー工科大学(RPI)でMBAを取得(専攻は技術経営)。銀行系と広告代理店系のコンサル会社勤務を経て、中小機械メーカーで取締役経営企画室長、タイ王国では現地法人を立ち上げて代表をつとめた。編訳書に『ガンディー 強く生きる言葉』『超訳ベーコン 未来をひらく言葉』(いずれも小社刊)がある。
***
マルクス・アウレリウスは「哲人皇帝」ではあったが、けっして聖人君子ではなかったのである。生身の人間だったのである。だからこそ、この本は聖人の教えとして読むべきではない。生身の人間であったマルクス・アウレリウスの肉声を聞き取ってほしいと思う。
世界史の教科書に出てくる偉人は、どこか違う世界に住んでいて、「その人だからそんなこと言えたんでしょ」と思ってしまうことも多いです。
ただこの「はじめに」を読んでマルクス帝の人間性を垣間見ると、
「自分と似たところもあるかもしれない」と、不思議と安心感を覚えました。
(営業部 滝口)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
