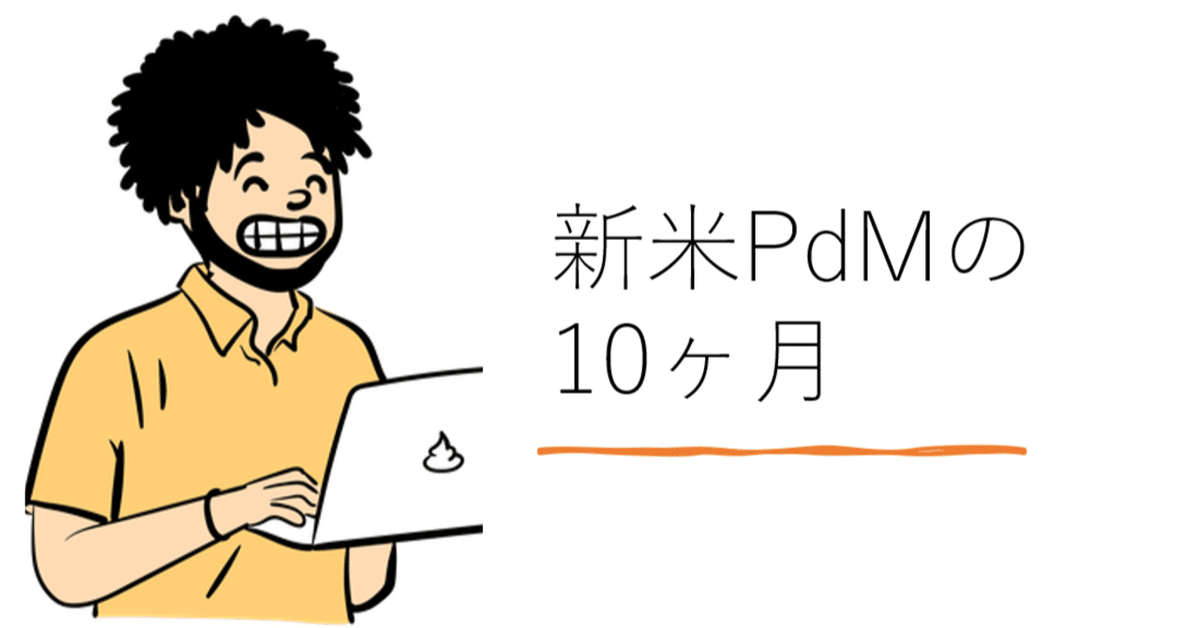
営業上がりの10ヶ月新米PdMがどのように成長しているのか
バイトル営業を1年、RPA営業1年やってきた自分がどのようにPdMという職業を学んでいるのかをここで発信していきたいと思います。
まず新米ってどれくらい??ってところですが、現在PdMになって10ヶ月が経ちました。
PdMとそもそも名乗れるのかという部分はそっとしておいてください。。。
どう成長してきたか
営業からPdMになった最初の1ヶ月
そもそもなぜ、営業からPdMになったのかという疑問があると思います。RPA営業をしたいた頃、RPAやプログラミングなど、それっぽいことをざっくりと学んでおいたほうが営業として強い!という営業としての能力を上げるために学んでいたことがきっかけです。
そして、学んでいくうちに興味が出始め、社内異動をしてきたという経緯です。
では、最初の1ヶ月
・何から始めればいいのか
・何を学んでいたのか
という点ですが、
結論!!
「分からないことが分からない!!」ので何をしよう状態でした。
これが最初の課題です。何から始めればいいのか、どう取り組み、学べばいいのか、ここをクリアにしていくのにすごく悩んでいました。
どのようにクリアをしたかというと、Gogoleで「PdM 初心者 やること」などと検索して片っ端から記事を見ていくという事をしていました。
ここで何を得られたかというと、色々な言葉を覚えました(笑)

一般的に調べていくと、記事の多くは、一人でPJを計画立案からやってみる、のような完全初心者向けの記事ではないことが多く、ある程度の知識がないとそれ出来なくない?というものばかりでした。
(最近未経験向けのおすすめの記事が集まっているNotionにやっと出会えたのでここに載せておきます!複製して保存しておくと便利です!もっと早く見つけたかった、、、)
ジュニアPMにおすすめインプット集

しかし、ありがたい事にそのような記事が多いおかげで、言葉を覚えることはもちろん、PdMの仕事の流れ的なことを学べることができました。
「あ~こうやって仕事をしていくのか」こんな感覚です。
営業の時は、リスト作成から始まり、コール、アポ取り、商談、区切っていくと「こんな形で仕事をするんだろうなぁ~」をなんとなく分かっていたのですが、PdMという職業は、そこからも何もわからずでしたので、まずはそこから学ばなければいけなかったのです。
・飛び交う言葉を覚え、
・どう行動を起こし、
・どうやって学んでいくのか、
最初の1ヶ月はとにかく行動して、言われたことはとにかくチャレンジしての繰り返しでした。
新卒で営業に配属された直後の事を思い出しました。
とにかく出来る人の真似、とにかく行動、とりあえずやってみる、
こんなことをずっと言われていた気がします。
何事にも全力で取り組む大切さを改めて実感しております。
営業での経験、多少のエンジニア経験、こられの業務を真面目にやってきたおかげで、現在はその経験や知識が非常に役に立っております。
半年後
半年が経った頃、自分はPJのPdM補佐として動いております。
社内でいくつもPJが走っている中、新規PJにジョインをさせて頂くことになりました。
そのPJは社内事情で今はなくなってしまいましたが、とてもいい経験ができたPJだと今でも思っております。
なぜ良かったのか。それは、営業の業務内容を手助けするPJだったからです。元々営業ということもあり、相手の立場になって物事を考えることがすぐ出来たので、そこに関わる業務に集中することが出来ました。
今思うと上長陣が、上手くジョインさせてくれたんだなと思っています(笑)。
PJをやっていく中で、企画段階からジョインしていたこともあり、機能要求を決めていた頃の話です。
営業の出身ということもあり、あの機能もあれば便利!これも!あれも!といくつも提案したことがありました。その時に注意を受けたことがあります。
何がダメのかというと、その機能を開発するには費用がかかり、自分たちがターゲットにしているユーザーは、果たしてそこまでの機能を必要としているのかという点です。

その時の自分は、自分の営業スタイルの事ばかりを考え、便利な事だけを考え、提案をしていたということです。
ダメダメですね。営業時代であれば即失注です(笑)
もちろんですが、提案するにも根拠などが必要だなと実感しました。
・この製品は、誰をターゲットにしているのか、
・そのユーザーの視点に立てているのか
この2点は機能を考える上で非常に重要だと考えています。
このPJ自体は開発前でペンディングしたため機能を考えるところまでしか出来ませんでしたが、企画~開発前までをここでは勉強させて頂きました。
どういった観点が必要だったか下記に記載しておきます。
・RFP作成
①パワポ図形、色を分けるか分けないか迷ったら考えること
②“ダサい”を卒業する図形素材集「モノクロスライドテンプレート」
・機能を開発するにはどういう手順や考えが正しいのか。
①そのユーザーファースト、本当にユーザーファーストですか?
・ベンダー選定の際の注意点や見つけ方
・図の書き方や考え方
・フィジビリ営業で得られる情報や視点
このような観点は特に重要だなと感じた部分です。(考え方についての参考記事も載せておきます)
現在
ついこの間までは、新規PJと既存PJ(常連コボット)のPdM補佐として動いていましたが、現在は常連コボットというPJを担当しております。
今まで担当した新規PJは2つともペンディングしたため、今回この常連コボットのPJで、初めて新機能開発を体験しております。
リリースというのを10ヶ月目にして初めて味わいました!とても嬉しかったです(笑)
初めてリリースなどを体験したという事は、仕様書関連も初めて体験したという事です。そもそも仕様書ってどれくらい種類あるのだろう?どれをどのタイミングで書くのだろう?というところから疑問でした。
そのため、そういった内容も本やネット、外部セミナーを通じて勉強しています。
参考Webサイト:
「仕様書の参考例と、こんな内容を仕様書に最低書くといいというお話」

例えば上記画像のように、ネットで上がっている見本をいくつも拝見し、どれが見やすいか、どれが最適かをいつも確認しています。要はいいとこ取り作戦です(笑)
ここらへんは外部セミナーではなかなか勉強ができないため、作成力のある人の仕様書をネットで探して勉強するしていました。
PdMとして10ヶ月経過していますが、まだまだ分からないことが多いです。しかし、「分からないことが分からない」という状況はなくなりました。
ここまで学んだ経験から言えることは、PdMそのものの職業理解、飛び交う単語の理解、業務で作成されるドキュメントの把握、そして仕事の流れを覚えることが重要だなと。開発観点の知識などはその次でいいと自分は考えていたので、これらを重要視して学んでいました。
そうすることで、何が分からないのかは自然に消えていくと考えています。
もし何も知らないところからPdMを目指したいという方は参考にしてもらえると嬉しいです。
今は、アプリが出来るまでの工程や、AWSについて学んでいます。
アプリが出来るまでの工程は、一通りシステムについて学べると思ったからです。なので実際にアプリを作成しております。
下記参考画像です。


AWSについては、今流行りということもあり、概念からサービスについてまで幅広く学んでおります。このように次に自分には何が足りてないのかを把握しておくことで成長につながると考えています。最後に、今まで受けてきた外部セミナーとおすすめの本を紹介しようと思います。
学んできたこと
今まで受けた外部セミナー
基本的に「connpass」というWebサイトで外部セミナーを探しています。
タイトルのみになりますが、下記です。
・新規事業アイデアの発想&検証フレームワーク
・【UXデザイン】ユーザーテストの進め方
・SaaSの開発ロードマップ、マイルストーンどう決める?
・事業開発チームのための仮説検証インタビュー入門
・オウンドメディアのペルソナ設定とカスタマージャーニーの作り方
・実践!プロダクトづくりとNotion活用事例
・副業・フリーランスPMってプロダクト開発どうやってるの?
・大公開!プロダクトグロースを支えるナレッジシェアの仕組みと文化
半年目ぐらいから月に2回ほど外部セミナーを受けて勉強しています。
それ以外にもAWSの概念からAWSサービスなどの勉強をして社内に共有していたりします。勉強したものを共有するため、「自分なりに再度まとめてアウトプットする」これがすごく大事だなと実感しております。
おすすめの本
1冊目:プロダクトマネジメントの全て
「PdMとは」を全て習得できます。

2冊目:外資系金融のExcel作成術
弊社では仕様書などをExcelで作成することが多いため、基本を学ぶにはとてもいい本です。ちなみにこちらのPowerPoint版もあるのでそちらもおすすめです。RFPなどの作成時に役立ちます。

3冊目:エンジニアリング組織論への招待 ~不確実性に向き合う思考と組織 のリファクタリング
IT業界で働くのであれば一度は読んでおいたほうがいいなと思う本です。

dip株式会社の紹介
最後に、弊社に興味がありましたらこちらから
ご覧いただければ幸いです。
求人一覧はこちら
・プロダクトマネージャー(PdM)
・プロジェクトマネージャー(PjM)
・ QAエンジニア
・ リードエンジニア
・ インフラエンジニア
・データエンジニア
・Webアプリケーションエンジニア
・PMM/商品企画・推進マネージャー
以上となります。
最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
